障がい者雇用のトラブル事例とは?対処法や相談先を解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.07.25
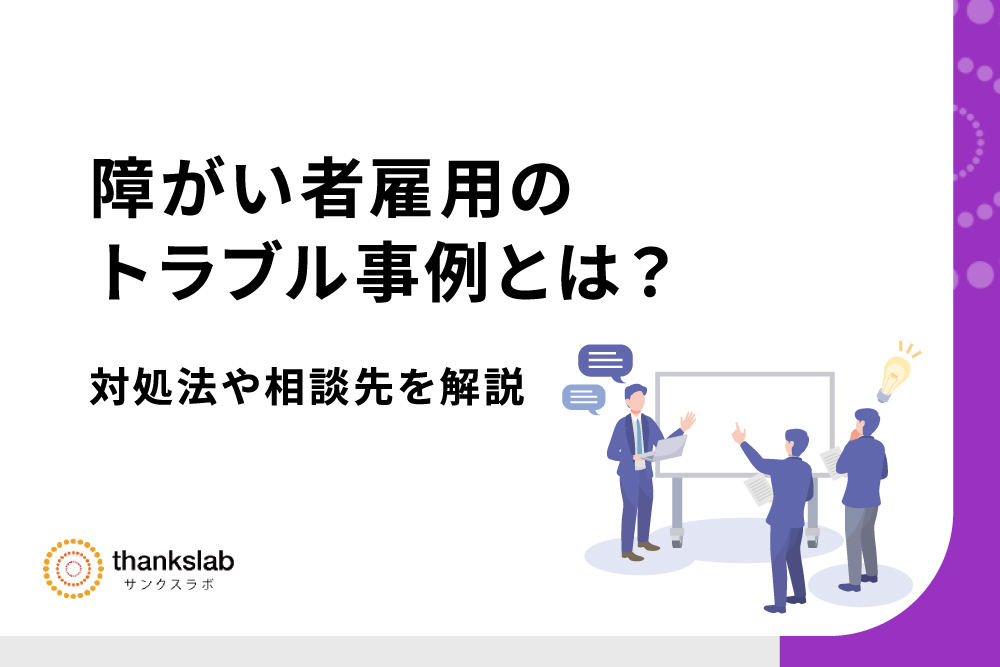
「従業員の増加によって障がい者の雇用義務が生じたが、トラブルがおきないか心配」「障がい者雇用を前向きに検討しているが、気をつけるポイントを知りたい」といった悩みや心配を抱えている企業は多いことでしょう。
障がい者を雇用してスムーズに働いてもらうためには、職場の環境を整えて従業員の理解を深めると同時に、障がい者を雇用した際に起こったトラブルの事例を把握しておくと役立ちます。
本記事では、障がい者を雇用した際に発生したトラブル事例を対処法と共に紹介します。
障がい者雇用でトラブルが起こる理由とは?
はじめに、障がい者を雇用した際にトラブルが起こる理由を紹介します。障がい者を雇用する会社同様、雇用される障がい者もさまざまな不安を抱えています。トラブルが発生する理由がわかれば、対処法も立てやすくなるはずです。
障がい者が抱える不安が解消されない
障がいにはさまざまな種類があり、ひとりひとり症状や必要な配慮が異なります。また、会社の障がい者に対する態度も異なります。障がいに対する理解を深めようと積極的な会社もあれば、他の仕事が忙しいといった理由でおざなりになっているところもあるでしょう。
障がい者はハンディを抱えているだけでなく、障がいの種類によっては他人とうまくコミュニケーションができない方もいます。障がい者が抱えている不安が解消されないまま働き続けていると、ストレスがたまって働き続けるのが難しい場合もあるでしょう。
障がい者が定着しない職場の中には、障がい者の意見や不安に耳を傾けていないところもあります。
賃金や労働に関する不満
障がい者の中には、賃金や労働に関する不満を抱えているケースもあります。例えば、「専門知識を活かせる職場に就職したのに、雑用ばかりやらされる」「別の業者に委託した農作業が業務だった」「同じ仕事をしているのに、健常者よりも給与が安い」といった事例もあります。
賃金や労働に不満があれば、離職率が高まりがちです。特に、障がいの程度が軽く、高いスキルを持っている方ほど賃金や労働条件に不満があったら改善を求めずに転職活動を検討する方もいるでしょう。
また、不満をうまく言葉にして職場の方々に伝えることができず、ストレスを貯めて仕事が続けられないケースもあります。
担当者への負担が大きくなって通常業務に影響がでた
障がい者を職場で受け入れる際は、職場の環境を整えてサポートを行う人員を配置する必要があります。障がい者のサポートには知識と経験が必要です。障がい者を雇用するにあたって、会社ぐるみで障がいへの理解を深めるために勉強するケースも多いでしょう。
しかし、障がい者への対応は1人1人異なります。障がいに配慮しつつ仕事を教えるのは個人ではとても難しいでしょう。そのため、担当者の負担が大きくなりすぎて通常業務に影響が出るといったトラブルが発生することも珍しくありません。
障がい者をサポートするならチームで対応する、誰か1人に責任を押し付けない、必要ならば社会福祉士、精神福祉士等のプロフェッショナルと連携を取るなどの対処が必要です。
障がい者雇用のトラブル事例
ここでは、障がい者雇用のトラブルの事例をいくつかご紹介します。障がい者を雇用する際は、トラブル事例を知っておくと対処もしやすいでしょう。なお、障がい者を雇用するとトラブルが多発するとは限りません。
しかし、障がいは本人のやる気や能力に関係なく、トラブルの要因となる可能性があります。障がいを理解するうえでも、トラブル事例は一定数把握しておきましょう。
雇用した障害者の症状が悪化した
主に精神障がいを持っている方に多く見られるトラブルです。精神障がい者の中には、頑張りすぎてしまい、ある日突然調子が悪くなる症状が現れることも珍しくありません。そのような方は、就業したばかりのころは健康な人と変わらない働きぶりを見せる方もいるでしょう。
また、発達障害の方の中には、特定の分野では健康な人よりも優秀なケースもあります。しかし、ある日突然スイッチが切れたように仕事ができなくなります。場合によっては無断遅刻、無断欠勤が続いた後で唐突に退職するケースもあるでしょう。
出勤しても、仕事が手に付かなかったりミスが多くなったりします。はた目から見れば、仕事に慣れてきたとたん「さぼり癖」が出たように見えるかもしれません。しかし、これらは障がいの症状の場合もあります。
「就職したのだから」と頑張りすぎた結果、限界を突破してしまうのです。障がいに理解がないと「その人がだらしがないからだ」と判断してしまうこともあるでしょう。
障がい者と職場とのコミュニケーションがうまくいかない
障がい者の種類によっては、自分の気持ちを相手にうまく伝えられない場合もあります。また、その場の状況や雰囲気に合わせた対応ができない場合もあるでしょう。
一例を挙げると、「自分が思ったことをそのまま言ってしまう」「過去の経験や体験から、わからないことでもわかったようなふりをしてしまう」などです。
そのため、障がいに対する理解がないと「人を馬鹿にしている」「ふざけている」と思われがちです。職種によっては、お客様とトラブルになるケースもあるでしょう。また、上司にも同僚のように接したり、異性の同僚と度を越した親密さで接しようとしたりするケースもあります。
職場によっては「仕事を任せられない」と担当者が悩んでしまうこともあるでしょう。
教育担当者の負担が大きい
障がいの程度によっては、繰り返し辛抱強く教えないと仕事の手順がわからなかったり同じ失敗を繰り返したりする方もいます。障がいの程度に合せて適切な指示を出すには、専門的な知識と経験が必要です。
しかし、会社によっては障がい者を雇用しても教育までに人材や費用、時間を割けないところも珍しくありません。その結果、付け焼刃の勉強で障がい者の教育担当者になる方もいるでしょう。
障がい者に仕事を覚えてもらい、障がいに配慮しつつスムーズに仕事をしてもらうには時間だけでなく経験も大切です。会社の経営者がその点に理解が薄いと「健康な方の新人教育同様、数カ月で仕事を覚えさせてほしい」といった無茶な要求をすることもあります。
教育担当者の負担が大きすぎると離職やモチベーションの低下につながります。
仕事内容や評価への不安
会社によっては、法定雇用率を高めるために障がい者を雇用したものの、任せられる仕事を創出できず、比較的容易な仕事や会社の主要な仕事には関係ない仕事に従事させるケースもあるでしょう。
障がい者によっては、かつては同種の仕事に就いて第一線で働いていた方もいます。また、障がい者の能力や特性に合っていない仕事を任せた結果、仕事がうまくいかないケースもあるでしょう。
仕事に対して正当な評価をされなければ、仕事に対するモチベーションを失ってしまいます。それは、障害の有無に関係ありません。
障がい者は雇用して終わりではなく、雇用して働いてもらい、結果を出してもらう必要があります。そこがうまくいかないと、障がい者の雇用はうまくいかず、トラブルの原因になるケースもあるでしょう。
障がい者雇用のトラブルを防ぐための対処法
最後に、障がい者雇用でトラブルを防ぐための対処法を紹介します。障がい者を雇用したものの早期離職に悩んでいる担当者の方にも参考になるはずです。
障がいへの理解を深める
障がい者を雇用してトラブルを防ぐために最も重要なことは、障がいへの理解を深めることです。一口に障がい者といっても「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」「発達障がい」などさまざまな種類があります。
さらに、障がい者1人1人で対応方法が異なります。そのため、障がい者を雇用する必要が生じたからといってやみくもに雇用するのではなく、任せられる仕事の内容や、対応できる従業員の人数などをしっかりと把握したうえで、「このようなら障がいの方なら雇用できます」と具体例を示すことが重要です。
障がい者への教育はチームで対応する
障がい者雇用では、雇用後に丁寧な教育が必要です。一般的な社員の教育に実績が豊富な従業員でも、障がい者の方への教育は難しいケースもあるでしょう。障がい者への教育はチームで対応するのがおすすめです。
チームで対応すれば適切な対応を話し合って決められるだけでなく、誰か1人に責任が集中せずにすみます。1人に責任がかかってしまうと、負担が大きすぎて教育担当者の離職につながる恐れもあるでしょう。
また、だれか1人に障がい者教育の役割を任せきりにしてしまうと、障がい者が「その人でないと仕事の指示が受けられない」「その人が休みだと仕事がうまくいかない」といったことになるケースもあるでしょう。
必要ならば外部へ相談する
障がい者の雇用は、国や自治体が推進しています。そのため、地域によっては会社に対するサポートも手厚く、精神福祉士や社会福祉士などの相談サポートを受けられる仕組みが整っていることもあります。
また、民間企業の中にも障がい者雇用をサポートしてくれるところもあり、企業だけでは対応できない部分を担当してくれるところもあるでしょう。したがって、すべてを企業で対応しようとはせず、必要ならば外部に相談をし、サポートを依頼しましょう。
まとめ
本記事では、障がい者雇用を進める中で発生するトラブルについて解説しました。障がい者と健康な方が共に同じ職場でサポートしあいながら仕事をするのが理想です。
しかし、職場によっては障がい者への理解が進まなかったり仕事と障がいの特性とのマッチングがうまくいかないケースもあるでしょう。
障がい者雇用におけるトラブルが発生したら、放置せず可能な限り早く対応することが大切です。必要ならば外部からのサポートも受けましょう。そのほうが解決が早まることもあります。
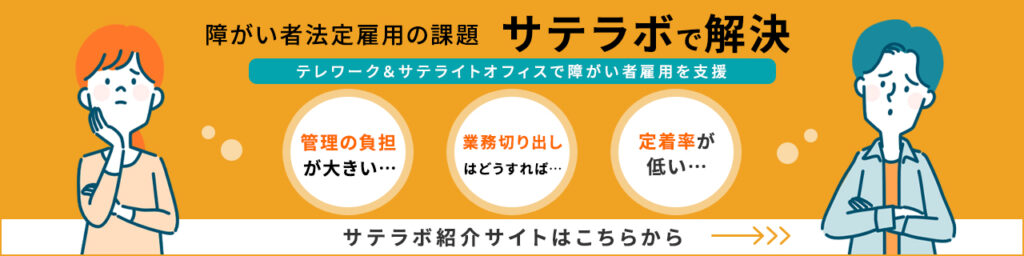
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。








