障害者雇用におけるテレワーク導入のメリットと注意点
- 公開日:
- 2025.03.14
- 最終更新日:
- 2025.05.20
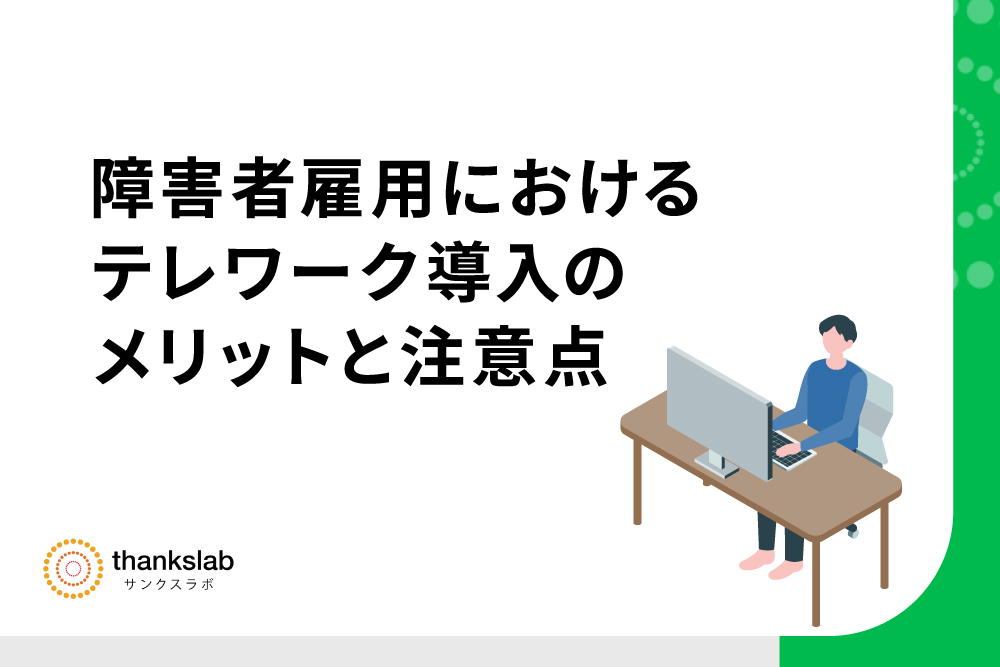
新型コロナウイルス以降、テレワークを実践する企業も増えていきました。障害者雇用においても在宅勤務やサテライトオフィスでのテレワークでの勤務が増えてきています。
ただ、「テレワークを障害者雇用で取り入れてみたいが、どのように実践したらいいかわからない」と悩んでいる人事担当者もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、障がい者のテレワーク雇用が企業にもたらすメリットや実際に導入する前に知っておきたい注意点などについて解説していきます。
障がい者のテレワーク雇用が企業にもたらすメリットとは
障がいを抱える人にとって、テレワークは「対人コミュニケーションを少なくできることによるストレスの軽減」「通勤時の不自由さの軽減」などに役立ちます。
また、この「障がい者のテレワーク」は、企業にとっても多くのメリットをもたらします。ここでは、まずは「障がい者のテレワークが企業にもたらすメリット」について解説していきます。
環境の整備費用が削減できる
障がい者を雇用しようとするとき、企業側はその人が働きやすい環境を整えなければなりません。
現在の会社はその多くがバリアフリー化していますが、建物・設備が昔から変わっていないという場合はバリアフリー化するための費用がかかります。
また、「周りの目が気になる人のために、仕切りなどを作って個室のようなかたちで作業できるスペースの確保」「プライバシー性も保てる休憩室の設置」なども考えなければなりません。
このような改築は大きな金銭的負担を生じさせやすいものです。しかし、テレワークの場合は環境の整備費用が大幅に削減できます。もちろんネットワーク環境の整備などには費用がかかりますが、それでも、建物の改築などに比べればその費用は大きく抑えられるでしょう。
優秀な人材を全国から採用できる
テレワークの場合、採用対象となる応募者の範囲が全国に広がるため、より多くの優秀な人材からの応募も期待することができます。
障がい者側に対するアンケートでは、「テレワーク導入のもっとも大きなメリット」の1位に「通勤の負担軽減」が1位に挙げられており、候補となる企業が横一直線で並んだ場合、通勤の負担が少ないテレワークを導入している企業は、非常に大きなアドバンテージを握ることになります。
障害者雇用のニーズとしても高い、通勤の負担を軽減できるテレワークを導入することで企業はより多くの候補者の中から優秀な人材を雇いやすくなります。
NIVR障害者職業総合センター「調査研究報告書 No.171テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査」
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku171.html
離職率低下と職場定着率向上
障害者雇用において、離職率を下げ職場定着率を向上させることは、企業と働く側の双方に大きなメリットをもたらします。
テレワークを取り入れることで、障害者が自分に合った環境で働きやすくなり、結果として長期的な雇用につながりやすくなります。
障害者雇用でテレワークを導入する時の注意点
障害者雇用でテレワークを導入する場合、企業側に大きなメリットをもたらしますが、いくつか注意点もあります。
在宅勤務に合った業務の切り出し
在宅勤務で障がい者が活躍するためには、適切な業務を切り出すことが重要です。いざテレワークを障害者雇用で導入しようと考えても、自社の業務で在宅勤務に合うものが切り出せなければ、在宅・テレワークでの雇用は難しくなります。
テレワークに適した仕事は、直接的な対面が不要で、インターネットやPCを利用して効率的に進められる業務が挙げられます。
例としては以下のようなものがあります。
- 文書やデータの入力・加工
- 資料の作成・修正
- Webサイトのパトロールや管理
- 情報収集やリサーチ調査
- デザインやWeb制作業務
これらの業務は、業務の進捗状況をオンラインで確認しやすく、成果物を通じて評価が可能なため、管理がしやすい特徴があります。
社内でこういった業務が切り出せるかどうか検討し、テレワーク導入を進めるのが良いです。
コミュニケーション不足
テレワークを導入する際に課題となりやすいのが、従業員間のコミュニケーション不足です。特に、障害者雇用では、業務指示の伝達や進捗共有がスムーズにいかない場合、業務効率の低下や誤解が生じることがあります。
例えば、在宅勤務では、日常的な対面での会話が減少するため、業務上の疑問点がすぐに解決できない状況が発生しやすくなります。また、障害特性によっては、オンラインでのコミュニケーションが苦手な場合もあり、職場全体における協力関係の構築が難しくなることもあります。
このような課題を解決するためには、以下の対策が有効です
- 定期的なオンライン会議の実施
進捗状況の確認や業務の課題を共有する場を設けることで、業務の方向性を揃えやすくなります。 - チャットツールやタスク管理ツールの活用
SlackやTrelloといったツールを利用することで、情報共有がリアルタイムで可能になり、コミュニケーション不足を補うことができます。 - オンライン面談の活用
上司やチームメンバーとの個別面談を定期的に行うことで、心身の状態把握や業務のフィードバックができる環境を整えます。
これらの取り組みによって、テレワーク環境でも障害を持つ従業員が安心して働ける職場を実現することが可能です。企業側には、適切なツールの導入と運用が求められます。
障害者雇用でテレワークを導入する時の相談窓口
障害者雇用でテレワークの導入を検討している場合の相談窓口としては以下があります。
(1) 公的機関や専門サービスの利用
障害者雇用においてテレワークを導入する際、公的機関や専門サービスを活用することは有効です。
これらの機関は、障害特性に応じた支援や環境整備についての情報提供やサポートを行っています。以下、主な公的機関や専門サービスの例です。
| 機関/サービス | 主なサポート内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 求人募集サポート、職場実習の調整、雇用管理に関する助言 |
| 地域障害者職業センター | 業務内容設計、合理的配慮の提供方法に関する相談、ジョブコーチの派遣 |
| 障害者就業・生活支援センター | テレワーク環境や生活の課題に関する相談、障害者と家族を含めたサポート |
(2) テレワークに特化した障害者雇用支援サービスの活用
障害者雇用のサポートをおこなっている、障害者雇用支援サービスの中にはテレワークに特化したものもあります。
- テレワーク人材の紹介
- 業務の切り出し支援
- 勤怠・タスク管理
- 定着率の向上
こういったサービスを提供しており、自社だけでは障害者雇用のテレワーク導入が難しいという時に活用することができます。
弊社サンクスラボでも「サテラボ」というテレワーク&サテライトオフィス型の障害者雇用支援サービスを提供しているため、もし障害者雇用でのテレワーク導入にお悩みの場合はぜひご相談ください。
まとめ
これまで障がい者とテレワークについて解説をしてきました。
障がい者のテレワークは、雇用される側はもちろん、雇用する側にとってもメリットが大きいものです。また、そのメリットを最大限得ることで、さらなる多様な働き方が可能になるものだといえます。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







