特例子会社とは?メリット・デメリット、成功事例をわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.12.26
- 最終更新日:
- 2026.01.15
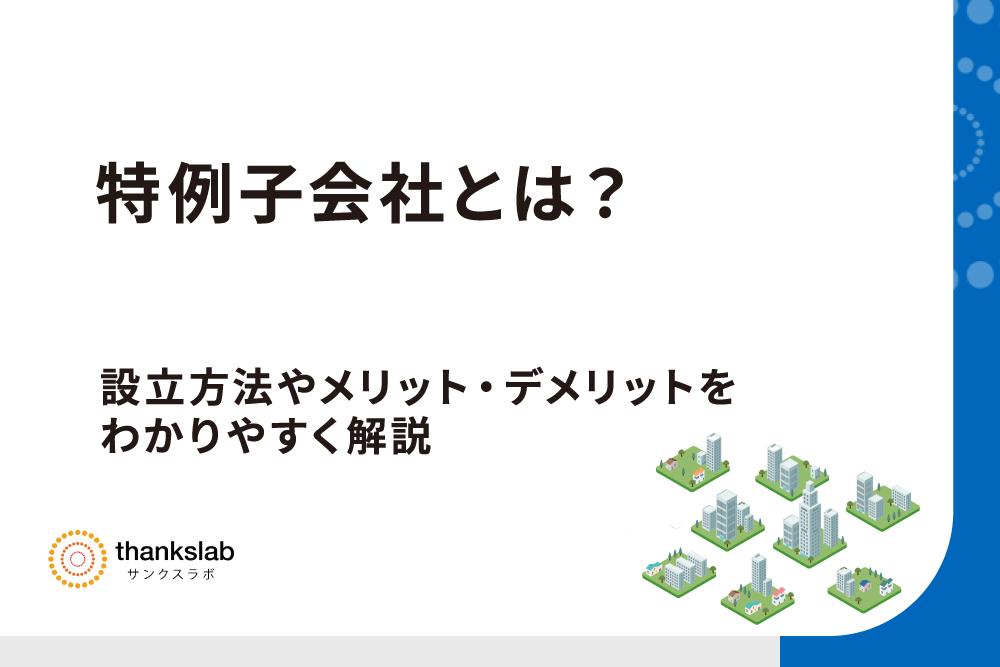
「特例子会社とは何?」
「特例子会社のメリット・デメリットを知りたい」
「特例子会社を設立する手順とは?」
法定雇用率の達成や、障がいのある方の働く環境を整えるために特例子会社を設立しようとお悩みの方もいるでしょう。
そこで今回は、特例子会社とはどういったものか概要や、メリット・デメリット、設立方法などをわかりやすく解説します。これから特例子会社を設立しようと考えている企業のご担当者様はぜひご参考にしてください。
また、特例子会社の設立方法の手順をまとめたマニュアルもご用意していますので、よろしければそちらもご覧ください。
<この資料でわかること>
・特例子会社設立の基礎知識やメリット・デメリット
・特例子会社設立に向いている企業
・特例子会社設立の手順
目次
特例子会社とは
特例子会社とは、障がい者の雇用を主な目的として設立される子会社のことです。
親会社と提携をはかって運営されるものであり、特例子会社で雇い入れた障がいを持つ方の人数を親会社などの法定雇用率としても算定できる仕組みです。
この特例子会社を設立するには、条件を満たした上で厚生労働省からの認定を受ける必要があります。
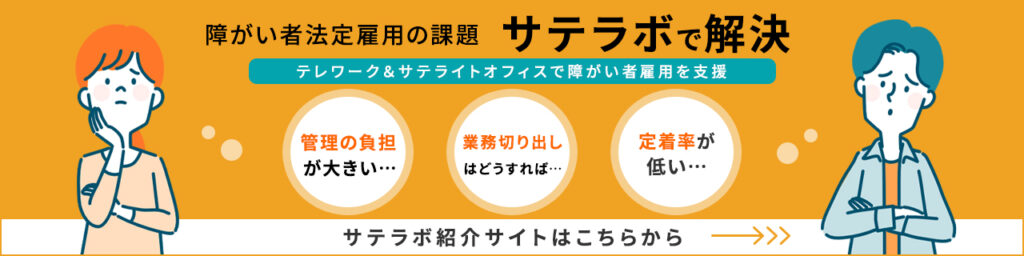
誕生した背景
特例子会社制度は、1987年の障害者雇用促進法の改正によって導入されました。
この制度は、一般の職場での障がい者雇用推進における企業の課題を解決し、法定雇用率の達成を支援する目的で誕生しました。
例えば、一般的な職場では配慮が難しい場面があったり、障がい特性に合わせた環境づくりや、柔軟な雇用管理が必要になることがあります。こうしたニーズに応える形で制度が生まれています。
特例子会社を設立することで、企業はより円滑に障がい者雇用を進められるようになり、障がいのある方々にとっても能力を十分に発揮できる環境が提供されることとなりました。
あわせて覚えておきたい制度
特例子会社制度のほかに、障がい者雇用の実雇用率を算定するための特例制度がいくつか存在します。そのうち、特に覚えておきたい2つの制度を紹介します。
企業グループ算定特例
平成21年4月から導入された「企業グループ算定特例」は、特例子会社を設立しなくても、親会社と関係子会社が所定の要件を満たすことで厚生労働大臣の認定を受け、企業グループ全体で実雇用率の通算を可能とする制度です。
グループ内に障がいのある方が就労しやすい業務を行う子会社がある場合、その子会社で雇用を推進することで、業務効率を重視しながらもグループ全体の障がい者雇用を両立できるというメリットがあります。
事業協同組合等算定特例
同じく平成21年4月から導入されたのが、「事業協同組合等算定特例」です。
これは、中小企業が事業協同組合や水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合などといった「事業協同組合等(特定組合等)」を通じて協同事業を行い、一定の条件を満たして厚生労働大臣の認定を受けた場合に適用される仕組みです。
この認定を受けると、組合とその組合員である中小企業(特定事業主)の間で、障がい者の実雇用率をまとめて計算できるようになります。
事業のつながり方や雇用管理の体制など、定められた要件を満たすことで認定を得ることができ、中小企業における連携した障がい者雇用を後押ししています。
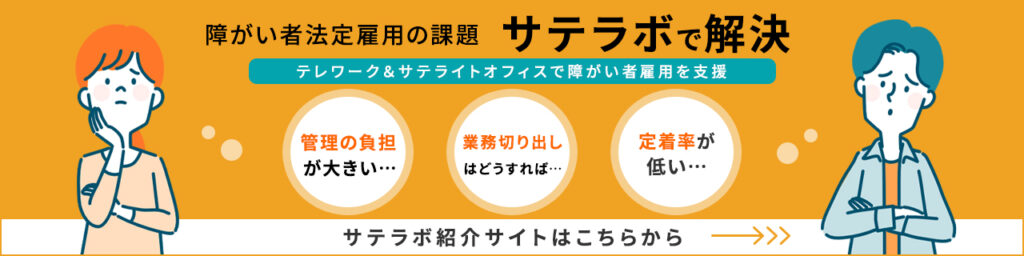
特例子会社と一般企業での障がい者雇用との違い
特例子会社と一般企業での障がい者雇用の違いは、主に雇用環境や支援体制にあります。
特例子会社は、障がい者雇用を目的に設立され、法定雇用率を本社と合算できる仕組みが特徴です。専門スタッフの配置や業務の配慮が充実しており、障がい者が働きやすい環境が整っています。
一方、一般企業では、通常の職場で他の従業員とともに働くことが多く、合理的配慮は求められるものの、特例子会社ほどの支援体制が整っていない場合があります。
どちらも障がいのある方の能力を活かすことが求められますが、職場環境やサポートの違いが大きなポイントです。
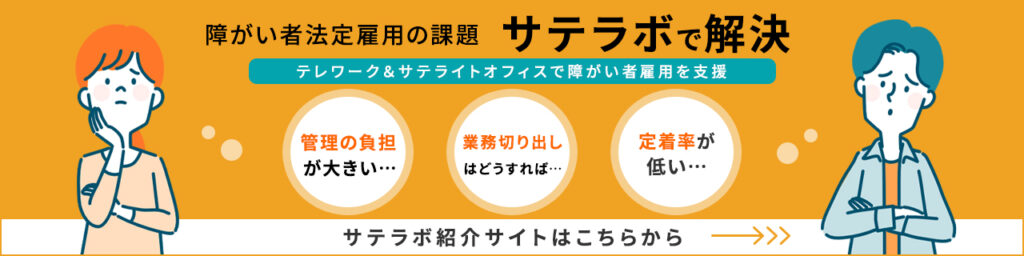
特例子会社は何社設立されている?
令和6年6月1日現在において、特例子会社として認定を受けている企業数は614社に上り、前年と比較して16社の増加がみられます。現在の日本の企業総数と比較すると、決して多くはないものの、着実にその数は増え続けています。
また、特例子会社で雇用されている障がい者の総数は、同日現在で50,290.5人に達しており、前年(46,848.0人)から大きく増加しています。
その内訳を見ると、知的障がい者が25,553.5人と最も多く、次いで身体障がい者が12,488.5人、精神障がい者が12,248.5人であり、特例子会社が多様な障がいのある方の雇用を担っていることが分かります。
特に精神障がい者の雇用者数は前年から大きく伸びており、雇用環境の整備が進んでいることが伺えます。
なお、特例子会社の考え方自体はかなり昔から存在しており、日本で初めて特例子会社として認定を受けたのは、45年以上前に誕生したシャープ株式会社の特例子会社(シャープ特選工業株式会社)で、長い歴史があります。
出典:厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」P2~3
特例子会社設立は企業にとってメリットが大きい
特例子会社を設立する際には、メリットとデメリットの両方を事前に知っておくことが重要です。ここではまず、設立によって得られるメリットについて紹介します。
・法定雇用率に算定できる
・障がい者の方に合わせた労働環境を整備しやすい
・柔軟な働き方の実現も可能
・特例子会社の離職率は低い
・企業のCSR・ブランディング向上
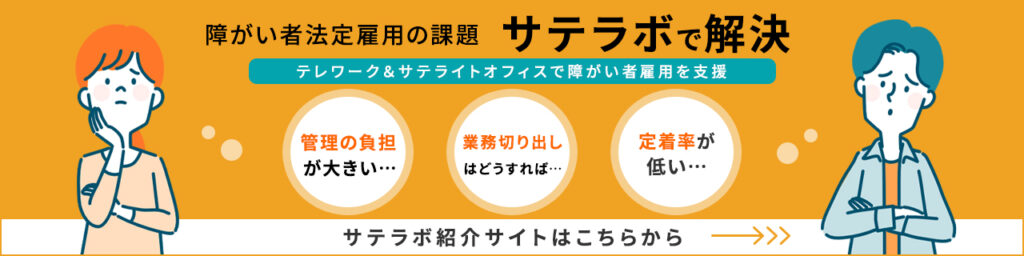
法定雇用率に算定できる
特例子会社で雇い入れた障がい者の数・割合は、親会社の法定雇用率に算定できます。
そのため、なんらかの理由で親会社で継続的に障がい者を雇い続けることが難しい場合でも、特例子会社で障がい者を雇用することによって、法定雇用率を下回った場合のペナルティを避けることが可能です。
障がい者の方に合わせた労働環境を整備しやすい
障がい者の方を雇い入れるときは、会社の労働環境を整えることが求められます。例えば、エレベーターを導入したり、車いすでも入りやすいトイレを作ったり、広めの休憩所を作ったりなどの工夫です。
この際、本社の一部を修繕・改修をするよりも、特定子会社として1から構築したほうが効率化できる場合があります。
柔軟な働き方の実現も可能
障がい特性によって、「仕事の能力は高いが、人との対面のやり取りが非常に大きなストレスになる」「体調の波が大きく、9時5時では働きにくい」「電車に乗るのが難しい」などのようなさまざまな事情を抱える方もおられます。
特例子会社を設立することで、そのような方々に対して、柔軟な働き方を提案しやすくなります。
例えば対面での打ち合わせなどは少なくしてメッセージでやりとりするようにしたり、完全フレックス制を導入したり、リモートワークを導入したりといったことが可能です。
特例子会社の離職率は低い
特例子会社の場合は離職率が低いということがデータからわかっています。
厚生労働省の調べた、障がい者の職場の離職率(1年後)は、最も少ない層でも28.5パーセントに達しています。特に精神障がい者の場合は離職率が高く、1年間勤め続けられる方は2人に1人以下です。
▼離職率が高い理由について詳しくはこちら
「障害者雇用が定着しないのはなぜ?離職理由と対策を解説」
しかし、特例子会社の場合はまったく異なった状況が見えてきます。
過去5年間の離職率を調べたデータでは、最も離職率が高い層(離職者数が1人~2人)であっても22.7パーセントにすぎず、10人以上20人未満および20人以上の離職者が出た特例子会社はそれぞれ10.0パーセントを切っています。
また、194社中33社(17.0パーセント)は、そもそも離職者を出していません。特例子会社で雇い入れることで定着率が高まり、そして定着した人材を自社にとって有益な人材に育てることができるようになるのです。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「多様化する特例子会社の経営・雇用管理の現状及び把握・分析に関するアンケート調査結果」P35
企業のCSR・ブランディング向上
特例子会社を設立して障がい者雇用を進めていくことで、「この企業は、社会貢献をしている企業である」「多様な働き方を推進している」として、顧客や取引先にポジティブな印象を与えやすくなります。
良い企業イメージを持たれている企業は、企業統治ができている企業であるとして、ESG投資の対象にもなりやすいといえます。投資を受けることは企業の成長にとってとても重要です。
特例子会社の設立およびその特例子会社での障がい者の雇い入れは、自社を成長させるきっかけともなるのです。
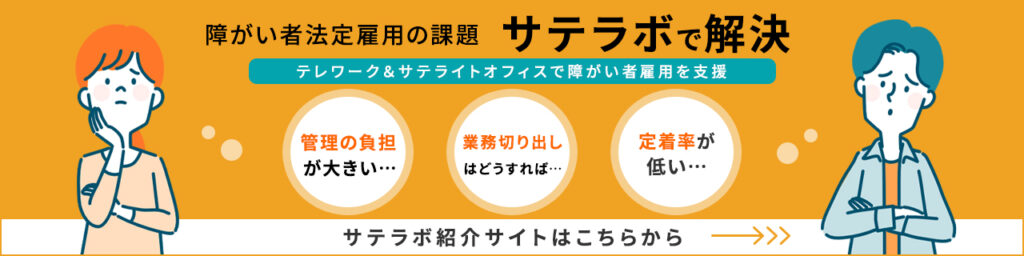
特例子会社設立のデメリット
特例子会社は多くのメリットがある一方で、その設立や運営にはいくつかのデメリットも伴います。ここでは、設立を検討する際に留意すべき点を見ていきましょう。
・管理職に負担が集中しやすい
・収益が確保できるかの問題がある
・本来の「障がい者雇用」の意味とずれることがある
管理職に負担が集中しやすい
障がい者雇用には、障がいを抱えていない方の雇用とはまた異なった負担が生じます。
特に精神に障がいを抱えている方を雇い入れる場合、それぞれの方に合ったツールの導入や、精神面でのサポートが求められます。
特例子会社はその特性上、比率として、障がいを抱えていない方の割合が少なくなりがちです。そのため管理職(や少数の社員)に負担が集中しやすく、ストレスとなる場合があります。
収益が確保できるかの問題がある
特例子会社は、設備を整えたり、障がいを持つ方が使いやすいシステムを導入したりする必要があります。そのため経営コストも高くなり、収益が出費を下回りやすくなります。
特例子会社もまた営利を目的とすることを考えれば、これは無視できないデメリットです。
また親会社の経営の影響を受けやすく、親会社の経営不振などによるダメージを受けやすい環境にあります。
本来の「障がい者雇用」の意味とずれることがある
特例子会社はもともと「どのような人でも社会で活躍できるように」という法律の下で作られたものです。
しかし特例子会社は、「親会社の法定雇用率を満たすためのもの」「独立化した場所」となりがちというデメリットがあります。
このため、親会社の社員の障がい者への理解が進まなかったり、雇用されている側もまたキャリアの限界を感じたりしてしまいがちです。
特例子会社の設立に向いている企業
特例子会社の設立に向いている企業は、一定数の障がい者を安定的に雇用できる規模の企業や、グループ全体で法定雇用率を満たしたい企業です。
例えば、以下のような企業が当てはまります。
・業務を切り出しやすい業種(事務、清掃、軽作業、ITサポートなど)
・障がい者の長期雇用やキャリア支援を重視したい
・専門スタッフを配置できる体制がある
また、CSR(企業の社会的責任)やダイバーシティ推進を重視する企業にとっても、特例子会社は有効な選択肢となります。
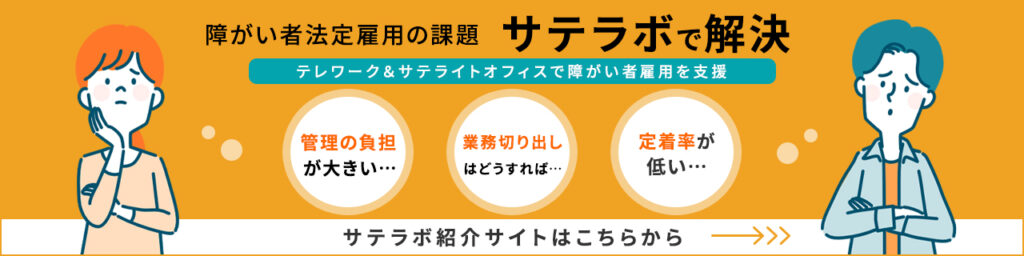
特例子会社の成功事例
ここでは、特例子会社を通じて、障がいのある社員の能力を最大限に引き出し、社会で活躍する機会を提供している企業の事例をご紹介します。
みずほビジネス・チャレンジド株式会社
みずほビジネス・チャレンジド株式会社は、みずほフィナンシャルグループの特例子会社です。主な業務は、親会社であるみずほ銀行の業務サポートであり、具体的には重要書類の電子化、帳票の印刷、書類の封入・発送、メール仕分けなどのバックオフィス業務の一部を担当しています。
同社の特徴的な取り組みとして、社員の自主性とモチベーションを高めるための仕組みづくりがあげられます。例えば、各期のはじめには「チャレンジシート」を用いて社員が自らの目標を設定する機会があり、また社員同士でOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)指導や人材育成を行う制度も設けられています。
さらに、社員講師による研修や、社員が自ら企画した拠点間交流による意見交換会なども実施され、社員の成長を多角的に支援しています。
株式会社王将ハートフル
株式会社王将ハートフルは、「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの特例子会社です。親会社の工場では店舗で提供される餃子の餡やスープなどの製造を行っており、王将ハートフルはそのうちキャベツ、ニンニク、玉ねぎといった主要食材の一次加工ラインを担っています。
王将ハートフルの成功の鍵は、社員のやりがいや成長に重きを置き、制度の整備を徹底している点にあります。具体的には、明確な役職制度や賃金制度、表彰制度などが整備されており、社員のキャリアパスを支援しています。
また教育面では、各種研修やOFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)を継続的に実施しているほか、指導員に対しても同様に研修を続けることで、全社的な指導・育成レベルの向上に努めています。
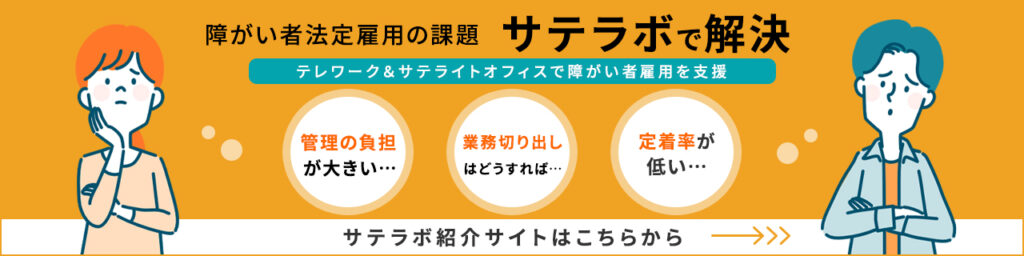
特例子会社設立のための条件
特例子会社を設立するための条件は以下の通りです。
①親会社と緊密な人間関係が保たれていること
②障がい者が相当数雇用されていること
③障がい者にとって、適切な労働環境が作られていること
④その他
①親会社と緊密な人間関係が保たれていること
親会社との連携を行っていることを証明できなければ、特例子会社の設立はできません。「まったく関係ないところに、まったく親会社の社員と関わることなく、運営していく名前だけの子会社」は、特例子会社とは認められていないのです。
ちなみにこの要件を満たす方法のひとつとして、「親会社から役員が派遣されている」などがあげられます。
②障がい者が相当数雇用されていること
特例子会社として認められるためには、
・雇用されている障がい者の数が5人以上
・かつ、全従業員中の20パーセント以上が障がい者であること
・雇用される障がい者のうち、重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の割合が30パーセント以上
であることが求められます。
つまり、「100人以上の子会社だが、軽度の重度身体障がい者が3人雇っているのみ」などの場合は、特例子会社の要件を満たしていないと判断されます。
③障がい者にとって、適切な労働環境が作られていること
例えば、必要とされるバリアフリー工事が施されていたり、専門的な知識がある指導員が専任で指導に当たっていたりすることなどが、この3の項目にあたります。
④その他
その他としては、障がい者の採用と、安定した働き方が達成できると判断されることが条件にあります。
また特例子会社はあくまで「子会社」であることもあり、親会社が子会社の意思決定機関を掌握していなければなりません。子会社の議決権を、半分以上親会社以外が持つことなどは認められていません。
出典:厚生労働省「「特例子会社」制度の概要」
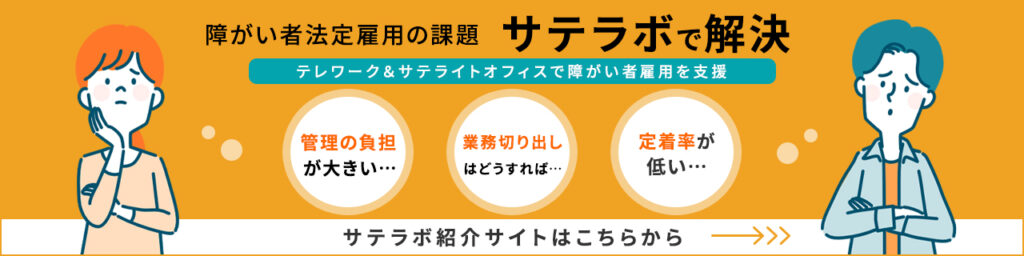
特例子会社設立までの流れ
最後に、特例子会社設立までの流れについて解説します。
1. 認定要件の確認
2. 書類の準備~設立のための手続き
3. 採用準備~採用
4. 特例子会社認定申請を出す
1.認定要件の確認
以下の条件を満たしているかを確認します。
①親会社と緊密な人間関係が保たれていること
②障がい者が相当数雇用されていること
③障がい者にとって、適切な労働環境が作られていること
④障がい者の採用と、安定した働き方がきちんと達成できると判断されること
2.書類の準備~設立のための手続き
要件を満たしていることが確認できたら、書類の準備を行います。特例子会社を設立するためには、子会社特例認定申請書や、子会社の社員名簿、子会社の図面など多くの書類が必要です。
また定款の作成を行い、官庁への届出を行う必要もあります。
3.採用準備~採用
採用準備を行い、障がい者の採用を行います。自社に必要な人材はどのような方か、どんな仕事を頼むべきかをまとめた上で採用をしていくと無駄がありません。
またこのときには、ハローワークの障がい者雇用担当者に相談すると、より良いアドバイスを受けることができます。
4.特例子会社認定申請を出す
特例子会社になるための認定申請は、障がいを持つ方を雇い入れて初めて可能になります。なお申請先はハローワークです。
※必要な書類については、厚生労働省がこちらにまとめています。
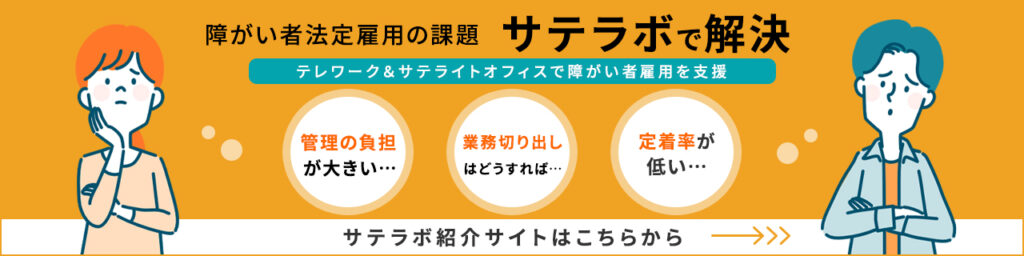
まとめ
これまで特例子会社について解説をしてきました。今回の内容をまとめると、以下の通りです。
・特例子会社の設立には数多くの書類が必要であり、条件を満たしている必要がある
・コストがかかりやすく、管理職に負担がかかりやすいので注意が必要
・しかし特例子会社は、「その子会社で雇い入れた方を、親会社の雇用する障がい者数として算定できる」という特徴を持っている
・離職率を低い数字で押さえられることで結果的に自社に有益な人材を育てることが可能になったり、ESG投資の対象として高く評価されやすくなるなどのメリットもある
特例子会社をつくる場合は、そのメリットとデメリットをしっかり比較し、検討していくことが求められます。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







