もにす認定制度とは?認定を受ける基準やメリットを解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.05.20
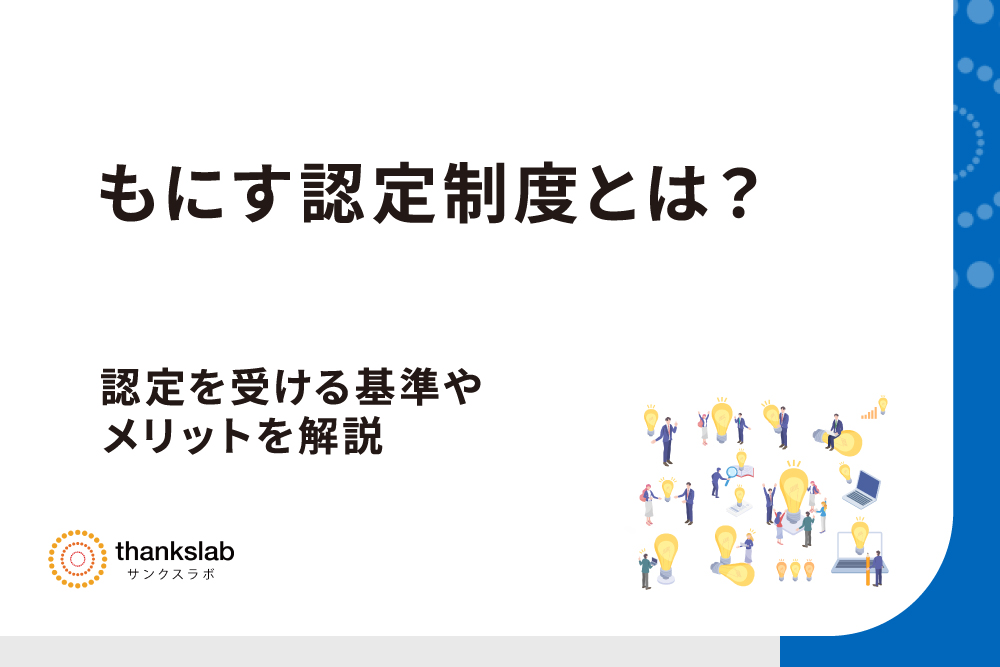
障がい者の雇用を前向きに検討している企業ならば「もにす認定制度」について一度は聞いたことがあるでしょう。「もにす認定制度は知っているが、取得すればどのようなメリットがあるのか?」と疑問を持っている方もいると思います。
本記事では、もにす認定制度の概要を説明するとともに、認定を受ける方法やメリットを解説します。障がい者を雇用している企業や、これから雇用を検討している企業は、制度を詳しく知っておくと何かと役に立つでしょう。ぜひ、最後まで読んで参考にしてください。
もにす認定制度とは?
「もにす認定」とは、「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」の略称です。厚生労働省が主催しており、300人以下の中小事業主が認定対象です。
「もにす」の相性は、「障がい者と企業がともに明るい未来へ進む」という目標に基づいて定められました。
もにすの認定基準
もにすは、認定対象になった事業主が申請することで厚生労働大臣から認定を受けられます。もにすに認定されるには、以下のような観点から審査を受ける必要があります。
- 障害者雇用への取り組み
- 数的・質的な面からの障がい者雇用の取り組み成果
- 情報開示
また、以下のような条件を満たす必要もあります。
- 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用している
- 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用している
それに加えて、かつて「もにす認定」を受けていたが取り消された経験がある場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していることが条件です。
もにす認定制度は、2022年よりはじまり最初に認定されたのは3件でした。もにす認定制度はまだ始まって10年未満の新しい制度で、まだ知名度も高いとはいえません。
しかし、障がい者雇用がもっと進めばもにす認定制度の知名度も上がってくる可能性は十分にあります。
もにす認定制度を利用するメリット
もにす認定を受けられると、さまざまなメリットがあります。ここでは、代表的なメリットとして以下の3つを紹介します。
- 自治体から優遇を受けられる
- 企業のイメージアップにつながる
- 働き方改革推進支援資金を有利な条件で受けられる
もにす認定について詳しく知りたい方はもちろんのこと、取得に前向きな企業の担当者も参考にしてください。
自治体から優遇を受けられる
もにす認定制度を利用すると、自治体から優遇を受けられる可能性があります。もにす認定を受けると、厚生労働省から認定マークの使用許可が受けられ、以下のような場所に使うことができます。
- 商品パッケージ(包装紙など)
- 会社及び商品の広告(もにす認定を受けました、と宣伝が可能)
- 取引や役所に提出する書類
- 営業所や事務所に掲示できる
- 公式サイトなどインターネット上
- 求人広告
つまり、さまざまな場所で「私たちは障がい者雇用に前向きであり、一定の成果を出しています」とPRできます。また、自治体にとっても障がい者雇用に前向きな企業が増えるのは大きなメリットです。
広報に利用したり、優先的に事業を依頼したりするなどするところもあるでしょう。
自治体で受けられる優遇は自治体ごとに異なるので、申請を検討している方は自治体のホームページ等から確認しておくことがおすすめです。
企業のイメージアップにつながる
障がい者雇用に前向きであり、一定の実績がある企業は消費者や取引先はもちろんのこと、社会全体からプラスのイメージを持たれます。小さな企業であっても、障がい者雇用をきっかけに知名度が上がる可能性は十分にあるでしょう。
また、障がい者雇用をきっかけに新しい仕事を創成した場合は、全国規模で宣伝できる可能性があります。このほか、企業がイメージアップすれば有利な条件で銀行などから融資を受けられる可能性も高まるでしょう。
イメージアップは企業にとって大いにプラスに働きます。イメージアップのために費用をかけてCMを作成している企業も珍しくありません。しかし、もにす認定を受けられれば、それだけで大きな宣伝になる可能性もあるでしょう。
働き方改革推進支援資金を有利な条件で受けられる
「働き方改革推進支援資金」とは、日本政策金融公庫が実施している融資制度であり、働き方改革に取り組むための設備資金や長期運転資金とすることを目的とした貸し付けです。一例を挙げると、「働き方改革推進支援資金(国民生活事業)」では最大7,200万円、「働き方改革推進支援資金(中小企業事業)」では最大7億2,000万円の融資が受けられます。
働き方改革には、非正規雇用の処遇改善や障がい者雇用の促進も含まれます。例えば、障がい者が働きやすいように、読み上げ機能があるパソコンソフトを導入する、スロープを付けるといったことにも費用を使えます。
もにす認定を受けられれば、信用度が高まって有利な条件で受けられる可能性があるでしょう。日本政策金融公庫は、一般的な金融機関より企業にとって有利な条件で受けられる融資が複数用意されています。その分審査が厳しい傾向があるので、もにす認定を受けられた企業と、受けられない企業では融資を受けられる金額に差が出る可能性もあるでしょう。
もにす認定制度の認定基準
ここでは、もにす認定制度の設定基準をもう少し詳しく紹介します。もにす認定制度は日本に本拠地を置く中小企業が対象です。自社が条件に当てはまっているか事前に確認してみてください。
認定される会社の規模
前述したように、もにす認定制度の認定を受けられるのは常時雇用する労働者数が300人以下の企業が対象です。常時雇用とは、以下のような条件を満たした労働者です。
- 雇用期間が無期限である
- 有期雇用の場合は、過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されているか、雇い入れ時期から1年以上引き続き雇用されると見込まれる
なお、雇用形態は問われません。正社員だけでなくパートやアルバイトも該当します。その一方で、上記2点を満たさなければ「常時雇用」には該当しません。例えば、従業員が1,000人いたとしても、常時雇用が300人以下ならば「もにす認定制度」の対象になります。
したがって、従業員の総数が300人ではないことを覚えておきましょう。
雇用される障害者の数
雇用される障がい者の数は、民間企業の法定雇用率は2.5%を満たしている人数です。例えば、40人常時雇用されている職場ならば1人以上雇用されていれば条件を満たしたことになります。さらに、指定就労継続支援A型の利用者以外で雇用率制度の対象障がい者を雇用していることも条件です。
なお、常時雇用している従業員が39名以下で雇用義務がある障がい者が0人であっても、実際に障がい者を雇用していれば、申請が可能です。つまり、障がい者を雇用している企業ならば、条件を満たしていれば問題なく申請できます。
その一方で、就業時間が週10時間未満のなど、雇用率制度の対象障がい者に含まれていない障がい者は数に含まれないので注意してください。
取組・成果・情報開示が評価される
もにす認定をうける審査要綱は、取組・成果・情報開示の3点です。
取組とは、障がい者が働きやすい環境づくりや障がい者がやる気を持って取り組めるように仕事の創成、さらに、障がい者をサポートできる組織作りを指します。例えば、障がい者を雇用しても、簡単な仕事しか与えない、障がい者がすぐにやめてしまうといった職場では審査に合格しません。
成果は、雇用状況などの数的側面とキャリア形成などの質的側面の両方が審査されます。障がい者を雇っても、単純作業だけに従事してもらってキャリア形成に貢献していない場合は、評価されません。ただし、キャリア形成の内容は障がいの程度や職種によって異なります。
例えば、製造業ならば障がい者が数カ月かけて不良品を出さずに製造ができるようになったらキャリア形成に貢献したと評価される可能性があります。
このほか、開示とは取組や成果をオープンにしているかどうかです。この3つの評価基準には最低点が定められており、もにす認定を受けるには最低点をクリアしつつ、3分野合計で20点以上(特例子会社は35点以上)を取得することが条件となっています。
もにす認定を受ける流れ
もにす認定を受ける流れの基本は、以下のとおりです。
- 厚生労働省のホームページから、申請書類をダウンロードする
- 都道府県労働局に申請書類を提出する
- 都道府県労働局による認定審査を受ける
なお、ハローワークを通しても申請は行えます。労働局が近くにない場合や、ハローワークのほうが申請しやすい場合はハローワーク経由で提出してください。
また、審査はハローワークの職員が職場に調査に訪れ、口頭による質問もあります。
そのため、虚偽の報告をしても訪問でバレる可能性は非常に高いでしょう。申請書類は正確に記入してください。
補正の指示や申告書の再提出が求められる場合もあります。
審査の結果が出るまで2~3か月ほどかかります。認定された場合は「基準適合事業主認定通知書」が送付され、認定が見送られた場合は「評価基準採点表」と「基準適合事業主不認定通知書」が送付されるので、不合格になったら採点表を確認して何が足らかったのか確かめてみましょう。再申請も可能です。
まとめ
もにす認定はまだはじまって10年未満の新しい制度であり、知名度もそれほど高いとはいえません。しかし、これから障がい者を雇用する企業が増えるにつれ、メリットも大きくなっていくことが予想されます。企業のイメージアップにも役立つので、チャンスがあったら申請をしてみるのがおすすめです。
自治体や国に積極的に企業の宣伝をしてもらえる可能性もあります。必要ならば、ハローワークで詳細を聞いてみてもいいでしょう。厚生労働省の管轄機関なので詳しく教えてもらえます。
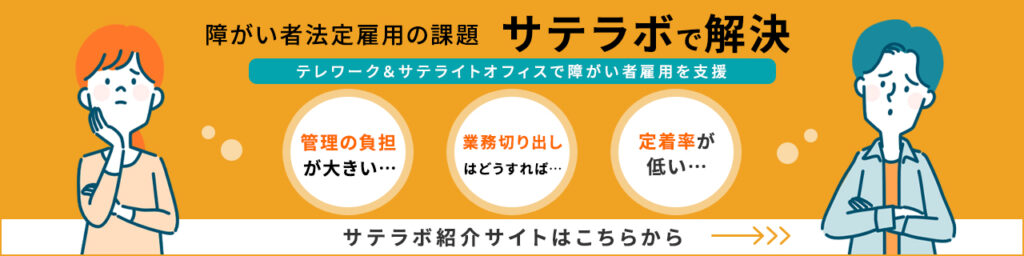
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







