障害者雇用のみなし雇用とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.05.23

障がい者のみなし雇用制度とは、障がい者を直接雇用しなくても「就労継続支援事業所」等に事業を発注するなど一定の条件を満たせば障害者の法定雇用率に変換できる制度です。
日本ではまだ制度化されていませんが、ヨーロッパの一部の国では、制度化されています。
本記事では、障害者のみなし雇用制度が導入された場合のメリットやデメリットをわかりやすく解説します。障害者のみなし雇用制度に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
障害者雇用におけるみなし雇用とは
みなし雇用とは、労働者を雇用するにあたって満たす必要がある雇用条件が満たされていない場合でも、「法律上、直接雇用しているものとみなす」と定めた制度です。
もともとは違法な条件で派遣されている非正規の労働者の権利を守るために生まれました。
一方、障害者雇用におけるみなし雇用とは、企業が就労継続支援事業所などに一定以上の量を継続して発注したなど定められた要件を満たした場合、障害者雇用の法定雇用率に換算することができる制度です。
日本ではまだ導入されていませんが、フランスなど一部の国では導入されていました。そのため、日本でも導入を望む声は多いです。その一方で、企業が障がい者雇用に消極的になったり、障がい者の自立がしにくくなるのではないか、といった懸念もあります。
障がい者をみなし雇用するメリット
障がい者の方をみなし雇用するメリットには以下のようなものがあります。
- 直接雇用以外の方法でも法定雇用率を満たせる
- 障がい者が働く選択肢が増える
- 調整金の支払いだけでなく法定雇用率に換算できる可能性がある
直接雇用以外の方法でも法定雇用率を満たせる
現在の障害者雇用促進法では、法定雇用の条件が明確に定められています。そのため、条件を満たさない働き方をしていても、法定雇用率に影響しません。法定雇用の条件は障害者が安心して働けるために定められたものですが、業種によっては障がい者の雇用を難しくしている側面もあります。
みなし雇用が認められれば、直接雇用しなくても障がい者の雇用促進に貢献できます。
例えば、障がいを持つ方々がストレスなく働ける「就労継続支援事業所」に仕事を発注することで法定雇用率に換算できれば、いろいろな会社が手軽に障がい者雇用に関わることができるでしょう。現在では法定雇用率に換算できない働き方もみなし雇用ならば認められる可能性があります。
障がい者が働く選択肢が増える
現在の障害者雇用促進法では、原則として週に20時間以上働かないと法定雇用率の達成に影響しません。
そのため、障がい者雇用を義務付けられている会社は、週20時間以上働ける方を対象に求人を行うことが多いです。
障がい者の中には、「週20時間も働くのは厳しい」「現在は週10時間未満しか働けないが、仕事に慣れたら働く時間を増やしたい」というケースもあるでしょう。また、障がいをよく理解しているサポーターがいたり住宅で仕事をしたりすればスムーズに働けるといったケースもあります。
みなし雇用が認められれば、障がい者が働く選択肢が増えます。みなし雇用であれば、「週何時間以上働かなければならない」といった明確な決まりを満たさなくても、法定雇用率に換算が可能です。
みなし雇用が認められれば、より多くの障がい者が就業のチャンスに恵まれることでしょう。
調整金の支払いだけでなく法定雇用率に換算できる可能性がある
障がい者を雇用している場合、障害者雇用納付金制度が利用できます。制度の中には、特例調整金、または特例報奨金と呼ばれるものがあります。
この調整金や報奨金は、在宅で仕事をしている障がい者に仕事を発注した場合や、在宅就業支援団体を通して仕事を発注した場合に利用できます。
障がい者を雇用する会社の負担を減らすために設けられている制度ですが、現在のところ在宅で仕事をしている障がい者は、仕事をしても法定雇用率に換算されません。
そのため、調整金が支払われるといっても、在宅仕事ができる障がい者への仕事の依頼の促進が進みにくいのが現状です。
みなし雇用が認められれば、調整金が支払われるだけでなく法定雇用率に換算できるようになります。そうすれば、在宅で仕事ができる障がい者の就業にも貢献ができるでしょう。
障害者をみなし雇用するデメリット
一方障がい者みなし雇用を導入すると障がい者を直接雇用する企業が減ってしまう恐れがあります。障がい者を雇用するには、会社の設備を整えるだけでなく従業員への障がいに対する理解を深める教育も必要です。
また、会社が障がい者を直接雇用することで、多様性を受け入れる社会の実現にも貢献しています。しかし、みなし雇用が認められてしまえば、「就労継続支援事業所」などに就業できる障がい者が集められてしまう可能性もあります。
さらに、就業できる障がい者が特定の場所に集められたり、住宅にこもったりしてしまうと健康な方と障がい者の分断が進む恐れもあるでしょう。
それに加えて、みなし雇用が中心になってしまうと、障がい者が就業できる仕事が限られてしまう恐れがあります。
みなし雇用に近い制度はすでに始まっている
現在でも、就労継続支援事業所などに発注すると、特例調整金や特例報奨金が支給される制度は行われており、調整金や報奨金が利用できるといった理由で就労継続支援事業所に仕事を発注したり、在宅仕事をしている障がい者と業務委託契約を結んだりする会社もあります。
仕事によっては、従業員やサービスを受ける人の安全性を理由に障がい者の雇用が難しい会社もあるでしょう。みなし雇用にはデメリットもありますが、それを解消できる仕組みができれば、導入される可能性もあります。
ちなみに、フランスでは2018年までみなし雇用制度が認められていました。しかし、その後直接雇用が上昇しないことを理由に廃止されています。日本でも期間を限ってみなし雇用制度が導入される可能性もあるかもしれません。
まとめ
みなし雇用制度は、「就労継続支援事業所」などに一定量の仕事を発注したり在宅で仕事をしている障がい者と業務委託契約を結んだりすれば、直接雇用とみなすという制度です。
日本ではまだ導入されていませんが、特例調整金や特例報奨金等の助成金が利用できる制度はすでに始まっています。もし、みなし雇用制度が導入されれば、障がい者が就業できる職種や勤務形態がより幅広くなるといったメリットがあります。
ただし、みなし雇用を導入すれば直接雇用が減ってしまうといったデメリットもあるので、期間限定で導入するなどの対策は必要になるでしょう。
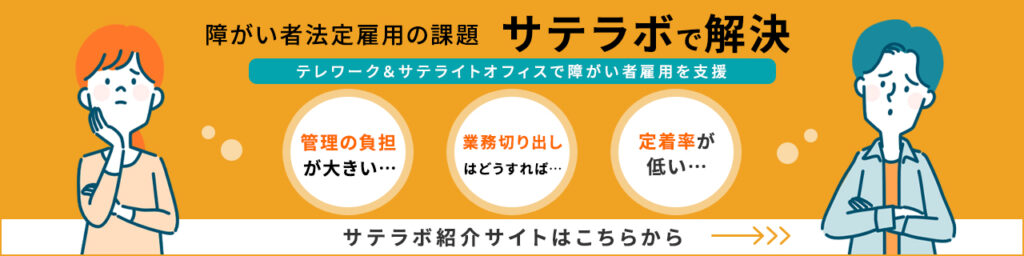
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







