精神障がい者のカウント方法は?採用・雇用の成功ポイントも解説
- 公開日:
- 2026.01.30
- 最終更新日:
- 2026.02.06
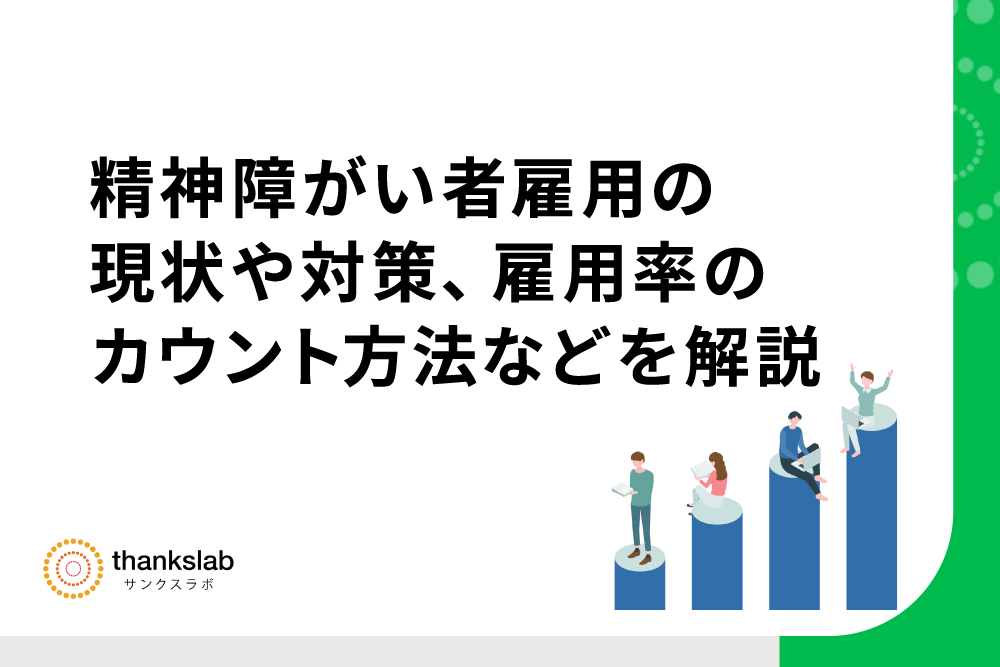
精神障がいをお持ちの方の雇用を考えている方の中には、採用に不安がある方も少なくないかと思います。
今回は、障害者雇用の中でも、精神障がい者に焦点を当てて、精神障がい者雇用の現状や、雇用率のカウント方法、採用するにあたっての対策方法などについて解説をします。
これから精神障がい者の方を採用しようと考えている方は参考にしてみてください。
また、すでに精神障がい者を雇用しているが離職率が高いことに悩んでいる方のために、定着率を上げるための方法をわかりやすくまとめた資料もご用意しています。
>>【資料をダウンロードする】精神障がい者の特性に合わせた雇用のポイント
目次
法定雇用率のカウント対象となる精神障がい者の等級
精神障がい者を雇用する場合、法定雇用率のカウント対象となる障がい者は、以下の通りです。
・精神障害者手帳の1級(他の方の手助けなくしては日常生活を送るのが難しいレベル)
・2級(生活を送れないわけではないが、大きな困難があるレベル)
・3級(日常生活を送れるが、支援は必要なレベル)のいずれかを交付されている方のみです。
精神障がい者を雇用する場合のカウント方法
精神障がい者のカウント方法は、手帳の等級が1級・2級・3級のいずれであっても、週30時間以上の雇用で「1」、週20時間以上30時間未満で「1」、週10時間以上20時間未満で「0.5」とカウントされます。
精神障がい者は、重度の身体障がい者・知的障がい者のようにダブルカウントされない点には注意が必要です。
なお、身体障がい者の場合、重度であれば、30時間以上働く方は「2」、20時間以上30時間未満の場合は「1」、10時間以上20時間未満の場合は「0.5」とみなされます。
対して重度に属さない身体障がい者の場合は、それぞれ「1」「0.5」「カウントなし」とされます。これは知的障がい者の場合でも同様です。
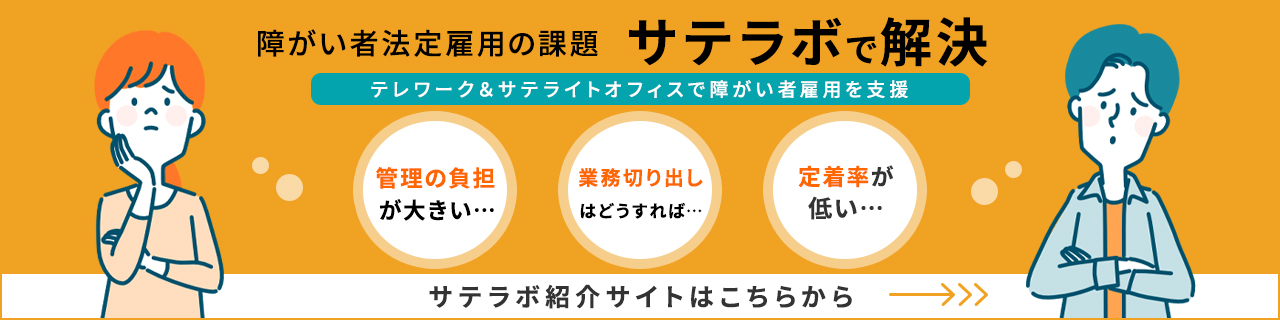
障がい者雇用率のカウントに活用できる計算フォーマット
サンクスラボが提供する「障がい者雇用率計算フォーマット【2025年最新版】」を活用すれば、従業員数や障がい者雇用数を入力するだけで、必要な雇用人数・不足数・実雇用率を自動で算出できます。
2026年施行の法定雇用率2.7%や除外率制度にも対応しており、計算作業は最短5分で完了します。
▼無料でダウンロードする
「障がい者雇用率計算フォーマット【2025年最新版】」
精神障がい者の採用に向けて知っておきたいこと
ここからは、精神障がい者の採用を取り巻く現状について見ていきましょう。
精神障がい者を雇用したい・雇用しなければと考えている事業者が押さえるべきは、以下の3点です。
・精神障がい者の雇用人数は、身体障がい者に比べて少ない
・正社員雇用で働いている精神障がい者は3人に1人以下
・定着率が最も低いのも精神障がい者
ひとつずつ見ていきましょう。
精神障がい者の雇用人数は、身体障がい者に比べて少ない
精神障がい者の雇用人数は、身体障がい者に比べて少ないという現状があります。
厚生労働省が出した「令和5年障害者雇用状況の集計結果」では、雇用されている身体障がい者の数は26万人を超えていますが、精神障がい者の雇用人数は13万人を切っています。つまり、精神障がい者の雇用率は、身体障がい者の半分以下ということです。
しかし内閣府が出したデータでは、「人口が1000人いると仮定した場合、身体障がい者の人数は34人であり、精神障がい者の数は33人である(補足:知的に障がいを抱える人は9人)」とされています。
つまり、身体障がい者の割合と精神障がい者の割合はほぼ等しいものであるにも関わらず、「雇用」の枠組みで見たとき、その差は2倍以上にもなるといういびつな違いが生じているということです。
これは制度上の問題などもありますが、「精神に障がいを抱えている方を雇うこと・雇い続けることが、事業者にとってかなり難しいこともある」という事実を表したデータと読めます。
正社員雇用で働いている精神障がい者は3人に1人以下
また、「正社員(正規雇用)」で働いている精神障がい者の割合の低さも、上記で述べた「精神障がい者の雇用は、事業者にとってかなり難しい面もある」ということを裏付けています。
精神障がい者の正社員雇用率は32.7%に留まり、これは身体に障がいを抱える方に比べて26%以上も低い数字です。同データでは精神障がい者と発達障がい者を分けて統計を取っていますが、後者でもその数字は36.6%に留まります。
「精神障がい者は、他の障がいを抱えている方に比べて、働く時間が短い(働ける時間が短い)」という点は、障がい者の採用において重要なポイントとなるでしょう。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します」
精神障がい者の定着率は低い
精神障がい者の雇用は、定着率の課題もあげられています。
NIVR障害者職業総合センターが2017年に出した統計結果では、就職後1年目の定着率を比較した場合(就職した時点を100とする)、発達障がい者の場合は72%程度、知的障がい者の場合は68%、身体障がい者の場合は61%程度であるのに対して、精神障がい者の場合は49%台と、唯一50%を切っています。
つまり、2人に1人以上が、1年後には仕事を辞めているということです。
このような現状だけを見ていれば、事業者として「本当に採用できるのだろうか」「採用したとして、自社に有益な人材に育ってくれるか」と不安に思うのはごく当たり前のことだといえます。
しかし、やり方を見直し、適切なアプローチを工夫することで、雇用される側にとっても、雇用する側にとっても有益な関係を築くことができます。
次項では「精神障がい者を雇い入れる事業者にとって有効な策」について取り上げていきます。
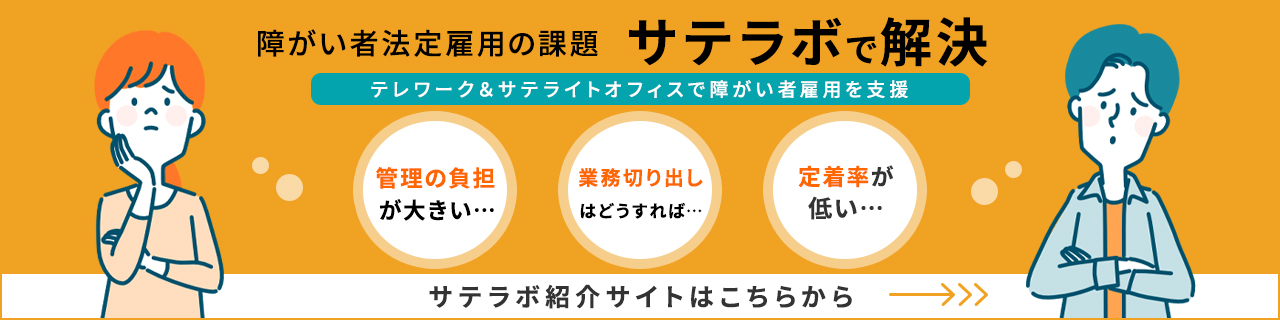
精神障がい者の雇用を成功させるポイント
精神障がい者を雇い入れようとするとき、できるだけ離職せず定着して欲しいと考えている方も多いかと思います。
定着率を上げる対策として以下のようなものがあります。
・精神障がいの特性や症状について理解する
・精神障がいに合わせた職場環境を整える
・リモートワークの実施
・連絡ツールを見直す
・医療機関との連携
それぞれ詳しく説明します。
精神障がいの特性や症状について理解する
精神障がいは、人によって特性や症状に違いがあります。なかには、うつ病や統合失調症、てんかんなど、複数の症状や特性が重なっているケースも少なくありません。
そのため、まずはそれぞれの症状や特性を理解すること、そして本人の性格や状態を把握した上で適切に関わることが重要です。こうした配慮を通じて、働きやすい職場環境を整え、より良い成果を引き出すことが可能になります。
精神障がいに合わせた職場環境を整える
精神障がい者に合わせた配慮を行い、業務の割り振りや働く環境を整えることで、定着率アップを目指せます。
例えば、
「人と接することに強いストレスを感じる」
「仕事は問題なくこなせるが、臨機応変や即時対応を求められるのが苦手」
などのような方に対しては、メールなどで完結できる(あるいは仕事の大部分をメールで済ませられる)仕事を振ると良いでしょう。
また、デスクをパーテーションで区切ることなども有効です。マニュアル化して、「するべき仕事」「手順」「やり方」を可視化するのも非常に有効です。個々人の得意とする仕事を把握しておき、その仕事を積極的に割り振っていくのもひとつの手です。
また、薬を飲みやすい環境を用意したり、フレックス制を導入したりすることで、その方の体調に合わせた働き方が可能になります。
精神障がいを抱えた方がストレスを感じずに働ける環境を整えることで、結果的に事業者の利益も上げやすくなります。
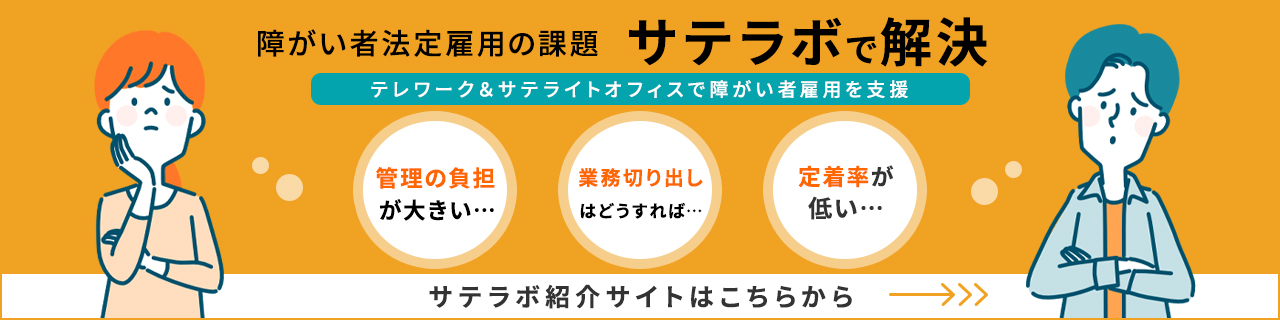
リモートワークの実施
精神を患っている方の中には、広場恐怖症(不安に襲われたときに逃げ場がない公共交通機関などを利用することを、恐怖する症状)などに罹っている方も多いため、「通勤そのもの」がストレスになることもよくあります。
このような状況を避けるためには、在宅勤務・リモートワークの実施が有効です。通勤の負担を減らすことで、本人が持つ能力を業務により集中して発揮できる環境を整えられます。
連絡ツールを見直す
精神障がい者の中には、「人と話すこと」や「臨機応変な対応」が苦手な方も少なくありません。そのため、対面ではなく、メールやチャットを使った連絡ツールを中心としてやり取りをしていくのもひとつの方法です。
ただ、上司や同僚からのフォローがないと不安に感じたり、一人で仕事をしていると孤立感が強まる方もいるため、定期的に面談を行ったり、声かけを行ったりすることは重要です。
医療機関との連携
精神障がい者を雇い入れ、また彼らに生きがいを持って働いてもらい自社の利益を得るためには、医療機関との連携も必要です。
精神障がい者の就労において医療機関は重要な役目を担っており、企業側に対しても「精神障がい者を雇う上での不安を教えてください」などの働きかけや、産業医との連携を図るなどのサポートを行っています。
医療機関としっかり連携をとることで、障がいを抱える方はもちろん、事業所にとっても安心できる職場を整備することが可能です。
まとめ
これまで精神障がい者の採用について解説をしてきました。事業者にとって、「社員の働きやすい環境」を整えることは非常に重要です。
今回の内容をまとめると、以下の通りです。
・精神障がい者も法定雇用率のカウント対象となる
・精神障がい者をとりまく就労の実態は厳しく、身体障がい者と比べて、正社員での採用率も、正社員として働いている方の割合も、定着率も低い
・しかし7年前に比べると数字は大きく改善している
・精神障がいに合わせた配慮やリモートワーク、医療機関との連携で、精神障がい者にとっても、それ以外の方にとっても、働きやすい環境を整備できる
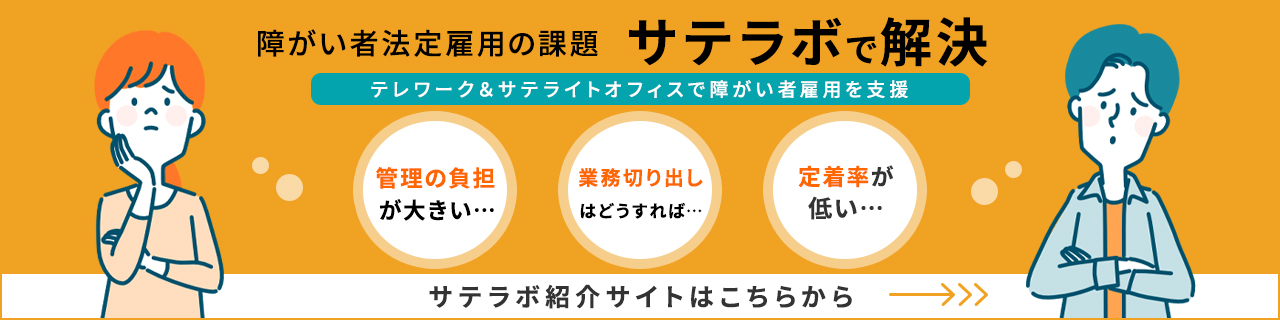
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







