障がい者法定雇用率の引き上げはいつから?今後の予定となぜ上がるのか解説
- 公開日:
- 2025.02.13
- 最終更新日:
- 2026.01.07

企業が障害者を雇用する場合、法定雇用率について理解を深めておくことが大切です。
法定雇用率は今まで約5年ごとに改正されており、年々引き上げが実施されている傾向にあります。法定雇用率が未達成の企業はリスクがあるため、十分に注意が必要です。
しかし、経営者のなかには「法定雇用率がどういったものかわからない」という悩みもあるでしょう。当記事では、法定雇用率の詳細から段階的な引き上げ、計算方法まで詳しく解説します。
未達成時に取り組むポイントや活用できる助成金、注意点なども紹介するので、ぜひ参考にご覧ください。
目次
法定雇用率とは
法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障害者の雇用率を指します。
法定雇用率は障害者雇用率制度のもとに割合を算出しており、障害者雇用を促進するために一定以上の割合で民間企業や国・地方公共団体に義務付けられています。
労働市場において障がいのある方は一般の就労者に比べて働きづらいため、障害者雇用率制度によって雇用機会を均等にする目的があります。
雇用義務のある企業について
障害者の雇用義務は法定雇用率によって大きく変動し、改正されたパーセンテージによって決定されます。2024年4月の改正では法定雇用率が2.5%となっており、2026年7月から2.7%に引き上げられます。
現時点では2024年4月の改正が反映されているため、従業員数40人以上の企業は障害者の雇用義務があります。そのため法定雇用率を定期的にチェックし、自社の従業員数と比較しながら該当するか判断するようにしましょう。
自社の障がい者雇用率がいま何%か把握したい方のために、数値を入力するだけで実雇用率・必要人数・不足数がすぐにわかる計算フォーマットをご用意しています。
法定雇用率2.7%に引き上がった場合のシュミレーションにも対応しているので、ぜひ現在の状況把握にご活用ください。
>>【法定雇用率2.7%対応】障がい者雇用率計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
障害者雇用の除外率制度について
除外率制度とは、障害者の就業が難しいと認められる業種に向けて、雇用義務を軽減するために制定された制度です。対象となる業種は、雇用労働者数を計算する際に除外率に相当する労働者は控除されます。
現時点では除外率制度が廃止されているものの、除外率設定業種ごとに除外率を設定する流れとなっています。
厚生労働省の公表によると、現在除外率が設定されている全ての業種で一律10%ずつ引き下げられる予定です。
今後の法定雇用率の引き上げ率
法定雇用率は年々引き上げ率が上昇している傾向にあり、民間企業は雇用している従業員数によって障害者の雇用が必要です。
今後更に法定雇用率が引きあがっていくと、未達成となってしまうという企業も増加すると考えられるため課題に感じている方も多いかと思います。
現時点では2024年4月の改正が対象となっており、法定雇用率は2.5%です。一部の業種を除き、従業員数が40名以上の企業は障害者雇用率制度の対象となります。
また、今後は2026年7月から法定雇用率は2.7%と上昇するため、従業員数37.5%以上の企業が対象に変わります。
例えば2024年4月の改正をもとに説明すると、300人の従業員を雇用している企業では7名の障害者雇用が義務付けられる仕組みです。
現在では法定雇用率の対象になっていなかったとしても、段階的な引き上げによって障害者の雇用が義務付けられる恐れがあると理解しておきましょう。
法定雇用率引き上げの背景
なぜ法定雇用率が段階的に引き上げられるのかについては、「障がい者の活躍の場を拡大する」という政策課題が背景にあります。
2023年1月18日に開催された第123回労働政策審議会障害者雇用分科会において、障がいのある方が更に活躍できる場を拡大させるために、厚生労働省は段階的に法定雇用率の引き上げを決定しました。
法定雇用率の未達成時に発生する問題
障害者の雇用対象義務となる企業は、毎年6月1日に雇用状況を所管のハローワークに報告しなければいけません。報告内容から法定雇用率が未達成の場合、以下のような問題が発生します。
- ハローワークからの行政指導
- 不足人数1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を徴収
ハローワークからの行政指導
法定雇用率が未達成になると、ハローワークから障害者雇入れ計画作成の命令が発出されるケースがあります。
障害者雇入れ計画の作成発出基準は、以下の通りです。
- 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
- 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
- 雇用義務数が3~4人の企業であって雇用障害者数が0人
障害者雇入れ計画作成の命令が発出された場合、その後の1月1日から2年間の障害者雇入れ計画を作成する義務があります。
もし計画に基づいた雇用状況の改善が見られないときは、特別指導や企業名の公表といったリスクがあるので注意が必要です。
不足人数1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金を徴収
法定雇用率が未達成になっていると、不足人数1人当たり月額50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます。
障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用促進と安定を図るために設けられた制度です。 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図り、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的としています。
雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金を徴収することで、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給する制度となっています。
障害者雇用納付金については以下の記事で詳しく解説をしています。
関連記事:障害者雇用納付金とは?計算方法や申告期限などわかりやすく解説
法定雇用率に関する障害者雇用率の計算方法
法定雇用率にもとづいた障害者雇用率の計算方法として、以下のような計算式で算出します。
自社の法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率(2.5%)
常用労働者とは1週間の労働時間が30時間以上の従業員を指しており、短時間労働者は1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の従業員のことです。
それよりも労働時間が短いアルバイトやパートは、対象となりません。
例えば、9時間勤務の正社員が100人と週20〜30時間勤務のパート従業員が10人いるなら、自社で雇用する障害者の数は(100 + 10×0.5)×2.5%=1.37人となります。
小数点は切り捨てるので、この場合は1人の障害者雇用が必要です。障害者雇用率の計算は障がいの種類や勤務時間の長さによって計算も変わるため、計算の手間を省きたい方は計算フォーマットをご活用ください。
▼障害者雇用率を半自動で計算
>>【法定雇用率2.7%対応】障がい者雇用率計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
雇用対象となる障害者の種類
企業の雇用対象となる障害者には、以下のような種類があります。
- 身体障がい者:身体障害者手帳1~6級に該当する人
- 知的障がい者:児童相談所等で知的障害者と判断された人
- 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
精神障害者保健福祉手帳には有効期間が設けられており、対象者と有効期間を把握することが大切です。
障害者の種類によって任せる業務も異なるため、企業側は事前に雇用環境の準備が必要になるでしょう。
法定雇用率の未達成時に取り組むポイント
法定雇用率の未達成時には、以下のような取り組むポイントがあります。
- 転職サイトを利用する
- 障害雇用支援サービスを利用する
- ハローワークに相談する
それでは詳しく説明します。
障害者雇用向けの転職サイトを利用する
障害者を雇用するには、転職サイトの利用がおすすめです。転職サイトに求人を出すことで、条件の合った障害者とマッチングできるようになります。
インターネットには障害者雇用に特化した転職サイトもあるため、求人を探している障害者に情報を届けられます。
一般的な求人サイトにも掲載できますが、求人情報には障害者雇用であることを必ず記載しておきましょう。
障害雇用支援サービスを利用する
効率良く障害者を雇用したいなら、障害雇用支援サービスを利用しましょう。
障害雇用支援サービスでは担当のスタッフからアドバイスを受けることができ、どのようにして障害者雇用を進めればいいのか提案してもらえます。
業務創出や採用のサポートも得られるため、障害者の働き方や採用基準を明確化できます。
当社が展開している「サテラボ」は、障害者雇用に関する幅広いサポートを提供しているサービスです。障害者の職場定着率99.3%と業界最高水準であり、企業で長期的に働ける従業員を創出しています。
初期費用は無料で今だけお試し導入キャンペーンを実施しているので、ぜひ気軽にご相談ください。
ハローワークに相談する
障害者の雇用に関する悩みや不安があるときは、ハローワークに相談することも大切です。
ハローワークでは障害者雇用の相談を受け付けており、支援方法や助成金制度などを紹介しています。障害者に向けた求人票の掲載も行っているため、総合的な支援を受けることが可能です。
法定雇用率の未達成時に発生するリスクについてもアドバイスを受けられるので、対策方法について考えられます。
障害者雇用で活用できる助成金
障害者雇用にはコストがかかるため、国や自治体が展開している助成金の活用がおすすめです。
こちらでは、障害者雇用で活用できる助成金について紹介します。詳細や特徴について詳しく説明するので、ぜひ参考にご覧ください。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、障害者を試行的に雇い入れた事業主や週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して支給される助成金です。
トライアル雇用助成金には「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2種類があり、それぞれ受給要件が異なります。
詳細については、厚生労働省の対象ページをご参照ください。
参考URL:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、雇用する障がい者の職場定着のための措置を行う事業主や、職場適応援助者による障がい者の職場適応の援助を行う事業主に対して、経費や賃金の一部が支給される助成金です。
法改正によって様々な対応が必要ですが、「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」の取り組みが推進されたことから働きやすく活躍できる職場環境の実現が可能です。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金には、以下のような2種類があります。
- 特定就職困難者コース:ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障がい者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給される
受給要件の詳細については、厚生労働省の対象ページをご参照ください。
参考URL:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
参考URL:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
障害者雇用で企業が注意すべきポイント
障害者雇用で企業が注意すべきポイントとして、以下のような点が挙げられます。
- 相談体制を整える
- 雇用管理上の留意点を理解する
- 障害者雇用納付金制度を理解する
それでは詳しく解説します。
相談体制を整える
事業主は障害者が働きやすい環境を用意するために、相談体制を整えることが大切です。
事業主だけでなく企業で働く従業員にも体制の整備について周知し、障害者が長期的に働ける環境を構築していきます。
また、相談者からのプライバシーを保護する取り組みを行い、同様に従業員へ周知するようにしておきましょう。
雇用管理上の留意点を理解する
障害者が安心して働くためには、職場で働く従業員が障害者雇用の理解を深めて配慮することが大切です。職場が障害者の雇用に否定的な態度を取ると、定着せず離職へとつながってしまいます。
障害者を雇用する上での留意点として、以下のような項目が挙げられます。
- 障害者の強みを活かせる組織・職場づくり
- 障害者の募集・採用
- 障害者の配置・職場適応・定着
- 障害者の職業能力開発
- 障害者の勤務条件等の整備
- 障害者の健康と安全
- 障害者のための職場環境
- 障害者へのカウンセリング(相談)
上記項目は、厚生労働省が掲げている留意点の一部です。詳しい内容について知りたい方は、厚生労働省のページをご参照ください。
参考URL:厚生労働省│障害者の雇用管理上の留意点
まとめ
今回は、法定雇用率の詳細から今後の段階的な引き上げ、計算方法、未達成時に取り組むポイントや活用できる助成金、注意点まで詳しく解説しました。
法定雇用率は企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障害者の雇用率であり、年々引き上げが進められています。企業の規模によって雇用すべき障害者の人数が変動するため、対象となっているときは定期的なチェックが必要です。
もし法定雇用率の未達成になっていると、ハローワークからの行政指導や障害者雇用納付金の徴収といった問題が発生します。
障害者雇用を促進させたいときは、転職サイトや障害雇用支援サービスなどを利用するようにしましょう。
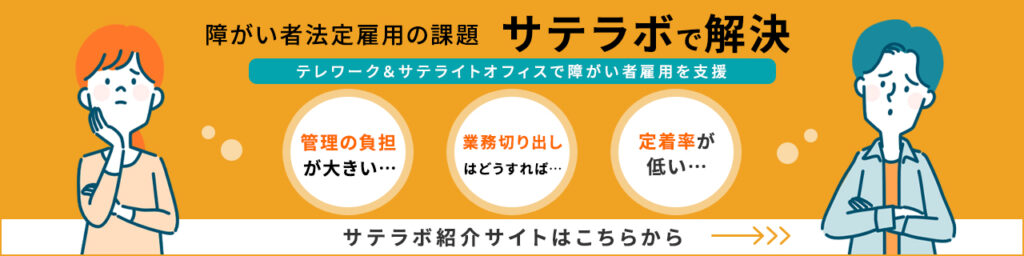
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







