就労選択支援とは?対象者やメリット・デメリットをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.27
- 最終更新日:
- 2025.06.02
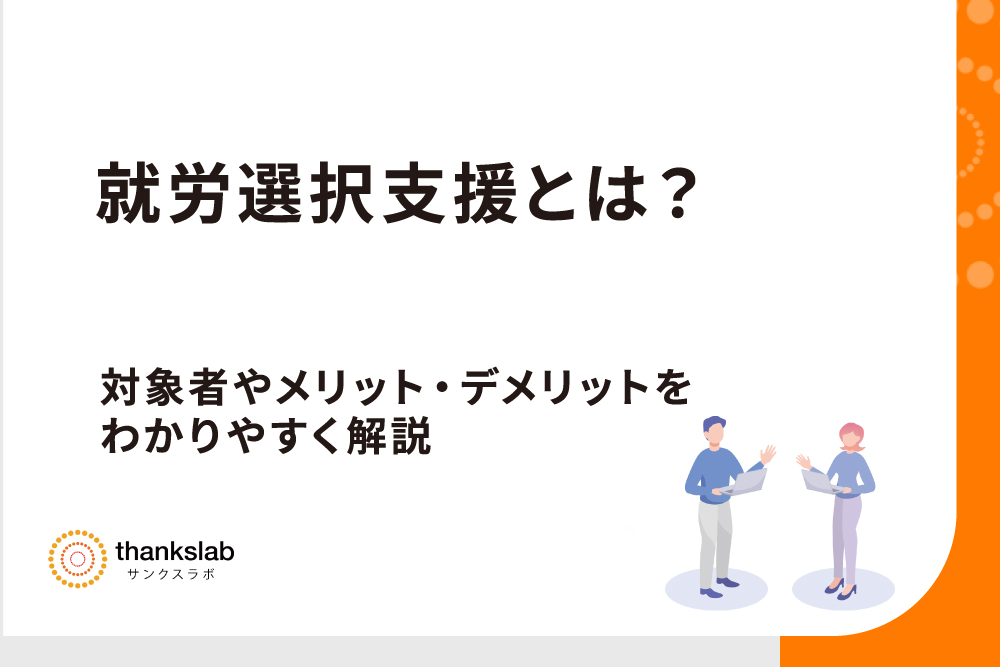
2025年10月から始まる新しい障がい福祉サービスである「就労選択支援」はどういったサービスなのか気になる方も多いかと思います。
そこで、本記事では就労選択支援とはどういったものなのか、サービス内容、対象者、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説していきます。
最後までお読みいただくことで就労選択支援の基本的なことを理解することができます。就労選択支援に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
就労選択支援とは?
就労選択支援とは、障害のある方が自分に合った仕事を見つけ、長く働き続けるためのサポートをする新しい障がい福祉サービスです。2025年10月から開始予定です。
これまでの就労支援では、最適なサービス選択が難しいという課題がありましたが、就労選択支援では、利用者の方の希望や能力、必要な配慮などを支援者と一緒に整理・評価し、最適な働き方や支援サービスを見つけるサポートをします。
就労選択支援の対象者
就労選択支援は、働く意欲があり、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)といった就労系障害福祉サービスの利用を検討している障害のある方が主な対象です。また、現在これらのサービスを利用中の方も対象となります。
具体的には、以下のような方が利用できます。
- これから就労系障害福祉サービスの利用を考えている方(特に2025年10月以降に新たに就労継続支援の利用を申請する場合、原則として就労選択支援の利用が必要です)
- 現在、就労継続支援サービスを利用しており、サービスの更新を予定している方(本人の希望に応じて利用可能)
- 現在、就労移行支援を利用している方
- 特別支援学校の高等部に在籍している生徒
- 特別支援学校以外の高等学校や大学などに在籍している障害のある学生
このように、就労選択支援は、障害のある方がご自身の希望や能力、適性に合った働き方や支援を見つけるための重要な機会となります。
幅広い方が対象となっており、就労に向けた最初のステップとして活用が期待されています。
就労選択支援のサービス内容
就労選択支援では、利用者が自分に合った仕事を見つけられるように、様々なサポートを提供します。主なサービス内容は以下の通りです。
情報提供
利用者の希望や適性に合う企業の募集状況などの情報を提供します。
状況把握
実際の作業場面などを通じて、利用者の能力や特性、課題などを把握します。この期間は1ヶ月程度が目安です。
ケース会議とアセスメント作成
就労選択支援事業所が中心となり、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携してケース会議を行います。その結果を基に、利用者の強みや課題、必要な配慮などをまとめたアセスメント結果を作成します。
連絡調整
アセスメント結果を本人や家族と共有し、話し合いの上で就労先や利用する福祉サービスを決定します。決定後は、利用者と関係機関との連絡調整を行い、スムーズな移行を支援します。
これらのサービスを通じて、利用者が主体的に就労先を選択できるようサポートすることが、就労選択支援の大きな特徴です。
就労選択支援の利用期間
就労選択支援を利用できる期間は、原則として1ヶ月間です。
この期間内で、ご本人の希望や適性、能力などを把握し、適切な就労先や福祉サービスを見つけるための支援が行われます。
ただし、ご本人の状況によっては、1ヶ月では十分な情報収集や評価が難しい場合もあります。
例えば、作業場面を通じてじっくりと状況を把握する必要があるケースなどが考えられます。そのような場合には、例外的に利用期間を最長2か月まで延長することが認められています。
就労選択支援を利用する際の流れ
就労選択支援の利用を検討されている方にとって、どのような流れでサービスを受けることができるのかは重要なポイントです。ここでは、一般的な利用の流れをステップごとに解説します。
1.相談・情報収集
まず、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、特定相談支援事業所に相談しましょう。就労選択支援のサービス内容や利用手続きについて詳しい説明を受けることができます。
2.利用申請
サービス利用の意向が固まったら、市区町村の窓口に利用申請を行います。申請に必要な書類や手続きについては、窓口で確認してください。
3.アセスメント・計画作成
申請後、特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人の状況や希望を詳しく伺い(アセスメント)、サービス等利用計画案を作成します。この計画案は、市区町村に提出されます。
4.支給決定・受給者証の交付
市区町村は、提出された計画案や本人の状況などを踏まえて支給決定を行い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証が、サービスを利用するために必要になります。
5.事業所との契約・利用開始
受給者証が交付されたら、希望する就労選択支援事業所を選び、利用契約を結びます。契約後、事業所の支援員との面談を通じて、具体的な支援計画が立てられ、サービスの利用が開始されます。
アセスメントに基づき、ご自身の強みや課題、希望する働き方などを共有し、就労に向けた準備を進めていきます。
就労移行支援との違い
就労選択支援と就労移行支援は、どちらも障害のある方の就労をサポートするサービスですが、その目的や対象者、サービス内容に違いがあります。
| 項目 | 就労選択支援 | 就労移行支援 |
|---|---|---|
| 目的 | 適切な障害福祉サービスへの橋渡しと、次のステップへの支援 | 一般企業への就労に必要なスキルや習慣の習得、職場定着 |
| 対象者 | 新たに、または更新で就労継続支援・就労移行支援の利用を希望する方 | 65歳未満で、一般企業への就労を希望し、知識・能力の向上や職場探し等を通じて就労が見込まれる方 |
| サービス内容 | 強みや特性の整理、自己理解の促進、情報提供、関係機関との連携など | 作業訓練、職場実習、求職活動支援、職場定着支援など |
就労選択支援は、ご自身の強みや特性を理解し、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、一般就労など、多様な選択肢の中から最適な働き方を見つけるためのサポートを行います。
一方、就労移行支援は、一般企業への就労を目指す方が対象で、そのために必要な知識やスキルの習得、求職活動、就職後の職場定着までを支援します。
つまり、就労選択支援は「どの働き方が自分に合っているか」を考えるためのサービスであり、就労移行支援は「一般企業で働く」という目標に向けた具体的な準備とサポートを行うサービスと言えます。
就労継続支援との違い
就労継続支援は、一般企業での就労が難しい障がい者の方へ、働きながら知識やスキルを習得する機会を提供するサービスです。一方、就労選択支援は、ご自身の希望や適性に合った就職先を「選択」するためのサポートです。
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 雇用契約 | 賃金 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働く | あり | 発生する |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約は結ばず、比較的短時間で軽作業を行い、生産物に対して工賃が支払われる | なし | 発生する |
就労選択支援と就労継続支援の主な違いは以下の通りです。
| 就労選択支援 | 就労継続支援(A型・B型) | |
|---|---|---|
| 目的 | 希望や適性に合った就職先の選択をサポート | 就労機会の提供と、知識・スキルの習得をサポート |
| 対象者 | 就労移行支援や就労継続支援の利用者・検討者など | 一般企業での就労が困難な障がい者 |
| 利用期間 | 原則1ヶ月(最長2ヶ月) | 制限なし |
| 賃金 | なし | あり(A型:給与、B型:工賃) |
このように、就労選択支援は就職先を選ぶための準備期間であり、就労継続支援は実際に働きながら訓練を行う場であるという点が大きな違いです。
就労定着支援との違い
就労選択支援と就労定着支援は、どちらも障害のある方の就労をサポートするサービスですが、その目的と支援のタイミングが異なります。
| サービス種別 | 目的 | 支援のタイミング |
|---|---|---|
| 就労選択支援 | 自分に合った仕事や働き方を見つけるための情報提供や相談、体験利用の機会提供 | 就職活動を始める前、または就職活動中 |
| 就労定着支援 | 就職後の職場定着をサポートし、長く働き続けられるように支援する | 就職後 |
就労選択支援は、これから就職を目指す方が、自分にどのような仕事が向いているのか、どのような働き方が合っているのかを具体的にイメージし、納得して就職活動を進められるように支援するサービスです。ハローワークや障害者職業センターなどと連携し、様々な情報提供や相談、職場体験の機会などを提供します。
一方、就労定着支援は、既に就職した方が、職場で抱える課題や悩みを解決し、安心して働き続けられるようにサポートするサービスです。職場訪問や面談を通じて、仕事内容の調整や人間関係のサポート、生活面の相談など、きめ細やかな支援を行います。
このように、就労選択支援は「就職活動の準備段階」を、就労定着支援は「就職後の定着」をそれぞれサポートする役割を担っています。ご自身の状況に合わせて、適切なサービスを選択することが大切です。
就労選択支援を利用するメリット
就労選択支援を利用することで、障害のある方が自分に合った働き方を見つけやすくなるという大きなメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
自分に合った働き方を見つけやすい
就労選択支援では、専門家が1ヶ月(最長2ヶ月)かけて、あなたの希望や適性、能力を丁寧に把握します。その上で、企業の情報提供や作業体験などを通じて、本当に自分に合った仕事や職場環境を見つけるサポートをしてくれます。
主体的な意思決定ができる
就労選択支援の最大の目的は、障がいのある方自身が「主体的」に就労先を選べるように支援することです。専門家からの情報提供やアドバイスを受けながらも、最終的な決定は自身で行います。これにより、納得感を持って就労生活をスタートできます。
多様な選択肢から検討できる
就労選択支援では、一般企業への就職だけでなく、就労継続支援A型・B型事業所など、様々な働き方の選択肢を提示してくれます。自身の状況や希望に合わせて、最適な選択肢を一緒に考えてくれるので安心です。
就労後のミスマッチを防ぎやすい
事前にじっくりと自分の適性や希望と向き合い、様々な情報を得ることで、就職後の「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぎやすくなります。
状況変化にも対応しやすい
就労後も、希望に応じて再度就労選択支援を利用できます。働き続ける中で状況や希望が変わった場合でも、柔軟に対応し、より良い働き方を見つけるためのサポートを受けることができます。
就労選択支援のデメリット
就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方を見つけるための新しいサービスですが、いくつかのデメリットも考えられます。
利用期間の制約
就労選択支援の利用期間は原則1ヶ月、最長でも2ヶ月と定められています。じっくりと時間をかけて自分に合った仕事を探したい方にとっては、この期間が短すぎると感じる可能性があります。
事業所の選択肢
就労選択支援を実施できる事業所は、過去3年間に3人以上の障がい者を一般就労させた実績があるなど、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、お住まいの地域によっては、利用できる事業所が限られてしまう可能性があります。
まとめ
就労選択支援は、障害のある方が自分に合った仕事を見つけ、長く働き続けるための新しいサポート制度です。これまでの就労支援サービスに加え、より個々の希望や能力、適性に合わせた就労選択が可能になるよう、2025年10月から開始される予定です。
就労選択支援の制度のポイントをまとめると以下の通りです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2025年10月(一部対象者は2027年4月以降) |
| 目的 | 障害のある方の希望や能力に合った就労先へのマッチング、ミスマッチの防止 |
| 特徴 | 本人と支援者が協同で強みや課題を整理・評価(就労アセスメント) |
| 期待される効果 | 適切な就労支援サービスの利用促進、一般就労への移行者増加 |
就労選択支援は、障害のある方が主体的に職業選択を行い、より豊かな社会生活を送るための重要な一歩となることが期待されています。制度の詳細はまだ検討中の部分もありますが、関係機関との連携強化により、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援の実現を目指しています。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







