【企業向け】ハローワークで障がい者雇用の求人を出す流れやサポート内容を解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.05.20
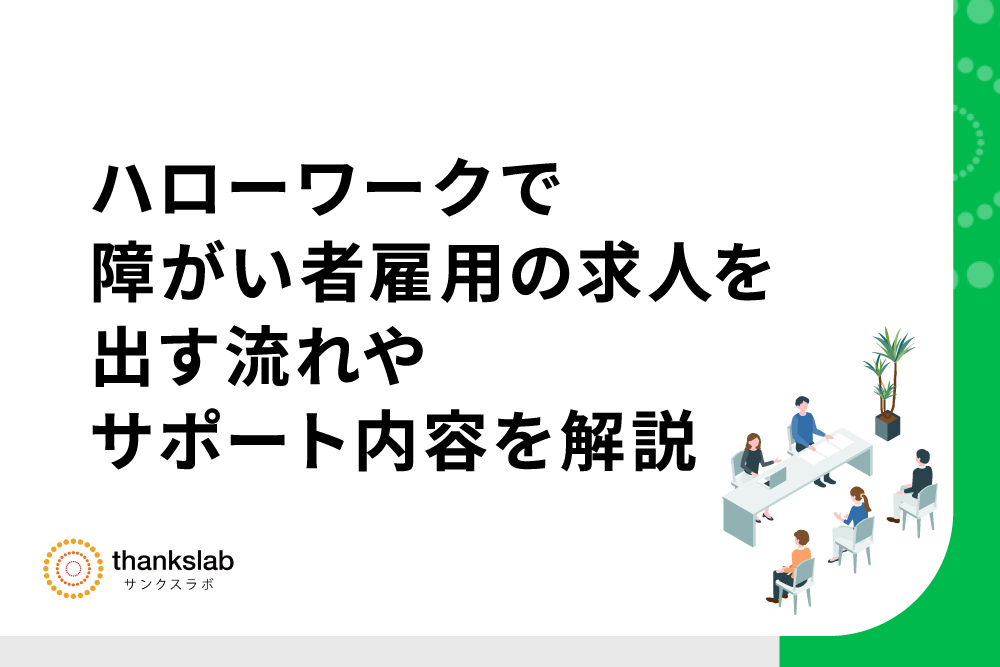
障がい者を雇用する際は、一般の求人同様ハローワークのサポートを利用できます。
「ハローワークに依頼するとどのようなサポートが依頼できる?」
「民間企業とハローワーク、依頼できる障がい者雇用に関するサポートに違いはあるのか?」
といった疑問を持っている採用担当者もいるでしょう。
本記事は、ハローワークに依頼できる障がい者雇用のサポート内容やハローワークを通じて求人を出す流れを紹介します。
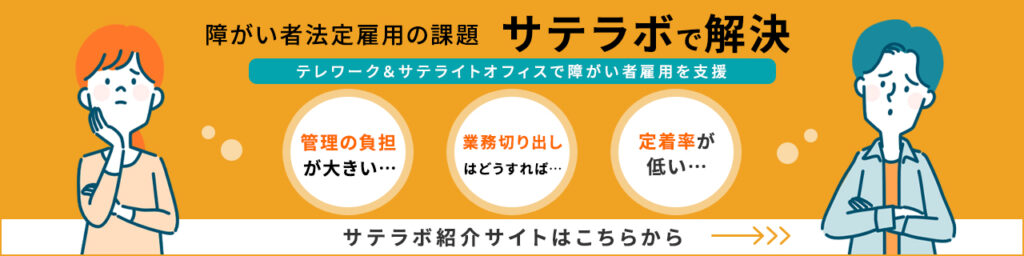
ハローワークが行っている企業向け障がい者雇用のサポート
ハローワークは厚生労働省が運営している国の機関であり、求職者や求人事業主を支援する総合的な雇用サービスを行っています。
障がい者雇用も国の指針で行っているため、障がい者雇用を促進するサポートも充実しており、ハローワーク経由で求人を出せば活用が可能です。
ここでは、ハローワークが行っている企業向け障がい者雇用のサポートを紹介します。
ハローワークには専門所部門と雇用指導官がある
ハローワークには障がい者雇用を推進するために、障がい者専門のサポートが設けられています。働きたい障がい者はもちろんのこと、障がい者を雇用したい企業も受け入れ態勢を整えるためのサポートが必要です。
ハローワークでは、働きたい障がい者には障がいの程度や本人の希望に応じて相談を受けたり職場を紹介したりしてくれます。また、ハローワークの雇用指導官が企業に訪問して、職場定着支援を行うこともあるでしょう。
障がい者雇用は障がい者が企業に就職して終わりではなく、長い間働き続けてこそ雇用が成功したといえます。そのため、雇用指導官は障がい者が企業に採用された後も、必要ならば企業に訪問して障がい者雇用に関する悩みや課題の解決をサポートしてくれます。
特例子会社設立の相談
特例子会社とは、障がい者雇用の促進や安定を図るために会社が設立できる組織です。特例子会社を設立するには、一定要件を満たし、厚生労働大臣から認定を受ける必要があります。
会社の規模や職種によっては、特例子会社を設立したほうが安定した障がい者の雇用につながることもあるでしょう。ハローワークでは、設立に向けてアドバイスや指導を受けられます。
関連:特例子会社とは?設立方法やメリット・デメリットをわかりやすく解説
助成金に関する相談
障がい者を雇用すると、さまざまな助成金を利用できます。ハローワークは、以下3つの助成金の窓口になっています。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する支援の助成金
これらの助成金を活用したい場合は、積極的にハローワークを利用すると受給までスムーズです。
関連:【2025年最新】障害者雇用の助成金の種類や条件、申請方法を解説
各種セミナー・見学会の開催
ハローワークでは、障がい者雇用に関する各種セミナーや見学会も開催しています。障がい者雇用をはじめて実施する会社の中には、障がい者を雇用する際に必要な環境やサポートの方法がわからないところも珍しくありません。
ハローワークには、蓄積された障がい者雇用のノウハウがあります。各種セミナーはノウハウを教えてもらえる機会です。
また、ハローワークは公共の雇用サービスですから、無料、もしくは安価で開催しているセミナーも多いので、費用を気にすることなく利用できるのも大きなメリットです。
トライアル雇用の実施
ハローワークを利用して求人を出した場合、「トライアル雇用」を利用できます。
トライアル雇用とは、障がい者を原則として3カ月間試験的に雇用する仕組みです。一般的な求人の試用期間と似ていますが、トライアル雇用は3カ月間でいったん雇用が終了します。
もし、障がい者自身が「実際に働いてみた結果、自分に適性がないとわかった」といった場合や、企業が「障がい者は頑張ってくれたが、残念ながら障がいの特性等を考えると当社で長く働いてもらうのは難しい」といった場合でも、雇用期間が3ヵ月であれば大きな問題にはなりにくいでしょう。
逆に、障がい者と企業のマッチングがうまくいった場合は、トライアル雇用後に改めて正式雇用が可能です。
関連:障害者トライアル雇用とは?メリット・デメリットや対象者・期間など詳しく解説
各種サポート機関への橋渡し役
近年は障がい者雇用を促進できるようさまざまなサポート機関が存在しています。機関によっては、障がい者の就職に関するさまざまなサポートを行ってくれます。
ハローワークを利用すれば各種サポート機関を紹介してくれるだけでなく、必要ならば障がい者や企業をサポートしてくれるように橋渡し役を担ってくれるでしょう。
各種サポート機関には、障がい者をサポートできるノウハウを蓄積しているところや専門的な教育を受けたスタッフが常駐しているところもあります。特に、はじめて障がい者を雇用する企業や、今まで雇用してきた障がい者とは異なる種類の障がいを持っている方を雇用する会社は、従業員だけでは対応しきれないこともあるでしょう。
そのような場合に、サポート機関は役立ちます。
ハローワークを通じて障がい者を雇用するまでの基本的な流れ
ここでは、ハローワークを通じて障がい者を雇用するまでの基本的な流れを紹介します。
近年は、民間の求人サイトも増えて「今までハローワークを使ったことがない」といった会社もあるでしょう。
障がい者への求人も、一般的な求人も基本的な流れは同じです。一度障害者の求人をハローワークを通して出して求人を出してみれば、一般的な求人にも対応できます。
雇用の計画を立てて職場の環境を整える
まずは障がい者雇用の計画を立てて、職場の環境を整えます。障がい者を雇用する場合、健康な方を雇用するよりさまざまな点で配慮が必要です。例えば、身体に障がいがある方を雇用するならば、エレベーターや手すり、スロープなどが必要になるケースもあるでしょう。
また、障がい者にどのような仕事を任せるのか、サポート体制はどのようにするのか、従業員が障がいへの理解を深めるにはどのような教育をすればいいのかなど、考えるべきことはたくさんあります。
ハローワークへの相談は、この段階から可能です。どのような障がい者ならば雇用が可能か、希望する条件の障がい者を雇用するにはどうすればいいのかなど、積極的に相談してみましょう。
そうすれば、ハローワークの専門担当部署や雇用指導官がいろいろとサポートをしてくれます。わからないことがあったら、会社がある地域を担当しているハローワークに相談してみましょう。
求人を出す
障がい者を雇用する準備が整ったら、求人を出します。まずはトライアル雇用から始めてもいいでしょう。また、職業訓練を行っている障がい者の中から雇用したい場合は、直接面接を行うこともできます。
どのようなスタイルで求人を出すかも、ハローワークの担当者と相談してください。そうすれば、「求人広告を出した結果たくさんの応募があったが、自社では引き受けられない方ばかりだった」といったケースを防げます。
また、求人を出したが応募が集まらなかったといった場合は、担当者と相談して条件を変えるなど対処が必要です。ハローワークを通じて求人を出した場合、費用はかかりません。しかし、長期間応募がない場合は求人広告の内容が求職者のニーズに合っていないと考えられます。
応募者に対して選考を行う
求人広告にある程度応募が集まったら、選考を行いましょう。障がい者雇用の場合は健康な方向けの求人のように1つの求人に大勢の求職者が短期間で応募があるケースは少ないでしょう。
しかし、仕事内容や地域によっては応募者多数になる可能性はあります。応募者が多数の場合は書類選考、集団面接、個人面接と複数の選考が必要ですが、応募者が少なければ採用を前提とした選考になるケースもあるでしょう。
選考の際、どのような基準を設けるかも事前に従業員の間で共有しておきましょう。特に、障がい者は、本人の努力ではどうしても改善できないところがあります。その点をどのように選考に含めるかも大切です。
雇用・入社手続き
選考が終了したら、雇用契約書を交わして入社してもらいます。トライアル雇用の場合は、まず3ヵ月間、障がい者が実力を発揮できるように会社がサポートをしながら仕事をしてもらいましょう。
トライアル雇用を得て正式雇用となる場合は、仕事量を増やすなど変更点があるならしっかりと説明してください。
障がい者の雇用はゴールではなくスタートです。障がい者にできるだけ長く働いてもらうためにも、コミュニケーションを密にとって改善できる点は改善していくことが大切です。
引き続きハローワークのサポートを希望する場合は、その旨を伝えてください。障がい者を雇用した条件や状況によっては、引き続きハローワークの雇用指導官が定期的に訪問して指導をしてくれます。
ハローワーク以外に障がい者雇用をサポートしてくれる機関
最後に、ハローワーク以外に障がい者雇用をサポートしてくれる機関について紹介します。
ハローワーク以外で障がい者雇用をサポートしてくれる機関は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 地方自治体の支援機関
- 民間企業が実施している障がい者雇用支援
ハローワークは就職支援をはじめとする雇用サービスに特化した国の機関ですが、障がい者雇用のサポートは全方位完ぺきではありません。そのため、ハローワークの就職支援以外の支援機関の存在を知っていれば、何かと便利です。
地方自治体による障がい者雇用支援
地方自治体によっては、独自の障がい者雇用支援を行っているところもあります。一例としては、東京都が行っている「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」などです。
どのような支援があるかは、自治体によって異なります。また、自治体の支援は原則としてその自治体に会社の住所があることが必要です。会社によっては、「別の自治体の境界線上に住所があり、どちらの支援が利用できるか微妙」といった場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
このほか、自治体によっては利用に条件や期限がある支援もあります。利用前にしっかり確認しておいてください。なお、すべての自治体で障がい者雇用支援が設定されているとは限りません。自治体によっては特別な支援がないところもあります。
民間企業が実施している障がい者雇用支援
民間企業が実施している障がい者雇用支援には、以下のようなものが挙げられます。
- 人材派遣業者が実施しているマッチング制度
- 雇用継続、雇用サポート
一例を挙げると農園型障がい者雇用支援サービスやサテラボのような、人材育成から障がい者を雇用した企業が抱えている問題解決のサポートをしてくれる企業などが挙げられます。
特に、サテラボに代表される障がい者を雇用した企業が抱えている問題解決のサポートする会社を利用すれば、「障がい者を雇用したものの想定外の問題がおきすぎて、会社では解決しきれない」といった場合も安心です。
また、民間業者の障がい者雇用支援は料金がかかる分対応がスムーズです。至急対応が必要な問題が出た場合は民間業者に相談してみましょう。
ハローワークと自治体・民間のサービスの併用が可能
ハローワークと自治体・民間のサービスは併用が可能です。例えば、普段はハローワークの障がい者雇用支援を利用し、必要あれば自治体や民間のサービスを利用してもいいでしょう。
また、民間のサービスを利用すれば、会社が求める人材の育成から障がい者が活躍できる職場づくりなどもワンストップで利用できます。障がい者の求人はハローワーク、職場の環境整備は民間業者に依頼といったように必要に応じてサービスを使い分けてもいいでしょう。
予算や会社の職種、規模、従業員にかかる負担などを加味したうえで考えましょう。
まとめ
本記事では、ハローワークが行っている障がい者雇用支援について解説しました。障がい者雇用は会社だけですべてを完結させるのが難しいケースが多いです。
ハローワークは求人だけでなく、障がい者の雇用支援や教育、企業からの相談など幅広い支援を行っています。しかも、公共の雇用サービスなので費用を抑えて利用できるのもメリットです。
必要ならば自治体が行っている障がい者雇用サービスや、民間の障がい者雇用サービスも併用しましょう。そうすれば、障がい者雇用がスムーズに行くだけでなく障がい者の教育や雇用が長続きできる環境づくりまでサポートしてもらえます。サテラボも幅広い障がい者雇用のサポートを行っております。まずはご相談ください。
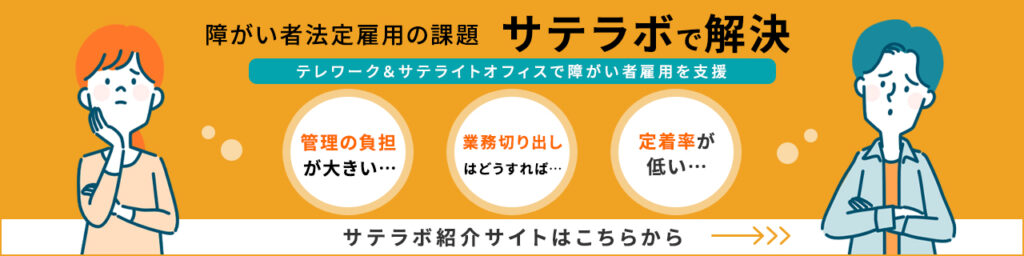
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







