障がい者雇用の除外率制度とは?計算方法や今後の引き下げ・廃止について解説【2025年最新】
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2026.01.07
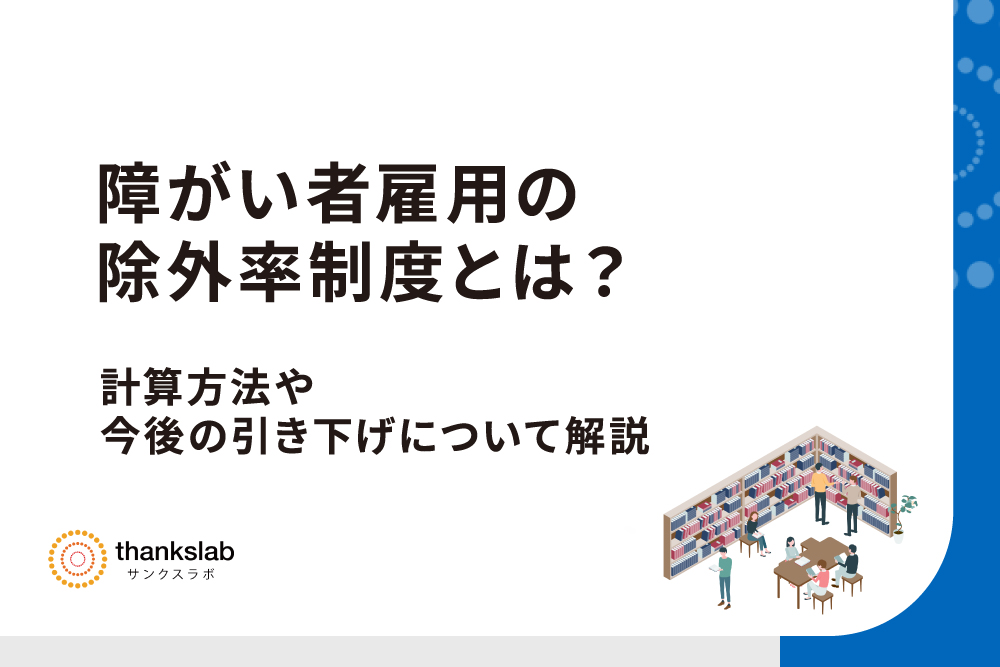
日本の企業は、障害者雇用促進法に基づき、常時雇用する労働者が40人以上の場合は原則として障害者雇用の義務があります。しかし、職務の性質や内容によっては障がい者の雇用が難しい場合もあるでしょう。
そのため、政府は業種によっては「除外率制度」を適用し、障がい者の雇用義務を軽減しています。
今回は、障害者雇用の除外率制度の概要や計算方法、今後の引き下げと廃止について改正をしていきます。
また、今後引き下げられる除外率の変更については無料ウェビナーでも解説しているため、除外率の理解を深めたい方はぜひご参考ください。
障害者雇用の除外率制度とは
障害者雇用促進法により、常時雇用している従業員が40.0人以上の企業には、法定雇用率2.5%以上の障がい者を雇用する義務があります。しかし、業務の性質上、障がい者の就業が一般的に困難と認められる業種も存在します。
除外率制度とは、このような業種について、雇用する労働者数を計算する際に、一定の割合(除外率)に相当する労働者数を控除することで、障がい者の雇用義務を軽減する制度です。
除外率は段階的に廃止される
ただし、この除外率制度は、障害のある人もない人も共に働き、社会参加できる「ノーマライゼーション」の考え方に基づき、平成14年の障害者雇用促進法の改正で廃止が決定されました。
現在は、完全廃止に向けた経過措置として、段階的に除外率の縮小が進められている状況です。
制度の変遷を簡単にまとめると以下のようになります。
- 平成14年:障害者雇用促進法の改正により、除外率制度の廃止が決定。
- 平成16年4月:最初の除外率引き下げ。タイヤ・チューブ製造業など6業種が対象外に。
- 平成22年7月:2回目の除外率引き下げ。有機化学工業製品製造業など5業種が対象外に。
- 令和7年4月:3回目の除外率引き下げ。非鉄金属製造業や採石業などが対象外に。
除外率は年を追うごとに低下したりなくなったりしていきます。現在、除外率制度が適用されている職種でも、こまめに除外率のチェックが必要です。
除外率が設定されている業種一覧
2025年4月現在、障害者雇用の除外率制度が適用されている業種は製造業や倉庫業、水運業、高等教育、医療職などです。障がい者が就業すると、安全かつ的確な業務の遂行が難しいとされる職業と考えるとイメージしやすいでしょう。
具体的な業種や令和7年4月の引き下げ後の最新の除外率の一覧は以下の表のとおりです。
令和7年4月引き下げ後の最新の除外率
変更前の除外率と令和7年4月の引き下げ後の除外率を記載しています。
| 業種 | 変更前除外率 | 変更後除外率 |
| ・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く) ・倉庫業 ・船舶製造 ・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) | 5% | 廃止 |
| ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) ・その他の鉱業 | 10% | 廃止 |
| ・非鉄金属第一次製錬 ・精製業 ・集配配達業以外の貨物運送取扱業 | 15% | 5% |
| ・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 20% | 10% |
| ・港湾運送業 | 25% | 15% |
| ・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 | 30% | 20% |
| ・林業(狩猟業を除く) | 35% | 25% |
| ・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 40% | 30% |
| ・特別支援学校 (もっぱら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 45% | 35% |
| ・石炭・亜炭鉱業 | 50% | 40% |
| ・道路旅客運送業 ・小学校 | 55% | 45% |
| ・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 60% | 50% |
| ・船員等による船舶運航等の事業 | 80% | 70% |
引用:厚生労働省「除外率制度について」
最新の改定により、令和7年4月1日からは新たな除外率が適用されています。例えば、これまで除外率が5%だった非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く)、採石業などは廃止となり、除外率が20%だった建設業は10%に引き下げられました。
その他全体的に変更前よりも除外率が引き下げられています。
今後も段階的な引き下げを経て、最終的には除外率制度は廃止される予定ですが、具体的な廃止時期については未定です。
除外率の変更については無料ウェビナーでも解説しているので、除外率について理解を深めたい方はぜひご参加ください。
⇒除外率変更についての無料ウェビナー詳細はこちらから
障害者雇用の除外率を計算する方法
障害者雇用における除外率は、常用労働者数から除外率に相当する労働者数を控除して算定します。具体的な計算式は以下の通りです。
(常用労働者数 - (常用労働者数 × 除外率)× 法定雇用率 = 雇用義務のある障害者
例えば、常用労働者数が1,000人、除外率が15%の業種、法定雇用率が2.5%の場合、雇用しなければならない障害者の数は次のように計算されます。
【計算例】
(1,000人 - (1,000人 × 15%) × 2.5% = 21.3人
※小数点以下は切り捨てとなるため、この企業が雇用すべき障害者の数は21人となります
障害者雇用の除外率が適用されている職種は、一度何人の雇用義務が免除されるか確認してみましょう。
なお、障害者雇用の除外率が廃止された場合は「1,000×0.025=25人」なので、最低25名は障がい者を雇用しなければなりません。
除外率が廃止されると雇用しなければならない人数が増える点に注意が必要です。
また、除外率が適用される業種にも対応した障害者雇用率計算フォーマットをご用意しています。除外率が適用される場合、自社は何人採用しなければならないのか、法定雇用率は達成しているのかが入力するだけで分かります。
計算の手間を省きたい方はぜひご活用ください。
▼除外率が適用される業種の雇用率を半自動で計算することができます
>>障がい者雇用率計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
2025年4月の引き下げで除外率が廃止された業種
令和7年(2025年)4月の引き下げにより、除外率が廃止された業種をまとめると以下の通りです。
・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く)
・倉庫業
・船舶製造
・修理業、船用機関製造業
・航空運輸業
・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る)
・採石業、砂・砂利・玉石採取業
・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)
・その他の鉱業
これらの業種では、今後は除外率が適用されず、通常の法定雇用率(2025年現在は2.5%)の達成が求められます。
今は除外率が設定されており法定雇用率が達成できていても、今後の引き下げや廃止によって未達成となる可能性がある企業は注意が必要です。
法定雇用率が未達成だと障害者雇用納付金を納める必要が出てきたり、行政指導の対象となるといったリスクも発生します。
まだ廃止となっている業種の企業も、除外率制度の今後の動向を注視し、障害者雇用を着実に進めていくのが良いでしょう。
まとめ
今回は、政府によって定められた「除外率制度」の概要や適用になる上限、障がい者の雇用義務がどのくらい軽減されるか計算する方法などを紹介しました。
「除外率制度」は、すでに廃止が決まっている制度です。しかし、いつ廃止になるかは明確になっていません。2025年4月より10年以上ぶりに除外率制度が改定され、いくつかの業種が対象外になりました。
また、除外率の引き下げも決定し、改定によって雇用する障がい者の方が増えたり新しく雇用する必要が生まれたりするところもあるでしょう。
障がい者をスムーズに雇用してストレスないように働いてもらうためには、職場の環境を整えて必要ならば新しい仕事を創出する必要があります。一朝一夕にはできないことなので、今から少しずつ環境を整えておきましょう。そうすれば、いざ雇用義務が生じたときでもスムーズに求人が出せるはずです。
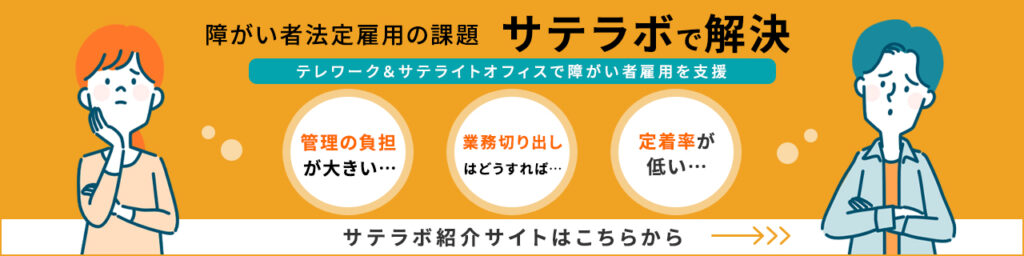
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







