身体障がい者の雇用ガイド| 就業状況や必要な合理的配慮について解説
- 公開日:
- 2025.05.12
- 最終更新日:
- 2025.05.21
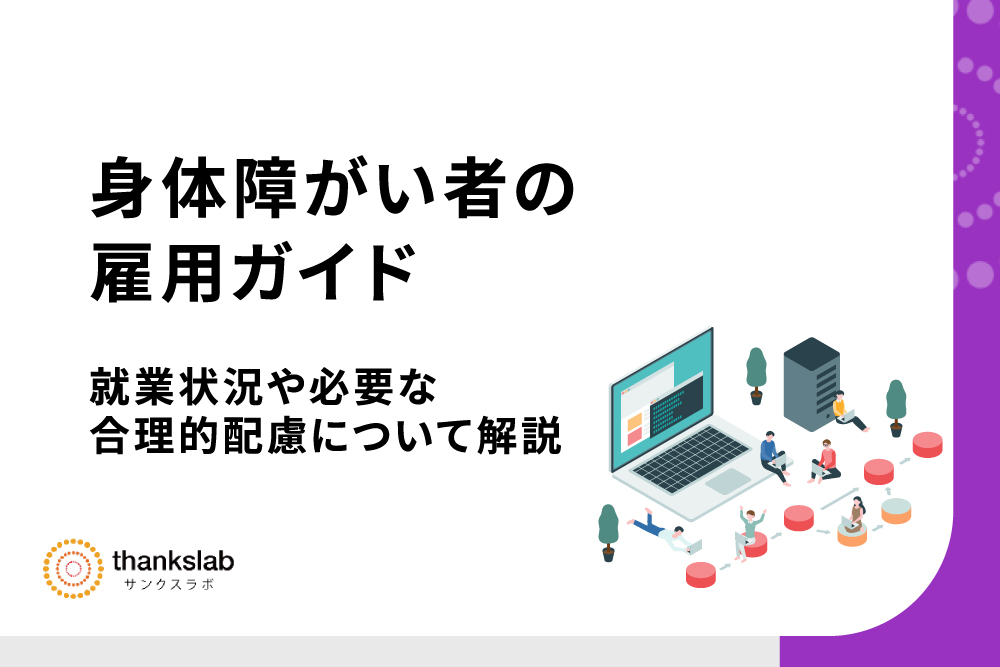
現在、常時雇用している労働者が40名以上いる企業は「障害者雇用促進法」に基づき、最低1名以上の障がい者を雇用する義務が課せられています。雇用の対象になっている障がい者は、「身体障がい」「知的障がい」「発達障がいを含む精神障がい」の3つに分類されます。
障がいを者を雇用するには障がい者全体に対する理解はもちろんのこと、自社が雇用する障がい者について、特に理解を深めることが重要です。
今回は、障害者雇用促進法に定められている障がいのうち、身体障がいを持つ方の雇用状況や向いている仕事、スムーズに仕事をしてもらうポイントを紹介します。
身体障がい者の就業状況は?

令和5年の障害者雇用状況の集計結果によると、身体障がいを持っている方で障がい者として雇用されている方は36万157.5人でした。前年比0.7%増であり、民間の企業に雇用されている障がい者の中で、最も割合が多くなっています。
職種別で見てみると最も多く雇用されているのは、製造業であり全体の21.3%です。次いで21.2%が雇用されているのが卸売業、小売業となっており、サービス業の14.9%が続きます。
反対に、農業や林業、建設業などは雇用される方が少数にとどまっています。これは、身体に障がいを持っている方が安全に行える仕事がこれらの業種には少ないためです。
しかし、農業や林業、建設業にまったく就けないことはありません。体を動かすことが少ない仕事、経理や総務などバックオフィス業務で活躍している身体障がい者の方もいます。
身体障がいの種類と特徴

ここでは、身体障がいにはどのような種類があるのか、特色と共に紹介します。知的障がいや発達障がいを含む精神障がいとの違いも解説するので、参考にしてください。
身体障がいの種類と定義
身体障がいとは、「身体障害者福祉法」によって「体の機能に障がいがあり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方」と定義されています。なお、18歳未満で身体障がいがある方は、児童福祉法にて「身体障がい」と定義づけられています。
障がい者雇用の対象になるのは、「身体障害者福祉法」によって定義されている身体障がい者のほうです。
身体障がい者手帳の交付対象となっている障がいの種類と程度は以下のとおりです。
| 身体障がいの種類 | 障がいの概要 |
| 視覚障がい | ・視力の低下 ・視野の狭まり |
| 聴覚・平均昨機能の障がい | ・声や音が聞こえない、聞こえにくい ・体の平均感覚の低下 |
| 音声・言語・咀嚼機能の障がい | ・発音が困難 ・発語が困難 ・咀嚼が困難 |
| 肢体不自由 | 両手・両足・胴体のいずれかの機能が低下している |
| 内部障害 | 心臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能のいずれかが低下している |
身体障がいは、外見からではわかりにくいものもあります。
また、同じ障がいでも、人によって程度が異なります。例えば、補助器具を使ったり薬を服用したりすれば、健常者と同じように動ける方もいれば、日常生活を送るのに手助けが必要な方もいます。
中途障がい者も多い
身体障がい者は、生来の方もいればケガや病気が原因で障がい者になった方もいます。一例を挙げると、交通事故や糖尿病、脳出血等があります。このような方々は「中途障がい者」と呼ばれます。
中途障がい者の中には、障がいを負うまでバリバリ仕事をしていた方も珍しくありません。
障がいを克服して仕事に復帰したい、今までの経験を活かして再度仕事をしたいと頑張っている方もたくさんいます。
一般就労する方もいる
身体障がい者の中には、障害者雇用ではなく一般就労する方もいます。
前述したように、同じ「身体障がい者」でも、人によって日常生活の不便さは異なります。障がいの種類や程度によっては「一般就労で再就職したほうが給与も良く、経験も活用できる」といったケースもあるでしょう。
しかし、身体障がい者の中には、補助器具やサポートがあっても健康な方と同じように働くのが難しい方もいます。「あの人は体が不自由でも頑張っているのに、どうしてもっと頑張れないのか?」と考えてはいけません。
身体障がい者がスムーズに働いてもらうポイント

ここでは、身体障がい者の方がスムーズかつ快適に働いてもらうポイントを紹介します。
身体障がいは、障害者雇用の枠で働いている人数が最も多い障がいです。その理由は複数ありますが、近年は公共の場所のバリアフリー化が進んだこと、スマホアプリなど個人で利用しやすい障害をサポートする手段が増えたことなどが挙げられます。
しかし、身体障がい者が働くには、公共のバリアフリーや個人の努力だけでは難しい場合も多いです。
身体障がい者が雇用された場合、どうすれば職場にスムーズに溶け込んでもらえるか、具体的な方法も紹介するので、参考にしてください。
希望する仕事を丁寧にヒアリングする
身体障がい者を障害者枠で雇用する場合、丁寧なヒアリングが重要です。「どのような仕事ができるのか」「希望する仕事はあるのか」といった質問だけでなく、「障がいが理由で苦手なこと、できないことは何か」「障がいをサポートする器具やアプリがあれば、希望する仕事ができるのかどうか」も重要です。
例えば、「長時間の立ち仕事は難しいが座って仕事をすれば健康な方と同様に働ける」「音声読み上げソフトがあれば、事務仕事も自分1人でできる」といった希望が聞ければ、職場として対処の仕様があります。
また「ラッシュの時間帯に通勤するのはつらいので、フレックスタイムで働ければうれしい」「リモートワークが可能ならば希望する」といった勤務形態についての希望が出されることもあるでしょう。
合理的配慮によって障がい者が働きやすい環境を整える
身体障がい者を雇用する際は、雇用する本人からヒアリングをおこなったうえ、障がい者の方が働きやすい環境を整える合理的配慮が大切です。仕事に使う道具はもちろんのこと、トイレや通路、建物の環境も重要です。
例えば、多目的トイレを使えるように手配する、トイレの数を増やす、廊下に手すりを付ける、デスクのライトを明るくする、室内用の点字ブロックを設置するなどすれば、障がい者自身でできることが増える可能性があります。
また、障がい者の方を受け入れる従業員への教育も重要です。障がいについて説明をするのはもちろんのこと、コミュニケーションの取り方や障がいのために時間がかかることやできないこと、サポートの仕方などを共有することも必要です。
健康な方ならば簡単にできることであっても、障がいがある方にとっては難しいこともあります。仕事を覚えるまでに時間がかかることもあるでしょう。その際、他の従業員がサポートの仕方を知っていれば、障がい者も安心して働けます。
必要ならば外部のサポートも頼る
障がい者が企業で継続して長く働き続けるには、外部のサポートを頼ることも大切です。企業によってはサポートチームや担当者を決めて障がい者が職場に早くなじむような環境を作ろうとするところもあるでしょう。
しかし、障がい者のサポートには専門的な知識や経験が必要です。雇用した障がい者をサポートする担当者を決めることはメリットもありますが、何か問題が起こった場合の対処や、日々のサポートが担当者に集中してしまうデメリットもあります。
障がい者をサポートする従業員にも自分の仕事があります。サポート業務が多くなれば、負担が重くなって仕事に対するモチベーションが低下して会社の業績に悪影響が出てくる恐れもあるでしょう。
身体障がい者を雇用し、スムーズに仕事をしてもらうためには、外部のサポートも積極的に利用してください。公的な支援には、「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」や「チャレンジホームオフィス」等があります。公的な支援は支援できる範囲や期間、回数が限られている等の注意点もありますが、費用を抑えて利用できるのがメリットです。
また、近年は民間でも障がい者を支援するサポート事業を行う会社が増えてきました。一定の費用がかかりますが、サポートをしてくれる範囲が広い、長期的な継続支援が可能等のメリットがあります。
コミュニケーションを取りやすい職場にする
障がい者がスムーズに仕事を続けるためには、コミュニケーションを取りやすい環境を作ることも大切です。「希望や要望があったら申し出てほしい」といっていても、会話が少なかったり、仕事が忙しかったりする職場では言い出しにくいでしょう。
言語によるコミュニケーションが難しい場合、メールで意見を述べられるようにしておくなど、対策しておくのも有効です。また、職場のほうから希望や要望があるか定期的に聞くようにしても効果的です。
まとめ
身体障がいをお持ちの方は、障がい者雇用だけでなく一般就労をして会社で働いている方も珍しくありません。近年は社会全体のバリアフリー化が進み、障がいをサポートしてくれるシステムも増えたため、障がいの種類や状態によっては就労も比較的容易です。
また、中途で障がい者になった方の中には、これまでの経験や知識、資格を活かして職場復帰をしたいと考える方もいるでしょう。
その一方で、障がい者本人のやる気や自助努力に任せているだけでは継続した就業がうまくいかない場合もあります。従業員の理解はもちろんのこと、職場全体で障がい者が働きやすい環境を整えていくことが大切です。必要ならば、外部のサポートも積極的に利用しましょう。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







