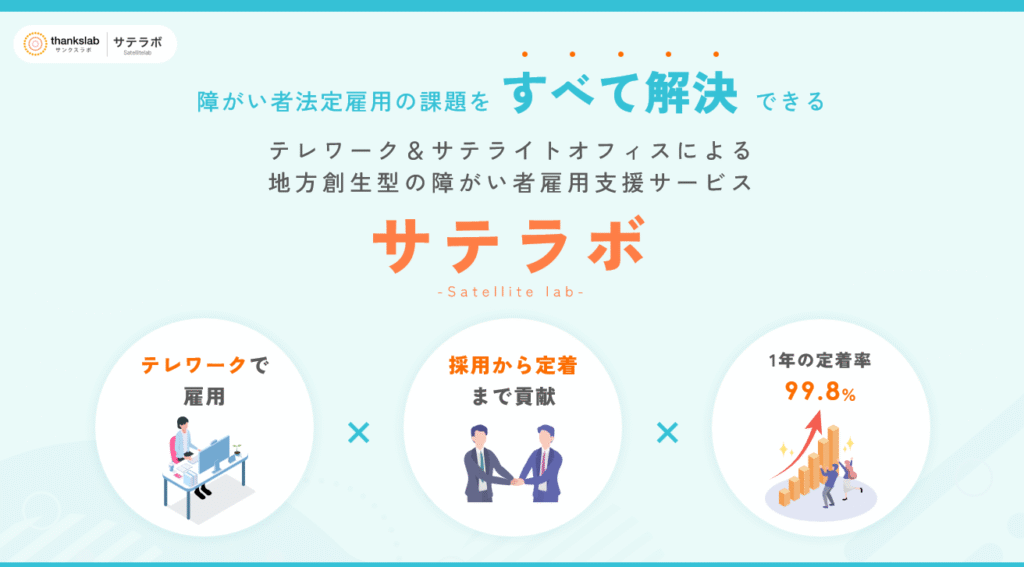障害者雇用率未達成だとどうなる?企業名公表や罰則について解説
- 公開日:
- 2025.02.13
- 最終更新日:
- 2026.01.07
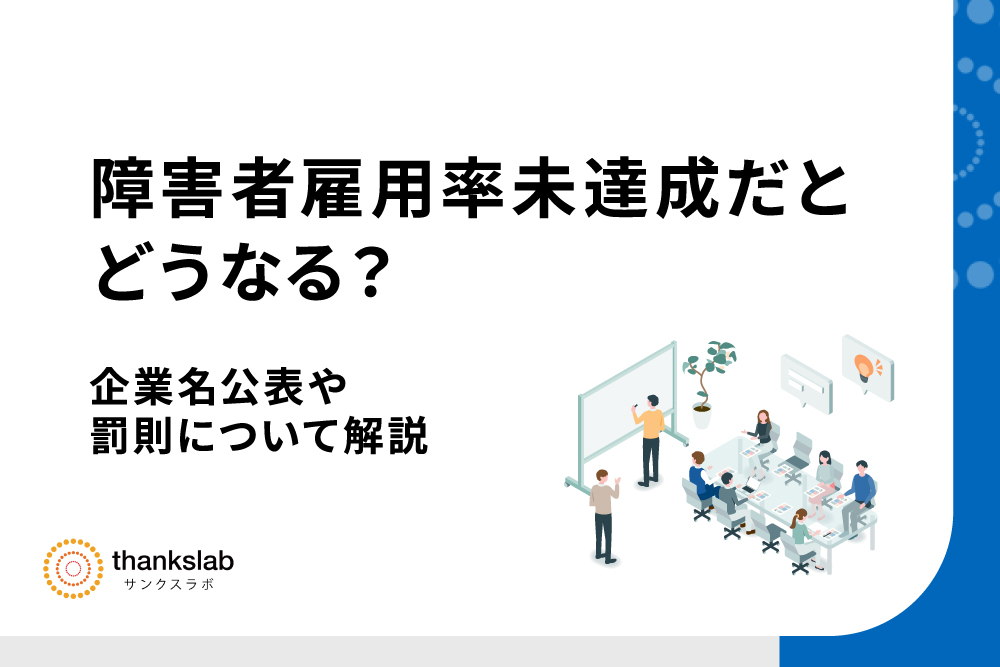
障害者雇用の法定雇用率未達成企業は障害者雇用納付金として不足1人あたり月額50,000円が徴収されることが、令和4年の法改正で決定されました(常用労働者が100人を超える企業の場合)。
このルールを定めた障害者雇用促進法では、従業員40以上の企業において、法定障害者雇用率を明確に定めています。また、障害者雇用納付金のほかにも、障害者雇用率未達成の場合、国が企業名を公表するといったペナルティが課せられる可能性があるため注意が必要です。
本記事では障害者雇用率が未達成の場合、どのようなリスクがあるのか、企業名公表や罰則について解説をしていきます。
目次
障害者雇用の法定雇用率が未達成だと罰金や罰則がある?
2025年5月現在の企業の法定雇用率は2.5%となっています。また、2026年7月には企業の法定雇用率が2.7%さらに引き上げられることが予定されており障害者雇用率の達成に課題を感じている事業者の方も増えてきています。
厚生労働省によると令和5年6月1日時点の障害者雇用未達成の企業の総数が53,963社と発表がされています。
障害者雇用の法定雇用率が未達成の場合、罰金や罰則があるのではないかという不安もでてきますが、達成できない場合は実際に次の2つのリスクが伴います。
- 障害者雇用納付金の徴収
- 行政指導を受ける
1.障害者雇用納付金の徴収
未達成企業は、障害者雇用納付金を徴収されます。納付金額は不足1人当たり月額50,000円です。
障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成している企業への報奨金・助成金などに使用されます。
なお徴収の対象となるのは、常用労働者が100人を超える企業のみです。小規模な企業の事業主であれば、納付金の徴収対象外となります。
ただし今後の改正で、さらに厳格化される可能性は0ではありません。小規模な企業であっても、可能な限り障害者雇用に取り組むことが期待されます。
2.行政指導を受ける
法定雇用率未達成の企業には、ハローワーク(公共職業安定所)と厚生労働省が、段階的に行政指導をおこないます。具体的には、次の流れです。
①障害者雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
↓
②障害者雇入れ計画作成命令(2年計画)
↓
③障害者雇入れ計画の適正実施勧告
↓
④特別指導
↓
⑤企業名の公表
一番不安な部分でもある「企業名の公表」は法定雇用率未達成だからとすぐに実施されるたけでなく、特別指導を実施しても改善が見られなかった場合に公表されることになります。
また、実際に上記の行政指導を受けた企業の件数は以下の通りです(令和4年度)
| 段階的に行政指導の内容 | 令和4年度の実績 |
| ハローワークへの雇用状況報告 | ー |
| 障害者雇入れ計画作成命令の発出 | 244社 |
| 計画の適正実施勧告 | 94社 |
| 特別指導の実施 | 55社 |
| 企業名の公表 | 5社 |
法定雇用率達成ならサテラボ
サンクスラボの「サテラボ」なら、テレワーク&サテライトオフィス型の障がい者雇用支援で、法定雇用率の未達成を無理なく解決できます。
障がいのある方の採用から業務切り出し、職場定着までをワンストップで支援し、定着率は99.8%を実現!雇用率未達でお困りの企業様に対し、業務の創出と長期的な定着を両立させる仕組みをご提供しています。
行政指導の内容と企業名公表までの流れ
では、行政指導はどのようなことが行われるのか、雇用状況報告から企業名公表までの流れをそれぞれ解説をしていきます。
1.ハローワークへの雇用状況報告
障害者雇用率を達成しなければならない企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
この報告書の内容から障害者雇用率を達成していない状況がわかった場合は、ハローワークからの行政指導に移行します。
関連:ロクイチ報告とは?障害者雇用状況報告書の提出期限と注意点について解説
2.障害者雇入れ計画作成命令の発出
2年間の障害者雇入れ計画の作成は、ハローワークの所長から障害者雇用率未達成の企業に対して命じられます。障害者雇入れ計画の作成を求められる対象の企業は、以下のように定められています。
- 実雇用率が全国平均未満であり、かつ不足数が5人以上の企業
- 不足数が12以上の企業
- 法定雇用障害者数が3人から4人であり、かつ障害者を1人も雇用していない企業
企業の実雇用率とは、企業で実際に雇用している障害者の割合を算定した数値です。実雇用率は、次の計算式で求められます。
障害者雇入れ計画の作成を求められた企業は計画書を作成し、本社所在地のハローワークに提出しなければなりません。
3.計画の適正実施勧告
ハローワークは計画の1年目終了時(12月)に、計画の実施状況を確認します。
このとき障害者雇入れ計画の実施が不十分と判断された場合は、適正な実施をハローワークが勧告。企業は、もう1年間の障害者雇入れ計画を求められます。
なお、令和2年4月1日から2年間の雇入れ計画作成命令を受けた企業は、250社であったと、令和5年3月に厚生労働省が発表した資料で公表されています。
出典:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」
4.特別指導の実施
2年におよぶ障害者雇入れ計画の期間を過ぎても、障害者雇用未達成の状態が改善されていない場合は、厚生労働省から企業に対して、9ヶ月間にわたる特別指導が実施されます。
- さまざまな雇用事例に関する情報提供
- 助言
- 求職情報の提供
- 面接会への参加推奨
特別指導の対象となる企業の条件
特別指導の対象となる企業の条件は、以下のとおりです。
- 実雇用率が最終年の前年の6月1日現在の全国平均実雇用率未満
- 不足数が10人以上
令和5年3月に厚生労働省が発表した資料によれば、特別指導が実施された企業は、55社にのぼります(対象期間は令和2年4月1日から2年間)。
| 規模別 | 1,000人以上規模企業 | 6社 |
| 1,000人未満規模企業 | 49社 | |
| 産業別 | 建設業 | 2社 |
| 製造業 | 8社 | |
| 情報通信業 | 8社 | |
| 運輸業、郵便業 | 2社 | |
| 卸売業、小売業 | 11社 | |
| 金融業、保険業 | 1社 | |
| 不動産業、物品賃貸業 | 3社 | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 2社 | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 2社 | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2社 | |
| 教育、学習支援業 | 1社 | |
| 医療、福祉 | 5社 | |
| 複合サービス事業 | 1社 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | 7社 | |
| 合計 | 55社 | |
出典:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について」
5.企業名の公表
特別指導後も改善が見られない場合は、それ以上の行政指導はおこなわれません。代わって、厚生労働省から企業名の公表が実施されます。
また、指導を受けても障がい者雇用に改善が見られない場合は企業名が再公表されます。
ただ、ここまでご説明した行政指導の流れからわかるように、企業名の公表はあくまでも最終手段です。計画書の作成とそれに基づく計画の実施、特別指導といった段階を経ても状況が改善されない場合に、企業名の公表がおこなわれます。
障害者雇用率未達成によって企業名が公表された件数
企業名の公表は、厚生労働省のホームページ上でおこなわれます。実際平成18年度以降毎年定期的に実施されており、4年までに45社の企業名が公表されました。
| 平成18年度 | 2社 |
| 平成19年度 | 1社(再公表) |
| 平成20年度 | 4社 |
| 平成21年度 | 7社(うち1社は再公表) |
| 平成22年度 | 6社(うち2社は再公表) |
| 平成23年度 | 3社(うち1社は再公表) |
| 平成24年度 | 0社 |
| 平成25年度 | 0社 |
| 平成26年度 | 8社 |
| 平成27年度 | 0社 |
| 平成28年度 | 2社 |
| 平成29年度 | 0社 |
| 平成30年度 | 0社 |
| 令和元年度 | 0社 |
| 令和2年度 | 1社 |
| 令和3年度 | 6社 |
| 令和4年度 | 5社(うち3社は再公表) |
| 合計 | 45社 |
障害者雇用納付金の徴収については、事業所の規模によって対象外となるケースがあります。しかし企業名の公表については、企業の規模を問いません。
企業名公表で開示される内容と情報開示のリスク
企業名公表で公表される内容は、具体的には次の3点です。
- 企業名
- 行政指導の経過
- 障害者雇用状況の推移など
公表された情報は、インターネット上に長期間にわたって残ります。たとえばクライアントや顧客が企業名を検索した際に、検索結果に表示される可能性があるでしょう。企業イメージに悪影響をおよぼすことが、懸念されます。
障害者雇用の未達成によるリスクを回避する5つのステップ
障害者雇用率の未達成を回避するためには、計画的かつ組織的な取り組みが必要です。以下の5つのステップを実践することで、法定雇用率の達成と障害者雇用の促進を図れます。
- 現状把握と計画立案
- 社内理解の促進
- 労働環境の整備
- 採用活動の強化
- 定着支援策の充足
1.現状把握と計画立案
法定雇用率の未達成によるリスクを避けるためには、「今、自社が何人の障がい者を雇う必要があるのか」を正確に知ることが第一歩です。
現状の雇用率と必要な雇用数を算出したら、部門ごとの配置計画を立てます。
さらに、効果的な障害者雇用を実現するために、以下の多様な雇用形態を検討することも重要です。たとえば、特例子会社を設立する方法があります。
特例子会社とは、障害者雇用に特化した子会社のことで、特例子会社で雇用している障がい者の方を親会社およびグループ全体の法定雇用率に算定することができるというメリットがあります。
2.社内理解の促進
障害者雇用を促進するためには、障害者雇用の重要性とともに法的義務であることを、経営層から現場の従業員まで、社内で共有することが大切です。
障害者雇用は社会的責任であるとともに、多様性のある職場づくりにつながる要素です。社内研修やセミナーを通じて、障害者との協働に関する理解を深め、受け入れ体制を整えましょう。
3.労働環境の整備
障害者が働きやすい環境を整備することは、雇用の促進と定着につながります。バリアフリー化などの物理的な環境改善に加え、業務フローの見直しや補助器具の導入など、障害特性に応じた合理的配慮をおこないます。
また、柔軟な勤務時間や在宅勤務の導入など、多様な働き方を可能にする制度設計も重要です。
こういった労働環境の整備は、障害者はもちろんのこと、既存の社員にとっても働きやすい環境を整える効果につながります。さまざまな条件や特性を持った従業員が、協力しながら快適に働ける環境に整備できれば、社内全体の雇用の促進と安定が期待できます。
4.採用活動の強化
ハローワークや障害者就労支援機関との連携を強化し、適切な人材の紹介を受けましょう。障害者向けの採用説明会や、職場体験の実施も効果的です。
5.定着支援策の充足
採用後の定着支援も重要です。障害のある従業員一人ひとりに対するメンター制度を導入し、日常的なサポート体制を整えましょう。
また障害特性に応じたキャリアパスを設計し、長期的な成長を支援します。定期的な面談や評価制度の見直しをおこない、働きがいのある職場環境を整備することも、離職率の低下と雇用率の維持につながる重要な施策です。
法定雇用率達成ならサテラボ
サンクスラボの「サテラボ」なら、テレワーク&サテライトオフィス型の障がい者雇用支援で、法定雇用率の未達成を無理なく解決できます。
障がいのある方の採用から業務切り出し、職場定着までをワンストップで支援し、定着率は99.8%を実現!雇用率未達でお困りの企業様に対し、業務の創出と長期的な定着を両立させる仕組みをご提供しています。
まとめ
障害者雇用の法定雇用率未達成の場合、障害者雇用納付金の徴収や企業名公表などのペナルティがあります。しかし未達成企業の割合は約49.9%であり、多くの企業が課題を抱えているのが現状です。
まずは障害者雇用の法定雇用率と実雇用率を把握し、社内で一丸となって、労働環境の整備や採用活動の強化、定着支援策の充実を促進しましょう。同時に、特例職員の設置や在宅雇用支援制度の活用など、多様な雇用形態を検討することも重要です。
障害者の能力を最大限に活かせる職場づくりを進めることで、障害者雇用の達成と障害者雇用の質の向上を目指しましょう。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。