障がい者雇用は義務?対象となる企業の条件や違反による罰則について解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2026.01.07
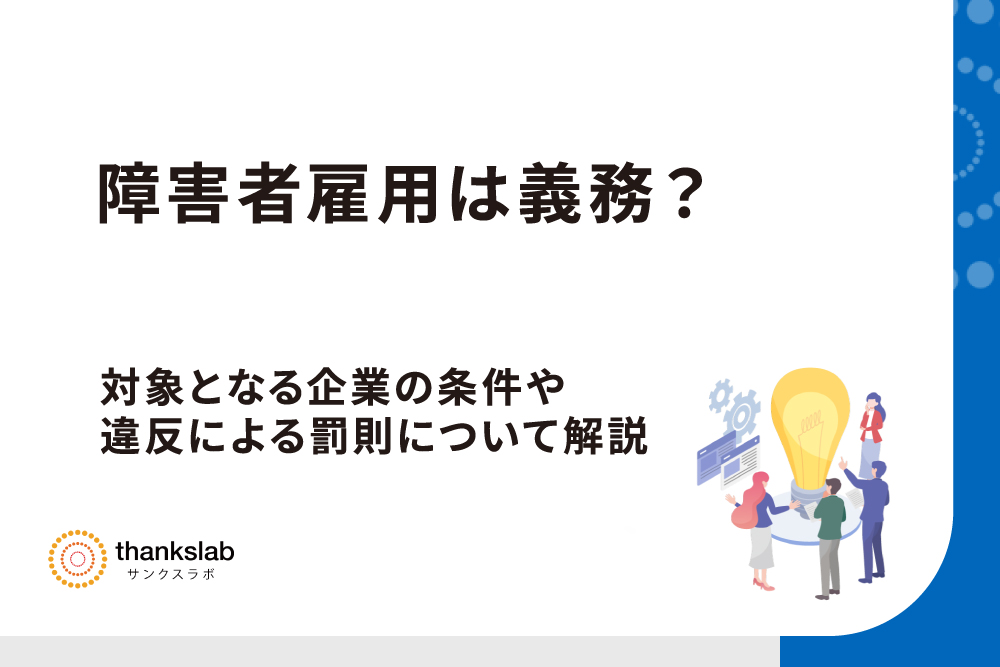
日本では、障害者雇用促進法に基づき常用雇用している従業員が40名以上いる企業には、企業には障害者雇用が義務付けられています。
「職種に関わらず、障がい者を雇用しなくてはならないのか」「障害者雇用促進法に従わない場合は、どのような罰則があるのか?」といった疑問を持っている方もいるでしょう。
本記事では、「障害者雇用促進法」が企業に求めている内容を紹介します。
障がい者雇用の義務とは

現在、日本では「障害者雇用促進法」によって、民間企業・官公庁問わず、障害者を雇用する義務を負っています。「障害者雇用促進法」は、昭和35年(1960年)に制定され、何度か改訂を繰り返し現在に至ります。
会社を運営している経営者の中には、「障害者雇用促進法」の名前を知ってはいるけれど内容はよく知らない方も多いでしょう。ここでは、「障害者雇用促進法」に定められている障がい者雇用の義務について解説します。
障がい者雇用が義務となる企業の条件
2025年4月現在、「障害者雇用促進法」では40人以上の従業員を雇用している民間企業に対して、1人以上の障害者の常用雇用義務を課しています。これを法定雇用率といい、民間企業は2.5%です。なお、法定雇用率は令和8年7月(2026年)には2.7%に変更されます。
2.7%に引き上げられた場合、37.5人以上の常用雇用している従業員がいる企業は1名以上の障がい者を雇用することになります。
なお、40名未満の会社は障がい者を雇用する義務はありません。しかし、会社によっては社会貢献、企業のイメージアップ、などの理由で積極的に障がい者の雇用を行っている企業もあります。
障害者雇用枠の対象になる条件
「障害者雇用促進法」に定められている障がい者とは、以下の条件を満たす方です。
- 身体障がい者:「身体障害者手帳」を所有している
- 知的障がい者:「療育手帳」を保有している
- 精神障がい者:「精神障害者保健福祉手帳」を所持している
また、どの障がいも症状が安定していて、就労可能な状態である障がい者が対象です。
つまり、障がい者である可能性があっても手帳を所有していない方は障害者雇用の枠では就業できません。「自分は生きにくさを抱えているので障がい者である」と名乗る方が障害者雇用の枠で応募してきても、採用したとしても義務を果たしていることにはなりません。
また、就労可能な状態であることも重要です。例えば、「1日1時間程度ならば、なんとか軽作業ができる」といった状態の障がい者を雇ってもやはり義務を果たしたことにはならないので、注意してください。
障害者雇用の義務に違反した場合の罰則は?
障害者雇用の義務がある企業が法定雇用率を達成できなかった、または一人も採用しなかった場合、違反による罰則があるのか気になる方もいるかと思います。
実際、法定雇用率を満たせない企業には大きく分けて2つのリスクが発生します。
- 障害者雇用納付金の徴収
- 行政指導を受ける
未達成企業は障害者雇用納付金と呼ばれるものを納める必要があります。金額は不足している障害者雇用人数1人あたり月額50,000円となるため、不足人数が多いほど企業に負担となります。
また、法定雇用率が達成できていないと行政指導が入り、改善が見られない企業は最悪の場合、企業名を公表されます。
こういったリスクのあるため、障害者雇用の義務がある企業は法定雇用率を達成するために気を付ける必要があります。
法定雇用率が未達成の場合の罰則・リスクについては「障害者雇用率未達成だとどうなる?企業名公表や罰則について解説」でより詳しく解説しているのでよかったらご参考ください。
障がい者雇用の現状
厚生労働省は、毎年「障害者雇用状況の集計結果」を発表しています。令和5年度の集計結果のよると、民間の企業では雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新しました。雇用障害者数は64万2,178.0人、対前年差2万8,220.0人増加、前年比からは、4.6%の増加となっています。
実雇用率2.33%で、対前年比0.08ポイント上昇しました。法定雇用率達成企業の割合は50.1%となり、対前年比1.8ポイント上昇しています。
しかし、それでも法定雇用率達成企業は全体の半分程度にとどまっています。近年は労働力不足が深刻な問題となっており、外国人の労働者に頼らざるを得ない企業もたくさんあります。障がい者の雇用がすすめば労働者不足の解消につながる可能性がありますが、現実はなかなか難しい状態です。
その一方で、「障害者雇用状況の集計結果」は、障害者雇用の枠で就職した障がい者しかカウントしていません。「障害者雇用促進法」に定められた条件に当てはまらない形で、就業している障がい者もたくさんいます。したがって、日本全体の障がい者雇用を正確に反映している集計結果でないことは、覚えておきましょう。
障がいのある方に任せる仕事に制限はない
「障害者雇用促進法」では、障がいのある方に任せる仕事に制限はありません。例えば、金融会社に就職したからといって、経理や営業をしなければいけないといったルールはないのです。
例えば、製造業や小売業を行っている会社で、清掃やメールの仕分け、書類のファイリングのみの仕事を行っていたとしても問題はありません。
そのため、「農園型障害者雇用支援サービス」のように、外部の業者に依頼して障がい者が働きやすい仕事を別途用意する会社もあります。また、「特例子会社」を設立する 会社もあります。
障がい者が働きやすい仕事を外部委託で用意したり、特例子会社を設立したりすることで、障がい者が働きやすい環境を整えられます。これにより、障がい者の勤務年数が長くなったり、仕事を覚えやすくなったりといったメリットもあるでしょう。その一方で、「この仕事をしたかったのに、まったく別の仕事を任された」といった不満を抱く方もいます。
この辺りは、双方の意見をすり合わせることが大切です。
障がい者雇用の基本的な流れ

障がい者を雇用する基本的な流れは以下のとおりです。
- 障害者雇用を検討し、従業員の意見を聞いて障がい者雇用に関する理解を深める
- ハローワーク・地域障害者職業センターなど支援機関への相談する
- ジョブコーチや障がい者を雇用する企業向け研修などを受ける
- 障がい者を受け入れる部署を決定して仕事を選定する
- 就労に必要な備品や設備を会社が整える
- 募集人数や採用時期を正式に決定する
- ハローワークや民間の就職サイトに求人を出す
- 雇用
- 雇用継続・定着のための施策実行
求人を出してからの流れは、一般的な求人と変わりありません。一方、特に初めて障がい者を雇用する場合は、求人を出すまでの準備を整える必要があります。
ハローワークには、企業側の障がい者雇用をサポートする制度がたくさんあります。 利用できるものは積極的に利用したほうが、障がい者の雇用がスムーズに進みます。
障がい者雇用をするメリット
障がい者の雇用は、ある程度の規模の会社に義務付けられていますが、メリットもあります。ここでは、会社が障がい者を雇用するメリットを解説します。
助成金や支援制度を利用できる
障がい者を雇用すると、国から助成金を受け取れます。また、支援制度も利用できます。助成金は、障がい者を雇用しつづけるために職場の環境を整えるために利用できます。
また、支援制度を利用すれば障がいに対する理解も深まり、二度目、三度目の障がい者雇用を行う際にも役立つでしょう。
業務の見直しができてSDGsに貢献できる
障がい者が働きやすい職場は、一般の従業員も働きやすい職場です。障がい者雇用をきっかけに職場の制度などを見直せば、改善点がたくさん見つかる可能性もあります。
また、障がい者を多く雇用すれば、企業のイメージもあがりSDGsにも貢献できるのがメリットです。障がい者雇用がうまくいけば、自治体の宣伝等にも使ってもらえるので、知名度をアップするメリットもあります。
障がい者雇用する際の注意点
障がい者を雇用する際は、以下のような注意点があります。
- 障がい者を雇用する場合はサポート役を誰かに押し付けない
- 障がい者の意見を聞けるような環境を整える
- 障がい者の仕事を作ったうえで求人をする
- 必要ならば外部のサポートを依頼する
障がい者雇用をする場合、一般の中途入社者や新卒者に比べると仕事を覚えるまでに時間がかかる場合も多いです。サポート役が必須ですが、特定の部署や人物だけに押し付けないようにしましょう。
特定の人物や部署だけに負担が重くなると、人間関係がぎくしゃくしたり仕事が滞ったりします。 トライアル雇用を利用して障がい者雇用に慣れてもらう、必要ならば外部のサポートを依頼するなど工夫が必要です
まとめ
本記事では、「障害者雇用促進法」の概要や会社に国が求めることなどを紹介しました。
障がい者雇用は、より幅広い人々が働きやすいように職場を整えることにも通じます。障がい者雇用が義務付けられる従業員数になったら、良い機会ととらえて会社の業務や設備を見直してみるのもおすすめです。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







