障がい者雇用での解雇・雇止めの注意点とは?合理的配慮についても解説
- 公開日:
- 2026.01.15
- 最終更新日:
- 2026.01.15
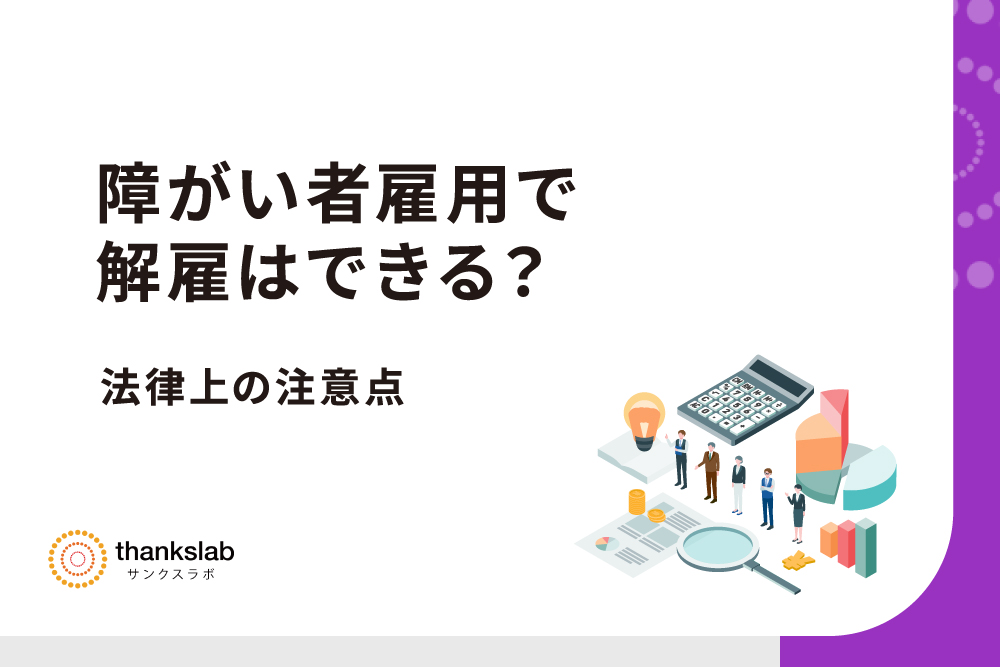
「障がい者雇用で、障がいを抱える方を雇い入れた。しかしこのまま雇い続けることは難しいので、解雇したい」と考える経営者もいるでしょう。
そこで今回は、「障がい者を解雇することの法律的解釈」「解雇が認められる理由」「解雇時の助成金などの取り扱い」を解説します。
なお、解雇の合理性判断の要素となる「合理的配慮」について詳しく知りたい担当者の方は、以下の資料もご覧ください。
【無料でダウンロードする】「合理的配慮提供の義務化」進め方ガイドブック

<この資料でわかること>
・合理的配慮の基本理解
・合理的配慮の具体的な実施ステップ
・合理的配慮の他社事例
目次
「障がい者であること」を理由として解雇することは違法となる
まず、日本では一度雇い入れた障がい者を解雇することには高いハードルがあるということを理解しなければなりません。
その理由として、以下の2点があげられます。
・日本では労働者の権利がかなり強く守られている
・障がい者の場合はさらに解雇が難しい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
日本では労働者の権利がかなり強く守られている
日本では、障がいの有無にかかわらず、すべての労働者の権利が法律によって強く保護されています。そのため、企業が労働者を自由に解雇することはできません。
例えば、労災による休業期間中およびその後の30日間は、解雇が法律で禁止されています。
また、性別や出産・育児・介護を理由とした解雇も認められていません。
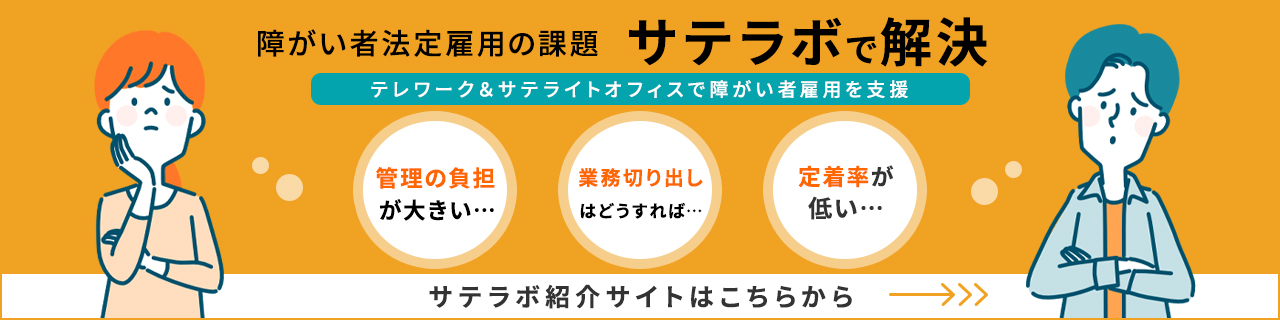
障がい者の場合はさらに解雇が難しい
日本では労働者の権利が法律によって強く保護されていますが、障がい者に対する権利保護は、さらに手厚く設けられているといえます。
「障害者差別禁止指針」において、
“イ 障害者であることを理由として、障害者を解雇の対象とすること。
“ロ 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
“ハ 解雇の基準を満たす労働者の中で、障害者を優先して解雇の対象とすること。
ー引用:厚生労働省「障害者差別禁止指針 障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」p7
「障がい者であることを理由として解雇することは認められない」はもちろん、解雇対象者が複数人いる中であっても、特別な配慮を必要とする障がい者を優先して解雇することは違法とされている点には注意が必要です。
なお、これは労働契約の更新においても同様であり、障がいを理由に契約更新を拒否したり、不利な条件を提示したりすること、障がいのない方を優先して更新の対象とすることも、法律により禁止されています。
一般の労働者は、労働基準法や労働契約法、男女雇用機会均等法などによって権利が守られていますが、障がい者にはこれらに加えて、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の権利も適用されます。
そのため、障がい者の解雇は、そうではない方と比べてさらに厳しく制限されています。
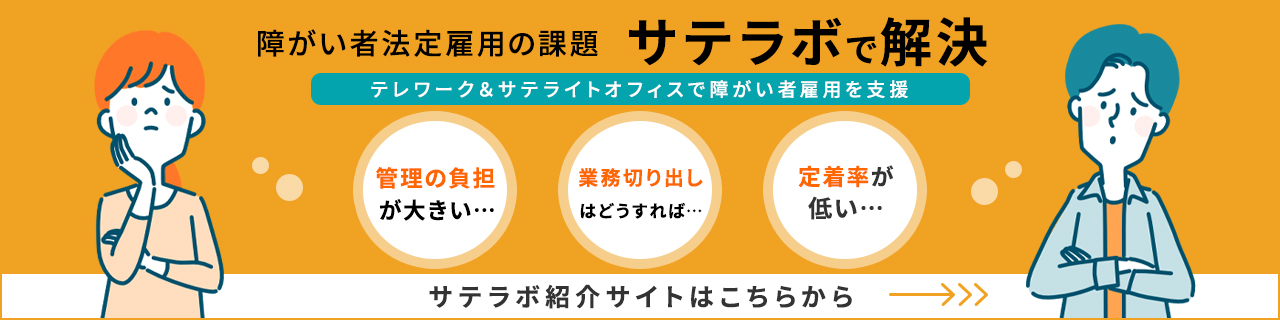
「解雇」と「雇い止め」の違い
労働契約を終了させる場面では「解雇」と「雇い止め」という言葉が使われますが、法的な意味や扱いは大きく異なります。
ここでは両者の定義や違いを整理し、実務上注意すべきポイントについて解説します。
「解雇」とは何か
解雇とは、使用者が解約権を行使することにより、労働者の意思にかかわらず一方的に労働契約を終了させることを指します。
解雇は使用者にとって強い権限行使となるため、労働基準法や労働契約法により厳しい制約が設けられています。客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければ、解雇は無効と判断される可能性があります。
また、原則として30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いも必要となります。
「雇い止め」とは何か
雇い止めとは、有期労働契約において、使用者が労働者の意向にかかわらず契約更新を行わず、契約期間の満了をもって労働契約を終了させる取扱いを指します。
形式上は期間満了による終了であり、解雇とは異なり、契約を途中で打ち切るものではありません。
ただし、契約が反復更新されていた場合や、労働者が更新を期待することに合理性がある場合には、雇い止めが問題となることがあります。このようなケースでは、実質的に解雇と同視され、合理的な理由や適切な手続が求められる点に注意が必要です。
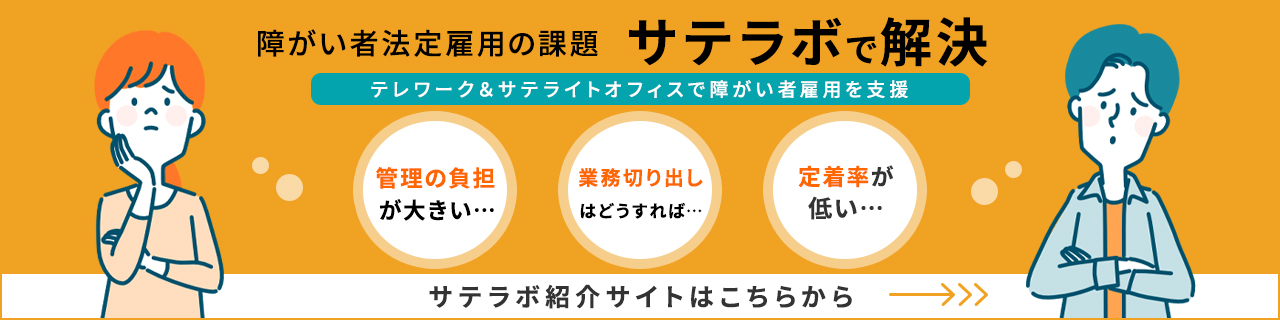
障がい者の解雇が正当であるケース
障がい者の解雇は、非常に難しいものです。ただし、「一度障がい者を雇い入れたら、絶対に解雇できない」というものではありません。
「正当な理由」とは、以下の通りです。
・就業規則や、社会通念上守るべき項目を守れていなかったことによる正当な解雇
・業績の不振によるもの
なお、正当な理由に該当すると考えられる事例であっても、実際の判断は個別のケースをよく精査した上で行われます。そのため、解雇を考えている場合は、専門家に相談したほうが安心です。
就業規則や、社会通念上守るべき項目を守れていなかったことによる正当な解雇
「仕事をしていく上で、当然に守るべき社会通念や、就業規則を守れていなかった」と判断される場合は、障がい者であっても解雇対象とできます。
例えば、「特段の理由もなく、無断欠勤や無断遅刻、無断早退を繰り返す」「仕事中であるにもかかわらず、緊急の要件でもない私用電話を何度も行っている」「昼休みに外に出て、昼休みが終わってもずっと喫茶店にいる」などのような状況です。
また、このような状況に対して、周囲が再三にわたって指導や注意、叱責を行っていたにもかかわらず、まったく改善しなかった場合は、解雇理由となります。
「障がいを抱えていることは、社会通念上当然とされる職務態度や就業規則を守らなくても良いという理由にはならない」と判断されるわけです。
業績の不振によるもの
「ずっと障がい者を雇い続けてきたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響もあり、業績が不振になった」「新しい技術の台頭により売り上げが落ちて、今まで通り従業員を雇い続けることが難しくなった」という場合は、従業員の整理解雇が必要になる場合もあります。
ただ、もともと整理解雇は、企業側が一方的に従業員側を解雇するものであるため、非常に厳しい制限が設けられています。
まず企業側が整理解雇を行う場合は、
・人員整理の必要があると判断される経営状況であること
・希望退職者を募り、配置換えなどの対策を行い、解雇を避けるための可能な限りの努力をしたにもかかわらず、解雇が必要になった
・人員の整理基準が、客観的な視点に基づいた公平なものである
・従業員に対して、しっかりと説明をした
などの条件を満たす必要があります。
整理解雇が必要になった場合かつ上記の条件を満たした場合、企業は障がい者も解雇対象とできます。
しかしすでに述べたように、障がいそのものを理由にした解雇は認められませんし、整理解雇のときにも「他の部署に配置換えができないか」などの検討を事前に行う必要があります。
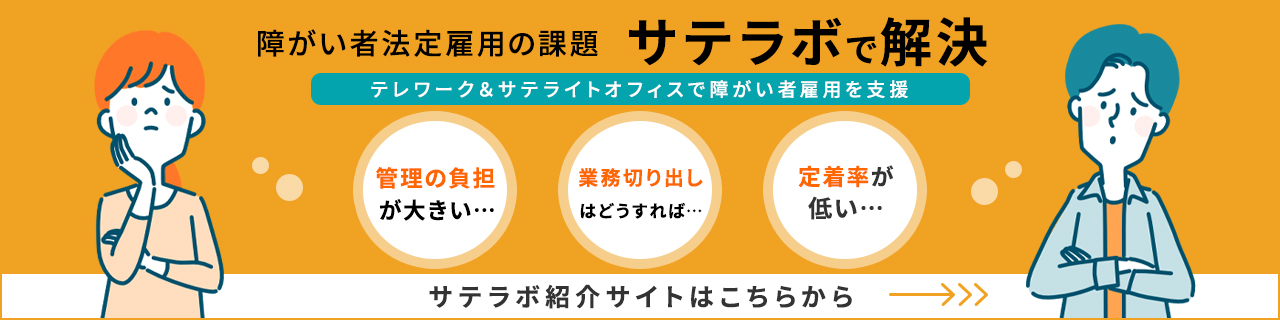
障がい者の解雇前に企業が行うべき「合理的配慮」
障がいのある従業員の雇用を継続するか検討する際、企業には解雇を判断する前に「合理的配慮」を尽くすことが求められます。合理的配慮は法的義務として明確化されており、適切に対応しなければ企業リスクにも直結します。
ここでは、解雇前に企業が押さえるべき合理的配慮の考え方と実務上のポイントについて解説します。
▼「合理的配慮」についてより詳しく知りたい方はこちら
「合理的配慮とは?職場での具体例や企業の義務化について簡単に解説」
「合理的配慮」とは
合理的配慮とは、障害者差別解消法の改正により、2024年4月から事業者にも提供が義務化された考え方です。
行政機関や事業者が事務・事業を行うにあたり、個々の場面で障がいのある方から社会的バリアの除去を求める意思表示があった場合に、過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことを指します。
内閣府のリーフレットでは、以下のように定義されています。
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
引用:内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
具体例
合理的配慮は、職場環境や業務内容に応じて柔軟に検討されます。
例えば物理的環境への配慮として、車椅子利用者が働きやすいよう作業スペースを確保するケースがあります。
また、意思疎通への配慮として、難聴と弱視の双方に配慮し、太いペンで大きな文字を使った筆談を行う対応もあげられます。
さらに、業務ルールの柔軟な変更として、板書を書き写すことが困難な場合に、撮影やデータ共有を認めることも合理的配慮に該当します。
注意点
合理的配慮は無制限に求められるものではなく、業務の目的や機能に照らして、必要な範囲に限られることが前提です。
具体的には、以下の3つを満たす必要があります。
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
引用:内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
また、障がい者の方にとって特定の仕事が「過重な負担」に当たるかどうかは、企業規模や職場状況などを踏まえ、個別具体的に総合判断する必要があります。
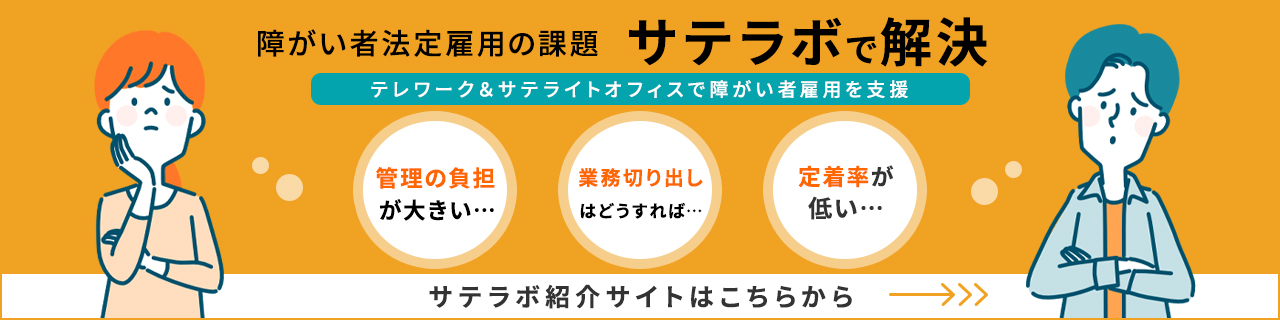
障がい者雇用で解雇した場合、助成金や処分はどうなる?
最後に、「さまざまな理由があり、障がい者を解雇した場合、企業はどのような対応をとらなければならないか」について解説します。
障がい者解雇届の提出が求められる
障がい者雇用を止め、障がい者を解雇した場合、企業側は速やかに解雇届を提出しなければなりません。
これは障がい者雇用促進法81条1項に定められたもので、提出先はハローワークです。速やかに解雇届が届けられることで、障がい者はすぐに次の職場を探すことができるようになりますし、ハローワークもさまざまな支援を行いやすくなります。
ちなみにかつては紙媒体で提出していたこの解雇届ですが、現在は電子申請でも行えるようになりました。
場合によっては助成金を全額返金しなければならない
障がい者を雇い入れた企業には、助成金が出されます。細かな金額はここでは取り上げませんが、かなり金額は大きく、その支援額が100万円を超えるケースもあります。
この助成金は、障がいを抱える方を雇い続ける企業に対して出されるものであるため、対象従業員を解雇した場合は当然助成金を受け取り続けることはできません。
▼障がい者雇用の助成金について詳しくはこちら
「【2025年最新】障がい者雇用の助成金一覧!受給条件や注意点も詳しく解説」
また、それのみならず、場合によっては返金請求が出されることもあります。「企業側の責任で対象の障がい者を離職・解雇した場合は、全額返還を求めることもある」とされているため、注意が必要です。
加えて、以下でも詳しく触れますが、解雇によって障がい者の法定雇用率を下回った場合は、助成金の全額返金を求められることのみならず、障害者雇用納付金の納付が求められます。
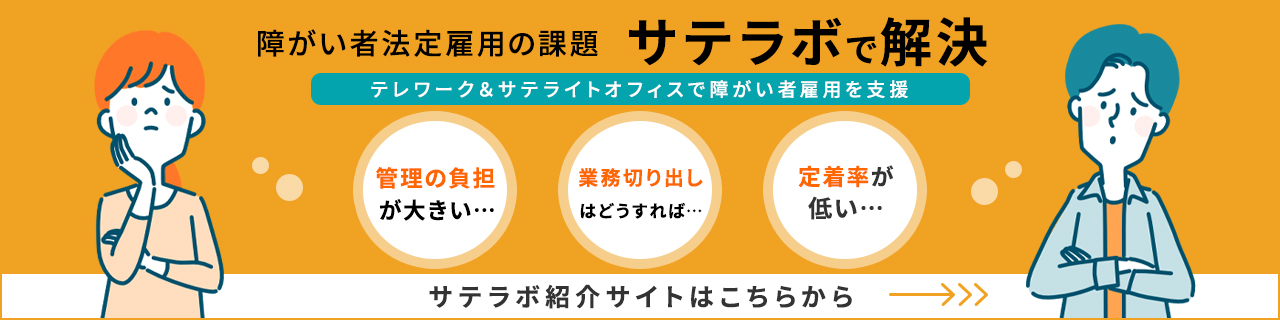
解雇によって法定雇用率を下回った場合は企業名の公開にいたることも
日本では「(障がい者の)法定雇用率」という考え方があります。これは、「企業(40人以上)は、従業員の一定割合を障がい者としなければならない」と定めているもので、基本的には2.5%(100人うち2~3人、ただし除外率が適用される業種もあり)とされています。
障がい者を解雇したことで、この法定雇用率を満たさなくなってしまうことがあります。法定雇用率を満たさなくなった企業は、場合によっては企業名を公表されてしまいます。これは特にBtoCの企業にとって、大きなイメージダウンとなります。
ただ、この「企業名の公表」は即時行われるわけではありません。
「2月に障がいを持つ従業員を解雇した。そうすると、3月の障がい者の雇用率が2.4%になってしまった。企業名が公表されてしまうのではないか」と不安に思うことはありません。企業名の公表にいたるまでには、何度か国からの警告が行われるため、解雇した後にまた新しく障がいを抱える方を雇い入れれば問題はありません。
▼雇用率未達成の場合の取扱いについて詳しくはこちら
「障害者雇用率未達成だとどうなる?企業名公表や罰則について解説」
まとめ
これまで「障がい者雇用と解雇」について解説をしてきました。
今回の内容をまとめると以下の通りです。
・障がい者の労働の権利は、そうではない方に比べてより強く守られている
・ただし、「業績の不振によるもの」「企業側が合理的な配慮をしているにもかかわらず、十分に働いていなかった」「就業規則や社会通念上守るべき項目を守れていなかった」などのような場合は、解雇対象となりえる
・障がい者を解雇した場合、「解雇届の提出」「場合によっては助成金の全額返金および障害者雇用納付金の納付」が求められる
・改善が見られない場合は、企業名の公表に至る
障がいを持つ方を一度雇用した場合、解雇にはさまざまな制限がかけられます。そのため、常に「より良い働き方は何か」「適切な配慮はできているか」などについてしっかり考える必要があるでしょう。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







