障害年金とは?もらえる条件などわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
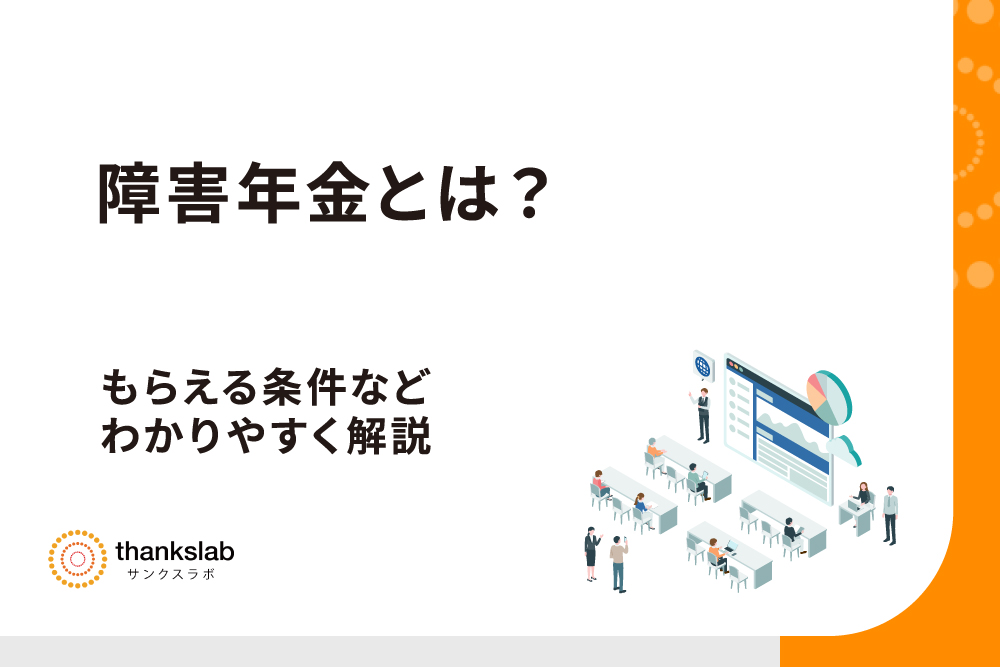
障害年金は、病気やけがにより日常生活や就労に困難を抱える方々の生活を支えるために設けられた公的制度です。
しかし、その仕組みは複雑で、申請の条件や手続きについて悩む方も少なくありません。
そこで、当記事では、障害年金の概要や受給要件、申請の流れをはじめとして、誤解されがちな点や申請時の留意点、不支給となった場合の対応策などを解説します。
目次
障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで生活や仕事が難しくなった方が、国から受け取ることができるお金(年金)です。
事故や病気は突然やってくるものですが、そんなときに生活の支えとなってくれるのが障害年金となります。
「年金」と聞くと高齢者向けの制度と思われがちですが、対象となるのは働くことが困難な20歳以上の65歳未満の方が対象です。
また、「20歳前傷病」と呼ばれる先天性疾患や20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある傷病により、法令で定める2級以上の障害状態に該当する方も障害年金を受け取ることが可能です。
■ 対象となる人の例
障害年金の受給対象となる方の例を見ていきましょう。
例えば、
・交通事故で手や足が不自由になった
・心臓や肺の病気で働くことがむずかしくなった
・精神疾患(うつ病、統合失調症など)で日常生活が困難
・発達障がいなどにより就労が安定しない
といったケースなどが該当します。
障害年金の対象は、事故で障がいを負った人や生まれつき障がいがある方だけではありません。精神疾患や発達障がいをはじめ、がんや指定難病、中には糖尿病でも障害年金の対象になっている方もいらっしゃいます。
医師による診断や障がいの程度(等級)によって、客観的に働くことができない状態だと認められることが重要です。
■受給のための条件
障害年金を受け取るためには、次の3つのポイントが大事です。
初診日
「初診日」とは、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日を指します。障害年金の申請において非常に重要な基準日であり、他の要件の判定基準にもなります。
申請時には、初診日の証明として当時受診した医療機関の「受診状況等証明書」が必要です。廃院などで証明が難しい場合は、診察券やお薬手帳などを用いて申立書を提出する方法もあります。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料の納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること。
・または、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例要件、令和8年3月31日までに初診日がある場合)。
初診日が平成3年4月30日以前の場合は、異なる基準が適用されます。
障害認定要件
原則として、初診日から1年6か月を経過した日(またはその期間内に症状が固定した日)を「障害認定日」とし、その時点で一定以上の障害等級に該当している必要があります。
障害認定日に等級に該当しない場合でも、その後に悪化して条件を満たせば、「事後重症」として申請することができます(原則、65歳の誕生日の前々日までに請求が必要です)。
障害年金の種類は?

障害年金には、
・障害基礎年金
・障害厚生年金
の2つの種類があります。
以下に簡単に説明を表にまとめます。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
| 制度の位置づけ | 国民年金に基づく | 厚生年金に基づく |
| 対象者 | 自営業、学生、無職など | 会社員、公務員など |
| 等級 | 1級、2級 | 1級〜3級(+障害手当金) |
| 年金額の特徴 | 一定額(定額制) | 報酬比例(加入期間と収入により変動) |
| その他の特徴 | 20歳未満の障がいも対象になることがある | 基礎年金に上乗せして支給される場合あり |
障害年金=障害基礎年金+障害厚生年金(+障害手当金)というイメージで、厚生年金の方は、障害基礎年金に「上乗せ」されて障害厚生年金を受け取ることができます。
つまり、会社員や公務員で厚生年金を支払っていた方のほうが、より手厚い支援を受けられる仕組みです。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どちらを受給できるかは、障がいの原因となった病気やけがの初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害基礎年金
国民年金に加入していた方が対象で、主に自営業・学生・無職の方などが該当します。
また、20歳未満で発症した場合も対象となります。
支給対象は1級または2級に該当する障がいを持つ方です。
障害厚生年金
厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象です。
1級〜3級まで支給対象であり、3級未満の軽度な障がいであっても、一定条件下で一時金として「障害手当金」が支給されることがあります。
支給額は報酬に応じて計算され、基礎年金よりも高額となる場合が多いです。
ちなみに、4級以下は一時金として障害手当金が支給される形となります。
基礎年金との併給
厚生年金加入中に初診日がある場合、障害等級が1級または2級に該当すれば、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の両方を受給できます。
これは年金制度が「基礎年金+厚生年金」の二階建て構造となっているためです。
障害年金の等級とは?

詳細は日本年金機構にありますが、障がいの程度に応じて障害年金の等級は定められています。
障害基礎年金では1級と2級、障害厚生年金では1級から3級までの等級があり、数字が小さいほど重度の障がいとされ、受給額も高くなります。
なお、障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なる独自の基準に基づいて決まります。たとえば、精神障害者保健福祉手帳で3級の方が、障害年金では2級に認定される場合もあります。
また、障害者手帳を持っていなくても、障害年金の要件を満たしていれば申請・受給は可能です。年金制度における障がいの判断は、医師の診断書などをもとに、年金機構が独自に行うためです。
■支給される金額の目安(2024年時点)
障がいの等級や年金の種類によって支給額は変わります。
受給の一例は、
| 障害基礎年金2級 | 年間約80万円(月あたり 約6万6千円) |
| 障害基礎年金1級 | 年間約100万円以上(月あたり 約8万3千円) |
などです。
さらに、18歳未満の子どもがいる場合などは、「子の加算」もついて支給額が増えることもあります。
障害年金を受け取る流れは?
■申請の流れ
障害者年金を申請するには、下記のような手続きの手順を取ります。
①初診日を確認する
最初にその病気・ケガで病院にかかった日が「初診日」として重要になります。
②診断書などの書類を集める
医師に依頼して、専用の診断書を作成してもらいます。
③申請書類を準備して提出する
必要な書類をそろえて、年金事務所または市役所に申請します。
④審査を受けて、結果が届く
審査に1〜3か月ほどかかることがあり、受給できるかどうかの通知が届きます。
障害年金によくある誤解とは?

障害年金に関する情報は多岐にわたり、インターネットや周囲からの話の中には、正確とは言えないものも含まれています。
その結果として、本来受給の可能性がある方が、「自分は対象外である」と誤って判断し、申請を諦めてしまうことも少なくありません。
ここでは、特に多く見受けられる誤解とその実際について整理いたします。
「働いていると受給できない・収入があるともらえない」という誤解
障害年金は、働いているかどうかや収入の有無ではなく、日常生活や仕事にどれだけ支障があるかで判断されます。
そのため、短時間勤務や配慮のある職場で働いていても、困難があれば受給できる場合があります。
また、原則として収入制限はありませんが、例外として「20歳前に発病した人」が受け取る障害基礎年金には、所得が一定額を超えると減額・停止の可能性があります。
精神疾患は対象外であるという認識について
精神疾患も、障害年金の受給対象となる疾患に含まれます。
例えば、うつ病、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、発達障がいなどがこれに該当します。
実際に、精神疾患を原因とした受給件数は増加傾向にあり、障がい等級の判定基準も明確に定められています。ただし、認定に際しては医師の診断書の内容と、日常生活への支障の程度が重視されるため、十分な準備と記録の整備が求められます。
過去の発症に対する申請は不可能か
過去に発症した病気に関しても、「初診日」が特定でき、その当時の状況を証明する資料が揃っていれば、障害年金を申請できる場合があります。
診察券、カルテ、診療明細書、または病院名が記されたメモなどが証拠として活用されます。
また、一定の条件を満たす場合には、「遡及請求」により過去にさかのぼって年金を受け取ることも可能です。
不支給だったときの対処法

障害年金を申請したものの、「不支給」と通知が届くこともあります。
不支給の通知が来たら終わりではなく、まだ取れる行動があるのでまとめていきます。
「審査請求」という再チャレンジ制度
不支給になった場合、まずできるのが「審査請求」という制度です。
これは、結果に納得できないときに異議を申し立てる制度のことを指します。
通知を受け取ってから60日以内に行う必要があるので気を付けましょう。
申請時の資料を見直して、医師の診断書や申立書に不備がないかを再度チェックすることも大切です。審査請求で認定されたケースも珍しくありません。
再申請・社労士への相談も選択肢
体調や状況に変化があった場合は「再申請」も可能です。
また、初回の申請を自分で行っていた方は、社労士(社会保険労務士)に相談するのもおすすめです。相談を行えば、専門的な目で資料をチェックし、通過しやすい形に整えてくれるサポートを受けられます。
障害者手帳との違いは?

「障害年金と障害者手帳ってどう違うの?」と混乱する方も多いですが、実は目的や内容がまったく異なる制度です。それぞれの違いを整理しておきましょう。
| 障害年金 | 障害者手帳 | |
| 目的 | 収入の保障 | 日常生活の支援 |
| 内容 | 月々のお金が支給される | 割引や支援制度が使える |
| 必要書類 | 診断書、病歴・就労状況等申立書など | 医師の意見書、本人確認書類など |
| 主なメリット | 生活費の一部が補える | 交通費の割引、税金の控除、就労支援などが受けられる |
つまり、お金をもらうための制度が障害年金で、日常生活の便利さをサポートするのが障害者手帳というイメージです。もちろん、両方を持っている方も多く、併用して支援を受けることができます。
他に活用できる支援制度の紹介

障害年金をもらえるようになったとしても、経済的な不安や生活の悩みはゼロにはなりません。ここでは、障害年金と併用しやすい支援制度やサービスを紹介します。
自立支援医療(精神通院)
精神科や心療内科に通院している方は、医療費が原則1割負担になる制度です。障害年金とは別の申請が必要ですが、費用を大幅に抑えることができます。
障害者控除
障害者手帳を持っている方や、障害年金の受給者が対象になることが多い制度です。確定申告や年末調整で「所得控除」が受けられ、所得税や住民税が軽減されることがあります。
生活福祉資金貸付制度
生活が困難な場合、市町村の社会福祉協議会を通じて無利子・低利子でお金を借りられる制度です。医療費や家賃、生活費に困ったときの選択肢として活用できます。
まとめ
障害年金は、障がいを抱えながらも安心して暮らすための大切な制度です。
今回の記事のポイントをまとめると、
・障害年金は働くことや生活が難しい人のための年金で、心の病気や発達障がいも対象になる。
・申請には、初診日・保険料・障害の重さ(等級)の3つがカギ。
・手帳なしでも申請可能、不支給でも再申請や異議申立てができる。
ということです。
「自分や家族が対象になるかも?」と感じたら、まずは市区町村の窓口や年金事務所に相談してみましょう。無料で相談できる「年金相談センター」もありますし、社労士(社会保険労務士)に手続きの代行を依頼することも可能です。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







