一般就労と障害者雇用の違いをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
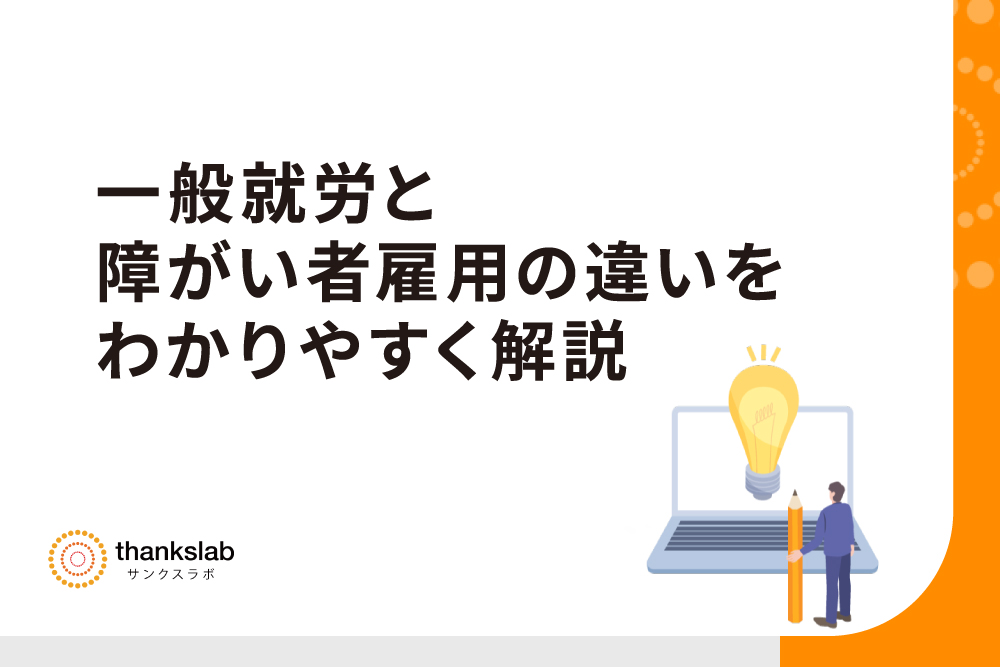
障害者雇用という言葉を聞いたことはあっても、どういった仕組みなのか分からない。そのように思われている方も多いのではないでしょうか。
障害者雇用は、特性の配慮を受けながら働くことができるので、障がいを持つ方が自身の能力を最大限に発揮し、安定した就労を得ることができるので助かる一方で、一般就労とは異なるデメリットも出てきます。
そこで、本記事では、一般就労と障害者雇用の違いについて詳しく解説し、求職者が自分に合った働き方を見つけるための情報をご紹介します。
一般就労と障害者雇用の違い
| 項目 | 一般就労 | 障害者雇用 |
| 募集形態 | 通常の採用枠 | 障がい者枠 (法定雇用率あり) |
| 採用基準 | 一般的な基準 | 個々の障がい特性に応じた考慮 |
| 勤務形態 | フルタイム・契約社員など多様 | 短時間勤務や特例制度あり |
| 配慮 | 特になし(自己責任) | 合理的配慮が義務付けられる |
両者の主な違いは、特別な配慮がない通常の雇用形態が一般就労であるのに対して、障害者雇用は企業が障害者雇用促進法に基づき、合理的配慮を提供する義務があることです。
一般就労、障害者雇用共に、どちらを選んでも障がいを持つ方にとって、それぞれメリット・デメリットが存在します。
また、障がいを持つ方が一般雇用枠に応募する際に、「クローズ就労」を選ぶか「オープン就労」にするかという選択も出てきます。
クローズ就労とオープン就労
| クローズ就労 | 障がいがあることを公開しないで働くこと |
| オープン就労 | 障がいがあることを公開した上で働くこと |
このように、障がいがあることを企業側に公開するかどうかの違いが、クローズ就労とオープン就労の差です。
一般雇用の方が選べる職種が広がりますが、障害者雇用に比べて採用率が下がる可能性もあります。また、障がいを持つ方への合理的な配慮が期待できないため、定着しにくいという問題も懸念されます。
障害者雇用とは?
障害者雇用ってどんなもの?
障害者雇用とは、障がいのある方が自分の力や得意なことを生かしながら働けるように、職場や仕事の内容などに工夫を加えて行う雇用のことです。
単に働く機会をつくるだけではなく、安心して長く働き続けられる環境を整えることがとても大切とされています。
その方のペースに合わせた働き方や、必要なサポートを取り入れながら、「働きたい」という気持ちを社会全体で支える仕組みです。
障害者雇用のルールは?
障害者雇用の土台になっているのは、「障がい者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」という法律です。
この法律は1960年から続いていて、時代の流れに合わせて何度も見直されています。
例えば、常時40人以上の従業員がいる企業には、全体の2.5%以上(2024年時点)の障がい者を雇う義務があります。
また、国や自治体の場合は、もう少し高く2.6%とされています。もし企業がこの割合を満たしていない場合は、「障害者雇用納付金」という形で金銭的な負担が発生する場合もあります。
こうした制度によって、障がいのある方が働ける場を社会全体で広げていくことが期待されています。
対象者は?
障がい者雇用の対象になるのは、以下のような方です。
・身体障害者手帳を持っている方
・療育手帳(知的障がいのある方)を持っている方
・精神障害者保健福祉手帳を持っている方
・発達障がいなど、医師から一定の診断を受けている方
特に発達障がいを含む精神障がいのある方については、2006年から法定雇用率の対象にも加わっています。
障害者雇用はなぜあるの?
障害者雇用は、ただの「企業の義務」ではありません。
働く方にとっても、企業にとっても、そして社会全体にとっても、とても意味のある取り組みとなっています。
例えば、
・障がいのある人が「社会の一員」として活躍し、自分らしく生活できる
・経済的にも自立し、安心できる生活を築くきっかけになる
・職場に多様な方がいることで、思いやりや柔軟な発想が生まれる
・社会全体が「誰もが働ける環境」へと近づく
などといった、障がいがあっても働けることが当たり前の社会づくりを目指す雇用システムです。
一般雇用と障害者雇用の働き方の違いは?
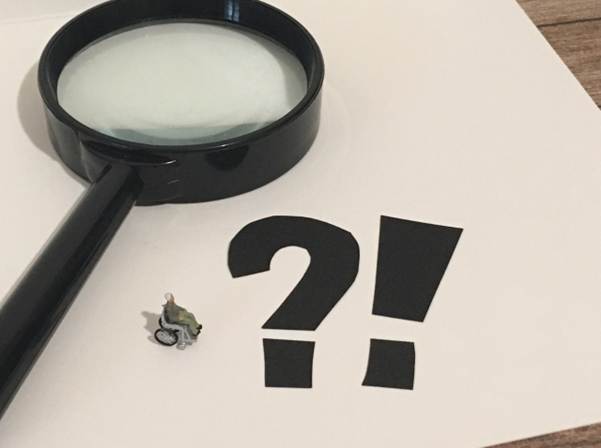
一般雇用と障害者雇用の働き方の違いを比較していきます。
【障害者雇用と一般雇用の比較】
| 項目 | 障害者雇用 | 一般雇用 |
| ① 勤務時間の柔軟性 | ● 体調や通院への配慮あり。 ・短時間勤務、週4勤務、時差出勤などが可能。 ・在宅勤務も選べる場合があり、通勤の負担が減る。 ・「今日は体調が良くない」などの状況に合わせて柔軟な対応がしやすい。 | ● 原則フルタイム(8時間勤務) ・勤務時間・出勤日数は一律で、調整は難しいことが多い。 ・急な早退・遅刻・中抜けは業務に支障が出るため配慮されにくい。 |
| ② 仕事内容の調整 | ● 一人ひとりに合わせて業務内容を調整。 ・得意、不得意を事前に共有しやすい。 ・簡単な作業や定型業務からスタートできる。 ・必要に応じて仕事内容の変更や再調整も相談可能。 ・マニュアル・視覚的サポートの工夫もある。 | ● 配属先で必要とされる業務をこなす必要がある。 ・業務量・業務内容の個別調整は原則行われない。 ・体調や特性に合わせて仕事を選ぶことは難しい。 |
| ③ サポート体制 | ● 職場適応のための支援が手厚い。 ・定期的な面談で悩みや不安を共有できる。 ・ジョブコーチや支援員の伴走型サポートあり。 ・上司・同僚への障がい理解促進の研修があることも。 ・困ったときに「相談できる場所がある」という安心感。 | ● 基本的に自立的な働き方が求められる。 ・困っても「自分で対処する」のが前提となることが多い。 ・障がい特性に対する理解や支援体制は整っていない場合がある。 |
1つずつ詳しく見ていきましょう。
① 勤務時間の柔軟性
障害者雇用の場合、体調や生活リズムに合わせて働き方を調整できることが多く、無理のない形で就労を続けやすい環境が整えられています。
例えば、1日4時間程度の短時間勤務や、週に3〜4日の勤務にするなど、勤務日数や時間を調整することが可能です。通院や体調管理のために必要な休息の時間を確保しやすくなります。
また、朝の体調が不安定な方には時差出勤の対応がされる場合もあり、混雑を避けたい方や、朝がつらい方でも出勤しやすくなります。
さらに、企業によっては在宅勤務(テレワーク)を取り入れているところもあり、通勤の負担を軽減することで、より安心して業務に取り組めるよう配慮されています。
このように、自分の体調や生活スタイルに合わせて働く時間や場所を柔軟に選ぶことができるため、就労に対する不安が和らぎやすく、自分のペースで仕事に慣れていくことができます。
② 仕事内容の調整
障害者雇用では、個々の体調や得意・不得意を考慮して、無理のない範囲での業務内容が設定されることが一般的です。これは、「できることを活かしながら働く」という考え方が重視されているからです。
例えば、マニュアルに沿って進める定型作業や、事務補助・データ入力などの集中力を活かせる作業、あるいは清掃業務など身体を動かす業務など、幅広い選択肢の中から、自分に合った仕事を担当することができます。
必要に応じて、作業の工程を分けてもらえたり、難しい作業を減らしたりといった調整もされるため、「仕事についていけるか不安…」という気持ちにも寄り添ってもらえる安心感があります。
自分の強みを活かしながら、少しずつ自信を積み重ねていける環境が整えられているのが特徴です。
③ サポート体制
障害者雇用では、「働き続けるための安心感」が得られるよう、職場でのサポート体制がしっかりと用意されていることが特徴です。
これは、仕事だけでなく「職場に慣れる」「気持ちを保つ」といった面でも大きな支えになります。
例えば、以下のようなサポートが受けられます。
〇定期的な面談
上司や人事担当と定期的に話す機会が設けられ、仕事の悩みや体調について相談できます。仕事に対する悩みや問題を早めに共有できる安心感があります。
〇ジョブコーチや支援スタッフの同行・伴走支援
仕事に慣れるまで、外部の支援機関のスタッフが職場に来てくれてサポートしてくれることもあります。必要に応じて、企業との間に立って調整してくれる役割も担ってくれます。
〇職場内の理解促進
同僚や上司向けに「障がいについての理解を深める研修」が行われることもあり、配慮や声かけの工夫がされやすい環境づくりが進んでいます。
このように、「一人でがんばらなくていい」環境があることで、働きながら不安を軽減し、より安心して仕事に取り組めるようになります。
障害者雇用で働くメリットは?

障害者雇用で働くメリットについて見ていきましょう。
適切な配慮を受けられる
障がいの特性に応じて、勤務時間の調整やバリアフリーな職場環境、業務内容の工夫など、無理なく働けるよう配慮がされています。
配慮があることで、障がいのある方が自分のペースで仕事をこなせるようになり、体力的・精神的な負担を軽減することができます。
ただし、配慮のための整備もコストがかかるため、企業によってどこまで環境を整えることができるかは差が出てきます。
職場定着支援が充実
定期的な面談や相談窓口が設けられており、困ったときやストレスを感じたときに、専門のサポートを受けやすい環境が整っています。
これにより、職場における不安や悩みを早期に解消でき、長期的に安心して働き続けられる可能性が高まります。
障害を開示することで理解が得られる
障がいについて開示することで、職場内で理解や協力を得ることができます。
障害に関する配慮が期待できるため、業務の調整や精神的なサポートが受けられるほか、職場での無理解や偏見からくる精神的な負担を軽減することができます。
自分の状況を理解してもらうことで、よりスムーズに業務に取り組むことができ、心の負担を減らしながら働くことができます。
障害者雇用で働くデメリットは?
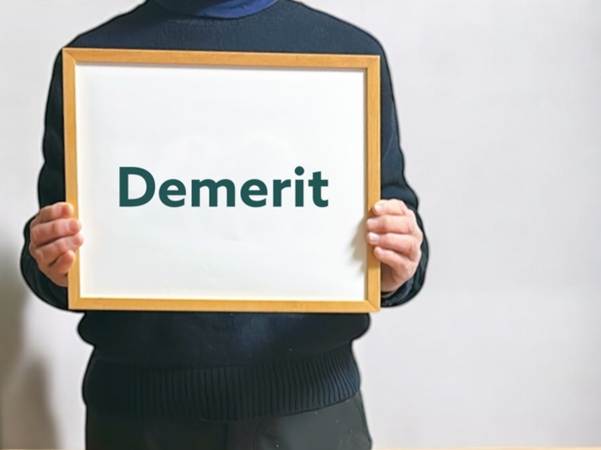
続いて、障害者雇用で働くデメリットもまとめていきます。
働き方が限られる
障がいの特性に応じた業務を担当することが多いため、一般的な就労に比べて業務範囲が狭くなることがあります。
例えば、業務に集中することが困難だったり、複数の業務を一度にこなすことが難しい特性がある方だと、働ける仕事の選択肢が制限されることとなります。
働き方が限られてしまうと、就きたいジャンルの職種に就けず、仕事に対するやりがいを感じにくくなったり、職場での役割に対する自信が持ちづらくなる場合もあります。
収入が低くなる可能性がある
障がい者雇用では、短時間勤務や補助的な業務を担当することが多く、これに伴い給与が低くなることがあります。
特に、フルタイム勤務が難しい場合や、特別なスキルを要しない業務が中心となる場合、給与が一般的なフルタイム勤務者に比べて少なくなる可能性が高くなります。
そうなると、生活面での不安や将来への不安を感じることがあるかもしれません。
キャリアアップの機会が少ないこともある
障がい者雇用の枠組みでは、一般的な昇進やキャリアアップの機会が限られることもあります。
特に、小規模な企業や障がい者雇用の枠が特別に設けられている企業では、昇進制度やキャリアパスが十分に整備されていない場合があります。
そのため、スキルや経験を積んでいく機会が少なく、職業的な成長を感じにくくなることがあります。
このような背景を受け、将来的にキャリアの選択肢が狭まることを懸念する声もあります。
障害者雇用で働くために活用できる社会制度

障害者雇用で働くことを決めた場合、活用できる社会制度を紹介します。
ハローワーク
ハローワークには、障がいを持つ方専用の就職支援窓口があります。
ここでは、障がい者の特性に合った求人を紹介してもらうことができます。
また、求人情報だけでなく、就職に向けたアドバイスや面接のコツ、履歴書の書き方の指導なども受けることができます。
地域ごとに窓口が設置されており、地域に根差した支援が行われています。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障がいを持つ方の職業適性の評価や職場定着支援を行う専門機関です。
職業適性を測るためのテストやカウンセリングを通じて、個々の能力や希望に合った職業を見つけるサポートを行っています。
また、就職後も定期的にフォローアップを行い、職場での適応をサポートしてくれるため、長期的に安心して働ける環境作りに貢献します。
就労移行支援
就労移行支援は、障がいを持つ方が一般就労を目指すための訓練を提供する制度です。
この支援は、就職前の準備段階において重要な役割を果たします。
就労移行支援では、職業訓練をはじめ、コミュニケーションスキルの向上や、社会生活に必要な基本的なマナーを学べるプログラムが提供されます。
また、面接対策や履歴書の書き方、仕事に対する心構えなども学ぶことができ、一般就労にスムーズに移行できるよう支援します。
訓練を受けた後は、企業とのマッチング支援が行われ、実際に職場で働くことを目指します。
まとめ
当記事では、障害者雇用と一般就労の違いなどを紹介してきました。
今回の記事のポイントをまとめると、
・自身の状況に合った働き方を見つけることが重要
・企業側と求職者双方の理解が必要
・社会制度を活用して職に就くのがおすすめ
ということです。
障害者雇用のメリットとデメリットを把握した上で、自分に合った働き方を選んでいきましょう。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







