発達障がい者の雇用ガイド|選考ポイント、適切な業務、配慮すべきことを解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.07.25
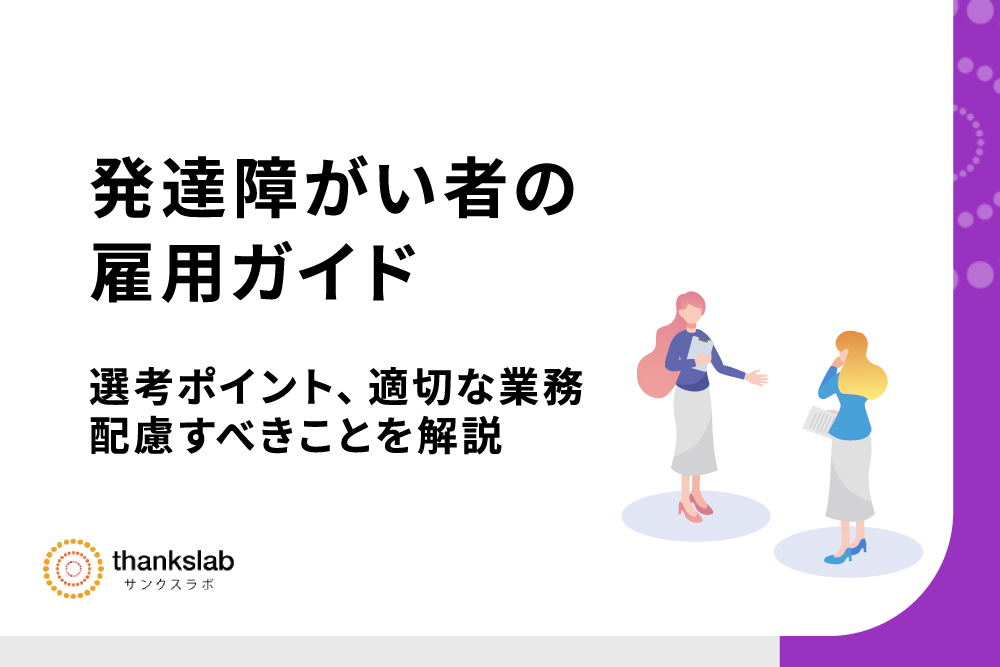
発達障がい者の雇用が近年増加しています。しかし、選考基準や職場での配慮といった課題を抱えている企業が少なくありません。
発達障がいをよく理解して、職場で適切な配慮をすることで、企業にとっても大きなメリットをもたらします。
このコラムでは、発達障がい者を雇用するための準備や選考ポイント、発達障がい者に向いている仕事などを紹介します。
目次
発達障がいとは?
発達障がいとは、生まれつき脳機能の発達に関係している障がいです。
コミュニケーションや行動、学習などさまざまな特性となってあらわれます。幼少期から症状があらわれる方が多いですが、思春期になってあらわれる方や大人になってから初めて気づく方などさまざまです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)
対人関係が苦手で、他の人とコミュニケーションを取るのに難しさを感じる傾向がある障がいです。こだわりが強く、特定の分野に強い興味を示し、高い集中力を発揮することがあります。
注意欠如・多動症(ADHD)
不注意・多動性・衝動性が特徴で、集中力が続かない、注意を持続することが苦手、落ち着いていられない、衝動的に行動するといった症状がみられます。
学習障害(LD)
知的発達には問題がないものの、読む・書く・計算するといった特定の学習分野に困難を抱える障害です。
発達障がい者の雇用状況
障害者雇用促進法が改正され、ある一定数以上の社員がいる企業に対して障害者雇用が義務化されました。それに伴い発達障がいのある方の雇用も増えています。
現在の発達障がいの雇用傾向
令和5年度障害者雇用実態調査によると、従業員5人以上の事業所に雇用されている発達障がいのある方は、9万1,000人です。5年前の前回調査時は3万9,000人であったため、5万2,000人も増加しています。
精神障害者保健福祉手帳の等級をみると、3級が41.1%で最も多いです。また、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい」が最も多く69.1%となっています。
雇用形態では、発達障がい者の36%が正社員となっています。前回の調査では22.7%であったため、13.3%も正社員として働いている方が増えていることがわかります。
身体障害者の雇用は、高齢になるほど多くなる傾向がありますが、発達障がい者の雇用は20代30代の若い世代が多いです。これは、発達障がいの診断基準が変更され、以前までは発達障がいとみなされなかった軽症例が診断されるようになり、障がい者手帳を取得している人が増えたためだと考えられます。
また、発達障がいに対する理解が深まり、発達障がいである人が就職しやすくなったことも理由としてあげられます。
現在の課題
発達障がいのある人の雇用は増えていますが、中小企業を中心にまだ多くの企業が法定雇用率を達成していません。令和6年に厚生労働省が行った調査によると、54%の企業が法定雇用率を未達成で、前年に比べると増加しているということです。
また、発達障がいについての理解が浅く、働きやすい職場環境の整備が不十分な企業も少なくありません。
発達障がい者を雇用するために準備・配慮すべきこと
発達障がいを持っている人を採用する前に、発達障がいについての理解と働きやすい環境作りに取り組んでおくことが大切です。以下のようなことに取り組んでおくと、定着率向上につながります。
職場環境の整備
発達障がいのある人は、光や音などに敏感な場合があります。そのため、照明や音の調整ができるよう整え、整理整頓され静かな作業スペースを確保しておくことが大切です。
また、仕事を進めやすくするために、業務の進行をサポートするツールを導入すると、ストレスをあまり感じることなく、スムーズに仕事を進められることにもつながります。
業務内容の見直しや調整
発達障がいの特性に適した業務を割り振ることが、生産性の向上には重要です。繰り返し作業が得意な人にはデータ入力、感性が豊かな人にはデザイン制作などの業務を割り当てるとよいでしょう。
急な変更に対応するのが苦手な人もいるので、計画的に進められる業務を割り当て、定期的に進捗状況を確認するのがおすすめです。業務の変更をせざるを得ない場合は、できるだけ早く伝えるようにしましょう。
コミュニケーションの工夫
口頭だけでなく文章を使ってコミュニケーションを取ると、理解しやすくなります。また、発達障がいの人は、抽象的な表現や曖昧な言葉の理解が難しいことがあります。指示を出すときは、はっきりとわかりやすい表現を使うと伝わりやすいです。
困っていることがあっても相談できない人も多いので、様子をみて声をかけてあげましょう。
勤務時間や休憩時間の調整
発達障がいがある人の中には、集中力が続かない人や疲れやすい人がいます。そのため、
フレックスタイム制の導入や勤務時間の短縮などを利用すると、働きやすくなり定着率向上につながります。また、休憩時間をこまめに取ることで、作業効率があがることもあります。
発達障がいの人を雇用する場合、勤務時間や休憩時間を上手に調整することが大切です。
発達障害に関する研修や教育の実施
発達障がいの人が働きやすい職場にするためには、周囲の同僚の理解が必要です。企業内で発達障がいについて理解を深めるための研修を実施したり、専門家からアドバイスをもらったりすることが有効です。
発達障がいについての理解が深まれば、適切な対応をとれるようになり、定着率の向上につながります。
相談窓口の設置
発達障がいの方が、長期間快適に働き続けるためには、悩みを気軽に相談できる環境であることが重要です。
企業内に相談窓口を設置し、仕事関係や人間関係の悩みについて気軽に相談できる体制を整備することで、メンタルが安定し雇用定着につながります。
発達障がい者を雇用するときの選考ポイント
発達障がいを持っている人を初めて雇用する企業では、採用基準に悩む方が多いでしょう。長期間安定して働いてもらえる人材を採用するためには、以下の基準を考慮するとよいでしょう。
発達障がいを理解し受け入れているか?
自分の発達障がいについて理解し、周囲に対してどのような対応や配慮をしてもらえると快適に働くことができるか説明できると、雇用定着につながります。
企業は説明された内容に沿った環境を整備できれば、長期的に働いてもらえる可能性が高くなります。
企業が求める職務に対する適性があるかどうか?
発達障がいの方を雇用する場合でも、自社が求める職務に対する適性があるかどうかは重要な採用基準です。
特性が求める職務に合っているかを確認してから採用することが、お互いにとって大切です。
就労意欲があるかどうか?
本人に就労意欲があるかは、重要な選考ポイントです。親に言われたから面接にきたが、それほど働きたいと思っていないような人では、すぐにやめてしまう可能性が高くなります。
採用後、仕事に意欲的に取り組んでもらえそうか、就労意欲やモチベーションを確認しましょう。
就労に必要なコミュニケーション能力があるか?
発達障がいを持ってる方の中には、人とコミュニケーションを取ることが難しい人もいます。そのため、就労に必要なコミュニケーション能力があるかどうかを、確認することが大切です。
ただし、人とコミュニケーションを取ることが苦手な人でも、業務に支障をきたさない場合もあるので、求める業務に必要なコミュニケーション能力の見極めも重要です。
どの程度まで自己管理できるのか?
ひとりでどのぐらい仕事が進められるか、時間やルールを守ることができるかを見極めることが大切です。自己管理がまったくできない人を採用してしまうと、多くのサポートが必要になり周りに過度の負担がかかってしまいます。
上司や同僚がどの程度のサポートができるかを把握し、そのサポートで業務が行えるかどうかを判断する必要があります。
どの程度の協調性や環境適応能力があるか?
同僚といい関係を築いていけるか、職場に適応することができるかも選考ポイントになります。ただし、職場で上手くやっていけるかは、周りの発達障がいへの理解度が大きく影響します。
そのため、採用面接前に、社内の発達障がいに対する理解度を把握しておくことも大切です。
発達障がい者に向いている仕事内容
発達障がいの人を雇用したいが、自社に適切な業務があるかわからないため採用に踏み切れない企業もあるでしょう。
そこでここでは、発達障がいを持っている人に向いている仕事を紹介します。発達障がいを持っている人は、一人ひとり異なる特性を持っているので、個々の特性を理解して、適切な業務を割り振ることが重要です。
ひとりでたんたんと進められる仕事
発達障がいを持っている方の中には、細かい作業や繰り返し作業が得意な人がいます。また人とコミュニケーションを取ることが苦手な人は、ひとりでたんたんと進められる仕事が向いています。
向いている仕事の具定例:データ入力、帳簿整理など
独特の感性や感覚を活かした仕事
発達障がいを持っている方の中には、独特な感性や感覚を持っている人がいます。そのような人は、柔軟な発想を活かし独創的な仕事が向いています。
向いている仕事の具体例:デザイナー、イラスト制作など
規則やマニュアルに沿って進められる仕事
発達障がいを持っている方の中には、臨機応変に対応することが苦手で、あらかじめ決められている規則やマニュアルに沿ってできる仕事が向いている人がいます。
向いている仕事の具体例:倉庫での軽作業、製造ラインでの組み立て作業、商品の梱包作業など
興味のある分野の知識を活かせる仕事
発達障がいを持っている方の中には、興味のある分野で高い集中力を発揮する人がいます。豊富な知識を持ち、専門的な仕事を任せると素晴らしい成果を発揮できる可能性があります。
向いている仕事の具体例:エンジニア、プログラマーなど
発達障がい者を雇用する企業の支援制度や機関
発達障がいを持っている人を雇用しようとしている企業は、さまざまな支援制度や機関を利用できます。支援制度や機関を利用すれば、企業の負担が抑えられるだけでなく、発達障がいを持っている人が働きやすい適切な環境作りにも役立ちます。
ここでは、発達障がいを持っている人を雇用するときに、企業が利用できる支援制度や機関を紹介します。
企業が利用できる助成金制度
特定求職者雇用開発助成金(発達障がい者・難治性疾患患者雇用開発コース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介で、発達障がいを持っている人を一定期間以上雇用した場合に、支給される助成金制度です。
支給される金額は、企業規模や雇用形態により異なるので、厚生労働省のホームページで確認してください。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
障がいを持っている人を正社員または無期雇用労働者に転換するときに、利用できる助成金です。
利用条件は、転換前に6ヶ月以上継続して雇用していることと、転換後に社会保険に加入して継続して雇用することです。
支給される金額は、障害の程度や転換後の雇用形態によって異なるので、厚生労働省のホームページで確認してください。
支援制度
ジョブコーチ支援制度(職場適応援助者支援)
発達障がいを持っている人が、職場に適応できるような環境作りを職場に出向いてサポートしてくれる制度です。また、雇用後に職場定着のためのアドバイスや職場環境の改善の提案もしてくれます。
相談・支援機関
ハローワーク
ハローワークは、求人募集に利用できるだけではなく、求人申し込み書の書き方、採用や選考についてのアドバイスなども受けられる機関です。また、利用できる助成金や支援制度などについても案内してくれます。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、各都道府県・指定都市に設置されており、雇用管理や職場環境の整備・改善のサポートを受けることができる機関です。
また、発達障がいを持っている人が、長期間安定して働けるように、コミュニケーションの取り方や指示の仕方などのサポートもしてくれます。
まとめ
発達障がいを持っている方の長期雇用を成功させるためには、それぞれの特性に合った業務を割り振り、適切な職場環境を整備することが重要です。
また、発達障がいを持っている方と定期的に話し合い見直す点があった場合は、柔軟に調整する必要があります。
働きやすい環境作りや選考についての疑問は、自社だけで解決しようとせずに専門機関のサポートを利用することをおすすめします。
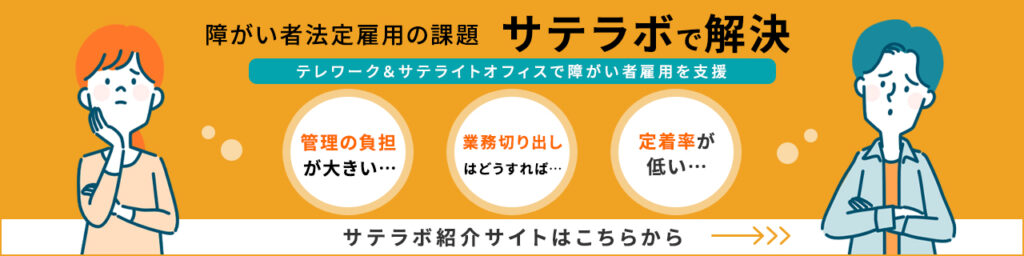
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。








