【2025年最新】障害者雇用率の計算の仕方は?カウント方法と早見表で解説
- 公開日:
- 2025.02.13
- 最終更新日:
- 2026.01.07

障害者雇用率の計算方法は、常用雇用で働いている従業員と短時間勤務の従業員の人数に0.5を掛けた数値を足し、そこに法定雇用率を掛けて算定します。小数点以下の端数は、切り捨てです。
この変更に伴い、より多くの企業が障害者雇用の対象となり、適切な雇用管理が求められるようになります。
そこで今回は、人事担当者が押さえるべき障害者雇用率の計算方法や関連する重要な情報について、詳しく解説します。
障害者雇用率の充足に対する意識は、これまで以上に高まっています。障害者雇用率は、今後徐々に引き上げられる予定です。
また雇用する必要がある障害者の人数を満たしていない場合、行政指導や罰則を受ける可能性があります。
今や、何人の障害を持つ従業員を雇用しなければならないのかを把握することは、健全な企業経営に欠かせない要素の一つです。
こういった社会情勢を受けて、障害者雇用率の計算方法について、当記事でわかりやすく解説していきます。障害者雇用の対象となる従業員の判断の仕方や、従業員の属性によって異なるカウントの仕方についても詳しく説明します。
また、計算が複雑な障害者雇用率を半自動で計算できるフォーマットもご用意しています。2026年7月から変わる法定雇用率2.7%や除外率が適用される業種にも対応しているため、雇用が必要な障がい者の方の人数や雇用率の計算の手間を省きたい方はぜひご活用ください。
▼障害者雇用率を半自動で計算
>>障がい者雇用率計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
目次
障害者雇用率の計算方法
障がいをもつ従業員を何人雇用すればよいかを算定する計算式は、冒頭で述べたとおりです。小数点以下の端数は切り捨てます。
しかしこの式で計算する場合は、次の要素を考慮しなければなりません。
- 自社の場合法定雇用率は何%か
- 障害のある従業員の数をどのようにカウントするか
民間企業における法定雇用率は、2024年4月に引き上げになり、2.5%になりました。障害者雇用の対象となる事業主の範囲も障害者の法定雇用率の引き上げに伴い、変更になっていますので、詳しく確認しておきましょう。
事業主別の法定雇用率
従業員数が40人以上の民間企業の場合の法定雇用率は、2.5%と定められています。これは、2024年12月現在の数値です。
| 事業主の種類 | 民間企業 | 国・地方公共団体等 | 都道府県等の教育委員会 |
| 障害者の法定雇用率 | 2.5% | 2.8% | 2.7% |
| 従業員数 | 40人以上 | 職員の人数は問わない | |
なお2026年7月からは、障害者の法定雇用率は、次のように変更されます。
| 事業主の種類 | 民間企業 | 国・地方公共団体等 | 都道府県等の教育委員会 |
| 障害者の法定雇用率 | 2.7% | 3.0% | 2.9% |
| 従業員数 | 37.5人以上 | 職員の人数は問わない | |
出典:厚生労働省「障害者雇用率制度の概要」
つまり2026年6月までは、40人以上の従業員を抱える民間企業であれば、少なくとも1人の障害がある人材を雇用する必要があります。
今後の法定雇用率の引き上げについては「障がい者法定雇用率の引き上げはいつから?今後の予定となぜ上がるのか解説」で詳しく解説しているのがよかったら参考にしてみてください。
複数の事業所をもつ民間企業の場合の取扱い
複数の事業所を有する民間企業の場合は、事業所単位ではなく、企業全体で従業員数をカウントします。そのため総従業員数が40人以上であれば、1人以上の障害がある人材を雇用しなければなりません。
しかしこの1人とは、企業全体での人数です。各事業所のうち、いずれかに1人以上の障害がある人材を配置すれば、法定雇用率を充足していると判断できます。
グループ会社をもつ民間企業の場合の取り扱い
企業グループ算定特例(関係子会社特例)の条件を満たした場合は、グループ企業全体で障害者の雇用率を合算できます。
条件の概要は、以下のとおりです。
| 条件が課される対象 | 条件詳細 |
| 親企業 | ・子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること(たとえば、子会社の議決権の過半数を有する、など) ・障害者雇用推進者を選任していること |
| 関係子会社 | ・常用労働者数に応じて、以下の障害者雇用が必要・167人未満:要件なし ・167人以上250人未満:障害者1人以上 ・250人以上300人以下:障害者2人以上 ・300人超:常用労働者数の1.2%以上(小数点以下切り捨て) ・障害者の雇用管理を適正におこなえること、または他の子会社の障害者雇用に関して緊密な関係があること |
| グループ全体 | ・障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること ・すべてのグループ会社を対象とすること |
出典:厚生労働省「「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要」
この制度は、平成21年4月に創設されました。グループ内で障害者雇用を進めやすい企業がある場合に、特例子会社を設立せずに一元的に障害者雇用を進められるメリットがあります。
しかし上記のとおり条件が厳しいため、活用している企業は多くないのが現状です。
障害者雇用率の計算シミュレーション
障害者雇用率の計算例を、複数の場合を想定して具体的に示します。
ケース1:民間企業(従業員100人)
- 従業員数:100人(常勤50名・短時間50名)
- 法定雇用率:2.5%(2024年4月時点)
上記計算式に当てはめると、(50+50×0.5)×0.025=1.875
ただし、障害者雇用率の計算では、小数点以下の端数を切り捨てるため、この企業では1人以上の障害者を雇用する必要がある、とわかります。
ケース2:民間企業(従業員50人)
- 従業員数:50人(常勤30名・短時間20名)
- 法定雇用率:2.5%(2024年4月時点)
この場合、(30+20×0.5)×0.025=1となり、1人以上の障害をもつ従業員を雇用しなければなりません。
ケース3:民間企業(従業員200人)
- 従業員数:200人(常勤150名・短時間50名)
- 法定雇用率:2.5%(2024年4月時点)
計算式は、(150+50×0.5)×0.025=4.375です。
小数点以下は切り捨てるため、この企業は少なくとも4人の障害者を雇用する必要があります。
▼障害者雇用率を半自動で計算
>>障がい者雇用率計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
対象となる従業員の判断基準
雇用対象となる障害者は、主に以下の5つのカテゴリーに分けられます。
- 身体障害者
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 重度知的障害者
- 精神障害者
それぞれに求められる条件を、確認しましょう。
障害のカテゴリーと必要な条件
| 障害者の分類 | 条件 |
| 身体障害者 | ・身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」の保有 ・障害の程度によって定めれらた等級の1~7級に該当する |
| 重度身体障害者 | ・1級 ・2級の障害がある、もしくは3級に該当する障害が2つ以上重複している |
| 知的障害者 | ・都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持 |
| 重度知的障害者 | ・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医から「A」に相当する判定書を受け取っている ・障害者職業センターで重度知的障害者と判定された |
| 精神障害者 | ・精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を所持 ・障害の程度によって等級が1~3級に該当する |
認定されている障害の内容によって、身体障害者と重度身体障害者、知的障害者と重度知的障害者といったように、異なるカテゴリーに分類されます。
カテゴリーが異なると、人数をカウントする際の考え方が変わるため、障害手帳等の書類で、障害の詳細を確認することが大切です。なおカテゴリーによって異なる人数のカウントの仕方については、後述します。
障害があると判断する際の注意点
いずれの場合も、原則として障害者手帳を所持もしくは、同等の認定書類などを有することが、算定対象となる必須条件です。
障害を有していても障害者手帳を保有していないケースは珍しくありません。そして企業には、障害者手帳の有無にかかわらず、誰もが働きやすい職場づくりを推進するよう求められています。
しかし2024年12月現在、障害者雇用促進法における障害者雇用率の算定においては、障害者手帳を有することが、障害のある従業員として認定される条件である点に、ご注意ください。
なお、これは障害の重さによって従業員の価値を定めるものではなく、あくまでも手続き上公正な判断を下すためのルールです
また、上記5つの障害のカテゴリーのどれに該当するかによって、人数のカウント方法が異なります。次の項で詳しく説明しますので、併せてご参照ください。
対象となる障害者カウント方法
障害を持つ従業員の場合、その人数がすなわち、法定雇用率の算定対象となる障害のある従業員の数、になるとは限りません。
障害をもつ従業員をカウントする際のルールが定められており、条件によって、1人以下もしくは1人以上としてカウントされるケースがあります。
障害をもつ従業員をカウントする際に適用されるのは、次の2つの基準です。
- 1週間あたりの総労働時間
- 障害の程度
労働時間や障害の程度によってカウント数が異なりますが、条件別でカウント数をまとめた早見表は以下になります。
早見表
| 1週間あたりの総労働時間 | 障害の程度 | カウント数 | |
| 常勤労働者 | 30時間以上 | 重度身体障害者・重度知的障害者 | 2.0 |
| 30時間以上 | その他の障害者 | 1.0 | |
| 短時間労働者 | 20時間以上30時間未満 | 重度身体障害者・重度知的障害者 | 1.0 |
| 20時間以上30時間未満 | その他の障害者 | 0.5(精神障がい者は1.0) | |
| 特定短時間労働者 | 10時間以上20時間未満 | 重度身体障害者・重度知的障害者 | 0.5 |
| 10時間以上20時間未満 | その他の障害者 | 0(精神障がい者は0.5) | |
| 10時間未満 | すべての障害者 | 0 | |
出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内」
ここからは、障害者雇用率のカウント方法について、それぞれくわしくご説明します。
>>障がい者雇用率自動計算フォーマット 無料ダウンロードはこちら
常勤労働者|週30時間以上勤務
常用雇用(週30時間以上勤務)の場合、1人を1人としてカウントします。
重度身体障害者や重度知的障害者の場合は、1人でも2人としてカウント可能です。
重度身体障害者や重度知的障害者をダブルカウントする理由には、重度障害者の雇用に積極的に取り組む企業に対してインセンティブを与えると同時に、より多くの支援を必要とする障害者の雇用機会が増加することへの期待が込められています。
1976年の障害者雇用促進法改正時に、重度障害者を採用する際の特例として、このダブルカウント方式が設定されました。当時、重度障害者の就業率が特に低かったことがこの制度導入の背景にあります。
短時間労働者|週20時間以上30時間未満の勤務
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。
短時間労働者である障害者は原則として、常勤労働者の1/2でカウントします。たとえば、身体障害者・知的障害者・精神障害者であれば、1人につき0.5人、重度身体障害者や重度知的障害者は1人とカウントする流れです。
ただし精神障害者の特例があり、条件を満たす場合は1人としてカウントされることがあります。具体的な条件は、次のとおりです。
- 週20時間以上30時間未満の勤務の精神障害者
- 新規雇入れから3年以内、もしくは精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内
当初は期限付きで開始された特例措置ですが、現在では恒久的な制度として扱われ、2025年4月からは精神障害者で週20時間以上30時間未満勤務の場合、雇用開始日や手帳取得日に関係なく常時1.0人としてカウントされることが決定しています(厚生労働省発表 2023年12月27日付通知より)。
特定短時間労働者|10時間以上20時間未満
週10時間以上20時間未満勤務の特定短時間労働者に関する制度は、2023年7月1日から施行された、比較的新しいものです。
身体障害者、知的障害者、精神障害者は1人当たり0.3人、重度身体障害者と重度知的障害者の場合は、1人あたり0.5人としてカウントします。
10時間未満勤務
週所定労働時間が10時間未満の場合はすべての障害者について、障害者雇用率の算定において0人としてカウントされます。
この基準は、障害の種類や程度を問いません。したがって週10時間未満の勤務の場合は、障害者雇用率の計算に含まれないことを意味します。
2024年4月からの制度改正により、週10時間以上20時間未満の短時間労働者が一部カウントされるようになりました。しかし10時間未満の超短時間労働者については、2024年12月現在も、引き続きカウント対象外です。
障害者の法定雇用率未達成時のリスク
法定雇用率を達成できない場合、次のようなリスクが想定されます。
障害者雇用納付金の納入
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成できていない企業に対して経済的負担を課する制度です。
- 対象:常用労働者100人超の企業
- 金額:不足人数1人につき5万円(年間60万円)
- 目的:障害者雇用の促進と企業経済的負担の調整
2点注意したいのは、納付金を払っても法定雇用率を達成する義務がなくなるわけではない点です。また法定雇用率を達成するまで、継続的に支払い続けなければなりません。
なお障害者雇用納付金は、障害者雇用に積極的な企業へのインセンティブとして活用されます。
障害者雇用納付金の納入義務が発生した場合の例
従業員500人の企業で法定雇用率2.5%を達成するには12.5人(小数点以下の端数は切り捨てるので12人)の障害者雇用が必要です。
しかし12人のうち5人しか障害がある従業員を雇用していない場合、不足人数は7人となり、年間で420万円(7人×60万円)の納付金を納入しなければなりません。
数年にわたって未達成の状況が続けば、年度ごとに不足人数分の納入金を納め続けることになります。
行政指導
法定雇用率を達成していない企業に対して、ハローワークは「障害者の雇入れに関する計画」の作成指導をおこないます。この計画作成命令の対象となる基準は以下のとおりです。
- 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
- 不足数が10人以上の場合
- 法定雇用障害者数が3人から4人の企業で、障害者を1人も雇用していない場合
障害者雇入れ計画書の作成手順
計画作成命令を受けた企業は、以下のような手順で計画書の作成と報告をおこないます。6月1日現在の状況を報告するので、ロクイチ報告と呼ばれています。
- 1月1日から2年間の障害者雇用計画を作成
- 毎年6月1日現在の実施状況を、7月15日までに報告
- 計画1年目の12月に、ハローワークが計画の進捗状況を確認
- 2年間の計画終了後も法定雇用率を達成できない場合、9ヶ月間の特別指導を実施
企業名の公表
行政指導後も改善が見られない場合、企業名が公表されることがあります。
公表は厚生労働省のホームページ上でおこなわれ、企業名や行政指導の経過、障害者雇用状況の時間などが公開されるため、企業の社会的信用の低下や、採用活動、取引関係に悪影響をおよぼす可能性は否めません。
またインターネット上に情報が残り続けるため、長期的な影響が懸念されます。さらに公表後も改善が見られない場合、企業名が再公表されるリスクがあるのも、見逃せません。
企業は法定雇用率達成に向けて計画的に取り組み、企業名公表のリスクを回避することが重要です。
関連:障害者雇用率未達成だとどうなる?企業名公表や罰則について解説
法定雇用率を超えて障害者を雇用するメリット
法定雇用率を超えて障害者を雇用すると、次のようなメリットが期待できます。
1.障害者雇用調整金の受給
常用労働者100人超の事業主を対象に、雇用している障害をもつ従業員数が1人を超える度に、月額29,000円が支給されます。
なお2024年4月以降は、支給対象人数が年間120人(月10人)を超える場合、支給額は月額23,000円です。
2.報奨金制度
常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主に対して、次の条件を満たすと、報奨金が支払われます。詳細は、以下のとおりです。
条件
各月の障害者雇用数の年間合計が、以下のいずれかを超えている必要があります
・①各月の継続雇用労働者数の4%の年間合計
・②月平均6人以上(年間72人)。いずれか多い方が基準になります
- 各月の障害者雇用数の年間合計が以下のいずれか多い方を超えていること
- 各月の継続雇用労働者数の4%の年間合計もしくは72人
報奨金額額
- 法定雇用数を超過して雇用した障害がある従業員1人につき月額21,000円
- 2024年4月1日以降、支給対象者数が年間420人(月平均35人)を超える場合、超過分は1人につき16,000円
ただし報奨金は、事業主の申請に基づいて支給されます。申請し忘れることがないように、ご注意ください。
3.企業イメージの向上
法定雇用率を順守した障害者の雇用は、社会的責任(CSR)を果たしていることのアピールにつながります。
取引先や株主からの信頼向上につながるでしょう。
障害者雇用に関する支援制度
障害者雇用を促進するために、次のような助成金制度が用意されています。法定雇用率未達成の課題を抱えている場合は、ここで紹介する助成金を活用することをご検討ください。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、障害者や高齢者などの就職困難者を継続して雇用する事業主を、支援する制度です。
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金 |
| 主なコース | ・特定就職困難者コース ・発達障害者 ・難治性疾患患者雇用開発コース |
| 支給額 | 対象者や企業規模により異なる(障害者の場合は、最大240万円) |
| 支給期間 | 最長2年間 |
| 申請方法 | ハローワーク等の紹介を受けて対象者を雇用し、支給対象期ごとに申請 |
| 問い合わせ先 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html |
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、障害者等を試行的に雇用する事業主に対して支給される助成金です。
| 制度名 | トライアル雇用助成金 |
| 主なコース | ・一般お試しコース ・障害者トライアルコース |
| 支給額 | ・一般トライアルコース:最大4万円/月(3ヶ月) ・障害者トライアルコース:最大8万円/月(3か月) |
| 支給期間 | 3ヶ月間 |
| 申請方法 | ・トライアル雇用開始から2週間以内に実施計画書を提出 ・終了後2ヶ月以内に支給申請 |
| 問い合わせ先 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html |
障害者作業施設設置等助成金
障害者作業施設設置等助成金は、障害者が働きやすい環境を整備するための施設・設備の設置・整備費を助成する制度です。
| 制度名 | 障害者作業施設設置等助成金 |
| 主なコース | ・第1種:建築等や購入による設置 ・整備第2種:賃借による設置・整備 |
| 助成率 | 費用の2/3 |
| 支給上限額 | ・第1種:450万円/人(作業設備のみの場合150万円/人) ・第2種:月額13万円/人(作業設備のみの場合月額5万円/人) |
| 申請方法 | 事前に受給資格認定申請をおこない、その後支給申請を実施 |
| 問い合わせ先 | https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000205996.pdf |
障がい者雇用で活用できる助成金については「【2025年最新】障害者雇用の助成金の種類や条件、申請方法を解説」に詳しくまとめているのでよかったらご参考ください。
まとめ
障害者雇用率の適切な計算と管理は、企業の社会的責任を果たすだけでなく、組織の多様性と創造性を高める重要な取り組みです。法定雇用率の段階的引き上げに備え、企業は長期的視点で雇用戦略を立てる必要があります。
各種助成金も活用しながら、障害者と企業が共に成長できるような雇用の在り方を追求することが、今後の企業経営の重要な課題となるでしょう。
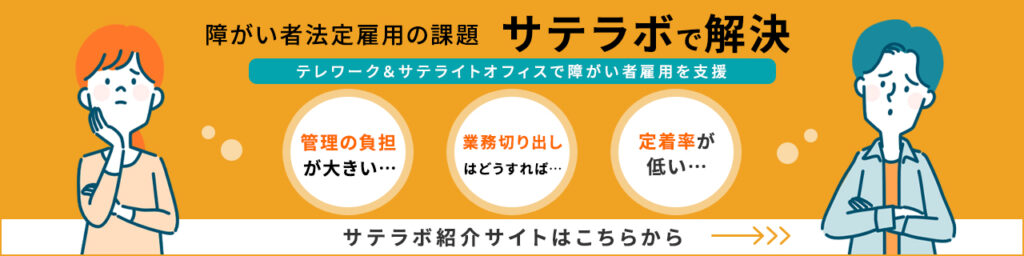
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







