障がい者雇用の相談窓口はどこにある?企業と求職者向け別に解説
- 公開日:
- 2026.01.15
- 最終更新日:
- 2026.01.15
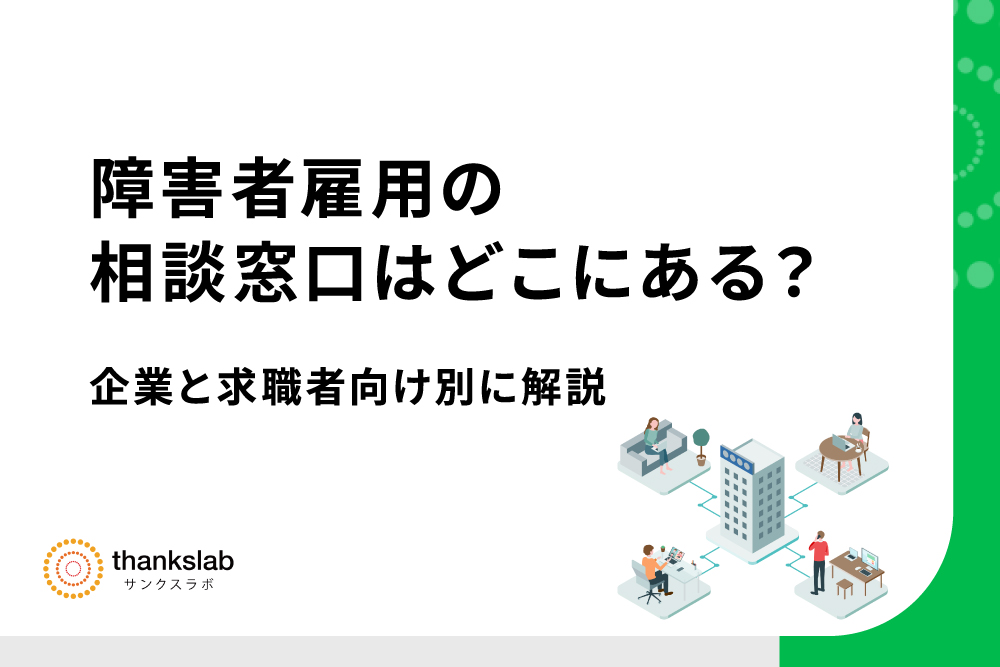
障がい者雇用の相談窓口は、企業と障がい者の双方を支援する重要なシステムです。しかしさまざまな種類があるので、どの窓口を利用すれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、障がい者雇用の相談窓口をフェーズ別、また企業と従業員の立場別に紹介します。この記事を読めば、障がい者雇用に関するお困りごとを相談する窓口が明確に見極められるようになります。
目次
これから障がい者雇用を始める企業向けの窓口
障がい者雇用をこれから開始する企業が相談できる窓口は、次の通りです。
|
相談窓口の種類 |
相談窓口 |
相談窓口の管轄・運営元 |
|
これから障がい者雇用を始める企業向けの窓口 |
ハローワーク |
厚生労働省 |
|
地域障害者職業センター |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
それぞれの窓口の詳細とともに、具体的にどのような相談に対応できるのかについて、例を挙げながら詳しくご紹介します。
1.ハローワーク
障がい者雇用をこれから始めようと検討している企業にとって、ハローワークは、最初の相談窓口です。
全国のハローワークには、障がい者雇用に関する専門の窓口が設置されています。障がい者雇用に関する専門知識を持つスタッフが常駐するこの窓口では、企業の個別のニーズに応じた支援の提供が可能です。
|
|
メリット |
おすすめの企業 |
|
全国に設置された障がい者雇用の基本的な相談窓口 |
・アクセスしやすい ・求人から採用までの実務的な支援が受けられる ・障がい者の求職登録が多く、採用促進につながる ・助成金の情報が得られる |
・初めて障がい者雇用に取り組む企業 ・制度の概要を知りたい企業 ・採用活動を始めたい企業 |
ハローワークの障がい者雇用に関する窓口で受けられるサポート内容の例
ハローワークの障がい者雇用に関する窓口では、企業に対して以下のようなサポートを提供しています。
|
・障がい者雇用に関する基本的な情報提供 |
法定雇用率や各種助成金制度について詳細な説明 |
|
障害者雇用促進法に基づく障がい者雇用率達成に向けた指導育成 | |
|
・求人票の作成支援 |
障がい者からの応募が集まりやすい求人票の作成をサポート |
|
・障害を持つ就労希望者とのマッチング |
企業のニーズにあった求職者を紹介 |
|
・職場実習の調整 |
障がい者の適正と企業とのマッチング度合いを測るための職場実習の調整 |
|
職場実習の計画策定と実施支援 | |
|
・職務の選定や配置部署の検討をサポート | |
|
・障がい者雇用に関するセミナーの開催 | |
|
・関係機関との連携や紹介 | |
|
・助成金の案内と申請サポート | |
ハローワークの障がい者雇用専門窓口では、まず、法定雇用率や助成金制度に関する詳細な情報提供とともに、障害者雇用促進法に基づく雇用率達成に向けた指導をおこないます。
自社で何人の障がい者を雇用しなければならないのかわからない、具体的にどのように障がい者雇用を促進すれば良いのか迷っている場合は、ハローワークに相談しましょう。的確で具体的なアドバイスを受けられます。
またハローワークは、障がいがある就労希望者に向けた求人票の作成も、サポートします。ハローワークに登録している人材の中で、企業が求めている人材像に合致する就労希望者がいる場合は、紹介を受けることも可能です。
採用を検討したい人材に出会えた後も、ハローワークの支援を受けられます。例えば、就労希望者と企業双方の希望やスキル・キャパシティなどを考慮し、どのような部署でどういった業務が適切かを検討する際に相談できます。
さらに、障がい者雇用に伴う各種助成金の案内や手続きのサポートも、受けられます。
ハローワークは、障がい者の法定雇用率を達成した後も、必要に応じて適宜相談可能です。
障がい者雇用についてハローワークに相談するメリット
障がい者雇用についてハローワークに相談するメリットは、次の通りです。
・障がい者雇用に関する専門知識を有するスタッフから、支援を受けられる
・障がい者雇用における計画の立案から求人・対応後の職場定着まで、一貫して支援を受けられる
・障がい者雇用に関する他の支援機関と連携したサポートを受けられる
・障がい者雇用に関する支援を無料で受けられる
・障がい者雇用における助成金の情報提供を受けられる
ハローワークを活用すれば、コストを抑えながら効果的な障がい者雇用の計画立案・実行が可能です。
障がい者雇用の検討段階でハローワークに相談すれば、現在の状況から人材像、採用後の定着率まで、一連の経緯を共有できます。
これによって、より的確なアドバイスが可能となるでしょう。
障がい者雇用についてハローワークに相談する際の注意点
障がい者雇用をこれから始める企業がハローワークに相談する際は、次の点にご注意ください。
・相談に出向く前に、自社の業務内容や職場環境、受け入れ可能な障害の種類などを整理する
・継続的にコミュニケーションを取りながら、安定した雇用を確保できるよう努める
・管轄地域のハローワークを利用する
ハローワークの担当者が企業の実情を正確に把握し、的確な支援を提供できるよう、継続的な関係構築が欠かせません。
相談事ができたときだけ訪れるのではなく、継続的に状況を報告し、安定した雇用を確保するよう努めることが大切です。
またハローワークは、地域ごとの管轄区域に基づいて運営されています。ハローワークを訪れる前に、自社の地域を管轄するハローワークがどこか確認してから、相談に訪れてください。
管轄のハローワークは、以下から見つけられます。
・厚生労働省の都道府県労働局所在地一覧
・ハローワークインターネットサービス
2.地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、ハローワークでの初期相談や職業紹介を補完する役割を果たす、障がい者雇用の相談窓口です。より深い専門性と継続的なサポートを提供することからハローワークの「次の段階」の支援機関と位置づけられます。
採用予定の人材が決まったら、地域障害者職業センターに相談しながら、具体的な受け入れ態勢の整備を整えましょう。
|
|
メリット |
おすすめの企業 |
|
専門家による職業リハビリテーションサービスを提供 |
・専門家のサポートが無料で受けられる ・職務の切り出しや環境整備など具体的な助言が得られる |
・障害特性に応じた雇用管理の方法を知りたい企業 ・職場定着に課題がある企業 ・専門的な支援が必要な企業 |
地域障害者職業センターで受けられるサポート内容の例
地域障害者職業センターで受けられるサポート内容は、次の通りです。
・個々の障がい者に合わせた職業リハビリテーション計画の作成
・ジョブコーチによる、障がい者と事業主の双方に対して専門的な支援
・雇用管理に関する専門的な助言
障がい者雇用について地域障害者職業センターに相談するメリット
障がい者雇用について地域障害者職業センターに相談することで期待できるメリットは、以下の通りです。
・障がい者雇用に詳しい専門家から助言を受けられる
・助言を受けられるジョブコーチによる職場適応支援を受けられる
・障がい者の雇用管理における具体的なアドバイスを得られる
・障がい者が担当可能な職務の選定に関するサポートを受けられる
・無料で支援を受けられる
障がい者雇用では、入社直後の離職率が最も高い傾向があります。受け入れ環境の整備は、障がい者雇用を推進する企業にとって、大きな課題です。
ハローワークと同様に、地域障害者職業センターも無料で利用できます。障がい者の法定雇用率達成を目指して、密に連携を取りましょう。
障がい者雇用について地域障害者職業センターに相談する際の注意点
地域障害者職業センターを十分に活用するために、相談する際は次の点にご注意ください。
・就労する障がい者の就労経験や希望する職種など、詳細な情報を事前に整理する
・長期的な関係を構築する
・都道府県単位で定められた管轄の、地域障害者職業センターを利用する
・利用に際して、あらかじめ予約する
ハローワークと同様に地域障害者職業センターも、一時的な職業設計紹介ではなく継続的な支援を前提としています。長期的にコミュニケーションを取りながら、情報を共有しましょう。
地域障害者職業センターは、全国47都道府県に設置されており、各センターはその設置された都道府県全域を管轄しています。事業所の所在地を管轄する地域障害者職業センターをご利用ください。
また、地域障害者職業センターの多くは予約制を採用しています。以下で連絡先を確認の上、事前に予約してから相談に出向きましょう。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式サイト
すでに障がい者雇用を行っている企業向けの窓口
障がい者雇用についてすでに実施している企業の採用担当者が相談できる窓口には、次のようなものがあります。
|
相談窓口の種類 |
相談窓口 |
相談窓口の管轄・運営元 |
|
すでに障がい者雇用を行っている企業向けの窓口 |
障害者就業・生活支援センター |
都道府県知事が指定する社会福祉法人など |
|
障害者テレワーク雇用の相談窓口 |
厚生労働省の委託事業 |
それぞれの窓口の詳細とともに、具体的にどのような相談に対応できるか、詳しくご紹介します。
1.障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センター(通称「なかぽつ」)は、すでに障がい者雇用を行っている企業の、相談窓口です。国と都道府県から事業を委託された法人が、運営しています。
|
|
メリット |
おすすめの企業 |
|
就業面と生活面を一体的に支援する地域密着型機関 |
・生活面も含めた総合的な相談対応が可能 ・地域との連携も促進できる |
・すでに雇用している障がい者の定着を図りたい企業 ・生活面の課題が仕事に影響している場合 ・長期的なサポートを求める企業 |
障害者就業・生活支援センターで企業が受けられるサポート内容の例
障害者就業・生活支援センターは、障がい者の就業面と生活面の一体的な支援を提供すると同時に、企業向けに以下のようなサービスを提供しています。
・障がい特性を踏まえた雇用管理についての専門的なアドバイス
・定期的な職場訪問や相談を通じたサポート
・職場環境の調整に関するアドバイス
・障がい者の生活面でのサポートによる、安定就労の支援
・関係機関との連携による包括的な支援
障害者就業・生活支援センターは、障がい者と企業の間に入り、認識や理解の齟齬を埋め、双方の距離を縮めるサポートを提供します。
障がい者雇用について障害者就業・生活支援センターに相談するメリット
障がい者雇用について障害者就業・生活支援センターに相談するメリットは、次の通りです。
・就職準備から職場定着まで、継続的な支援を受けられる
・障がい特性を踏まえた雇用管理について、専門的な助言を得られる
・ハローワークや地域障害者職業センターなど、他の支援機関と連携したサポートを受けられる
・相談や支援サービスは無料で利用できる
障害者就業・生活支援センターに相談することで、当該障がい者に対する直接のサポートも含めて、包括的な支援を受けられるのは、大きなメリットです。
また、障害者就業・生活支援センターは無料で利用できるため、コストを抑えながら安定的な障がい者雇用の促進を図る効果も期待できます。
障がい者雇用について障害者就業・生活支援センターに相談する際の注意点
障がい者雇用について障害者就業・生活支援センターに相談する際は、次の点に注意しましょう。
・事前に予約を取る
・長期的な支援を視野に入れて継続的な関係性を構築
・企業の業務内容や職場環境の情報を共有
障害者就業・生活支援センターには、地域ごとに管轄が定められています。企業の所在地ごとに管轄のセンターは異なるため、あらかじめ確認の上、相談に出向く際は事前の予約を取りましょう。
どのセンターが管轄か、調べる際は以下をご利用ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営する全国の地域障害者職業センターの一覧
2.障害者テレワーク雇用の相談窓口
障害者テレワーク雇用の相談窓口は、企業の障がい者テレワーク雇用の円滑な導入と運営を支援します。厚生労働省が開設した、企業向けの無料相談サービスです。
|
|
メリット |
おすすめの企業 |
|
就業面と生活面を一体的に支援する地域密着型機関 |
・ICT環境整備の支援を受けられる ・働き方の多様化も推進可能 |
・通勤困難な重度障がい者の雇用を検討する企業 ・地方在住者を採用したい企業 ・既存社員にテレワークを導入したい企業 |
障害者テレワーク雇用の相談窓口で受けられるサポート内容の例
障害者テレワーク雇用の相談窓口で受けられるサポート内容には、次のようなものがあります。
・障がい特性に応じた職場環境整備に関するアドバイス
・テレワーク雇用の制度設計を支援
・テレワーク導入に際して必要な機器・ソフトウェアの選定に関する助言
・採用計画策定と求人作成サポート
・従業員の体調管理やコミュニケーション方法の提案
・テレワークでの勤怠・業務進捗管理の助言
障がい者雇用をテレワークで実施する試みは、多くの企業に採用されています。自社の場合はどのように導入すれば良いかと迷う場合は、障害者テレワーク雇用の相談窓口を活用するのがおすすめです。
障害者テレワーク雇用の相談窓口で相談するメリット
障害者テレワーク雇用の相談窓口で相談するメリットは、次の通りです。
・経験豊富な専門アドバイザーから、無料で個別に課題解決に向けたサポートを受けられる
・業務構築から採用、定着・活躍支援まで、総合的なサポートを受けられる
・成功事例や先進的な取り組みの情報を得られる
・ICTを活用したテレワーク環境の整備や制度設計について、具体的な助言を受けられる
・1社当たり最大5回(新規テレワーク雇用導入時は追加2回)の支援を受けられ、継続的なフォローアップが可能
・情報収集段階や相談事項が明確でない状況でも、課題整理から支援を受けられる
障害者テレワーク雇用の相談窓口で相談する際の注意点
障害者テレワーク雇用の相談窓口で相談する際は、次の点に注意すると、より効果的に活用できます。
・複数回の相談を想定する
・オンライン相談の準備を万全にする
障害者テレワーク雇用の相談窓口は、最大5回(新規テレワーク雇用の場合は追加2回)の支援が可能です。チャンスをフル活用し、継続的な相談を検討しましょう。
また障害者テレワーク雇用の相談窓口の利用は、原則オンラインでの相談です。あらかじめ、必要なICT環境を整備しましょう。あわせて、可能な限り具体的な質問や課題を準備することも重要です。
障害者テレワーク雇用の相談窓口への申し込み方法は、以下の通りです。
・Webサイト:特設サイトから申し込む
・電話:TEL:03-4213-7222(受付時間:土日祝・年末年始を除く平日9時~16時)
・メール:support@twp.mhlw.go.jp
申し込みの際は、企業名や担当者名、連絡先などの基本情報に加えて、相談したい内容や希望する日時などを伝えましょう。
障がい者雇用に関して企業が相談する際のポイント
障がい者雇用を成功させるためには、相談機関との効果的なコミュニケーションが不可欠です。ここでは、企業が相談する際に押さえておくべき重要なポイントについて解説します。
業務内容や職場環境を具体的に伝える
相談をスムーズに進めるためには、どのような業務を任せたいか、職場の物理的・人的環境がどのようなものかを具体的に伝えることが重要です。
業務内容については、日々のルーティンワークの種類や作業時間、必要なスキルレベルなどを明確にしましょう。
また、職場環境に関しては、バリアフリー設備の有無、通勤アクセス、フロアの配置、騒音レベル、照明の明るさなどの物理的要素を説明することが大切です。
加えて、チーム構成や上司・同僚のサポート体制といった人的環境も詳しく伝えることで、相談機関は適切なマッチングや支援策を提案しやすくなります。
>>【無料でダウンロードする】業務切り出しの方法に関するお役立ち資料
求める人物像・スキルを明確にする
企業が求めるスキルや人物像、安定して勤務できるかといった点を明確に伝えることで、より適切な人材マッチングや支援につながります。
具体的には、必須スキルと歓迎スキルを分けて整理し、PCスキルやコミュニケーション能力、作業の正確性など、業務遂行に必要な要素を明示しましょう。また、勤務時間や勤務日数の希望、将来的なキャリアパスの可能性についても伝えることが大切です。
合理的配慮について検討しておく
障がい特性に応じた「合理的配慮」の提供は企業の義務です。合理的配慮とは、障がいのある方が業務を遂行する上で必要な調整や支援を指し、企業には過度な負担にならない範囲での提供が求められています。
必要な配慮や提供可能な配慮を事前に検討しておくと、相談機関から具体的なアドバイスを得やすくなります。
▼合理的配慮について詳しく知りたい方はこちら
「合理的配慮とは?職場での具体例や企業の義務化について簡単に解説」
障がいをお持ちの方向け相談窓口
ここからは、障がいをお持ちの方向けの相談窓口を4か所、ご紹介します。
|
相談窓口の種類 |
相談窓口 |
相談できる内容 |
|
これから働きたい方向けの窓口 |
ハローワークの障がい者専用窓口 |
求人情報の提供や職業紹介就職活動のサポート |
|
障害者就業・生活支援センター |
就業面と生活面の一体的な支援職業訓練や職場実習のあっせん | |
|
すでに働いている方向けの窓口 |
市町村の福祉担当課や福祉事務所 |
福祉制度やサービスに関する相談 |
|
なんでも相談センター |
福祉に限らず、生活全般の相談必要に応じて適切な専門機関へつなぐコーディネート機能 |
ご自身の状況に合わせて、使い分けてください。
これから働きたい方向けの窓口1|ハローワークの障がい者専用窓口
ハローワークの障がい者専用窓口は、障がいがある方の就職活動の入り口として、最適な機関です。
ハローワークでは、障がい特性を理解した専門スタッフが、求人情報の提供から職業紹介、就職準備支援、職場実習の調整まで、総合的なサポートを無料で提供します。利用の際は、障害者手帳や診断書を持参するとスムーズです。
ハローワークは全国ネットワークを活用しているため、基本的にはどこでも利用できます。ただし、求職の申し込みは、原則として管轄地域のハローワークでおこなわなければなりません。
求人情報はインターネットで検索できますが、応募に際しては、窓口で相談する必要があります。ご自分の住まい先を管轄するハローワークがどこにあるかは、以下をご参照ください。
厚生労働省「ハローワークの所在地一覧・管轄」
これから働きたい方向けの窓口2|障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、就業面と生活面の包括的な支援を行う機関です。職業準備から就職後の定着支援まで長期的なサポートを受けられるほか、生活リズムの確立や金銭管理など、日常生活の支援も受けられます。
ただし利用に際しては、事前の予約が必要です。また継続的な支援を前提としているため、単発の相談には向きません。
居住地域のセンターを利用する必要がありますが、関係機関と連携した包括的な支援を受けられる点は、大きな魅力です。
厚生労働省「令和6年度障害者就業・生活支援センター一覧」
すでに働いている方向けの窓口1|市町村の福祉担当課や福祉事務所
市町村の福祉担当課や福祉事務所は、主に行政サービスや福祉制度に関する相談窓口として機能します。障がい福祉サービスの利用申請や手続きのほか、生活保護などの公的扶助に関する相談なら、市町村の福祉担当課や福祉事務所で相談可能です。
地域に密着した支援が受けられますが、就労に特化した支援には不向きです。地域の福祉サービスについて幅広く相談したい場合は、市町村の福祉担当課や福祉事務所を訪れると良いでしょう。
すでに働いている方向けの窓口2|なんでも相談センター
なんでも相談センターは、包括的な支援を提供する窓口です。福祉に限らず、生活全般の相談を受け付けます。
障がい者が24時間利用できる「なんでも相談センター」としては、次のようなものがあげられます。
|
相談先 |
|
応対時間 |
相談できる内容 |
サービス提供者 |
|
よりそいホットライン |
0120-279-338(フリーダイヤル・無料) |
24時間365日 |
障がい者を含むさまざまな悩みの相談に対応 | |
|
いのちSOS |
0120-061-338(フリーダイヤル・無料)チャットWeb |
日曜日から火曜日、金曜日、土曜日は24時間対応 |
自殺防止を目的としていますが、障がい者の相談にも対応可能 | |
|
あなたのいばしょチャット相談 |
公式サイト |
24時間365日 |
さまざまな悩みに対応 |
※2025年12月現在
また勤務先からのパワハラに悩んでいる場合の相談窓口は、次の通りです。
|
相談先 |
問い合わせ先 |
応対時間 |
相談できる内容 |
サービス提供者 |
|
社内の相談窓口 |
企業内の「障がい者相談窓口」や「ハラスメント相談員」 |
企業により異なる |
就労に関する悩み全般 |
各企業 |
|
労働局・労働基準監督署 |
住まい先を管轄する労働局・労働基準監督署 |
窓口での相談:平日の午前8時30分から午後5時15分まで電話での相談:平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
就労に関する悩問題で、法規に反する内容について |
労働局・労働基準監督署 |
|
ハローワーク |
障がい者担当窓口 |
原則として平日8時30分から17時15分まで |
就労に関する悩み全般 |
厚生労働省 |
|
障害者就業・生活支援センター |
就業支援担当員 |
原則として平日9時から17時15分(地域によって異なる) |
就労に関する悩み全般 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
|
みんなの人権110番 |
0570-003-110もしくは公式サイトからWeb相談 |
平日午前8時30分から午後5時15分 |
職場でのいじめやハラスメントに関する相談 |
法務局 |
|
法テラス |
法テラス・サポートダイヤル |
法テラス・サポートダイヤル(一般的な法的トラブルの相談)平日:9時から21時土曜日:9時から17時(祝日・年末年始を除く) |
パワハラに対する法的措置の相談 |
総務省 |
企業担当者・従業員共通の相談窓口
企業担当者・従業員共通の相談窓口として、次の2つがあります。
・社会保険労務士
・労働基準監督署
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家です。企業の人事労務管理や従業員の福祉向上を支援します。書類作成や手続き代行、労務管理の相談などのサポートが可能です。
労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法令の遵守を監督・指導する国の機関です。労働条件や安全衛生に関する相談、労災保険の手続きなどに対応します。違法行為の是正指導や調査を担当するのも、労働基準監督署の役割です。
障がい者雇用の相談に関するよくある質問
障がい者雇用の相談に関するよくある質問を3つ取り上げて、ご紹介します。
企業には、障がい者雇用の相談窓口の設置義務はありますか?
はい。障害者雇用促進法第36条の4の2項に基づき、事業主は障がい者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する義務があります。
参考:e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」
障がい者雇用は、どこまで配慮すれば良いでしょうか?
企業は「過度な負担にならない範囲」で、合理的配慮を提供する必要があります。
ただし障がいの種類や程度、職場環境によって、必要な配慮は異なるため、障がい者本人と企業が十分に話し合い、個別の状況に応じた配慮の検討が大切です。
精神障がい者が24時間相談できる窓口はありますか?
以下が、24時間対応しています。
・こころの健康相談統一ダイヤル
電話番号:0570-064-556
全国どこからでも24時間365日、相談を受け付けています
・よりそいホットライン
電話番号:0120-279-338
24時間365日対応しており、精神障がいを含むさまざまな悩みの相談に応じています
このほかにも、各地域で窓口を設けていることがあります。
まとめ
障がい者雇用の相談窓口は、企業と障がい者双方にとって重要な支援システムです。ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど、さまざまな機関が連携して包括的なサポートを提供しています。
これらの窓口を適切に活用することが、障がい者雇用の促進と安定、そして障がい者の就労と生活の質の向上のために欠かせません。
ニーズに合った適切な窓口を選択し、効果的な支援を受けましょう。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







