就労継続支援B型とは?働き方やA型との違いをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
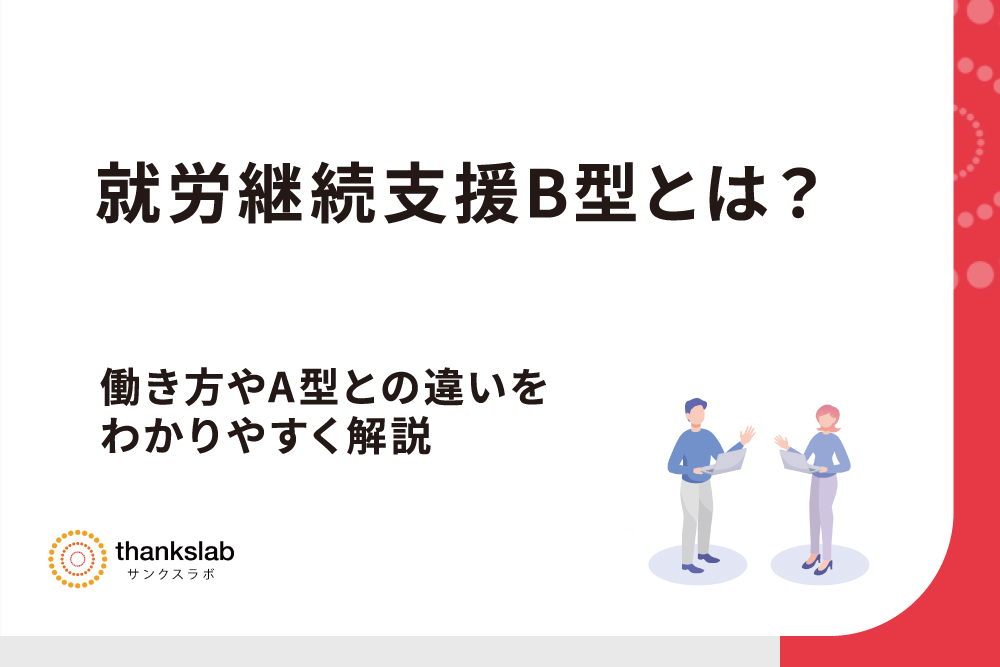
障がいを持つ方が働く方法は複数あり、就労継続支援B型もその1つです。「どのような支援か知りたい」「A型との違いを知りたい」と考えている方も多いでしょう。
本記事では、就労継続支援B型とはどのようなサービスなのか概要や仕事内容、就労支援A型との違いを解説します。
目次
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障害や病気の影響などで一般企業へ就職することが困難な方や、A型事業所での雇用が難しい方に対し、働く機会や作業訓練の場を提供する福祉サービスです。「生産活動」をおこない、その対価として「工賃」を受け取る形式で働きます。
利用している障がい者は事業所でスタッフのサポートを受けながら仕事をします。仕事のやり方はもちろんのこと、就労継続のための基礎的な能力や生活リズムを身につけるサポートを受けることも可能です。
また、一緒に仕事をしている方も障がいを持っているので、障がい者雇用で採用されて一般の企業で働くよりもストレスなく働きやすい傾向があります。
さらに、スタッフのサポートもあるため、メンタル面でも落ち着いて仕事ができるのがメリットです。
就労継続支援B型と障がい者雇用枠での就労との違い
障がい者が障がいに関する配慮を受けながら就労をするという点では、就労継続支援B型と障がい者雇用枠での就労は同じです。しかし、障がい者雇用で採用されて一般企業で働く場合、健康な方に混じって働く必要があります。
障がいは考慮されるので、健康な方同様に1日8時間働く必要がない職場も多いでしょう。しかし、企業で働く以上、一定の成果は求められます。さらに、職場によっては障がい者を受け入れるのが初めてだったり、障がいに関する知識が薄かったりするデメリットがあります。
一方、就労継続支援B型は作業時間や作業量も柔軟に調整できるため、障害の程度や体調に不安がある方、体力的に負担が大きい方でも利用しやすいのが特徴です。就労をサポートしてくれるスタッフは、障がいに関する知識を持ち、障がい者をサポートしてきた実績も豊富です。
したがって障害による困りごとの状況や症状などに合わせて、無理のないペースで働くことができるのが大きなメリットです。
就労継続支援A型とB型との違い
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。A型とB型の違いは雇用契約です。就労継続支援A型を利用する場合は、作業所と雇用契約を結びます。そのため、最低賃金以上の給与が必ず支払われるのが特徴です。また、働いている時間によっては、社会保険の加入もできます。勤務時間・日数など労働条件が明確にもなっているため、一般的な就労に近い形です。
一方就労継続支援B型は、雇用契約を結びません。そのため給与ではなく「工賃」という形で仕事の報酬が支払われます。雇用契約を結ばないため、給与や労働条件の縛りがない分、柔軟に利用できるのが特徴です。例えば、「障がいで長時間、毎日働くのが難しい」といった場合、週に1度、2時間だけといった働き方もできます。
なお、就労継続支援B型を利用し、仕事への自信と日常生活を送るうえでのリズムが確立できたら、A型への移行も可能です。したがって、「障がいを持っているが仕事をしたい、しかし障がいを抱えて仕事をする自信がない」という方や、「就労継続支援A型を利用したが、働き続けることができなかった」といった方でも利用しやすくなっています。
仕事をするだけでなく、仕事をしながら社会とのつながりを持って生活リズムを整えることが、就労継続支援B型を利用する目的です。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型の対象者は、以下の条件に当てはまる方です。
- 障がいを持っていたり難病に罹患したりした方で就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった
- 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者
- 就労アセスメントでB型事業所が適切と判断された
なお、障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」を自治体から発行してもらえば、就労継続支援B型を利用可能です。さらにA型やほかの福祉サービスを受けるうえでも受給者証は必要です。
A型は原則として18歳から64歳までの利用年齢制限が設けられているに対し、B型は、利用期限や年齢制限は設けられていません。例えば、40代まで健康で一般的な社会人として就業して生活していたが、病気や交通事故等で障がい者になってしまった方が、社会復帰の第一歩として利用するケースもあります。
また、養護学校に通っていた方が就労継続支援B型を利用したい場合は、就労アセスメントを受ける必要があります。就労アセスメントとは、複数の面から評価を行い、具体的な作業や模擬的作業を通じて就労意欲や能力を評価する方法です。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の仕事内容は、各種加工・組立て、袋詰め・パソコン作業・シール貼り・検品・印刷などの軽作業が中心です。A型にも似たような作業がありますが、より細分化されているところが多い傾向があります。
例えば、A型ならば物品の組み立て、袋詰め、シールはりまで同じ人が行うのに対し、B型は組み立て、袋詰め、シール貼りを別の方が行う作業所もあります。
就業時間は、1週間に20~25時間の方が多いですが、週5日4時間ずつ働く方もいれば、1日3時間週6日働く方もいるでしょう。事業所によってはフルタイムで働く方もいます。
継続支援B型の工賃とは?
就労継続支援B型の生産活動(作業)は雇用契約を結ばずに行われるため、労働基準法に基づく「賃金」ではなくに働いた分の対価として「工賃」が支給されます。賃金ではないので、最低時給は保障されていません。
厚生労働省が発表した「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によると、月額の平均は1万7,031円、時間給にして243円です。令和3年の工賃がは月額16,507円で、時給換算すると233円なので、時給にして10円、月額にして500円、高くなっています。都道府県ごとにも差があり、東京の場合は1万6320円と平均よりも低くなっているのが特徴です。
なお、就労継続支援B型だけでは経済的な自立はほぼ不可能です。経済的に自立したいと思っている場合は、年金や生活保護なども活用しましょう。また、就労継続支援A型、就労移行支援、障がい者雇用枠での就業などステップアップしていく方法があります。かつで就労しており、まだ一般的な会社で働きしたいといった場合は検討してみてもいいでしょう。
就労継続支援B型の利用方法
ここでは、就労継続支援B型を利用するまでの基本的な流れを解説します。一般的な会社への就労との違いも把握しておくとスムーズに行動ができるでしょう。作業所を選ぶポイントも紹介するので、参考にしてください。
障害者支援センターに相談して事業所を探す
まずは、障害者支援センターや自治体の障害者福祉相談窓口等を利用して、就労継続支援B型の作業所を探します。インターネットを活用してもいいでしょう。自治体によってサポートや相談窓口が異なるので、まずは市役所の福祉相談窓口に相談する方法もあります。
作業所の選び方は、仕事内容のほか通勤時間も重要です。希望する働き方ができる作業所であっても、通勤時間が長いと体調に影響ができる可能性があります。
1人で探すのが難しい場合は、家族や自治体の職員によるサポートを依頼しましょう。
事業所を見学して利用を検討する
就労継続支援B型の作業所の中には、見学や体験入所をしているところもあります。見学を申し出れば大抵の作業所で受け入れてもらえます。ただし、作業所によっては定員いっぱいで新しい方を受け入れられないところもあるので、問い合わせの際に空き状況も確認しましょう。
なお、作業所によって仕事に対する取り組みも異なります。例えば、障がい者が仕事をすることで社会とつながりを持ち、生活のリズムを安定させることを最大の目標にしている作業所もあります。このような作業所は、働く方の体調や仕事の継続性を重要視するところも多いです。「和気あいあいと仕事ができればそれが一番」と考えているところもあるでしょう。
一方、就業継続支援A型への移行や一般的な企業に障がい者雇用での採用を最終的な目標としているところもあります。そのような作業所は、仕事を通じてスキルアップしたり、長時間仕事ができたりといった点が特徴です。
仕事に対する考えやスタイルに合った作業所を選ぶことも大切です。
市町村の福祉課に利用申請する
利用する作業所が正式に決まったら、お住いの自治体にある福祉課に利用申請を行います。障害者手帳を所有していない方は、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」を申請しましょう。
なお、申請した場合は、現在の状況やサービス利用する目的、将来の目標等について聞き取り調査があるのが一般的です。
自分の考えをまとめておくと話し合いがスムーズにいきます。
また、A型同様「サービス等利用計画案」の提出が必要ですが、これは相談支援員等に依頼できます。自分で作成しても問題ありません。さほど複雑なものではないので、できるならば自分や家族が作成しても大丈夫です。
利用許可が下りたら利用開始する
審査の結果、利用許可が下りたら作業所に通勤して利用を開始しましょう。なお、就業継続支援B型の作業所は障害者福祉サービスの一つなので、世帯年収によっては利用料が必要です。市町村民税が非課税世帯は利用料がかかりませんが、課税世帯の場合は最大で3万7,200円の利用料が必要です。
就労継続支援B型を利用する際の注意点
[最後に、就労継続支援B型を利用する際の注意点を紹介します。
将来の働き方について考える必要がある
就労継続支援B型は、仕事の経験を積む、社会とのつながりを持つ、生活のリズムを整えるといった目的をもって運営されています。利用期限はありませんが、ずっと利用していても経済的な自立は難しいでしょう。
A型に移行するのか、利用を続けて社会とのつながりを保ち続けるか、将来について考える必要があります。
「利用さえできれば、生活は問題ない」といったサービスではありません。
自分の状態にあった働き方を選ぶ必要がある
就労継続支援B型は、作業所によって目標が異なります。一般的な企業で仕事をするのは難しいが、できることはしたいと考えているのか、A型、障がい者雇用の枠での就職を目標としているかによって、適したところが異なります。
「通えればどこでもいい」といった考え方では通所が続かない可能性もあるので、注意しましょう。
まとめ
本記事では、就労継続支援B型の概要や働き方、A型や障がい者雇用での就職との違いについて解説しました。就業支援B型は、一般的な働き方は難しいけれど就業はしたいと考えている障がい者にとって利用するメリットが大きなサービスです。
就職したいがいきなり障がい者雇用に挑戦する自信はない、A型を利用したがついていけなかったといった方も利用を検討してましょう。
ただし、給与ではなく「工賃」なので得られるお金は少なく、所得によっては利用料が必要なことも把握しておいてください。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







