就労継続支援A型とは?仕事内容や給料の平均などわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
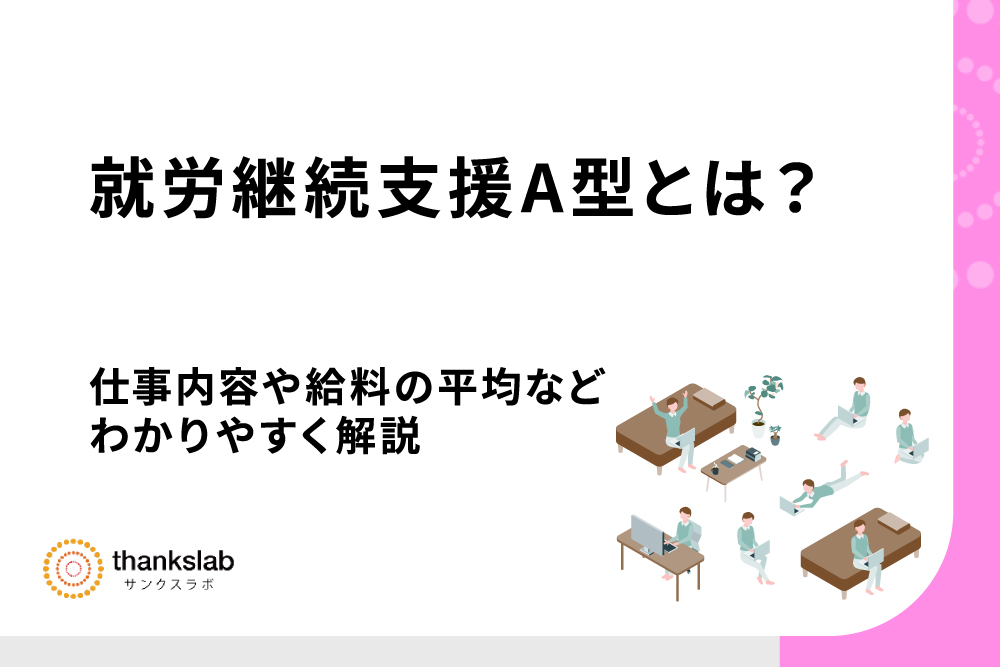
近年は障がいを持っていても就業して経済的に自立する障がい者も増えています。障がい者の働き方は複数あり、就労継続支援A型もそのひとつです。
「障がい者雇用や一般的な就業と何が違うのか」「就労継続支援A型と障がい者雇用のどちらを利用して就業するか迷っている」といった方もいるでしょう。
本記事では、就労継続支援A型とはどのような仕事内容か知りたい方に向けて、概要や仕事内容、平均給与、一般就労との違いを解説します。
目次
就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。
企業などで働くことが困難な障害のある方に対し、雇用契約を結んだ上で、就労の機会や生産活動の機会を提供し、その知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援A型は、雇用契約に基づくため「雇用型」とも呼ばれ、安定した収入を得ながら、自身のペースで働くスキルを身につけたい方に適したサービスとなっています。
障がい者雇用で働く準備としても利用できる
障がいをお持ちの方によっては「障がい者雇用で働きたいが、一般企業で働いていけるか心配」と悩んでいる方も多いでしょう。
そのような場合、就労継続支援A型を利用して就業経験を積み、自信をつけてから障がい者雇用での就職を目指すことも可能です。
企業にとっても、就業経験がない障がい者より就業経験を持っている方のほうが安心して雇用できます。「障がい者雇用で就業を目指しているが、就業経験がないので採用までに至らない」といった場合も、就労継続支援A型を利用するとキャリア構築の参考になる可能性もあります。
就労継続支援A型の対象者
就労継続支援A型で働けるのは身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)などの障がいや病気があり、一般就労が難しい方です。障がい者雇用とは異なり、障害者手帳は必要ありません。
例えば、「障害者手帳を取得したかったが、指定医に診察を受けた結果、手帳取得までにが至らなかった」といった方でも就労継続支援A型の利用は可能です。
ただし、医師の診察を受けたうえで自治体に申請をする必要があります。「医師の診察を受けていないが、自分は健康な方と一緒に働くのは難しいと自覚している」といったケースは、まず医師の診察を受けてください。
また、「適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能な人」であることも条件です。雇用契約に基づく就労が難しい場合は、就労継続支援B型のほうが適しているケースもあるでしょう。A型とB型のどちらにしようか迷っている場合は、自治体の福祉担当窓口に相談してみるのがおすすめです。
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事内容は、事業所によって多岐にわたります。利用者は、自身のスキルや興味関心に合わせて、様々な業務に挑戦することができます。
代表的な仕事内容としては、以下のようなものがあります。
| 分類 | 仕事内容の例 |
|---|---|
| 事務作業 | パソコン入力、データ入力、書類作成、電話応対、受付業務 |
| 軽作業 | 部品組み立て、検品、梱包、清掃作業 |
| 接客・販売 | カフェやレストランでの接客、商品の陳列・販売、レジ業務 |
| クリエイティブ | Webデザイン、イラスト作成、動画編集、パンフレット作成 |
| その他 | 農作業、パンや菓子の製造、クリーニング作業 |
これらの仕事を通じて、利用者は就労に必要なスキルを習得したり、働くことへの自信を深めたりすることができます。事業所によっては、資格取得支援やキャリアアップのための研修なども行っています。
就労継続支援A型の利用期間
就労継続支援A型の利用期間は、原則として18歳~65歳未満の方が利用できます。就労支援B型の場合は年齢制限の上限がないのに対し、就労継続支援A型は64歳までが対象となっています。
ただし、65歳になったらいかなる理由であれ就労支援の利用ができなくなるわけではありません。利用者の事情によっては臨機応変に対応してくれるので、60歳を超えているが就労支援A形で働きたい場合は、お住いの自治体にある福祉課の相談窓口で相談してみましょう。
また、就労継続支援A型は利用期間の制限はありません。例えば、18歳から64歳までの利用も可能です。
就労継続支援A型と一般的な就労の違い
就労継続支援A型と一般的な就労の違いは、「働くにあたってのサポートの有無」です。障がい者雇用で働く場合、前述したように企業に障がいに対する配慮を要求できます。
しかし、障がい者が希望する配慮がすべて反映できるとは限りません。また、障がい者雇用の場合、一緒に働く方は健康な方がほとんどです。そのため、障がいに関する理解が低い可能性もあります。障がいの種類や程度によっては健康な方と働くのは難しいケースもあるでしょう。
一方、就労継続支援A型の場合は障がい者とスタッフで働きます。自分の体調やスキル、適性などを考慮してもらいながら働けるのが特徴です。体調やスキルによっては、短時間から働けます。
就労継続支援A型の平均給与
なお、就労継続支援A型の平均給与は8万1,645 円です。職種や就業時間によってはもっと給与を得られる場合もある一方で、平均給与ほど給与を得られない可能性もあります。
就労継続支援A型で得られる給与は年々上昇傾向にありますが、それでも就労支援のみで経済的に自立するのは難しいケースが多いでしょう。
経済的に自立したい場合は、家族で生活する、障害者年金や生活保護なども併せて受給するなどの方法を考える必要があります。
就労継続支援A型と就労移行支援や就労定着支援との違い
障がい者の就労支援や就労サポートには、就労継続支援A型以外に「就労移行支援」や「就労定着支援」があります。就労移行支援は、一般就労を希望する人が対象のサービスであり、最長で2年間利用できます。就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援などを利用して就労した方が、できるだけ長く職場で働けるようにサポートを行うサービスです。
就労支援は「就労すること」をサポートするのが目的なのに対し、就労移行支援や就労定着支援は障がい者雇用を含む一般企業への就職する方を対象としています。
例えば、就労継続支援A型を利用して就労に関する経験を積んだ後、就労移行支援を受け、一般企業に就職するといったステップアップ方法もあります。
同じ「就労」でも利用できるサービス内容が異なるので、よく確認したうえで利用してください。
就労継続支援A型で働くには?
ここでは、就労継続支援A型で働くにはどのような手順で就業すればいいのか、基本的な流れを解説します。
一般的な就労とは異なる点も多いので、確認したうえで就労に向けた行動を開始しましょう。
就労継続支援A型の事業所を探す
まずは、就労継続支援A型の事業所を探します。仕事内容はもちろんのこと通勤のことも考えましょう。就きたい仕事であっても通勤時間が30分を超える場所は障がいを持っていると働き続けるのが難しくなる場合もあります。
また、事業所の雰囲気やスタッフとの相性も大切です。障がいの種類や程度によっては職場の雰囲気があっていないと働き続けるのが難しくなる可能性があります。
就労継続支援A型を運営しているスタッフは、障がい者の就労に関するサポート力に優れています。就職に前向きであれば積極的にサポートしてもらえるでしょう。
事業所の選考を受ける
就職したい事業所が決まったら、選考を受けましょう。就労継続支援A型社会福祉サービスの一環ではありますが、企業と雇用契約を結んで働きます。したがって、一定レベルの仕事ができることが重要です。
また、本人のやる気があっても障害の状態によっては仕事をするのが難しい場合もあるでしょう。その一方で、パソコンでの入力作業など一般的な企業と同じような仕事ができるケースもあります。
就労支援は本人のやる気だけでなく、障がいの程度や自身の体調に合わせて仕事を行う働き方です。しっかりとスタッフに希望を伝えたうえで、最適な働き方ができるように調整しましょう。
市区町村窓口で利用申請する
就労継続支援A型は就労ではなく社会福祉サービスの一環です。そのため、市町村の窓口で利用申請をする必要があります。なお、利用申請は許可が下りるまで時間がかかる可能性があるため、事業所の選考を受ける前に利用申請してもいいでしょう。
利用申請を行うと申請先の市区町村の担当職員から、生活状況などの聞き取り調査を受けます。また、障害者手帳を持っていない場合は、受給者証を発行してもらう必要があるため、医師の診察をするように求められます。
このほかでサービス等利用計画案を作成、提出も求められるので就業予定の事業者、もしくは自分で作成して提出してください。さほど複雑な書類ではありませんが、先に事業者の選定を受けていれば、利用計画案作成のサポートもしてもらえます。
受給者証を発行してもらい勤務開始
申請した内容に問題がなければ、利用開始となります。障害者手帳を持っていない場合は、受給者証を発行してもらう必要があるので、発行後に就業します。
なお、申請から就業開始まで1ヶ月ほどの時間がかかるのが一般的です。
アルバイトのように、面接後すぐに「じゃあ、明後日から働いて」ということはありません。そのことを承知しておきましょう。「この日から就業したい」といった希望がある場合は、日付を逆算して申請を行ってください。
就労継続支援A型で働く際の注意点
最後に、就労継続支援A型で働く際の注意点を紹介します。就労支援と一般的な就労との違いを把握しておくことが大切です。
利用料金がかかる場合がある
就労継続支援A型は、障害福祉サービスの一環です。そのため、世帯所得によっては利用料金がかかる場合があります。「仕事をするのにどうして料金を働かなければならない」と疑問に思う方もいるでしょう。
就労継続支援A型を行っている事業所は、利益を出す企業ではなく障害者福祉サービスです。そのため、自治体からの支援金等で運営しているところもあります。
利用料金は最大で3万7200円です。なお、世帯年収300万円までの場合は無料で利用できます。
賃金だけでは自立が難しい可能性がある
前述したように、就労継続支援A型の平均月収は10万円未満です。そのため、毎日6時間働いた場合でも1人で部屋を借りて自分の収入だけで生活をするのは難しいでしょう。
例えば、「病気や交通事故などで人生の途中で障がい者となったが、今までずっと仕事をしてきた」という場合は、就労支援A型を利用して仕事に再チャレンジしてみて、仕事を続けられそうならば、就労移行支援を利用して一般の企業に移行できるように行動してみてもいいでしょう。
また、月10万前後でも収入がある場合は、障害者年金と併せれば生活できるケースもあります。就業していれば社会的信用度も上がり、転職のチャンスを得られる可能性も高まるでしょう。
申請から利用開始まで時間がかかる場合がある
前述したように、就労継続支援A型を利用するには自治体に申請を行い、審査を受ける必要があります。また、利用計画書の提出も必要です。仕事をしようと考えてから実際に仕事をするまでに時間がかかります。
そのため、「新年度にあわせて仕事をしたい」と思った場合、申請から許可が下りるまでの期間を逆算して行動する必要があります。
まとめ
本記事では、就労継続支援A型の特徴や対象、一般的な会社への就職とのちがいなどを紹介しました。就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ形ではありますが、障害者福祉サービスの一環でもあります。
そのため、障がいについて知識や経験があるスタッフのサポートを受けながら無理のない範囲で仕事をすることができます。
通常の会社では就労が難しいが、仕事をしたいと考えている方には適した働き方です。障がいの種類によっては、通常の会社で障がい者雇用枠で仕事をするよりも、ストレスや肉体的な負担を少なくして働き続けることができるでしょう。また、社会の一員であるという自信も持つことができます。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







