障がい者雇用とは?一般雇用との違いやメリットをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.05.23
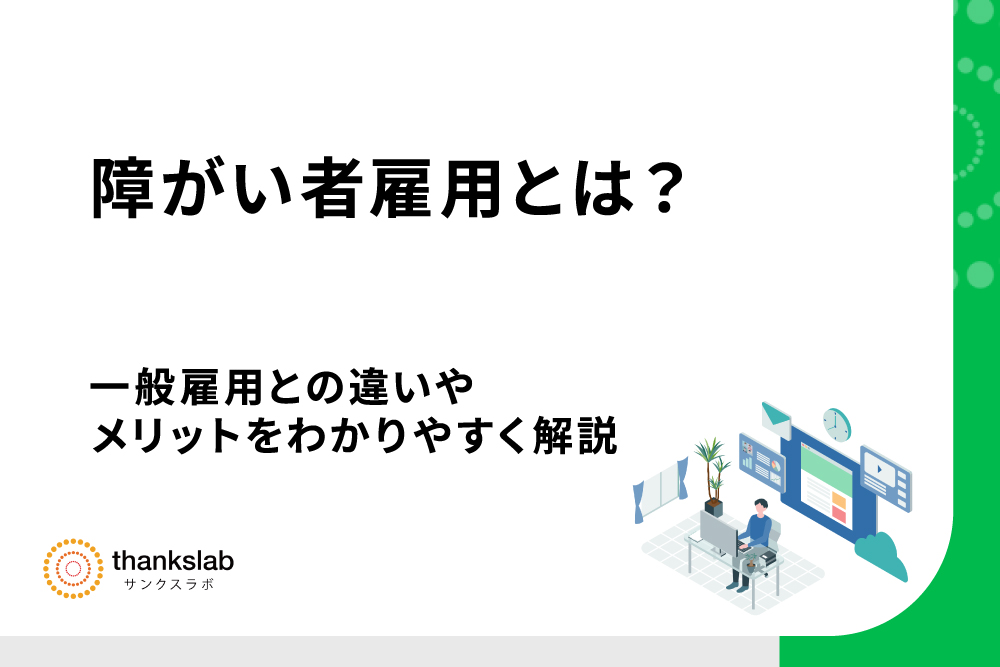
「障害者雇用ってどういう制度?」
「障害者雇用と一般雇用にはどのような違いがあるんだろう?」
障害者雇用を考えている企業担当者の方は、このような悩みを持っている方が少なくありません。障がいのある方を雇用する場合、企業が果たさなければならない義務があり、採用に際しても障害の特性を考慮し、職務負担や業務内容を調整する必要があります。
ここでは、障害者雇用と一般雇用の違いや進め方、果たすべき義務などについてわかりやすく紹介していきます。企業の担当者様はよかったら参考にしていただき障害者雇用を進めてみてください。
また、これから障害者雇用について知識を深めたい方のために入門向けの資料もご用意しています。基本的な障害者雇用の知識や採用のポイントについて知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
障害者雇用とは
障害者雇用とは、心身に障がいを持っている方を一般雇用とは別枠で雇用することです。
ここでは障害者雇用の定義や障がいを持っている方が障害者雇用で働く目的、障害者雇用に関連する法律を紹介します。
障害者雇用の定義
障がい者雇用とは、障がいのある人が働く機会を得られるよう、企業が適切な環境を整えて雇用することです。
日本では「障害者雇用促進法」で、障がいを持っている方が、個々の特性に合わせた働き方ができるように規定されています。また、障害者雇用促進法は、企業が果たすべき義務や差別の禁止なども定められている法律です。
障害者雇用の対象者と働く目的とは?
障害者雇用の対象者は、障害者手帳を持っている方です。障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。
身体障害者手帳は身体に障がいを持っている人、療育手帳は知的障がいを持っている人、精神障害者保健福祉手帳は精神疾患(発達障害を含む)を患っている人が持っている手帳です。
障がいを持っている方が障害者雇用で働く目的は、障害を持っていることを理解した上で雇用した企業で働くことは、障害に対する理解、環境整備などに配慮を受けやすくなるからです。
その結果、仕事に安定して就けるようになり、経済的自立や生活の安定につながります。
障害者雇用促進法とは?
障害者雇用促進法は、正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法律です。
障害者雇用率制度
一定数以上の社員がいる企業は、一定割合以上の障害者を雇用(法定雇用率)しなければいけない制度です。
法定雇用率を以下の表にまとめました。(2025年4月時点)
| 企業・団体の種類 | 障害者雇用率 |
| 民間企業 | 2.5% |
| 国・地方公共団体、特殊法人 | 2.8% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
従業員を40人以上雇用している企業は、障がいを持っている方を1人以上雇用しなければいけません。
短時間労働者は、1人を0.5人とみなし、重度身体障害者と重度知的障害者は1人を2人、短時間重度身体障害者、短時間知的障害者は1人とみなします。
例えば、100人雇用している民間企業は、2.5人の障がいを持っている方を雇用しなければいけません。
法定雇用率を達成していない100人以上雇用している企業は、1人当たり月額5万円の納付金支払い義務が発生します。一方、法定雇用率以上に障がいを持っている方を雇用した企業には、報奨金が支給されます。
差別禁止・合理的配慮の義務
障がいを理由に、採用や待遇で不利になる扱いをすることが禁止されています。これを差別禁止といいます。
また、障がいがある人が、働きにくくなるような支障がある場合、これを取り除かなければならない義務があります。これを合理的配慮の義務といいます。
具体例としては、車椅子の人が働きやすいように社内をバリアフリー化することや、聴覚や言語障害がある人には、筆談でコミュニケーションを取ることなどが該当します。
障害者雇用の現状と課題
日本における障害者雇用は年々進展していますが、依然として多くの課題が残されています。障害者雇用の環境改善には、企業と行政、社会全体のさらなる取り組みが必要とされています。
日本における障害者雇用の現状
参照元:厚生労働省ホームページ「障害者雇用状況の集計結果」
雇用障がい者数は、11年間連続で過去最高を更新しており、令和4年は61万人以上の障がいを持っている方が雇用されています。
特に精神障がい者の雇用者数は、11年間で約6.5倍に増加しており、今後もこの傾向が続くと考えられます。
障害者雇用について企業が直面している課題
法定雇用率未達成企業が多い
雇用障害者数は、年々増加していますが、法定雇用率未達成企業が中小企業を中心に多く、令和6年に厚生労働省が行った調査によると、54%で前年から4.1%増加しています。
法定雇用率未達成の理由は、企業によりさまざまですが、障がいを持っている人に任せられる仕事がないと考えている企業もあるようです。
また、障がいを持っている人を雇用するための環境整備のノウハウ不足や、財政的な余裕がなく実行できない企業も少なくありません。
障がいへの知識が不十分で、障がいを持っている方への配慮が難しい
障がいといっても身体障害や知的障害、精神障害などさまざまな特性があり、それぞれの知識を十分に持っていないと、適切な職種や仕事内容、環境整備をどうすればよいのかわかりません。
障がいに対する知識が不足しているために、障害者雇用を実行できない企業が多くみられます。
企業に求められる役割
障害者雇用は、法的義務のみではなく企業が果たすべき社会的な責任の一つといえます。企業が積極的に障害者雇用を推進することで、多様性を尊重し、誰もが自分らしく働ける社会の実現に貢献できます。
企業は、すべての人が働く機会を得られる社会を構築するために、障がいを持っている方に対して公平な雇用機会を提供する責任があります。障がいの特性に応じて仕事内容を調整し、働きやすい環境を提供しなければいけません。また、
定着支援やキャリア形成のサポートを行い、障がいを持っている人が長期的に活躍できる環境を提供する役割を果たす必要があります。
障害者雇用と一般雇用との違い
障害者雇用を検討している企業にとって一般雇用との違いを理解し適切なサポート体制を整えることが重要です。ここでは、障害者雇用と一般雇用の違いを紹介します。
一般雇用で働く場合
一般雇用は、条件さえ満たせば誰でも応募でき、求人数や職種も多いのが特徴です。しかし、障がいを持っている方にとって、障がいへの理解や配慮が得られにくく、長期的に働くことが難しいケースが多くみられます。
企業にとっては、労働基準法や雇用対策法などを遵守しなければいけませんが、雇用率や合理的配慮の提供義務などはありません。必要とする人材を自由に採用できます。また、一般的に企業側の職場環境や規則、勤務時間を調整する必要もありません。
障害者雇用で働く場合
障がいを持っている方にとって障害者雇用で働くことは、障がいについて企業が理解し、働きやすい環境を整えてくれるため、配慮を受けながら働くことができます。また、企業が勤務時間や休憩時間、業務内容などを相談しやすい体制も整えてくれています。
しかし、一般雇用に比べると求人数や職種が少なく、希望通りの仕事を見つけることが難しくなるといったデメリットがあります。
企業は、法定雇用率を達成しないと納付金を支払わなければいけなくなるため、一定割合以上の障がいを持っている人を雇用する義務があります。さらに、障がいを持っている人に対して合理的配慮を提供する義務を果たさなければなりません。
採用時に障害の程度や特性に応じた仕事内容や、配属先を決める必要があります。採用後も必要に応じて仕事内容や勤務時間の調整をして、障害者雇用の担当者を設け相談窓口の設置を考えなければなりません。
障害者雇用の条件
障害者雇用には、法的な要件や企業側が満たすべき条件があります。適切に運用することで障がいを持っている方が働きやすい環境を整えられます。ここでは、障害者雇用に関する企業が果たすべき条件について説明します。
法定雇用率の達成
一定数以上の社員がいる企業は、社員数に応じて一定割合以上の障がいを持っている人を雇用する義務があります。
法定雇用率を未達成の企業は、不足1人に当たり毎月5万円(年額60万円)の給付金を支払わなければなりません。
障害者の雇用状況の報告
企業は障害者雇用の状況を、1年に1回ハローワークを通じて障害者雇用状況報告書を厚生労働省に報告する義務があります。
障害者雇用状況報告書には、企業の総労働者数、雇用している障がいを持っている人数、障がいを持っている人の雇用形態などを書く必要があります。
この報告書は、企業が法定雇用率を遵守しているかを確認するものであるため、報告しなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。
差別禁止・合理的配慮の提供
障害者雇用促進法で企業は、障がいがあることを理由に、給与や昇進、採用、待遇などで差別することを、障害者雇用促進法で禁止しています。
また、企業は合理的配慮を提供する義務があります。これは障がいを持っている人が働きやすいように職場環境を整備することです。
合理的配慮を提供しなくても罰則はありませんが、行政指導や是正命令が出される場合があります。
解雇制限
障がいを持ってる人が長期的に安定して働けるように、不当な理由で解雇することを制限されています。以下のような解雇は禁止されています。
- 障がいを持っているという理由で解雇する
- 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合、障がいを持っている人にだけ不利な条件を与える
- 障がいを持っている人を優先的に解雇する
障がいを持っている人を解雇する前に確認すべきことは以下の3点です。
- 合理的配慮の提供を行ったか
- 適切な指導や注意を行ったか
- 業務内容や配属先の検討をしたか
上記を怠った場合は、不当解雇となるので気をつけてください。
ただし、企業が合理的な配慮を十分したにもかかわらず、仕事をするのが難しい場合や重大な規則違反をした場合は、解雇が認められることがあります。
企業側の障害者雇用のメリット
企業側の障害者雇用のメリットをご紹介していきます。
労働力の確保
少子高齢化でさまざまな分野で人手不足の状態の中、障害者雇用は、貴重な労働力確保の手段になります。適切な業務に割り当てることで、企業にとって有益な戦力として働いてもらうことができます。また、長期的な雇用の安定につながり、採用コストの削減にも寄与します。
企業ブランディングの向上
障害者雇用を積極的に進めることは、社会的責任を果たしていると評価され、企業のブランド価値の向上につながります。消費者や取引先から信頼を得るだけでなく、優秀な人材の確保にも良い影響を及ぼします。
組織の活性化
多様な人材がともに働くことで、組織の柔軟性や創造性が向上します。障害者雇用を通じて、社員同士が互いに理解を深め、協力し合う雰囲気が作り出されることで、組織全体のコミュニケーションが活性化し、チームワークの強化につながります。
助成金・優遇措置の活用
障害者雇用を進める企業には、各種助成金や税制優遇措置を利用できます。
これにより、雇用環境の整備や業務支援のための費用負担を軽減することができます。これらの制度を活用することで、企業の経営負担を抑えつつ、社会貢献にもつながります。
企業側の障害者雇用のデメリット
環境整備のためのコスト
障がいを持っている人が働きやすい職場を整えるためには、バリアフリー化や業務補助機器の導入などが必要となります。
また、障がいの特性に応じた作業環境の調整や、安全対策の実施が経済的負担となることが少なくありません。このようなコスト負担は、企業にとって経済的な問題を引き起こす可能性があります。
業務調整やマネジメントの負担
障がいを持っている人が、スムーズに業務が行えるよう、業務内容の見直しや調整が必要となります。また、障がいの種類や個々の特性に応じた指導サポートが必要になるため、同僚の負担が増える可能性があります。
多くの中小企業にとって、こうした業務調整やマネジメントの負担が問題となっています。
相談窓口設置など人的コスト
障害者雇用を適切に進めるためには、専門の担当者を配置したり、社内に相談窓口を設置することが望ましいです。しかし、こうした体制を整えるには、人的コストが発生します。
特に、障がいに関する専門知識を持つスタッフの確保や育成が必要になるため、人材に余裕のない企業にとって大きな負担となる可能性があります。
障害者雇用の進め方
障害者雇用の進め方は以下の4つの段階に分けることができます。
現状把握と目標設定
最初に自社の雇用状況を確認し、法定雇用率の達成状況や障がいごとにどのような職種や業務が適しているかを分析します。
その後、社内に障がいを持ってる人に任せられる業務があるのかを確認し、どのような人材を採用しどのような職場環境に整備していくのかなどの目標を設定します。このように計画的に障害者雇用を進めていくことが大切です。
職場環境の整備
障がいを持っている人が安心して働けるよう、必要な設備の導入や就業規則の見直しなどを行います。バリアフリー化や支援機器の活用に加え、社員が障がいについての理解を深めるために研修を実施することも効果的です。
働きやすい環境を整えることで、採用後の定着率向上にもつながります。
採用活動
ハローワークや人材紹介会社、支援機関などを活用しながら採用活動を進め、ニーズに合った人材を探します。応募者の障害特性や希望を正確に把握して、適切な業務を割り当てることが大切です。
面接や選考のときには、業務内容や職場環境について丁寧に説明し、必要に応じて職場見学をしてもらい、自社で働く意思に変わりがないことを確認します。
採用活動中にしっかりコミュニケーションを取り、お互いに理解を深めることが重要です。
定着支援とフォローアップ
採用後は、定期的な面談や相談の機会を設け、働きやすい環境を確保するためのフォローを行います。
上司や同僚とコミュニケーションを取りやすい環境作りも、定着につながる重要な要素です。
必要に応じて業務の調整やフォローアップ、サポート体制の見直しを行い、長期的に安心して働ける環境を整備していきます。
障害者雇用に関する助成金・支援制度・相談先機関
障害者雇用に関係する助成金や支援制度、相談先を紹介します。
障害者雇用に関する助成金
障害者雇用を促進するために活用できる助成金制度があります。特定求職者雇用開発助成金は、雇用困難と考えられる人を雇用した場合、職場環境を整備するためにかかった費用を支援してくれる助成金のことです。
障害者雇用に関する助成金を活用することで、企業の負担を抑えながら、障がいを持っている人が働きやすい環境を整えられます。
障害者雇用に関する支援制度
円滑に障害者雇用を進めるためには、支援制度を利用することが重要です。
例えば、障害者職業センターは、障害者雇用に関する企業のニーズや雇用管理に関係する課題を分析してくれて、専門的なアドバイスや援助が受けられます。
また、トライアル雇用制度は、障がいを持っている人を一定期間試しに雇用し、業務への適性を見極めてから常用雇用に移行できます。適性が低い場合は、試用期間が過ぎたら契約解除をすればよいので、ミスマッチの少ない採用活動が行えます。
障害者雇用についての相談先機関
障害者雇用の進め方や環境整備などについて疑問があるときは、支援機関からサポートを受けられます。さまざまな支援機関があり、相談内容によって適切な支援機関は異なります。
例えばハローワークは、募集方法や面接の進め方など障害者雇用の基本的な悩みを相談するのに向いている支援機関です。地域障害者職業センターは、障害特性に合った業務や配慮がわからないなどの悩みを相談するのに向いています。
求めるサポートや相談内容に適した支援機関を選ぶことで、スムーズに障害者雇用を進められるようになります。
まとめ
障害者雇用は企業にとって、法的義務を果たすだけでなく、職場の多様性を促進し、社会的責任を全うする重要な取り組みです。
一般雇用とは違い、障がいを持っている人に配慮した職場環境の調整が求められます。企業は、法定雇用率の達成や障害者の就労支援を通じて、社会的評価や企業文化の向上につながり、さらには助成金や税制優遇を享受できます。障害者雇用を進めるには、計画的かつ継続的なサポートと柔軟な対応が必要です。
成功のカギは、障がいを持ってる人が活躍できる環境を整え、その才能を最大限に引き出すことにあります。この取り組みが企業の成長に繋がり、長期的な利益をもたらすことを期待できます。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







