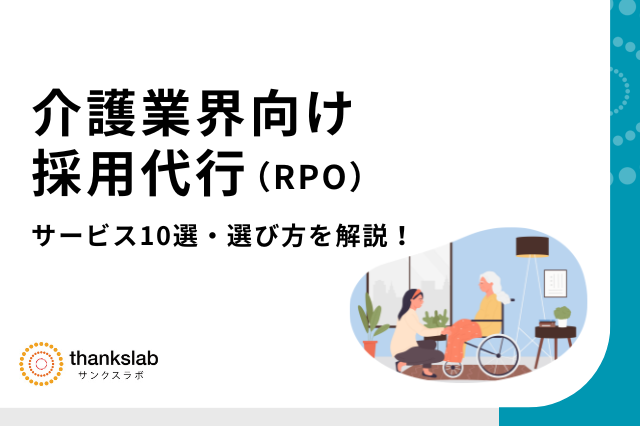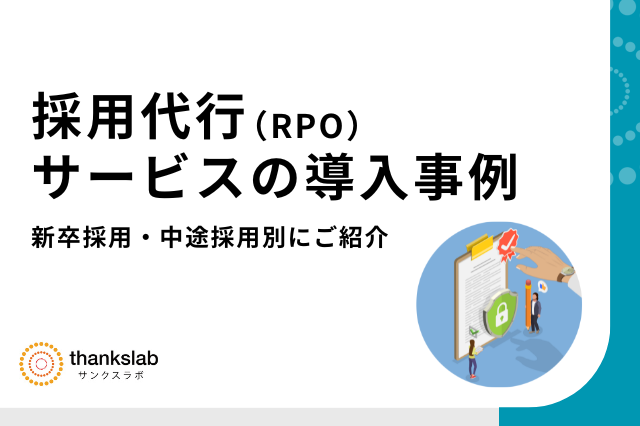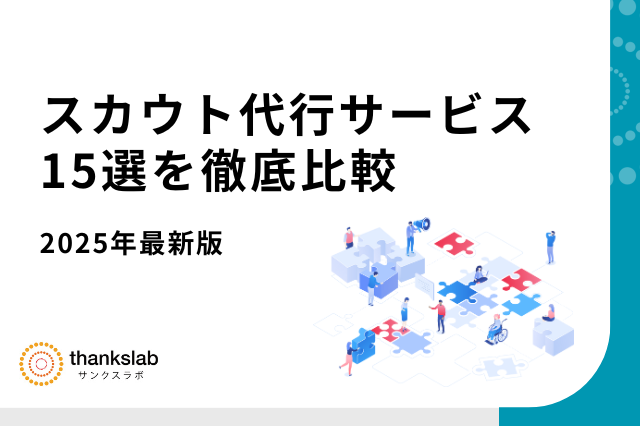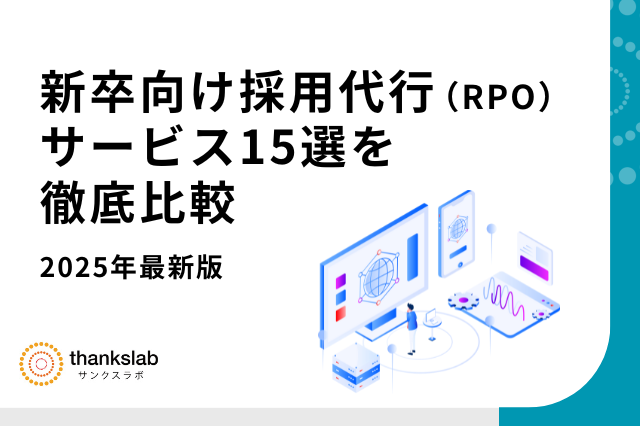15名の採用に成功!障がい者雇用×サンゴ養殖でSDGsにも貢献
- 公開日:
- 2025.03.20
- 最終更新日:
- 2025.09.30

コロナ禍という未曾有の事態に直面し、大きな打撃を受けた旅行業界。その中で、日本旅行様は旅行業で培ってきたノウハウを活かし、ソリューション事業という新たな領域へと舵を切りました。
旅行業に限らず多様なクライアントの課題解決に挑む日本旅行様は、障がい者雇用においてもサンゴ礁の養殖といった社会課題解決に取り組まれています。
今回は、総務人事部の三宅様と佐野様に、サテラボを活用した障がい者雇用の現状と今後の展望についてお話を伺いました。
企業プロフィール
会社名:株式会社日本旅行様
URL:https://nta-corporate.jp/
業種:旅行事業・ソリューション事業
従業員数:3,442名〈グループ全体〉(2024年1月1日現在)
障がい者雇用で抱えていた課題:従業員数増加による法定雇用率の遵守と採用活動
インタビューにご協力いただいた方
総務人事部マネージャー
三宅 佳広 様
総務人事部マネージャー
佐野 武弘 様
旅行業の枠を超えてソリューション企業へ

ー 本日はよろしくお願いいたします。まず、日本旅行様の現在の事業内容、そしてお二人の役割について教えていただけますか?
佐野様:当社においては、創業以来旅行業をメインとして事業をおこなってきました。しかし、ご存知の通りコロナ禍で業界全体が厳しい状況に直面し、大きな転換期を迎えました。
当社もその影響を受けながらも、ワクチンのコールセンター事業や、これまで培ってきた旅行業のノウハウを活かし、旅行業・非旅行業も含めてソリューション事業に注力を置くような事業展開を進めています。
役割としては、私は総務人事部に所属しており、教育研修、労務、システム周りなどを担当しています。三宅については主に採用やシステム周りなどを障がい者雇用導入時には担当しておりました。
法定雇用率の達成や採用の難しさが大きな課題に
ー ありがとうございます。まさに変化の時代に対応した事業展開ですね。それでは、障がい者雇用の取り組みについて、いつ頃から、どのように始められたのでしょうか?
三宅様:以前から障がい者雇用は取り組んでおりましたが、2023年12月にグループ会社が合併し、社員が大幅に増加しました。
また、2024年4月には新卒採用も120名おこなったことでさらに社員が増え、これに伴い、法定雇用率の達成がより重要な課題となりました。
同時に、法定雇用率自体も2.3%が2.5%、そして2.7%と段階的に引き上げられることが決まっていることも把握しておりましたので、障がい者雇用をより積極的に進める必要性を昨年から感じ、行動をしていました。
ー 組織改編や法改正など、様々な要因が重なったのですね。障がい者雇用を進めるにあたって、どのような課題がありましたか?
三宅様:障がい者の方向けの転職フェアに以前参加をし、履歴書を見ながらお話をする機会があったのですが、時間とコストがかかる一方で当社の仕事にマッチするような方との出会いは難しいものでした。
また、障がい者の方向けの転職サイトに掲載させていただいたこともあるのですが、Webでの募集だと顔が見えないため、その方に合った仕事を提供できるかどうか判断がしづらいといった点に非常に課題を感じていました。
管理者不要やサンゴ礁保全事業への取り組みがサンクスラボ導入の決め手に

ー 採用活動の難しさ、そしてミスマッチという課題。多くの企業が抱える悩みですね。そのような中で、サンクスラボ(サテラボ)の導入を検討されたきっかけは何だったのでしょうか?
三宅様:きっかけは、グループ会社からの紹介でした。「サンクスラボという障がい者雇用の会社がある」という話を聞き、興味を持ったのが始まりです。
サンクスラボさんの資料を拝見すると、多くの障がい者雇用支援サービスでは企業側から管理者を出す必要があると思うのですが、サンクスラボさんの場合は、管理者もサンクスラボさん側で用意いただけるとのことで、人的リソースの面でも大きなメリットを感じました。
また、サンゴ礁保全事業にも取り組んでいることを知り、旅行会社で唯一SDGs宣言をしている当社にとって、間接的にとは言え世の中に貢献できる点は非常に魅力的でした。
最初は不安だったが、手厚いフォローで安心することができた
ー サンゴ礁再生事業への共感、そして管理者不要という点が決め手となったのですね。実際にサンクスラボを利用してみて、いかがでしたか?
佐野:そうですね。今回15名もの方々を採用したので、正直なところどれくらい大変なのか最初は不安もありました。
また、基本的にオンライン上での繋がりになるため、直接顔を合わせて仕事内容を確認できないという点も不安には思っていました。しかし、実際には定例ミーティング等を通じて、障がい者の方が働く上で確認したいことなど、色々な情報を逐一ご報告やご連絡いただけるので、安心することができました。
ー 佐野様は、導入前の不安が払拭されたのですね。三宅様はいかがですか?
三宅様:私も佐野と同じく、正直なところ最初は不安がありました。
特に、採用した15名の方は一か所に集まっているわけではなく、それぞれの場所で、それぞれの業務に従事しているため、どのように働いているのかタイムリーに状況把握ができないという面では少し不安でした。
しかし、実際に始めてみると、支援員の方々が本当に一人ずつ手厚くきちんと見ていただいているのだなというのは日々のメールや定例のオンラインミーティングで読み取ることができ安心しました。
また、昨年、沖縄に出張する機会がありましたので、時間を見つけて実際にサンゴ礁を養殖している場所や那覇のオフィスに訪問させていただきました。
そこで、採用させていただいた社員の方3名とお会いして、どんな仕事をされているのかお話を伺ったり、整理整頓されている綺麗な職場や、専門の方がしっかりサンゴの養殖を指導されているのを自分の目でみることができ、安心してお任せできるなと感じましたね。
オンラインでの距離感は感じなくなった
ー テレワークという特殊な環境だと距離感の問題というのは当初は不安に感じていたところはあったのでしょうか?
佐野様:実際にそれはありました。距離感を埋めるためにはどうしたら良いのかという不安感はありましたが、オンラインが主流になっている中、距離の詰め方やコミュニケーションの取り方は1つではないと思いますし、定例ミーティングなどをしていただいているので、今では距離感は感じなくなりましたね。
旅行業のノウハウを活かして社会の課題解決へ
ー そういった不安感が今ではなくなったということで、私どもも嬉しく思います。先ほど冒頭で旅行業以外にもソリューション事業を進めているというお話がありましたが、今後の事業展望などもう少し詳しく伺えますか?
三宅様:当社は今年120周年を迎えるのですが、旅行業から始まり日本で初めての団体旅行を実施したというところが会社の起源となっております。
自社で物を持たず、ホテルや交通機関など様々な企業様と協力しながら旅行を作り上げてお客様に提供するといったことを生業としてきたのですが、コロナで旅行需要がなくなり大きな打撃を受けました。
それでも、その中で「自分たちに何ができるのか?」と考えるようになり、旅行の手配のノウハウを色々なものに汎用できないかと視座を変え、旅行に限らず世の中の様々な課題のソリューションを提供する事業を今は進めています。
例えば、地方自治体であれば人口流出や高齢化、財政難の問題に対して、今まで培ってきたノウハウや他の企業さんと手を取り合って観光誘致するような施策を一緒に考えて提案して観光客の方に来ていただいたり、あるいは若い方が出て行ったとしても戻ってこられるような仕組みや仕掛けを提案してそれを実施していただくといったことをおこなっています。
教育分野でも、単なる修学旅行ではなく、色々な企業様と連携して新しい学習コンテンツを学校に提案したりもしています。
全世界のソリューション解決というと大げさかもしれませんが、旅行業の枠を超えて、様々な社会への貢献を果たしていくことが、私たちの使命だと思っています。
障がいのある方の個性や強みを活かせる可能性を感じた
ー ありがとうございます。今回の事例で、初めて日本旅行様がこういった事業もされていると知った方も多いのではないかと思います。最後に、障がい者雇用に関しては、今後取り組みたいことはございますか?
佐野様:今回サンクスラボさんを利用させていただいて、障がいのある方の個性や強みを活かせる可能性を感じました。
例えば、サンゴの業務で働いている2人は非常に絵が上手く、毎回レポートにも絵を描いてくださり、せっかくなので当社の新入社員研修用のウェルカムボードの作成をお願いして飾ってみようということになりました。
こういったそれぞれの個性や強みを活かした色々な働き方があるんだと感じましたので、また何か得意なことに気づいたら副次的に業務を依頼するのも良いのではないかと思っています。
ー ウェルカムボードについてお話が出ましたが、弊社はBPO事業もしておりまして、デザイナーやライターといったクリエイティブに強いなど、 障がいはあっても実は幅広いバックボーンを持っている方々が多くいらっしゃいます。
サンゴの養殖をきっかけに、絵が上手だからウェルカムボードを依頼しようといった、障がい者の方の活躍の場の広げ方に気づいていただき非常に嬉しく思います。本日はお忙しい中インタビューにお答えいただき、ありがとうございました。
取材日:2025年2月5日
※本記事の内容は取材時のものであり、組織名や役職等は取材時点のものを掲載しております。