障害者手帳とは?等級や種類、取得するメリットをわかりやすく解説
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
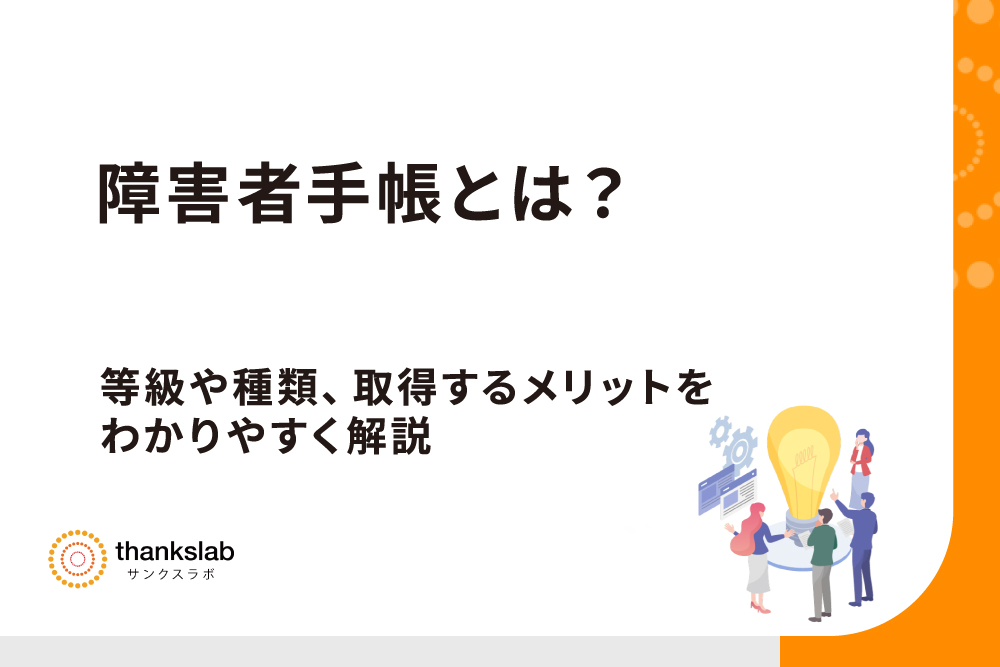
障がい者雇用の対象になるのは、障害者手帳を取得している方です。「障がい者はすべて手帳を取得しているのではないのか?」「障害者手帳にはどのような種類があるのか?」等障害者手帳に関する疑問を持っている方も多いでしょう。
本記事では、障害者手帳の種類や等級、取得する方法や条件、メリットを紹介します。障がい者雇用を検討している企業の担当者はもちろんのこと、障がいに関する理解を深めたい方も、最後まで記事を読んで参考にしてください。
目次
障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害が原因で自立が難しかったり日常生活に支援を必要だったりする方を対象に、自治体が交付する手帳です。障害者手帳には以下の3種類があります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
障がい者は障害の種類や程度によって障害者手帳を取得します。なお、身体障害者手帳と療育手帳には期限がありませんが、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。
ただし、身体障害者手帳も障害が軽くなる可能性がある場合は、再認定が行われる場合もあります。
現在、身体障害者手帳は約478万3,000人、療育手帳は約128万1,000人、精神障害者保健福祉手帳は約144万人が取得しています。
障害者手帳を取得するとさまざまなサポートが受けられる
障害者手帳を取得すると、障害者総合支援法の対象となり、以下のような補助が国や自治体から受けられます。
- 医療費の負担が軽減される
- 税金の減免や控除
- 補装具購入費が支給されたり一部が補助されたりする
- 障害者が自立するために行う住宅リフォーム資金の支援
- 電車・バス等公共交通機関の通行料の割引
- 郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料などの割引や無償化
障害者は健康な方に比べると経済的な自立が難しい傾向があります。そのため、国や自治体がいろいろな形で支援を行っているのです。
また、常時雇用している従業員が40名以上いる企業に義務付けられている「障がい者雇用」は、障害者手帳を持っている方が対象です。
障がい者雇用は、障がいに応じた配慮をしてもらいながら働くことができるのが大きな特徴です。障がいの種類や程度によっては障がい者雇用を利用して採用されたほうが、働きやすい可能性があります。
障害者手帳の種類と等級

ここでは、障害者手帳の種類や等級をもう少し詳しく紹介します。
障害者手帳にも障害の種類や程度によって受けられる補助などが異なります。障がい者雇用にも関係してくる可能性もあるので、種類や等級を一通り知っておくことが大切です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいがあって健康な方に比べて日常生活や社会参加に制限がある人が取得可能です。
身体障がいの対象となる障がいは、以下のようなものが挙げられます。
- 視覚障害(見え方の障害)
- 聴覚障害・平衡機能障害(聞こえ方の障害、平衡感覚の障害)
- 音声・言語・そしゃく機能障害(話す・食べる機能の障害)
- 肢体不自由(手足や関節など運動機能の障害)
- 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など内臓の障害)
- そけい(排泄機能の障害)
身体障がいというと、車いすを利用している方や目が見えない方など行動に制限があるイメージがありますが、内臓に障がいを持っている方も身体障がいにカテゴライズされます。
障害は1~6級の6段階で1が最も重度です。ただし、障がいによっては1~3級、もしくは1~4級までしかないものもあります。障がいが重いほど手厚い支援が受けられる自治体が多い傾向があります。
身体障がいは個人差が大きな障害です。そのため、等級も細かく分かれているのが特徴です。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所や的障害者更生相談所から知的障害があると判定された方に対して交付される手帳です。自治体によって名称が異なり「愛の手帳」といった明蝶のところもあります。
療育手帳は、重度(A)と中度・軽度(B)といった区分をするところが一般的ですが、自治体によっては「A1」「A2」といった細かく分けているところもあります。取得するには、知的障害に関する判定機関での検査や面談を受けることが必要です。
なお、療育手帳は一度取得すると原則として更新はありません。近年は子どものうちに療育手帳を取得するケースが増えましたが、年配の方の中には大人になってから取得するケースもあります。
障がい者雇用で働く知的障がい者は中度・軽度が多かったのですが、現在はAの療育手帳を取得している方も自分ができる仕事をして社会参加をする方も増えてきました。
療育手帳は子どものころから取得するケースが多く、原則として一度取得すれば障害所持できます。なお、知的障害がない自閉症をはじめとする発達障がいの場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持っている方や発達障害の方が取得できる手帳です。精神障害は統合失調症・うつ病・躁うつ病・てんかんといった病気のほか、アルコール依存症や薬物依存症といった依存症も対象です。
さらに近年はADHDやASDといった発達障がいへの理解が広まったことから、発達障害の方でも手帳を取得する方が増えました。精神障がいは1~3級まで等級があり1級が最も症状が重いと判定されます。
なお、精神障害は適切な治療と時間の経過で症状が軽減する可能性もあります。そのため、有効期限は2年です。また、再認定を受けて手帳の交付が認められないケースもあるでしょう。
障害者手帳を取得する必要性とメリット

障害者手帳を取得すると、前述したように国や自治体からさまざまなサポートが受けられます。ここでは、障害者手帳を取得する必要性やメリットをもう少し詳しく紹介します。
障害者手帳を取得すると様々なサポートが受けられる
障害者手帳を取得できれば、国や自治体が「支援が必要な人」と認められたことになります。前述したように、障がいがある方は健康な方に比べて自立が難しいケースが多いです。
また、障がいは生まれついてのものだけでなく、人生の途中で障がい者になった方も珍しくありません。特に精神障がいや身体障がいは、大人になってから病気やけがをして障がい者になった方も多いでしょう。
依然と同じように働けなくなっても、国や自治体から補助が出れば経済的な負担が軽減できます。
さらに、障がいの中には外見からではわからない種類もあります。障害者手帳を取得することで、自分に障がいがあることを素早く的確に伝えられます。
医療機関を受診する際や継続的なサポートを利用する際、障害者手帳があったほうがスムーズに手続きが進むでしょう。
障がい者雇用枠で就職ができる
障がい者雇用の枠で就職したい場合は、必ず障害者手帳が必要です。近年は障がいに対する理解も深まり、健康な方と同じ条件で就職する方も増えました。しかし、障がいの程度や種類によっては、健康な方と同じ条件で働くのが難しい方もいます。
障がい者雇用で就職した場合は時短勤務が可能であったり、障がいがある方でも働きやすいように職場の環境を整える義務が生じたりします。したがって、障がい者でも無理のないペースで働くことができるでしょう。
また、企業側も40名以上の常用雇用者がいる会社は障がい者雇用が義務づけられています。そのため、障がいを持つ方が健康な方と同じ条件で働くより就職しやすい傾向があります。
障害者手帳を取得するには?
ここでは、障害者手帳を取得する手順や条件に付いて解説します。
障害者手帳は原則として年齢に関係なく取得可能です。そのため、0歳児から高齢者までさまざまな年齢の方が取得しています。
障害者手帳は自治体に申請して受け取る
障害者手帳は、自治体が発行しています。基本的な流れは全国共通ですが、窓口や受付方法などは自治体によって異なります。したがって、まずはお住いの自治体の申請方法をチェックしましょう。
一例を挙げると、東京都の場合は発行から1年以内の診断書や意見書、写真、交付申請書が必要です。診断書を申し込む医師は法律の指定を受けたところとも指定されています。
条件を満たしていないと申請を受け付けてもらえないので注意してください。なお、申請方法や必要な書類は自治体のwebサイトに記載されているので、確認してみてください。窓口で質問も受け付けています。
自治体によっては社会福祉士をはじめとするソーシャルワーカーに相談が可能です。障害者手帳の取得方法がわからない、1人では申請が難しいといった場合は相談をしてみましょう。
医師の診察を受けて交付条件を満たしていることが必要
障害者手帳を取得するには、障害分野ごとに定められている指定医師の診断を受けて障害者手帳を申請ができるかどうか、診断を書いてもらう必要があります。
身体障害、知的障害、精神障害と、障害の種類ごとに指定医師が定められており、指定医師以外の医師に診断を受けても認められません。
また、指定医師でも「精神障がい者の指定医師が身体障がい者の診断をした」といった場合も無効です。指定医師は、自治体のwebサイトで検索できるところもあります。
かかりつけ医がある場合は、医師に相談すれば指定医を紹介してくれる場合もあるでしょう。
障害者手帳の取得は任意
障害者手帳の取得は任意です。障害があるからといっても、障害者手帳を取得していないからといって罰則が科せられるわけではありません。
かつては、人の目を気にして障害者手帳を取得しないケースもありましたが、今では取得するメリットが大きいので取得する方が増えました。
しかし、うつ病や統合失調症など症状が改善する可能性がある病気の場合は「障がい者と認められたくない」といった理由で手帳を取得しない方もいます。
また、障害があっても障害者手帳の取得が認められる基準を満たさない場合は、取得が認められないケースもあるでしょう。
例えば、知的障がいの場合は、病院で検査を受けたがIQ70未満が該当します。そのため、IQ70以上の場合は生活に困難を抱えていても障がい者としては認められないケースがあります。
障がい者雇用で採用されたい場合は、まずは病院を受診して障害者手帳を所有できるか相談してみてください。
障がい者雇用と障害者手帳について
障がい者雇用枠で働く場合は、障害者手帳を所有している方であることが条件です。「体が不自由」「発達障害がある」等の自称では認められないので注意しましょう。
また、身体障がいや精神障がいの場合は、障がいの程度が軽くなったことにより障害者手帳が再度交付されない場合があります。このようケースは障害者手帳の再交付が行われなかった時点で、障がい者雇用としては雇用し続けられません。
正社員や契約社員、パートやアルバイトとして雇用を継続するかどうか本人と話し合う必要があります。
まとめ
本記事では、障害者手帳の種類や取得する必要性などを紹介しました。障害者手帳は全部で3種類あり、等級は最大で7種類あります。障害者手帳を取得するには、指定医の診断を受ける必要があります。自己申告では申請できないので注意しましょう。
障害者手帳の取得は任意です。しかし、障がい者雇用で採用されるには、障害者手帳を取得する必要があります。障がい者雇用枠で働きたい場合は、まず手帳を取得してください。
なお、障がいの種類によっては治療や時間の経過によっては、症状が軽減して障害者手帳が必要なくなる場合もあります。この場合は、障がい者雇用では働き続けることができなくなるので、職場に報告したうえでこれからの働き方について相談してください。
記事監修者:衛藤 美穂
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。
■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得







