就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いを徹底解説!
- 公開日:
- 2025.05.21
- 最終更新日:
- 2025.05.21
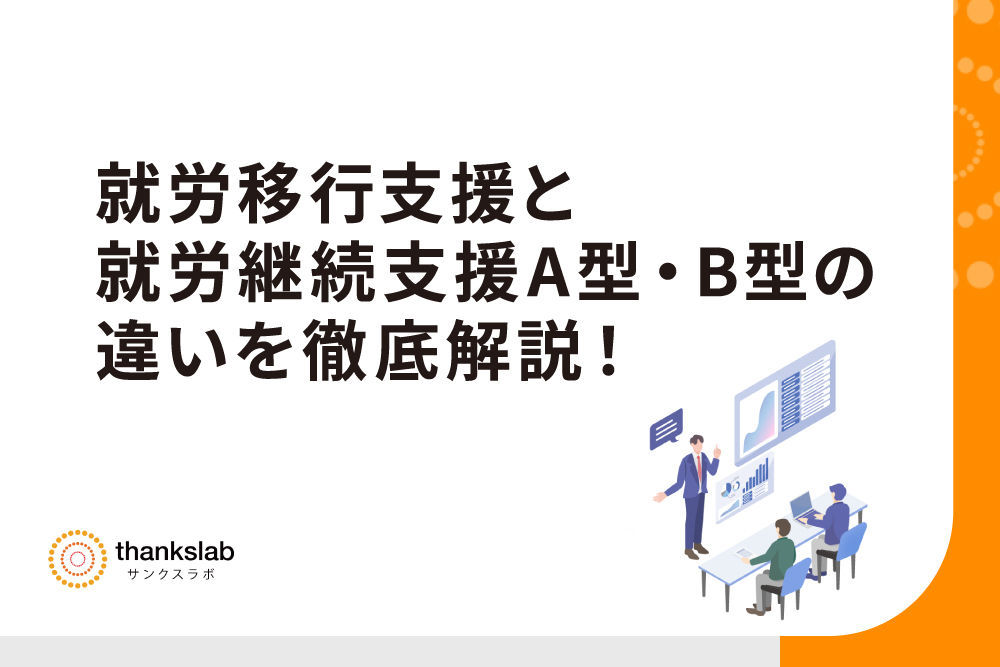
近年、障がいのある方の就労を支援する制度が充実してきています。
その中でも、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」は、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスで、働きたいと考える方にとって重要な選択肢として挙げられます。
しかし、それぞれの制度の違いが分かりにくく、どれが自分に合っているのか悩む方も多いでしょう。
本記事では、「就労移行支援」「A型」「B型」の違いを詳しく解説し、自分に合った支援を選ぶためのポイントを紹介します。
目次
就労移行支援とは?

就労移行支援の目的
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の一つで、障がいや難病を持つ方が定職に就くことを目指し、必要なサポートを受けられる制度です。
この支援では、働くために必要な知識やスキルを習得する職業訓練や、履歴書作成・面接対策などの就職活動のサポートを行い、スムーズな就職を目指します。
障害者手帳を持っていない方でも、医師の診断書などがあれば自治体の判断で利用できることがあります(例:難病や発達障がいの方など)。
「就労移行支援事業所」は、働きたい気持ちはあるものの、不安や課題を抱えている方が、適切な支援を受けながら就職を目指すための場所です。
対象者
・65歳未満の方
・一般就労を希望する障がいや難病を持つ方
・ハンディキャップがあっても就労に必要なスキルを習得したい方
支援内容
・職業訓練(ビジネスマナー、PCスキル、SST、グループワークなど)
・企業見学・企業実習(インターンシップ)
・就職活動サポート(面接対策・履歴書作成支援)
利用期間と費用
利用期間:最長2年間(状況により延長可)
費用:本人または配偶者の前年度の所得に応じて利用料が決まります。
福祉サービスの利用料は、サービスの提供に要した費用の1割負担となります。
所得によって異なる詳しい利用料を下記にまとめます。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 *1 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 *2 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
*1 3人世帯で障害基礎年金1級の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
*2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象
上記のように、細かい区分がありますが、就労移行支援事業所を利用している9割の方が無料で利用しているのが実情です。
就労移行支援のメリット
まずは就労支援のメリットから見ていきましょう。
一般就労に向けたスキル習得ができる
PCスキルやコミュニケーション能力を向上させる研修が受けられます。
また、グループワークやSSTを通じて、社会生活や対人関係を円滑にするために必要なスキルを身に着けることができます。
社会生活の訓練になる
週に5回、就労移行支援事業所で職業訓練をすることができれば、企業側に社会生活を送れるというアピールにも繋がります。
また、利用する方の自信にもなるので、双方にメリットが生まれます。
企業実習を通じて実践経験を積める
実際の職場で実習体験ができるので、雇用前に適性が確認できます。
実習経験を積んでからの雇用の場合、事前に仕事内容や職場の雰囲気を掴んでいるため、新しい環境に馴染むのが苦手な特性がある方でも順応しやすくなります。
就職活動のサポートが受けられる
面接対策や履歴書作成などの手厚い支援を受けられるので、スムーズに職に就きやすくなります。
書類作成など苦手な分野があっても、力を貸してもらえるので心強い存在となります。
就労移行支援のデメリット
続いて、就労支援のデメリットもまとめていきます。
収入が得られない
職業訓練という扱いなので、就労移行支援事業所に通っても給与は支払われません。
そのため、別途生活費の確保をする必要が出てきます。
就職できる保証はない
就労移行支援事業所に通ってスキルを身につけても、必ずしも希望の仕事に就けるとは限りません。
利用期限がある
最長2年でサポートが終了するため、その間に就職活動を進める必要が出てきます。
2年以内に就職先が決まらなかった場合、自治体に延長申請をすることができますが、延長することで就職の見込みがあると判断された場合のみ、1年間の延長が認められます。
就労継続支援A型とは?

■ 就労継続支援A型の目的
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んだうえで、一定の支援を受けながら働ける福祉サービスです。
最低賃金以上の給与が支払われるので、一般就労が難しい方でも安定した収入を得ながら働くことができます。勤務条件によっては、各種社会保険への加入も可能です。
■ 対象者
・特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
・就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった方
・一般企業などでの就労経験がある中で、現在は働いていない方
■仕事内容
仕事内容は作業所によって異なるので下記は一例です。
・手芸品の製作
・パンやお菓子の製作
・工場での加工・検品
・カフェやレストランなどでの接客・調理
・お弁当の調理・盛り付け
・倉庫などでの商品の梱包・発送などの軽作業
・Webデザイン・プログラミング・データ入力
・清掃作業
・車部品などの加工
■給与と社会保険
給与:最低賃金以上
社会保険:労働時間に応じて加入
就労継続支援A型のメリット
まずは就労支援のメリットから見ていきましょう。
安定した収入が得られる
最低賃金以上の給与が保証されているので、安定した収入が得られます。利用期間の制限もないので、長期に渡って働くことも可能です。
サポートを受けながら働ける
障がいによる困りごとがあり、一般企業での就職が難しくてもA型ならサポートを受けながら働くことが可能です。
サポート内容は困りごとに合わせて、面談などを行った上で配慮されるので、安心して働けます。
就労の機会を得やすい
A型での職務経験を積むことで、仕事のスキルやコミュニケーション能力などを培っていくことができます。
厚生労働省の調査によると、A型を利用した方の5人に1人程度が一般就労へと移行しています。
就労継続支援A型のデメリット
続いて、就労支援のデメリットもまとめていきます。
一般就労より給料が少ない
最低賃金は保証されているものの、勤務時間が短いことが多く、厚生労働省の調査によると、令和4年度の就労継続支援A型の平均賃金は月額8万3551円、時給947円となっています。
A型での給料だけで生活するのが難しいなど、一般就労と比べると月収の少なさが感じられます。
地方の場合、業務の幅が限られる
A型は働く機会の提供が目的なので、一般就労とは違い、地方の場合だと業務の幅が限られることがあります。
地方によっては農作業が多いなどの偏りがあり、希望した職種に就けないケースも出てきます。
就労継続支援B型とは?

■就労継続支援B型の目的
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず、週に1回の勤務でも可能など、比較的自由な働き方ができる福祉サービスです。
無理のない範囲で作業に取り組みながら、工賃(報酬)を受け取れます。
■対象者
・一般企業での就労が困難な人
・A型のような雇用契約を結ぶのが難しい人
■仕事内容
A型と同様に一例ですが、
・パンやお菓子の製造
・カフェでの接客
・農作業
・屋内外の清掃作業
・クリーニング
・部品加工
・手工芸
などがあります。
■工賃
B型の場合、報酬は給料ではなく工賃と呼びます。
作業をした量や出来高に応じて支払われる歩合制の事業所もあれば、日給として低額で支払われる事業所もあります。工賃は給料とは違って、雇用契約がないので最低賃金の保証はなく、労働基準法も適用されません。
地域・事業所により異なりますが、平均月額は16,000円程度です。
就労継続支援B型のメリット
まずはB型のメリットから見ていきましょう。
自分のペースで働ける
週5出勤などと決められていないので、体調に合わせて無理なく働くことができます。
ただし、その分収入には結びつかないため、工賃を得るのが目的ではなく、就労トレーニングの場として考えた方がいいでしょう。
高齢者も利用できる
就労移行支援やA型は65歳未満の利用と年齢制限がありますが、B型の場合、年齢制限がありません。
そのため、働く意欲や体調面なども考慮して、自治体が必要と認めた場合、高齢の方でも利用できるケースがあります。
就労継続支援B型のデメリット
まずはB型のデメリットから見ていきましょう。
施設利用料が発生する
B型は仕事に応じた工賃が受け取れますが、支援を受けるサービス料の支払いも発生します。
サービス利用料は、就労移行支援の区分と同様となります。
そのため、0円で利用している方も多くいらっしゃいます。
A型と比べても一般就労につながりにくい
A型と比べて自由度の高いB型は、不規則な働き方でもあるので、一般就労へは繋がりにくいという側面があります。
まとめ
当記事でご紹介したように、障がいや難病を抱えている方でも、福祉サービスを利用して就職の機会を得ることが可能です。
もう1度押さえておきたいポイントをまとめると、
・自分に合った支援を選ぶことが大切
・まずはハローワークや相談支援センターに相談を
・継続的な支援を受けながら、自分に合った働き方を見つける
ということです。
自分に合った支援を選ぶことが、働きやすさや将来の安定に繋がるので、就労移行支援、A型、B型のそれぞれの特徴を理解し、自分の希望や体調、働き方に合った支援を見つけていきましょう。
衛藤 美穂(心理カウンセラー・夫婦カウンセラー)
サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム
福岡県出身。 アメリカの大学で心理学を学び、仕事の傍ら、自己啓発やカウンセリングのスキルアップを目指し、常に勉強すること10年以上。家族関係専門。
サンクスラボ入社前は不動産、メーカー、教育関係の仕事を経験。約2,500社以上の管理職、取締役に対して提案営業、問題解決等を行う。







