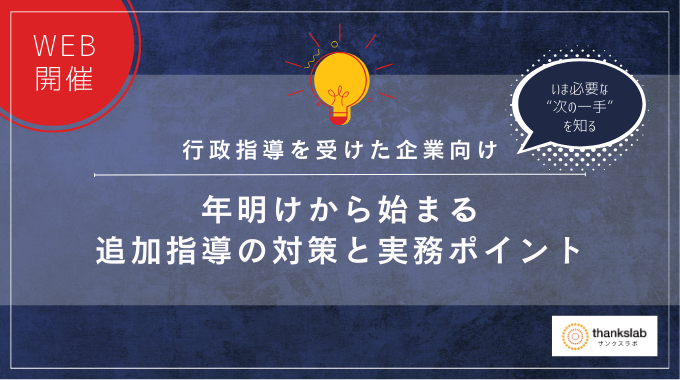【2025年最新】障がい者雇用における現状の課題・解決へと導く対策を解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.11.25
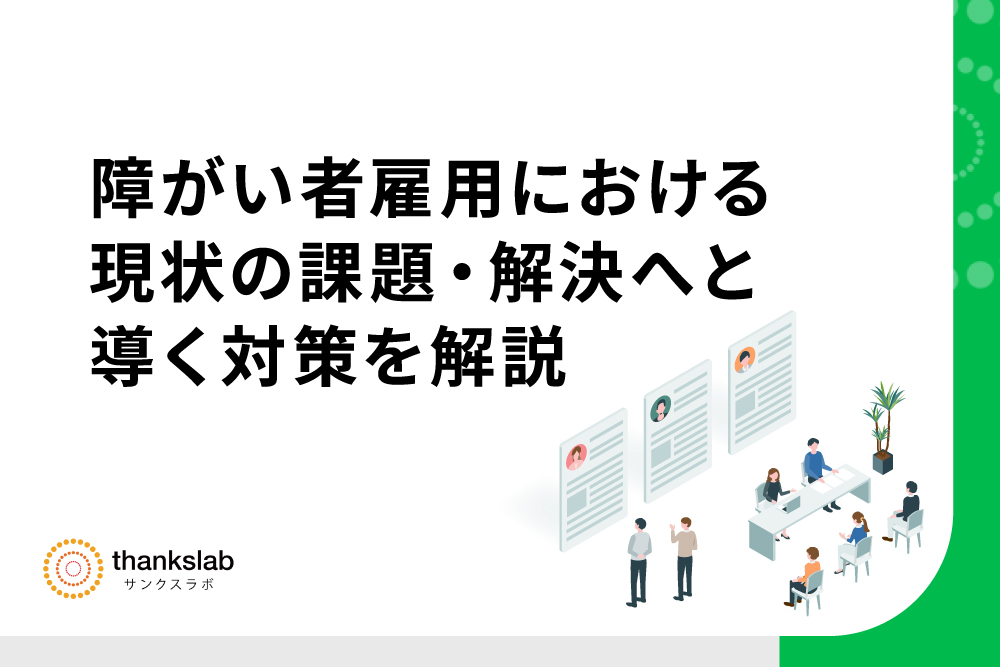
民間企業において障がいのある方の法定雇用率が上昇しており、新たな組織作りをはじめる取り組みが進んでいます。また、少子高齢化による人材不足が問題となっていることから、障がい者雇用への関心が広まっています。
ただし、障がい者雇用にはいくつかの課題が存在するため、企業は対策方法を理解しておくことが大切です。
当記事では、障がい者雇用における現状の課題から解決へと導く対策方法まで詳しく解説します。
障がい者雇用の取り組みを進めるためにも、ぜひ参考にご覧ください。
障がい者雇用の概要
障がい者雇用とは、一般枠とは別に障がいのある方を対象とした応募枠を作り採用・雇い入れを行うことです。
障害者基本法第1条における「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目的としており、障がい者雇用を通じて障がいのある方の社会参加を促進しています。
障がい者雇用は障がい者雇用促進法によって企業義務が定められているため、法定雇用率が未達成の場合は納付金が徴収されます。
法定雇用率は年々引き上げられているので、企業は規模に合わせて障がい者雇用を進める必要があるのです。
障がい者雇用の現状
障がい者雇用の現状として、以下のような点が挙げられます。
- 身体障がい者の雇用率は上昇傾向
- 障がい者雇用の拡大に伴い給与も上昇
- 企業の法定雇用率の達成度は約半数
それでは詳しく説明します。
身体障がい者の雇用率は上昇傾向
厚生労働省が公表している「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」のデータによると、2023年6月時点で障がい者雇用率は642,178人となっています。
前年差は28,220人増加しており、過去10年の雇用障がい者数は右肩上がりに増えています。
とくに身体障がい者の雇用者数が最も多く、過去最高の結果となっています。
多くの企業が障がいのある方の雇用促進に向けて取り組んでいるため、今後も障がい者の雇用率は上昇していくと考えられます。
障がい者雇用の拡大に伴い給与も上昇
障がい者雇用の拡大に伴い、企業が支払う給与も上昇傾向にあります。
厚生労働省職業安定局の公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、2023年時点の障がい者の平均給与は約17.3万円と過去最高を更新しています。週所定労働時間別平均賃金の場合)
ただし、障がい種別に見ると身体障がい者と知的障がい者・精神障がい者では、約10万円程度の差があります。
理由として、雇用形態や仕事内容の差があることが大きな原因です。
例えば身体障がい者は無期契約で正社員雇用率が高いですが、知的障がい者・精神障がい者はパートやアルバイトなどの雇用形態が多いです。
雇用形態によって勤務時間や給与体系が変わるので、平均給与に大きな差が生まれるでしょう。
企業の法定雇用率の達成度は約半数
厚生労働省が公表している「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」のデータによると、2023年の民間企業の法定雇用率達成度は50.1%となっています。
約半数の民間企業が達成しているため、積極的に障がい者雇用に力を入れていることが分かります。
法定雇用率とは、従業員が一定数以上の規模の事業主が雇用すべき身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合のことです。
例えば従業員を40名以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用する義務があります。
法定雇用率を満たしていなければペナルティがあるため、企業にとって障がい者雇用は大きな課題となっているのです。
身体障がい者の雇用現状
身体障がい者の方はほかの障がいに比べて働きやすく、正社員として雇用されるケースも多いです。
身体障がいとは身体機能の一部に障がいがあることを指しており、視覚や聴覚、内臓、肢体不自由などに障がいのある方が対象となっています。
厚生労働省職業安定局の公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、無期契約の正社員が53.2%と雇用されている割合が多いです。
1週間に30時間以上働けているケースが多く、通常の正社員と同じように稼働しています。基本的な業務は事務作業が中心となっており、50歳以降の雇用者数が多くを占めています。
1ヶ月の平均給与は235,000円(超過勤務手当を含む)であるため、問題なく自立して生活することが可能です。
平均勤続年数も12年2ヶ月と長く、継続的に働ける身体障がい者が多い傾向にあります。
精神障がい者の雇用現状
精神障がい者の雇用率は年々上昇していますが、定着率の低さが課題となっています。
精神障がい者はストレスやダメージが脳に悪影響を与えることで、精神的な以上をもたらします。
厚生労働省職業安定局の公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、無期契約の正社員が29.5%と身体障がい者と比べて雇用されている割合が少ないです。
1週間に30時間以上働く精神障がい者は56.2%と過半数を超えており、身体障がい者以上の稼働時間となっています。また、身体障がい者と同じく事務作業が多く、20代〜40代の雇用者数が多い傾向にあります。
パートやアルバイトなど雇用形態が制限されていることから、1ヶ月の平均給与は149,000円(超過勤務手当を含む)と身体障がい者に比べて少ないです。
平均勤続年数は5年3ヶ月と低いため、継続して勤務できる環境の構築が課題となっています。
知的障がい者の雇用現状
知的障がい者の雇用率も上昇傾向にありますが、身体障がい者と比べて正社員で働ける割合は少ないです。
知的障がい者は18歳頃までの発達期に脳に何らかの障がいが発生し、感情のコントロールや考え、理解、会話などに支障が出ます。社会への適応能力が低いことから、適応できるような環境作りが必要です。
厚生労働省職業安定局の公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、無期契約の正社員は17.3%と身体障がい者や精神障がい者と比べて雇用される割合は少ないです。
ただし、1週間に30時間以上働く知的障がい者は64.2%と過半数を超えており、障がい種別のなかでは最も長い稼働時間となっています。サービス業に従事している知的障がい者が多く、20代〜30代の雇用者数が多い傾向にあります。
1ヶ月の平均給与は137,000円(超過勤務手当を含む)と少なめに設定されていますが、平均勤続年数は9年1ヶ月と精神障がい者と比べて長いです。
知的障がい者は若い世代で発症しやすいことから、若者に向けた配慮をおこなう必要があるでしょう。
障がい者雇用を実施する5つのメリット
障がい者雇用を実施することで、以下のような5つのメリットがあります。
- 多様な人材採用につながる
- 障がい者雇用の助成金を受け取れる
- 多様性のある組織づくりができる
- 企業のイメージアップにつながる
- 業務効率化・見直しにつながる
それでは順番に解説します。
1.多様な人材採用につながる
障がいのある方の特定を理解した上で適切な職場配置をおこなえば、定着率を向上させて長く働いてもらえるようになります。適切な人事評価制度やマネジメントを実施することで事業の生産性は向上し、戦力として活躍することが可能です。
現在ではITツールやシステムが進化しており、障がいのある方が対応できる仕事の幅が広がっています。
また、テレワークの普及によって場所や時間を選ばず働けるようになっているため、障がいのある方に合わせた環境で生産性を向上可能です。
障がいのある方の特性を活かしたスキルや強みを業務に活用できるので、一般雇用よりも戦力になる人材の確保へとつなげられるケースもあります。
社会的な変化から、障がいのある方でも活躍できる環境は今後も広まっていくでしょう。
2.障がい者雇用の助成金を受け取れる
企業が障がい者雇用に取り組むことで、国や自治体の助成金を受け取れるようになります。
助成金の中には施設や設備のメンテナンスに活用できるものがあり、企業の一時的な経済負担を軽減できます。
障がい者雇用の取り組みには雇用管理などのコストがかかるため、助成金をうまく活用することが大切です。
障がいのある方の継続的な雇用や新規採用を進めるためにも、助成金から負担を軽減できる点は企業にとってメリットといえるでしょう。
関連:【2025年最新】障害者雇用の助成金の種類や条件、申請方法を解説
3.多様性のある組織づくりができる
世界的にダイバーシティの考え方が広がりつつあり、さまざまな属性を持った人々が共存できる社会作りを進めています。
ダイバーシティとは日本語で「多様性」という意味で、一般企業においても多様化を進めるために障がい者雇用を実施しています。
障がいのある方と共に働くことで、違いを尊重し合いながら助け合いの環境を作り出すことが大きな目的です。
自由な発想を生み出すことや組織の活性化につながり、新たなイノベーションを生み出すことが可能となります。
障がい者雇用による多様性のある組織づくりは、企業にとってメリットとなるでしょう。
4.企業のイメージアップにつながる
企業が障がい者雇用を進めることにより、活躍できる場を提供することで社会的な貢献へとつながります。
障害者雇用率制度とは、障がいのある方が社会保障費を受給する立場から労働して対価を得ながら自立できる社会づくりをするために設けられた制度です。
障がい者雇用に取り組むことで、社会的な責任を果たしている企業としてイメージアップにつながります。
アメリカでは障害者平等指数であるDEI(Disability Equality Index)の指標から、障がい者雇用の取り組みについて0点〜100点までで算出・評価しながら優良企業リストを毎年発表しています。
障がい者雇用の取り組みを続けることで、国内においても評価される企業となっていくでしょう。
5.業務効率化・見直しにつながる
障がい者雇用がきっかけとなり、日常業務の内容や工程、進め方などを見直せるようになります。
データ整理やリスト抽出、資料整理などを改善することで、障がいのある方だけでなく部署や社内全体の業務効率化につながります。
効率良く進められる環境を構築すれば、生産性を向上しながら利益率をアップできるようになるでしょう。
障がい者雇用の現状から見える3つの課題
障がい者雇用の現状から見える課題として、以下のような3点が存在します。
- 法定雇用率を満たせないことがある
- 地域によって雇用機会に差が出やすい
- 障がい者雇用後の定着率が低い
障がい者雇用を進めるためにも、ぜひチェックしてください。
1.法定雇用率を満たせないことがある
法定雇用率は年々上昇傾向にあるため、企業によっては達成できないことがあります。
前述でも説明した通り、2023年の民間企業の法定雇用率達成度は50.1%と2社に1社が雇用率を満たせていない状態となっています。
法定雇用率を満たせない場合、以下のようなリスクがあるので注意が必要です。
| 法定雇用率を満たせない場合のリスク | |
| 納付金を納める必要がある | 不足する障がい者数1人につき、月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付が必要(常用労働者が100人を超える場合) |
| ハローワークの行政指導を受けなければいけない | ・法定雇用率を達成するために「障がい者の雇入れに関する計画」作成を命じられる、実雇用率が全国平均よりも下回っている ・不足数が10人以上の場合は「特別指導」の対象になる |
| 企業名が公表される恐れがある | 特別指導を受けても改善されない場合、企業名や本社所在地、代表者名が広く公表される |
ダイバーシティやDEIなどの取り組みが進んでいる現代において、世間的に障がいのある方の法定雇用率未達成が広く公表されてしまうと企業のイメージダウンにつながってしまいます。
ただし、これまで障がい者雇用をしたことがない企業は、どのように社内環境を整えればいいのか分からないと思います。
そんなときは、全国のハローワークや地域の障がい者就業・生活支援センター、地域障がい者職業センターなどの相談がおすすめです。
就職から職場定着まで一貫した支援を実施しているため、自社だけでは対応が難しいときは一度相談してみましょう。
2.地域によって雇用機会に差が出やすい
障がい者雇用は、地域によって雇用機会に差が出やすくなっています。
東京や大阪などの都心部では全体的な人口比率が高いため、障がい者雇用の機会が多いです。
一方で地方は都心部と比べて人口比率が低いので、障がい者雇用機会も比例して低くなります。都心部にも課題はあり、障がい者雇用を進めたくても障がい者不足から雇用できないケースも存在します。
また、都心部は大手企業が集中していることから法定雇用率が高く、障がいのある方の採用競争が起きやすいです。都市部と地域の課題を把握しながら、地域のギャップを埋められる施策を考えるようにしておくと良いでしょう。
3.障がい者雇用後の定着率が低い
障がい者雇用は、障がいのある方の定着率が低いことが課題となっています。
独立行政法人 高齢・障がい・求職者雇用支援機構が公表している「障害者の就業状況等に関する調査研究」によると、就職後1年時点の平均職場定着率は63%と約4割が退職しています。
定着率が低いと採用活用を継続できず、法定雇用率を達成できない企業が増える問題が発生しやすいです。
障がいのある方の退職理由は人によって様々ですが、業務を進める上での課題や人間関係の悪化が原因になっていることが多いです。
雇用する障がいのある方の特性を理解し、適切な環境整備やコミュニケーション方法を工夫すれば徐々に定着率を高められるようになるでしょう。
障がい者雇用で企業が実施すべき5つの対策
障がい者雇用で企業が実施すべき対策方法として、以下のような5つがあります。
- 障がい者雇用について理解しておく
- 障がい者に任せる業務を明確にする
- 障がい者雇用のルールを整理しておく
- 障がい者採用後のミスマッチを防止する
- 障がい者のサポート体制を構築する
障がい者雇用をスムーズに進めるためにも、ぜひ参考にご覧ください。
1.障がい者雇用について理解しておく
障がい者雇用では、会社全体で理解を深めることが大切です。
厚生労働省が公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、企業が障がい者雇用をしない理由として「イメージが沸かない」、「障がい者向けの業務がない」という意見があります。
障がい者雇用に関する専門的な相談先に相談することで、理解を深めながら雇用促進に向けて取り組めるようになります。
ほかにも障がい者雇用について法律の調査や実施中の企業見学などをおこなうことで、障がいのある方の理解を深めることが可能です。
障がいのある方の雇用促進をおこなうためにも、理解を深める取り組みをおこなうようにしましょう。
2.障がい者に任せる業務を明確にする
障がい者雇用を促進するためには、事前に任せる業務を決めておくことも重要です。
障がいのある方の特性によって任せられる業務は異なりますが、どのような仕事であれば取り組めるのかを検討しておくと入職後のイメージが分かりやすくなります。
配属部署や業務の洗い出し、タスクの細分化などをおこなうことで、どんな業務範囲まで対応できそうか検討がつきます。
例えばマルチタスクが苦手な知的障がい者に業務を任せる場合、特定の数字を入力してもらうところまで任せるといった判断が可能です。このように障がいのある方に任せる業務の検討をつければ、求める範囲まで対応してもらえるようになるでしょう。
3.障がい者雇用のルールを整理しておく
企業が障がいのある方を雇用して終わりではなく、必要な調整ができるように社内のルールや制度を整えておくことが大切です。
社内のルールや制度を整える際には、障がいのある方と企業が相互理解をしながら調整が必要です。例えば障がいのある方の意思を尊重せず、長時間の稼働やサポートが不要であると判断してはいけません。
また、障がいのある方とほかの社員を区別し、独自のルールや制度を設けることは差別になる恐れもあります。まずは障がいのある方の理解を深める社員教育を実施しながら、社員からの理解を得ることが大切です。
また、人間関係の課題を解決するためにも、理解を深める研修やコミュニケーション方法の研修などを実施することも重要です。
そして障がいのある方から意思をチェックし、要望に合わせてルールや制度を設定しましょう。
4.障がい者採用後のミスマッチを防止する
企業が障がいのある方を採用する際には、特性と業務内容が合っているかチェックすることが大切です。
障がいのある方の特性が業務内容に合わない場合、早期退職へとつながる恐れがあります。社会全体の障がい者数は増加傾向にあるため、今後は量よりも質を重視する傾向にあります。
障がいのある方の特性や能力を客観的に判断する評価制度の実施や看護師などを含めた面談などをおこなえば、障がい者採用後のミスマッチを防止可能です。
ただ障がいのある方を雇用するのではなく、企業と障がい者の相互理解を深めながら働きやすい採用活動を実施するようにしましょう。
5.障がい者のサポート体制を構築する
障がい者採用後にはトラブルが発生することもあるため、柔軟な対応ができるサポート体制を構築することが大切です。
例えば障がいのある方が外部サービスのサポートを受けられるサテライトオフィスを用意すれば、万が一のときにも対応できます。
ほかにも在宅ワークを実施することで、障がいのある方の親族にサポートしてもらいながら安心して働いてもらえます。
社内のリソースだけで対応が難しいときには、外部のサポートをうまく活用するようにします。
障がい者雇用で受け取れる助成金
こちらでは、障がい者雇用で受け取れる助成金について紹介します。
事業や組織作りの負担を軽減するためにも、ぜひ利用を検討してください。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、日本の厚生労働が実施している助成金制度です。
非正規雇用の労働者(契約社員、パート、派遣社員など)の適正化・処遇改善を促進するためのものです。キャリアアップ助成金にはいくつかのコースがあり、各コースによって要件が異なります。
助成金を受け取るためには、事前にキャリアアップ計画を作成して労働局に提出する必要があります。申請期限や要件は年度ごとに変更される可能性があるため、最新の情報を厚生労働やハローワークのサイトでチェックしておきましょう。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障がいのある方、母子家庭の母など就職が特に困難な求職者を雇用する事業主に対して、一定期間の助成金を支給する制度です。
厚生労働省が管轄し、ハローワークなどを通じて申請・支給がおこなわれます。雇用する対象者の条件や雇用形態(常用雇用、短時間労働者など)によって支給額や支給期間が異なります。
例えば高齢者や障がいのある方をフルタイムで雇用した場合、1年〜3年の間に一定額が助成されます。
事業主の条件や雇用形態によって助成金額が変わるため、詳細についてハローワークで相談することが大切です。最新の支給額や詳細な要件については、厚生労働省やハローワークの公式サイトをチェックしましょう。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、就職が困難な求職者を一定期間試用的に雇用し、その後の常用雇用につなげることを目的とした助成金です。
事業主が対象者をトライアル雇用(原則3か月)した場合、助成金が支給されます。厚生労働省が管轄し、ハローワークなどを通じて申請可能です。
対象者1人あたり最大4万円/月(障がい者などは最大8万円/月)となっており、原則3か月間支給されます。トライアル雇用開始前にハローワーク等を通じた紹介が必要なので、紹介なしに雇用すると対象外となります。
最新の情報や詳細な条件については、厚生労働省やハローワークの公式サイトをチェックしましょう。
まとめ
今回は、障がい者雇用における現状の課題から解決へと導く対策方法まで詳しく解説しました。障がい者雇用は年々上昇傾向にあり、多くの企業が積極的に取り組みをはじめています。
ただし、法定雇用率を満たせないことがあり、地域によって雇用機会に差が出やすく障がい者雇用後の定着率が低い点は課題となっています。
ぜひ当記事で紹介した対策方法を参考にしながら、障がいのある方の雇用を促進させていきましょう。
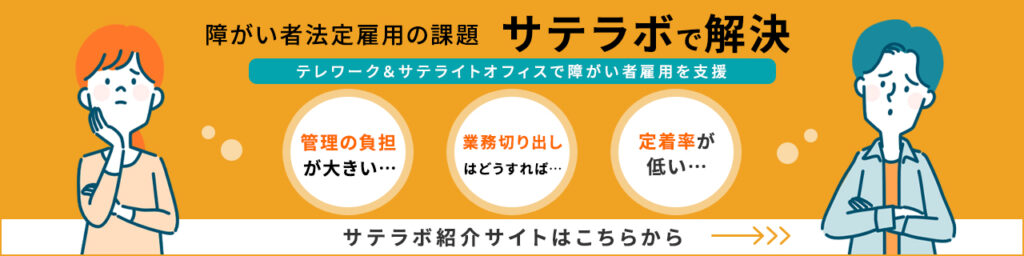
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。