チャレンジ雇用とは?メリットについても解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.07.25

「チャレンジ雇用ってどんな制度?」と気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本記事では「障害者雇用におけるチャレンジ雇用とは何か」「チャレンジ雇用のメリット」について解説していきます。
また、これから障害者雇用について知識を深めたい方のために入門向けの資料もご用意しています。基本的な障害者雇用の知識や採用のポイントについて知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
チャレンジ雇用とは
現在は企業側には障がい者の法定雇用率が設定されており、また障がいを抱える人のなかにも企業で働きたいと考える人が多くいます。
しかし企業側から見れば「就労経験のない人を雇うのは不安がある」となり、障がい者側から見ても「利益を目的とする企業で、いきなり働くのは怖い」となるため、なかなかマッチングが難しいという問題点もあります。
そこで、「まずは、公的性質を持つ官公庁や自治体が、障がい者を雇い入れて就労経験を積ませ、その経験を元に一般企業で働けるようにしていこう」とする考えが生まれました。そしてこの考えの元で設定されたのが、「チャレンジ雇用」です。
チャレンジ雇用の対象となるのは、知的・精神・身体のいずれかに障がいを抱える人です。ケースによって異なりますが、基本的には雇用期間は1年以内(3年程度にわたることもある)で、非常勤の形態で働くことになります。
チャレンジ雇用と障害者トライアル雇用との違い
チャレンジ雇用は、あくまで「官公庁」「自治体」などの公共性のある機関での雇い入れまたその制度を差す言葉です。
ただ、一般企業でも似たような制度があります。
それが「障害者トライアル雇用」です。
障害者トライアル雇用では、数か月間の間(3か月~12か月程度、試用として障がい者を雇い入れ、自社の仕事との適正を見る制度のことをいいます。
この制度の場合はチャレンジ雇用とは異なり、実施前に「雇い続けること」が前提となるものであり、障害者トライアル雇用で問題がないと判断されればそのまま働き続けることになります。
| 働く場所 | 期間 | 継続雇用 | 目的 | |
| チャレンジ雇用 | 官公庁や自治体 | 1年~3年程度 | なし | 「一般企業への就職を目的とし」就労経験を積ませる |
| 障害者トライアル雇用 | 一般企業 | 3か月~12か月程度 | あり | 自社との適性を見て、継続で働き続けられるかどうかを判断する |
関連:障害者トライアル雇用とは?メリット・デメリットや対象者・期間など詳しく解説
チャレンジ雇用のメリット
チャレンジ雇用は自治体などの公的機関が敷いているものであり、障がいを抱える人にとっては「社会で働く経験を得られる」「比較的配慮された機関のなかで、『初めての仕事』を開始できる」というメリットがあります。
また、チャレンジ雇用を経た障がい者を雇い入れることは、企業側にとっても以下のようなメリットがあります。
- 就労経験のある人を雇い入れられる
- 安定的な雇用に耐えうる人材が多い
- 社会貢献や企業イメージの上昇に繋がる
一つずつ解説していきます。
就労経験のある人を雇い入れられる
チャレンジ雇用で働いたことのある人は、社会人としての経験があるため、基本的な業務指示を聞けることが多いといえます。
障がいを抱えている人はそうではない人に比べて就労が難しく、また雇い入れる側も「指示が通るだろうか」「基本的な理解力や社会的常識がどこまであるか」を計りにくいというリスクがあります。しかし一度就労経験がある人の場合は、その能力が計りやすく、実際の業務でもトラブルが起きる可能性が低くなります。
また、このチャレンジ雇用を経験した人は就労に対して意欲的であり、「自らの力で仕事をしていきたい」として積極的に業務に取り組むと考えられます。
さらに、民間企業の場合の法定雇用率は2025年現在2.5パーセント(※原則。除外率が設定されている業種などもある)と決められていて、40人以上の従業員を抱える企業では障がい者を1人以上雇わなければなりません。
このような決まりがあるなかで、チャレンジ雇用経験者の「就労経験があって」「能力が計りやすく」「勤労意欲がある」障がい者を雇用できるというメリットは非常に大きいといえます。
安定的な雇用に耐えうる人材が多い
チャレンジ雇用による就労条件は各機関によって多少異なりますが、”毎週特定の曜日、週4日勤務/1日7時間45分(休憩時間は、45分又は1時間)ー引用:東京都東京教育委員会「東京都教育委員会版チャレンジ雇用
などのように、一般的な就労条件(週5勤務/1日8時間)に近いかたちで募集しているところが多いのが特徴です。東京都では、チャレンジ雇用の教育事務補助員の募集条件として、「上記の日数・時間で働けると見込めること」を挙げていて、「1日に3時間ほどしか働けない」などのような人はそもそも募集していません。
このような条件で働いてきたチャレンジ雇用経験者の障がい者は、一般企業で雇用した場合でも、同じように、安定的な働き方ができると期待される人が多いといえます。そのため、企業側としても「戦力」としてカウントしやすく、安定した雇用を行えます。
「雇ってはみたけれど、体調の波が大きく、欠席が多い。そのため、〆切のある仕事などを任せるのは難しい」「シフト制の仕事であるため、基本的には決まった勤務日に来てもらい、勤務時間内は働いてもらわなければならないのに、早退が多い」などのような雇用後の問題が起こりにくいのも、チャレンジ雇用経験者を雇うことのメリットだといえます。
社会貢献や企業イメージの上昇に繋がる
現在社会は顧客側・利用者側と企業側の距離が非常に近く、良いイメージも悪いイメージもすぐに顧客側・利用者側に伝わります。
そのなかで、「(チャレンジ雇用を経験している)障がい者を積極的に雇用している企業です」「多様な働き方ができる企業です」とアピールできることは、非常に大きなアドバンテージとなります。
特にBtoCの企業・業種の場合はこの傾向が顕著であり、企業としての社会貢献が売り上げの向上に繋がるケースも見られます。
そして、「社会貢献や企業イメージ上昇を目指しながらも、より自社に合った人材・社会人経験がある人を雇い入れたい」と考える企業にとって、チャレンジ雇用で働いたことのある人は非常に頼りになる人材になるといえます。
まとめ
これまでチャレンジ雇用について解説をしてきました。
今回の内容をまとめると以下の通りです。
・チャレンジ雇用とは、一般企業での就労を目指す障がい者を、自治体などが雇い入れて就労経験を積ませる制度である
・チャレンジ雇用は有期雇用であり、1年~3年ほどを限度とする
・チャレンジ雇用と似た制度として「障害者トライアル雇用」があるが、これは「一般企業が」「(適性やニーズが合えば)自社で雇用し続けることを前提として」「3か月~12か月の間、障がいを持つ人を雇う制度」である
・チャレンジ雇用を経験している人は基本的な指示が通りやすく就労意欲が高く、安定した働き方が見込める
・チャレンジ雇用で就労経験を積んだ人を雇用することは、自社にとって有益な戦力を獲得できることはもちろん、「働きやすさを考える企業」としてのイメージアップにも繋がる
チャレンジ雇用は、障がいを抱えた人はもちろん、障がいを抱えた人を雇用したいと考える企業にとってもメリットの多い制度だといえるでしょう。
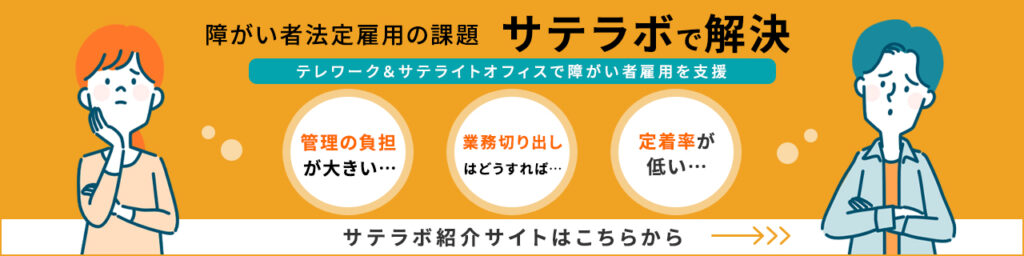
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。








