IT業界における障がい者雇用の現状とは?採用を成功させるポイントも解説
- 公開日:
- 2025.04.22
- 最終更新日:
- 2025.07.25
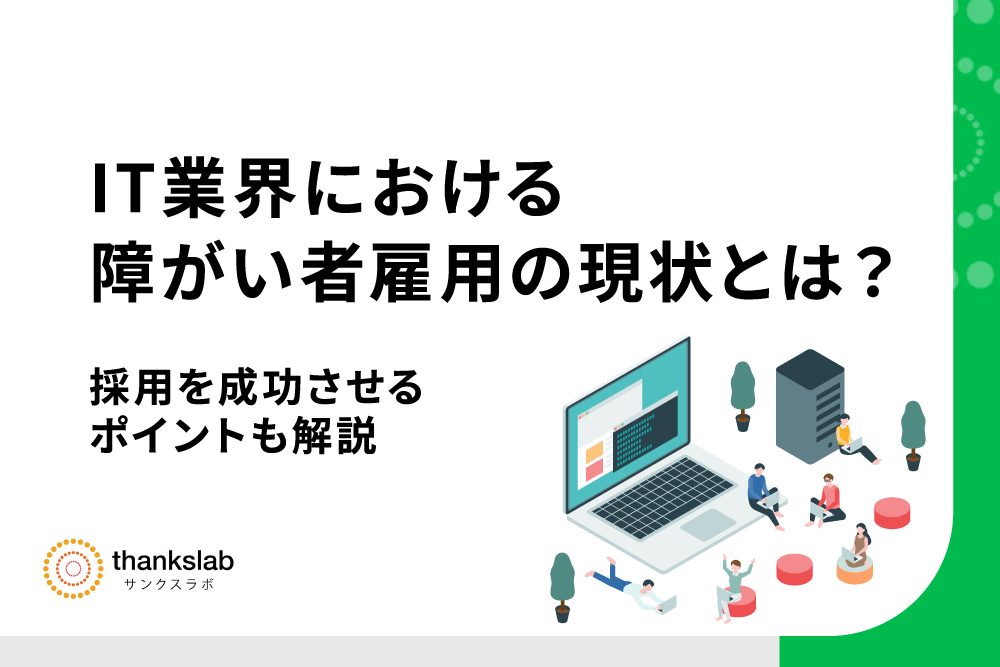
障害者雇用促進法により、常時雇用している従業員が40人以上の会社(事業主)は1人以上の障がい者を雇用しなければなりません。成長著しい企業の場合、「創業から2~3年で常時雇用している従業員が40人を超えてしまった」というところもあるでしょう。
特に、IT業界は成長著しい企業が多いため、障がい者の雇用に関して悩みを抱えているところも珍しくありません。本記事では、IT業界における障害者雇用の現状やIT業界が障がい者の雇用に関して抱えている問題、障がい者の雇用を成功させるポイントなどを紹介します。
障がい者雇用の義務が生じた会社や、障がい者雇用を検討している会社は、ぜひ参考にしてください。
IT業界における障がい者雇用の現状
厚生労働省が発表した「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、IT業界を含む「情報通信業」の雇用達成率は約27%にとどまっています。
最も達成率が高い「医療・福祉」は58.3%、「運輸業・郵便業」や「製造業」も50%以上を達成しています。また、「生活関連サービス・娯楽業」をはじめとして雇用達成率40%台を維持している職種も珍しくありません。
達成率が30%未満なのが、情報通信業のみであることからIT業界における障害者雇用の状態は低いといえます。
IT業界における障がい者雇用達成率が低い理由
ここでは、IT業界における障がい者雇用の現状を踏まえ、IT業界における障がい者雇用達成率が低い理由を3つ紹介します。
雇用達成率が低い理由が分かれば、対策も立てられます。障がい者を雇用したがすぐに離職してしまい、定着率が悪く悩んでいる会社も参考になるでしょう。
勤務形態が障害者雇用に適していない
IT業界における障がい者雇用達成率が低い理由として「勤務形態が障害者雇用に適していない」ことが挙げられます。
IT業界の働き方には、「客先常駐」があります。これは、システム開発などの仕事がある間だけ社員を客先に常駐させ、業務を請け負う働き方です。業務が終了すればまた新しい客先に出向きます。
この働き方は、「顧客に寄り添った業務を行える」「新規案件を獲得しやすい」といったメリットがある一方、人間関係や勤務地が流動的になりがちで、イレギュラーな仕事が多く臨機応変な対応が求められます。
障がい者の中には、環境や人間関係の変化が苦手な方もたくさんいます。また、客先常駐をした経験がある障がい者がいたとしても、健常者と同じペースで環境の変化に対応できないケースもあるでしょう。
会社によっては「客先常駐」が主な働き方のところもあります。障がい者を雇用して法定雇用率を上げたくても新しい仕事を創出する余裕がない、と悩んでいる会社もあるでしょう。
高いコミュニケーション能力が必要なため
IT業界は、高いコミュニケーション能力が必要とされる職種が多いです。特にチームで仕事を行う仕事や顧客の要望を聞いてシステムに反映させる仕事は、スケジュール設定・チーム内での仕事調整・情報の共有・仕事の進捗報告等を目的としたコミュニケーションが求められます。
障がいによっては、他者とのコミュニケーションが極端に苦手だったり、意思疎通が難しかったりする方もいます。
また、耳が不自由だったり発音が不明瞭だったりする場合は、コミュニケーション能力が高くても意思疎通が難しいケースもあるでしょう。
高い能力を持っていても、コミュニケーションがうまくいかないと仕事がスムーズに進まず、結果的に仕事を続けられない場合もあります。
企業が採用に消極的
IT業界は、業務に関わる新しい技術を常に学習し続ける必要があります。どの職種でも新しい技術や知識の取得は必要ですが、IT業界は短期間で新しい技術が登場し、最新技術もあっという間に古くなってしまいがちです。そのため、IT業界で働いている方々は日々勉強が欠かせません。
そのような中で、障がい者がストレスなく長期間働ける環境を整えるのは大変です。障がい者をサポートするために、障がいに関して学んだり教育係を任命したりする手間を考えたら、一定の費用を払って障がい者の雇用を避けたい会社もあるでしょう。
企業が採用に消極的なままでは、雇用達成率も低いままです。企業が雇用に消極的なままだと障がい者が働く環境が整わず、ますます障がい者雇用が難しくなる悪循環が生まれる可能性もあります。
IT企業で障がい者雇用を成功させるポイント
近年、労働人口の減少によって人材不足に悩んでいる企業は珍しくありません。その一方で、障がいの特性によってはIT業務と相性が良く、高いスキルを発揮できる方もいます。
ここでは、IT企業が障がい者の雇用を成功させるためのポイントを3つ紹介します。
ハローワークや民間の業者と協力して技術者を探す
ハローワークは職業あっせんだけでなく、スキルアップを目的とした職業訓練も行っています。ハローワークが主催しているものもあれば、民間の業者と協力して資格取得を目指す訓練も豊富です。
ITに関連する職業訓練も設けられており、発達障害者×IT人材育成への取り組みも行われています。発達障害の特性を活かし、能力の高いプログラマーやエンジニアになる方も多く、そのような技術者を雇用すれば、即戦力として役立つことでしょう。
障がい者を雇用する際は一般的な求人を出すだけでなく、職業訓練を終えてスキルアップした障がい者を対象にすると、優秀な人材を確保できます。
トライアル雇用を利用してみる
トライアル雇用とは、短期間の試用期間を設定して障がい者を雇用し、企業側と求職者側が相互に適性を判断するシステムです。一般的な雇用でも「試用期間」が定められていますが、トライアル雇用のほうがお互いに適性がないと分かったら、スムーズに雇用を終了させることができます。
また、障がい者を対象としたトライアル雇用には条件を満たせば助成金が利用できるケースもあります。トライアル雇用を利用すれば、求職者と受け入れる企業側のミスマッチも防げるのもメリットです。
採用の条件を見直す
IT関係の会社でも、総務や経理、営業事務といったバックオフィス業務もあります。やるべきことが決まっており、コミュニケーションをあまりとらなくてもできる仕事ならば、障がい者でもストレスなく働けるでしょう。
また、雇用達成率には影響ありませんが、在宅で働いている障がい者と雇用契約を結ぶ方法もあります。障がい者を雇用することで、従業員が障がい者に関する理解を深めるきっかけになることもあるでしょう。
会社全体で障害者が働きやすい環境をつくる
障がい者雇用は、これからも推進されつづけると予想されます。実際、2025年にも障がい者雇用率の引き上げが決まっています。「当社は職務の関係で障がい者の雇用は難しい」としても、やがて障がい者の雇用が義務付けられる可能性は十分にあるでしょう。
障がい者がストレスなく働ける職場づくりは一朝一夕では行えません。時間をかけてでも少しずつ障がいへの理解を深め、働きやすい環境をつくることが大切です。
まとめ
IT関係の仕事の中には、特定の障がいを持つ方が活躍できる仕事もあります。その一方で、仕事のスキル以外に必要とされることも多く、障がい者雇用率が低いままなのも現実です。
障がい者雇用は会社の環境を整え、従業員の理解を深めることも必要です。一朝一夕でできることではないので、時間をかけて取り組んでいきましょう。
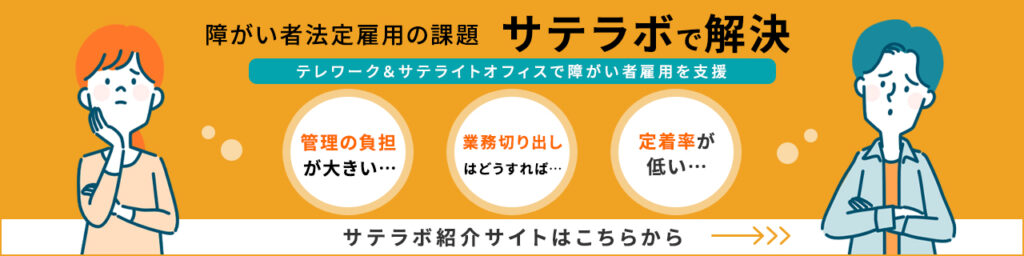
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。








