合理的配慮とは?職場での具体例や企業の義務化について簡単に解説
- 公開日:
- 2025.03.07
- 最終更新日:
- 2025.05.27
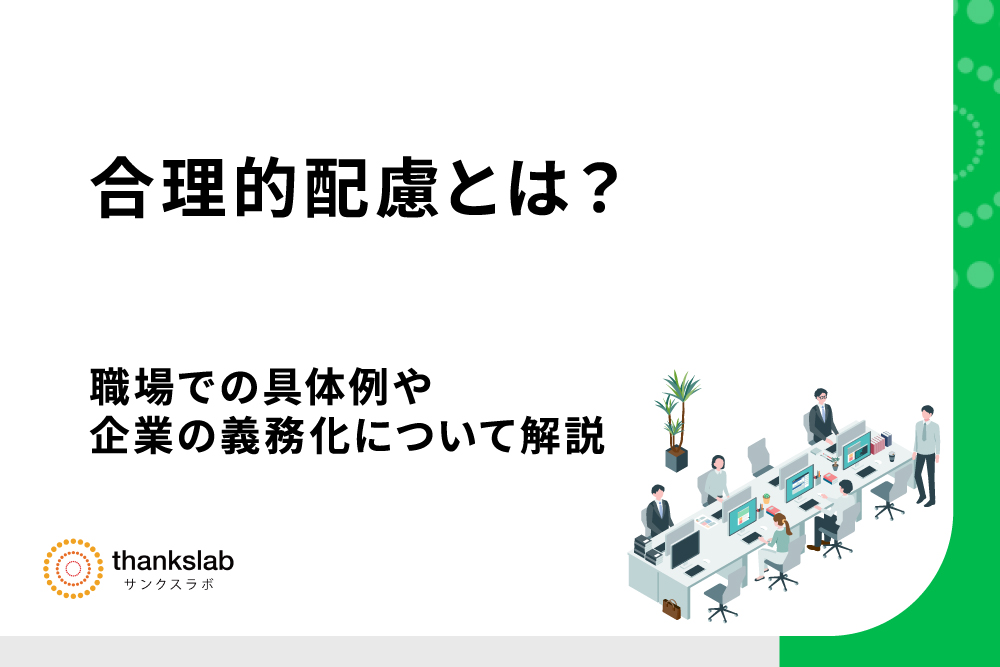
「合理的配慮とは何か」「具体的にどのような配慮をすればいいのか」など、悩んでいる企業の担当者も多いのではないでしょうか?
今回は、障がい者雇用における合理的配慮の概要や具体的な事例を解説します。
障がい者雇用をはじめて実施する企業はもちろんのこと、障がい者雇用を実施しているが、配慮の方法に悩んでいる担当者も参考にしてください。
また、合理的配慮を実施する手順や他社の事例をまとめた資料もご用意しています。読むだけで合理的配慮について理解することができるため、よかったらご参考ください。
■合理的配慮を自社で進めたい方に参考になる資料です。
>「合理的配慮提供の義務化」進め方ガイド 無料ダウンロードはこちらから
目次
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がいのある方が社会生活を送る上で直面する障壁(バリア)を取り除くために、個々の状況に応じて行われる調整や変更のことです。
この考え方の根底には、「障がいの有無に関わらず、全ての人が平等に人権と基本的な自由を享受できるべき」という理念があります。
重要なのは、全ての人に画一的な配慮を行うのではなく、それぞれの障がいの特性や置かれている環境を理解し、一人ひとりに合わせた対応を行うことです。
例えば、聴覚障がいのある方には筆談や手話通訳を、肢体不自由のある方にはスロープやエレベーターの設置といった配慮が考えられます。このように、個別のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。
事業者の合理的配慮提供の義務化はいつから?
障害者差別解消法により、令和6年(2024年)4月1日から事業者(企業)による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮の義務化は、単に障がい者の方を雇用するだけでなく、各個人の状況に応じた柔軟な対応を企業に求めるものです。これにより、障がい者がその能力を最大限に発揮し、活躍できる社会の実現を目指します。
企業は、採用から配置、昇進に至るまで、あらゆる段階で合理的配慮を提供する必要があります。
合理的配慮が必要な対象者
合理的配慮の対象となるのは、障害者手帳の有無にかかわらず、心身の機能に障がいがあり、日常生活や社会生活で相当な制限を受けている全ての方です。具体的には、以下のような方が該当します。
| 対象となる障がい | 具体例 |
|---|---|
| 身体障がい | 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がいなど |
| 知的障がい | 知的発達の遅れにより、日常生活や社会生活に支援が必要な方 |
| 精神障がい | 統合失調症、うつ病 |
| 発達障がい | 発達障がい(自閉スペクトラム症、ADHDなど)など |
| その他の心身の機能の障がい | 難病により、日常生活や社会生活に支障がある方など |
これらの障がいにより、長期間にわたって職業生活に制限を受けている、または職業生活を営むことが著しく困難な方も対象となります。
障害者手帳は、福祉サービスを受けるために必要な場合がありますが、合理的配慮の対象となるかどうかを判断する基準ではありません。手帳を持っていなくても、上記の条件に該当すれば合理的配慮の対象となります。
事業者に課せられる合理的配慮の義務
障害者差別解消法により、事業者は障がいのある人に対して「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。
不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは禁止されています。
これは、国・都道府県・市町村などの行政機関だけでなく、会社やお店などの民間事業者も対象です。
合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための対応を求められた場合、事業者は負担が重すぎない範囲で対応する義務があります。
以前は努力義務でしたが、2024年4月の法改正により、民間事業者も義務化されました。
ただし、合理的配慮の提供は、事業主にとって過重な負担にならない範囲で行うものとされています。過重な負担かどうかは、個別の状況に応じて総合的に判断されます。
合理的配慮に違反したら罰則はある?
企業が合理的な配慮を行わなかったからといって、直接的な罰則はありません。企業にはさまざまな種類や規模があるため、一律な配慮を求めるのは無理があるためです。
しかし、合理的な配慮が必要なのにできることを怠った場合は、行政から勧告や指導が入ることはあります。
勧告や指導に従わない、求められた報告を行わない、実際には行っていない配慮をやったことにして報告するなどした場合は、20万円以下の過料支払いが発生するので、注意してください。職場における合理的配慮の具体例
【障がい別】職場における合理的配慮の具体例
職場における合理的配慮の例としては障がいの種類によって様々なものがあります。
- 身体障がい
- 精神障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
大きく分けてこれら4つの障がいの種類によって提供すべき合理的配慮も変わってきます。
それぞれどういった合理的配慮があるのか事例を紹介していきます。いくつか例を挙げていきますが、障がいの種類だけでなく、各々によって配慮すべき点は異なるという点は注意が必要です。
身体障がい
職場における身体障がいへの合理的配慮は、障がいの種類や程度によって多岐にわたります。視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がいなど、それぞれの特性に合わせた配慮が必要です。
視覚障がい
視覚障がいのある方が職場で働く際には、様々な配慮が必要となります。例えば、コミュニケーションにおいては、相手を驚かせないように正面から声をかけたり、「こちら」「あちら」といった指示語ではなく具体的な距離や方向で伝えたりすることが大切です。
また、業務に必要な情報伝達においては、以下のような配慮が考えられます。
| 配慮の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 資料の提供 | 拡大文字や点字での資料作成、資料内容の読み上げ、テキストデータでの提供 |
| 事務作業のサポート | 書類記入やタッチパネル操作の代行(本人の意思確認のもと) |
| 移動のサポート | 職場内の移動や避難経路の確認、必要に応じた誘導 |
| 機器の利用 | 拡大読書器や音声読み上げソフトなどの利用しやすい環境整備、操作方法の説明・サポート |
聴覚障がい
聴覚障がいは音が聞こえにくい、または全く聞こえない状態を指します。障害の程度や種類は人によって異なり、コミュニケーションや情報収集に困難を伴うことがあります。
職場における聴覚障害のある方への合理的配慮には、以下のようなものがあります。
| 配慮の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| コミュニケーション支援 | ・筆談、メール、チャットなど、視覚的な情報伝達手段の活用 ・手話通訳者の配置 ・会議内容の要約筆記 |
| 情報保障 | ・音声情報の文字化(字幕、資料配布など) ・緊急時の連絡方法の確立(光や振動など) |
| 職場環境の調整 | ・騒音の少ない静かな作業場所の提供 ・話者の口元が見やすい座席配置 |
肢体不自由
肢体不自由とは、病気やけがなどにより手足や体幹の機能が永続的に低下している状態を指します。
肢体不自由のある方が職場で働く際には、さまざまな配慮が必要となります。
例えば、以下のような配慮が考えられます。
| 配慮の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 設備・環境面の配慮 | ・車いす利用者のために、スロープやエレベーターを設置する ・通路の幅を確保し、段差を解消する ・机や作業台の高さを調整できるようにする ・ドアの自動化や手すりの設置を行う |
| 業務内容・方法の配慮 | ・重い物を持つ作業や長時間の立ち仕事を避ける ・パソコン操作がしやすいように、マウスやキーボードの種類を工夫する ・書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する |
| コミュニケーションの配慮 | ・本人の意思を十分に確認しながら、業務を進める ・休憩時間や体調に配慮する |
その他、体温調節が難しい方のために室温に配慮したり、列に並ぶことが困難な場合に順番を待つ場所を別途用意したりすることも有効です。
内部障がい
内部障がいは、外見からは分かりにくい身体の内部にある障がいの総称です。身体障害者福祉法では、以下の7つの障害が内部障がいとして定められています。
| 障害の種類 | 主な症状・特性 | 職場での配慮例 |
|---|---|---|
| 心臓機能障害 | 身体活動による倦怠感、呼吸困難、むくみ、胸の圧迫感など。ペースメーカー装着者は電磁波の影響を受ける可能性あり。 | 作業負荷や残業時間の調整、電磁波を発する機器への配慮など。 |
| 呼吸器機能障害 | 刺激ガス、冷気、乾燥した環境で症状が悪化しやすい。風邪や肺炎にかかりやすい。 | 空調の風向き調整、喫煙場所への配慮など。 |
| 腎臓機能障害 | 疲れやすさ。進行すると人工透析が必要となり、定期的な通院が求められる。 | 定期的な通院への配慮(勤務時間・形態の調整)、体調に応じた休憩など。 |
| 膀胱・直腸機能障害 | 排尿・排便困難、頻尿、失禁など。 | トイレ休憩の確保、多目的トイレの設置など。 |
| 小腸機能障害 | 消化吸収不良による栄養維持の困難。重度の場合、経管栄養が必要となることも。 | 食事休憩時間の確保、体調に応じた休憩など。 |
| 肝臓機能障害 | 肝臓の機能低下により、疲れやすさ、食欲不振、黄疸などの症状が現れることがあります。進行すると肝硬変や肝不全に至ることもあります。 | 業務量の調整、定期的な休憩の確保、アルコールを伴う会合への配慮など。 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 免疫機能低下による易感染性、発熱、下痢、体重減少、倦怠感など。 | 定期的な通院への配慮、感染症予防のための環境整備、体調不良時の休憩など。 |
これらの障がいは、疲れやすさや特定の環境(例:電磁波、たばこの煙)での体調不良など、外見からは分かりにくい困難さを伴うことがあります。そのため、職場で働く際には、周囲の理解と配慮が不可欠です。
精神障がい
近年、精神障がいのある方の雇用数は増加傾向にありますが、その一方で、企業側が合理的配慮を「わがまま」と捉えてしまうなど、課題も見られます。
精神障がいのある方は、疲れやすさやストレスを感じやすいといった特性を持つ方が多く、精神的負担とならない配慮が重要になってきます。
精神障がいにも様々種類がありますが、うつ病・統合失調症を例に合理的配慮の事例を紹介します。
うつ病
うつ病は、脳内の神経伝達物質の不均衡により、抑うつ状態、意欲低下、食欲不振、不眠、動悸、めまいといった精神的・身体的な不調が生じる病気です。
「何も手につかない」「簡単な判断ができない」といった状態に陥ることがあり、普段通りの業務遂行が困難になる場合が少なくありません。
職場では、うつ病を抱える従業員に対して、以下のような配慮が求められます。
| 配慮の種類 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 業務内容の調整 | 負担の少ない業務への変更、業務量の削減 |
| 勤務時間の調整 | 短時間勤務、フレックスタイム制の導入 |
| 職場環境の整備 | 静かで集中しやすい作業スペースの提供、相談しやすい雰囲気づくり、在宅勤務・リモートワークの整備 |
| メンタルヘルスケア | 定期的な面談、産業医やカウンセラーによるサポート、ストレスチェックの実施とフォロー |
統合失調症
統合失調症は思考や感情、行動をまとめる能力が低下する機能障がいです。約100人に1人がかかるとされ、決して珍しい病気ではありません。
主な症状
| 症状の種類 | 具体的な症状例 |
|---|---|
| 陽性症状 | 幻聴(実在しない声が聞こえる)、妄想(ありえないことを信じ込む)、思考の混乱(話にまとまりがない)など |
| 陰性症状 | 感情表現の乏しさ、意欲や気力の低下、引きこもりなど |
| 認知機能障害 | 記憶力や集中力の低下、判断力の低下など |
職場での配慮のポイント
| 配慮事項 | 具体的な配慮例 |
|---|---|
| 業務内容 | ・手順が明確で、自分のペースで進められる業務を割り当てる ・突発的な対応や変化の多い業務は避ける |
| 勤務時間・休憩 | ・本人の体力や体調に合わせて、短時間勤務から徐々に時間を延ばすことを検討する ・休憩時間は、本人の希望を聞きつつ、あらかじめ時間を決めておくことで安心感につながる場合もある |
| コミュニケーション | ・気軽に質問や相談ができる担当者を決める ・休憩時間の過ごし方について本人の希望を確認し、一人で静かに過ごせるスペースを確保するなどの配慮を行う |
統合失調症の方は、服薬や通院を継続することで、多くの場合、安定して働くことができます。特性を理解し、適切な配慮を行うことで、能力を発揮しやすくなります。
発達障がい
発達障がいのある方が職場で能力を発揮するためには、個々の特性に応じた合理的配慮が不可欠です。
発達障がいには、主に注意欠如・多動症(ADHD)と自閉症スペクトラム(ASD)が含まれます。
ADHD
ADHD(注意欠如・多動症)のある方は、特性により仕事で困難さを感じることがあります。
ADHDのある方が抱えやすい困難さの例
| 困難さの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 集中力の維持 | 周囲の物音や動きに気が散りやすい、長時間集中することが難しい |
| 実行機能の困難 | タスクの段取りや優先順位付けが苦手、複数の業務を同時に進めるとミスが増える |
| コミュニケーション | 適切なタイミングで報告・連絡・相談をすることが難しい |
| 体調管理 | 生活リズムが乱れやすく、勤怠に影響が出やすい |
合理的配慮の例
| 配慮の分類 | 具体的な配慮例 |
|---|---|
| 作業環境の調整 | ・パーテーションの設置 ・静かな席への移動 ・ノイズキャンセリングイヤホンの使用許可 |
| 業務の進め方の工夫 | ・指示の文書化、メール化 ・タスクリスト、スケジュール管理ツールの活用 ・指示を一つずつ具体的に出す |
| コミュニケーション | ・定期的な面談の実施 ・指示系統の一本化 |
| その他 | ・短時間休憩の許可 ・フレックスタイム制、時差出勤の検討 |
ASD(自閉症スペクトラム)
ASD(自閉症スペクトラム)のある方は、コミュニケーションや対人関係の持ち方、特定の物事への関心の強さといった点に特性が見られます。職場においては、これらの特性がご本人の困難さにつながることがあるため、一人ひとりの状況に合わせた合理的配慮が重要になります。
ASDのある方が働きやすくなるための配慮は、業務遂行能力(ハードスキル)と職業生活遂行能力(ソフトスキル)の両面から考えることが有効です。
| 配慮の側面 | 具体的な配慮例 |
|---|---|
| ハードスキル面 | ・指示は口頭だけでなく、図や写真を用いたマニュアルを作成する ・作業内容を細分化し、一つひとつ分かりやすく伝える ・抽象的な表現を避け、具体的な言葉で指示する ・スケジュールを視覚的に提示する |
| ソフトスキル面 | ・1日に短時間でも相談できる時間を設ける ・コミュニケーションは口頭にこだわらず、メールやチャットなど文字でのやり取りも活用する ・職場のルールやマナーは、具体的に分かりやすく伝える ・ひとりで休憩できる場所を確保する |
ASDのある方は、仕事そのものよりも、周囲の音や光、人の視線といった環境要因がパフォーマンスに影響を与えることがあります。
そのため、実際に様々な業務を経験し、ご本人に合った仕事を見つけること(ジョブマッチング)が大切です。また、共に働く上司や同僚がASDの特性を理解し、受け入れる体制を整えることも、効果的な合理的配慮と言えるでしょう。
知的障がい
知的障がいとは、知的機能の障がいにより、日常生活に支障が生じている状態を指します。判断基準となる知能指数(IQ)は「おおむね70まで」とされ、コミュニケーション、社会的スキル、実用的な読み書き、計算などに制約が生じます。
知的障がいの方への配慮のポイントは以下の通りです。
| 配慮のポイント | 具体的な内容 |
|---|---|
| コミュニケーション | ・短い言葉で、ゆっくりと伝える ・絵や写真、メモなどを活用する ・落ち着いて話せる状況を作る |
| 業務指示・伝達 | ・業務の手順をホワイトボードやメモに書く ・作業指示は明確に、一つずつ行う ・抽象的な表現を避け、具体的な言葉で伝える |
| 業務量・進め方 | ・習熟度に応じて業務量を調整する ・得意なこと、できることに注目して業務を割り当てる ・マニュアルに図や写真などを活用する |
| 環境整備 | ・教育専任者や担当者を配置する(キーパーソン) ・定期的な面談を実施する ・連絡ノートや相談用紙などを活用する |
合理的配慮はどこまで行うべき?過度な負担について
障がいのある方に対する「合理的な配慮」には限りがありません。手厚く配慮しようと思ったら、他の従業員の負担が増えるだけでなく、手間や費用もかかります。
合理的な配慮は重要ですが、企業にばかり求めすぎると障がい者雇用に消極的になる恐れもあるでしょう。
そこで、法律では事業主に対する「過重な負担」がかかる場合は合理的な配慮を求めないとしています。ここでは、過度な負担の判断基準について解説します。
事業活動への影響
合理的配慮の提供を行うことにより、事業所における生産活動やサービス提供が滞る場合は、過度な負担と判断される可能性があります。例えば、障がい者が希望する仕事に就かせた結果、不良品が多発して生産活動が低下した場合などが該当します。
障がいのある方が特定の仕事を希望した場合、配慮を実施すれば仕事がスムーズに行えて顧客にも悪影響を与えないかを一つの判断基準としてください。
ただし、「障がいのある方が特定の仕事に関わると企業のイメージが悪くなるので、過重な負担がかかる」といった主張は認められません。
実現困難度
事業所の立地状況や施設の所有形態、さらに従業員の数などで可能な合理的な配慮は変わってきます。例えば、「粉塵や騒音が出る仕事なので、車通勤が必須な郊外に事業所を構えているが、障がい者が車での通勤ができない」といった場合は、リモートワーク等の対策は取れても、事業所を移転させることはできません。
また、聴覚が過敏な障がい者に配慮して「完全に無音の部屋をつくってほしい」といった配慮や、「常にサポートする従業員をつけてほしい」といった配慮も難しいでしょう。
障がいのある方の雇用を検討する場合「企業がどこまで施設の環境を整えられるか」と明確にすれば、実現が難しい要求をするケースは少なくなります。また、障がいのある方も「このような配慮をしていただければ、貴社で働けます」といった意思表示が重要です。
費用の程度
企業は利益を出すために従業員を雇用して仕事をしています。従業員が心地よく働くために就業環境を整えることは重要ですが、「数億を出して従業員がリラックスできるように社屋を建て替えました」といったことはできません。
障がいのある方への合理的な配慮は重要ですが、そのために捻出できる費用は限りがあります。企業は、あらかじめ「自社で出せる費用はこの程度」と明確にしておくと実現可能な配慮もわかってきます。
事業の規模や財政状況
事業の規模や財政状況によって、企業ができる合理的な配慮は限られています。
例えば、「新規事業を開拓するために、予算をつぎ込んでいるので他のことに回す余裕がない」という企業もあれば、「業績が順調なので、障がいのある方が働きやすいように環境を整える費用が多めに捻出できる」といったところもあるでしょう。
金融機関に過度な融資を受けてまで、過度な配慮は必要ありません。規模や財政状況に合わせた配慮を行ってください。
助成金の有無
障がいのある方が働きやすいように職場の環境を整えるには、企業努力だけでは難しい場合もあります。そのため、国や自治体は障がいのある方を雇用する際に助成金を支給しています。
自治体によっては、障がいのある方に支払う賃金よりも助成金の額が大きいところもあるでしょう。
その費用を環境の整備に役立てることも可能です。国や自治体がどこまで助成金を支給してくれるかを確認し、できる配慮を明確にする必要があります。国や自治体のサポートが手厚いならば、この機会に職場の環境を整えてもいいでしょう。
職場で合理的配慮を提供するポイント
最後に、職場で合理的な配慮を提供するポイントを紹介します。
可能なものを実践していけば、スムーズに合理的な配慮ができるようになるでしょう。
当事者の声に耳を傾ける
合理的な配慮は、配慮を受ける当事者が必要としていなければ意味がありません。
まずは、合理的な配慮を必要としている方の声を聴きましょう。ただし、障がいの程度によっては自分の要望をわかりやすく伝えることが難しい場合もあります。
そこで、当事者の意見を聴きたい場合は、以下のポイントに注意して場所を設けましょう。
- 本人が時間をかけて意見が言える時間を用意する
- 本人の希望ならば、書面で提出も受け付ける
- 知的障がい者の場合は、サポートをしている家族等にも話を聞く
- 本人の意見を最後まで聴く
例えば、仕事の合間に「どんな配慮が必要?」と問いかけてもうまく意見が聞き出せません。採用面接など時間があるときに聴きましょう。
また、実現できるかどうかは後で考え、まずは最後まで耳を傾けることが大切です。
希望する配慮が会社で実行可能か話し合う
当事者の希望を聞いたら、会社で実行可能かどうかを話し合います。この際、「お金がないから無理」「人材リソースが割けないから無理」と頭ごなしに否定しては、当事者が一方的に我慢するだけに終わってしまいます。
「全部は無理だが、部分的なら可能」といった妥協点を見つけていくことが重要です。
また、当事者の意見だけでなく従業員の意見も聞きましょう。従業員にどのようなサポートが可能か、誰か1人に負担がかかりすぎないようにするにはどうしたらいいか等の話ができれば、従業員に不満がたまりすぎることも防げます。
合理的配慮の内容を決定し実施する
意見がまとまったら、実行する合理的な内容を決定して実践します。
この際、ただ実行するだけでなく意見を出し合うことが重要です。話し合いを重ねても、実行すると不具合が出てくるケースは珍しくありません。そのことを自由に話し合える環境づくりも重要です。
また、当事者に「企業側はこれだけ配慮したから、しっかり結果を出してほしい」「不満はいわないでほしい」といった態度を示すと当事者が委縮してしまい、合理的な配慮がうまくいかなくなります。
経過を報告して必要ならば修正を行う
合理的な配慮を行い、しばらく時間が経過したらもう一度意見を出し合い、必要ならば修正を行います。
この修正が重要です。どのような配慮も最初からパーフェクトではありません。修正を重ね、より良い配慮にしていくことが大切です。
修正したら、また実践し、結果を話し合うといったルーティーンを確立しましょう。
まとめ
障がいのある方と健常者がまじりあって働ける環境は理想です。しかし、実現するためには手間と気遣いと資金が必要です。「予算がない」「人的リソースがない」というのは簡単ですが、自社にできるところから始めていきましょう。
そうすれば、障がいのある方だけでなく健常者も働きやすい職場になる可能性があります。
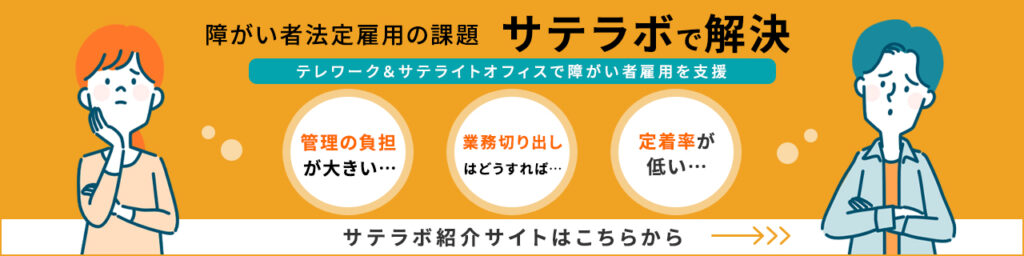
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







