障がい者雇用枠の給料は低い?平均相場や収入アップの事例を紹介
- 公開日:
- 2025.03.07
- 最終更新日:
- 2025.05.20
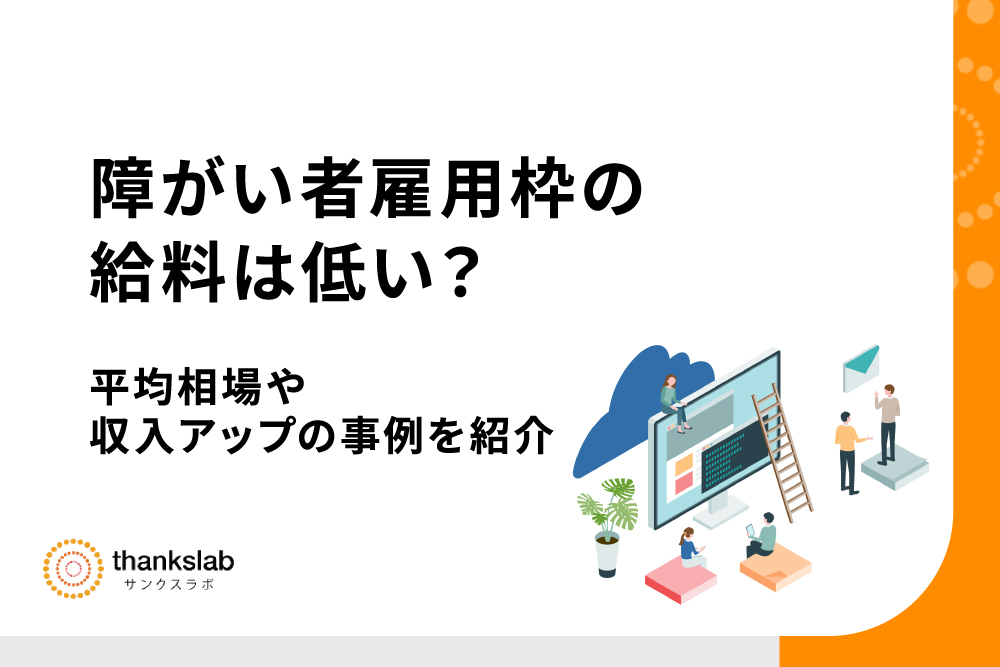
障がい者雇用促進法の制定をはじめとして、障がいのある方が働きやすい環境が整って行くにしたがって、会社で活躍する障がいのある方も増えています。
しかし、その一方で「障がい者雇用の枠で働くと、同じ仕事をしていても健常者の従業員より給料が低いのでは?」と不安を覚える方もいるでしょう。
就業にあたって、給料はとても重要です。モチベーションに直結し、後進にも影響を与えます。本記事では、障がい者雇用された場合の給料相場や、収入アップの事例を解説します。
障がい者雇用の枠での就業を検討している方は、参考にしてください。
障がい者雇用枠で働いた場合の給料はいくら?
厚生労働省が発表した令和5年度障害者雇用実態調査の結果によると、障がい者雇用枠で雇用された方の2024年5月の平均賃金は以下のとおりです。
なお、カッコ内は平成30年に行われた調査の数値です。
- 身体障がい者:23万5千円(21万5千円)
- 知的障がい者:13万7千円(11万7千円)
- 精神障がい者:14万9千円(12万5千円)
- 発達障がい者:13万円(12万7千円)
5年の間に賃金は上昇していることがわかります。一方、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、正社員の平均月給は31万8,300円となっており、最も賃金が高い身体障がい者と比べて約8万円高くなっています。
また、パートやアルバイトなど時短勤務の場合、2023年5月平均時給は1,412円でした。
日本の企業は勤務年数が長いほど高額になる傾向があり、平均月給は新入社員から勤務年数が長く役職に付いている従業員まで合算して算出しています。
そのため、「どの職種、どの職場でも障がい者枠で雇用された従業員と一般的な従業員で給与に大きな差がある」とは限りません。職種、職場、働き方によっては障害者枠で雇用された方と一般の従業員との差が小さいところもあるでしょう。
障がい者雇用枠で働いた場合の給料が低い理由
しかし、障がい者雇用の枠で採用された場合、一般的な手段で雇用された従業員に比べて給与が低い職場が多いのは事実です。
ここでは、障がい者雇用の枠で働くと給料が低い理由を解説します。転職をする際や働き方を選ぶ際の参考にもなるでしょう。
非正規雇用の労働者が多い
障がい者雇用の枠で働く従業員は、週30時間以上働く正社員待遇のほか、週20時間~30時間まで、週10時間~20時間までの短時間勤務で働く方もいます。また、正社員のほか、常用型の派遣社員、パート、アルバイトといった非正規で働く方も珍しくありません。
障がい者雇用の枠で働く無期限の正社員の割合は以下のとおりです。
- 身体障害者:53.2%
- 知的障害者:17.3%
- 精神障害者:29.5%
出典:令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書p4~15
最も割合が高い身体障がい者でも、50%近くの従業員が非正規雇用となっています。障がいのある方は健康な従業員と同様に働ける方ばかりではないため、非正規のほうが働きやすいケースも多いでしょう。
しかし、正社員と非正規雇用では給料に差が出てきます。基本給に差がなかったとしても、各種手当が付かずに総支給額が変わってくる場合もあるでしょう。
また、非正規雇用は時給計算の職場も多いので、休みが多いほど給与は低くなります。
また、非正規雇用だと管理職にもつけないため、役職手当等も発生しません。同じ職場で同じ仕事をしていても、非正規雇用のほうが昇給しにくい傾向があります。
短時間勤務での雇用が多い
障がい者雇用の枠で週30時間以上働くの常用雇用者の割合は、以下のとおりです。
- 身体障がい者:75.1%
- 知的障がい者:64.2%
- 精神障がい者:56.2%
平成30年度に発表された「障害者雇用実態調査報告書」で報告されたデータと比べると、週30時間以上働く障がいのある方は増えています。しかし、身体障がい者の約2割、知的障がい者の3割、そして精神障がい者の約5割が短時間勤務です。
短時間勤務の場合、多くの企業が時給で賃金が計算されます。正社員の場合は月給なので、休日があっても給与は変わりません。しかし、時給計算だと休日が多くなるほど給料は下がります。また、障がいがあると体調が悪くなることもあり、働きたくても働けなくなる時期が発生する方もいるでしょう。
週30時間働き続けられれば、障がい者雇用の枠でも期限なしの正社員として雇用される可能性も高まります。しかし、体調を崩して出勤できなくなれば元も子もありません。
最低賃金が減額される特例がある
障がいのある方を雇用する際、「障がいのためできる業務が限られている場合」や「一般的な従業員と比べて著しく業務をこなす速度が遅い」といった理由がある場合は、最低賃金以下の給料で雇用ができる、「最低賃金減額の特例許可」を受けられます。
障がい者雇用促進法では、「障がい」を理由に労働者を差別することを禁止しています。したがって、「障がい者だから」という理由だけで、最低賃金以下の給料を設定することはできません。
したがって、障がい者雇用の枠で雇用されたからといって給料が正社員と比べて著しく低く設定されることはないでしょう。
しかし、障がいの程度や業務の内容、試用期間中などは企業が地域の労働局に許可を得て、最低賃金より低い給料に設定することもあります。
このことは、雇用契約を結ぶ際に企業側から説明があるので、過度に心配することはありません。このような制度があるため、統計を取ると給料の平均額は一般的な従業員よりも下がる傾向があることは知っておきましょう。
障がいのある方でも収入がアップする事例
障がいのある方であっても、一般的な従業員と同じように収入アップ・昇給するケースもあります。障がいのある方は、健常者に比べるとできる仕事に限りがあります。そのため、障がいのある方が昇進、昇給を臨む場合は、健常者よりもキャリア形成を入念に考えることが重要です。
例えば、身体に障がいがあって発音が不明瞭だったり自分1人ではクライアントの元に行けなかったりする方に営業は難しいでしょう。しかし、システムの保守や構築、経理などの仕事は問題なく行えます。
障がい者であっても仕事を続けて自立したい場合は、自分にどんな仕事ができるのか考えたうえで、以下に解説することを実行してみましょう。
正社員雇用を目指す
正社員で雇用されれば、短時間勤務やフルタイムであっても非正規雇用に比べると、給料が上がります。また、退職金や有給など福利厚生も非正規雇用の従業員に比べると充実している企業が多い傾向があります。
従業員が40名以上いる企業は、障がいのある方を1名以上雇用することが義務付けられています。
企業は利益を出すことを目的に従業員を雇用するので、障がいのある方であっても会社にとって必要な人材であれば、健常者の従業員と同じかそれ以上の条件で雇用してもらえる可能性もあります。
資格を取得する
資格を取得すると、資格手当等で給料を増やしやすくなります。また、資格の中には一定の従業員が所属している事業所には必ず専属が必要なものもあります。そのような資格を取得できれば、よりよい条件で転職できる可能性が高まるでしょう。
資格の中には、誰でも受験資格があるもの、一定の実務経験が必要なもの、一定の学力が必要なものがあります。もし、現在の仕事が実務経験にカウントされるものならば、関連する資格取得を目指すのも一つの方法です。
また、資格には国家資格、公的資格、民間資格といった種類があります。難易度が高いですが仕事に役立つ資格が多いのが国家資格です。
民間資格は国家資格に比べると趣味の要素が強いものもありますが、「国家資格等は定められていないが、仕事をするには技術が必要」といった仕事に就く場合に役立つ資格もあるでしょう。
現在就いている仕事に関係する資格があるならば、それを目指してみる方法もあります。近年はバリアフリーの試験会場も増えて、障がいのある方であっても受験しやすくなりました。
転職を検討する
障がい者雇用促進法により、40人以上の常用雇用労働者を抱える企業は1名以上の従業員を雇用する義務があります。そのため、健常者に近い条件で仕事ができる障がいのある方や、短時間勤務であっても企業が求める能力を持っている労働者は、年齢に関係なく良い条件で働ける可能性があります。
現在の職場では昇給が望めない、出世も期待できないといった場合は転職を検討してみるのも一つの方法です。ただし、闇雲に転職してもうまくいきません。障がいの程度によっては、新しい環境に慣れるまで時間がかかることもあるでしょう。
必要ならば主治医と相談する、現在の職場と似たような仕事ができる職場を探す、就業時間の融通が効く職場を探すなど入念に準備したうえで転職をしてください。
障がい者枠で雇用されるメリットは?
障がい者雇用の枠で雇用されると、メリットもあります。
ここでは、障がいのある方が障がい者雇用を利用して仕事をするメリットを3つ紹介します。障がい者雇用の枠を利用するか、多少無理をしても通常の方法で働くか迷っている場合は参考にしてください。
障がいに対する合理的配慮を受けられる
一口に「障がい」といっても、人によって状態は異なります。同じ障がいを持っていても、問題なく仕事ができる方もいれば、長時間働くのが難しい方や、努力しても健常者と同じペースで仕事をするのが難しい方もいるでしょう。
障害者枠で雇用してもらえば、障がいに対する合理的な配慮を職場に求めやすくなります。例えば、特定の仕事を免除してもらったり、勤務時間を週に30時間までにしてもらうことも可能です。
また、障がい者枠で雇用されると職場の方々も心構えができます。就業前に障害に対して理解を深めてもらうこともできるでしょう。健常者と同じ方法で雇用してもらって働くより障害者本人だけでなく、他の従業員も余裕をもって接することができます。
一般枠より就職しやすい
障がいのある方が就職する場合、どうしても健常者よりも苦手なことやできないことが多くなります。前述したように、企業は利益を出すことが目的です。職種にもよりますが、健常者と比べて仕事ができない障害者はどうしても敬遠される傾向があります。
しかし、障がい者枠での就職ならば、あらかじめ「苦手なこと」「できないこと」をはっきりさせたうえで仕事ができます。企業も「ハンデのある方を雇用する」といった心構えができているので、働く環境を整備しやすいといったメリットがあります。
周りの理解が得やすい
障がいに関する話題はデリケートです。見た目で障がいがあるとわかる方でも、「何ができて何が苦手なのか」といった質問はしにくいでしょう。同じ職場で働く上司や同僚であっても同じです。
障がいの程度やできること、できないことを自分で周囲に説明して配慮を求められれば大丈夫ですが、障がいの種類や程度によっては難しい場合もあります。
障がい者雇用の枠で入社すれば、「配慮が必要な人が入社してくるので手助けが必要」という情報をいち早く職場全員で共有できます。そうすれば、従業員同士のコミュニケーションも取りやすくなり、お互いへの理解も深まるでしょう。
障がい者雇用枠の求人を探すには?
最後に障がい者雇用枠の求人を探す方法を2つ紹介します。
ハローワークを利用する
ハローワークは公的な機関なので安心して仕事を探せます。また、障がい者雇用に関しても案件を多く取り扱っているほか、就職に関する相談もできます。
職業訓練に申し込んだり失業保険に関する手続きも行えたりするので、求職以外でお世話になる方もいるでしょう。
転職エージェントを利用する
転職エージェントや民間の転職サイトは、ハローワークに比べると多くの案件を取り扱っているのが特長です。また、難関資格を取得している方向け、高収入を得たい方向けといった特長ある求人もあります。転職エージェントがサポートしてくれる機関ならば、履歴書の書き方や面接対策、企業の橋渡し役まで担ってくれます。
ただし、転職サイトや転職エージェントによっては障がい者雇用に関しては知識や案件が乏しい場合もあるので、注意しましょう。
まとめ
今回は、障がい者雇用の枠で就職した場合の給料事情を中心に解説しました。障がいの状態によって健常者と同様に仕事ができる方もいれば、短い時間に限られた仕事しかできない方もいます。そのため、どうしても給料が低いケースも出てきます。
給料を上げたい、健常者と同じように仕事をしたい場合は、正社員として雇用される、資格を取得するなどできることをしていきましょう。
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。







