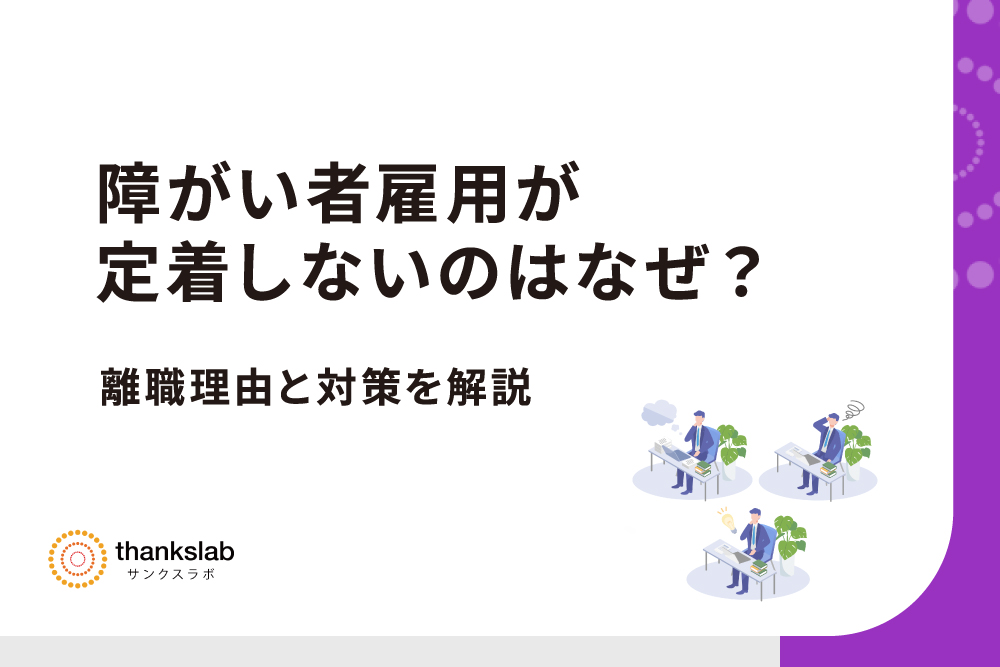障害者雇用の企業側のメリットとデメリットとは?
- 公開日:
- 2025.02.13
- 最終更新日:
- 2025.05.20
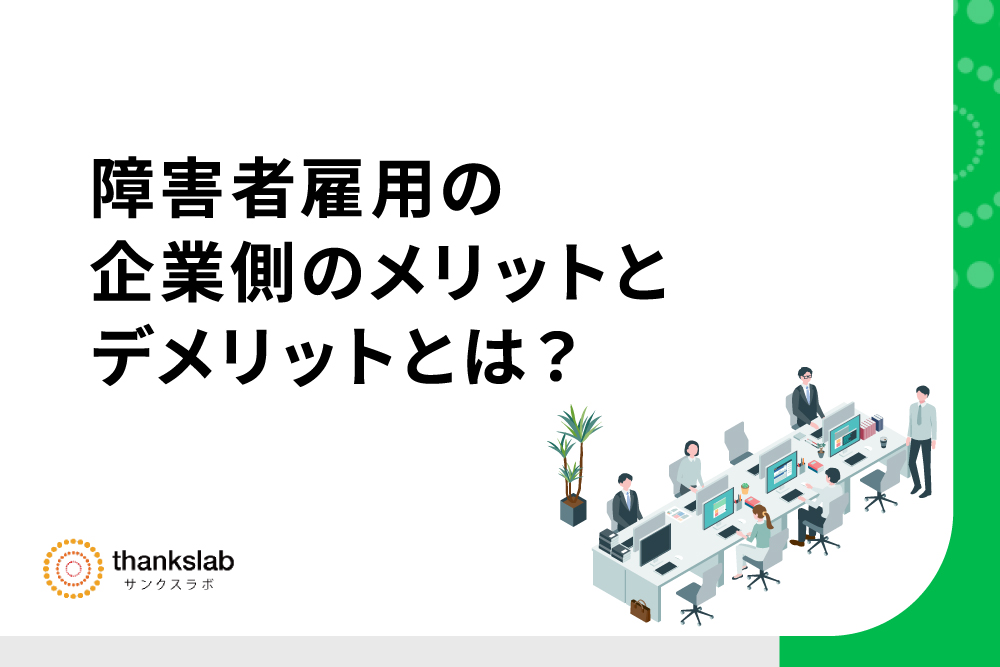
「障害者雇用を実施するメリットやデメリットについて知りたい」
「障害者雇用を進める方法がわからない」
これから障害者雇用を進めようと考えている企業では、このような悩みを持っているのではないでしょうか?障害者雇用は新しい取り組みになるため、企業が実施するには準備が必要です。
また、障害者雇用を実施することで、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのかは気になるポイントかと思います。
当記事では、障害者雇用を企業が実施するメリットや注意すべきデメリット、雇用を促進させる方法まで詳しく解説します。
目次
障害者雇用とは
障害者雇用とは、障害者が応募可能な枠を作成して採用・雇い入れを行うことです。
障害者手帳の所持者が対象となっており、障害者雇用を通じて障害者の社会参加を促進させることで人格と個性を尊重しながら共生できる社会の実現が目的です。
厚生労働省の障害者雇用促進法によって、障害者雇用の企業義務が定められています。
法定雇用率が未達成になっている企業は、ハローワークからの行政指導や障害者雇用納付金の徴収といったリスクがあります。
障害者雇用の必要性
障害者雇用が拡大されている背景として、障害者の雇用が困難になっている社会問題が大きく関係しています。障害者は健常者に比べて雇用の機会が少なく、採用されたとしても低賃金や不安定な雇用状況になる問題があります。
結果的に貧困な障害者が増えることになっており、厚生労働省は課題解決として障害者雇用の制度を作りました。
企業が障害者のスキルや強みを活かせる環境作りに力を入れることで、共生できる社会作りができるようになっています。
障害者の雇用を促進するために法定雇用率が定められているため、今後も障害者雇用は社会的に進んでいくでしょう。
障害者雇用を実施する企業側のメリット
障害者雇用を企業が実施することで、以下のようなメリットがあります。
- 多様性のある環境を構築できる
- 助成金を受給できる
- 企業のイメージアップにつながる
- 業務環境の見直しができる
- 人材不足を解消できる
それでは詳しく説明します。
多様性のある環境を構築できる
現在では社会的にダイバーシティ(性別や人種、障害に関わらず活用できる人材)の重要性が広がっており、企業が障害者を雇用することで多様性のある環境を構築できます。
健常者と障害者がお互いを理解することで、助け合いをしながら新しいアイデアや視点を見つけられるようになります。障害者の特性に合わせた職務配置を行えば、定着率を向上させて長く働いてもらうことが可能です。
また、適切なマネジメントや人事評価制度を実施すれば、生産性が向上して即戦力となる人材を確保できます。そのため多様性のある環境を構築できる点は、障害者雇用を企業が進めるメリットといえるでしょう。
助成金を受給できる
障害者雇用を進める場合、企業側は環境の整備や給与などのコストがかかります。そこで企業の経済的な負担を軽減するために、障害者を雇用する企業は国や自治体からの助成金を受給することができます。
助成金とは、国や地方自治体が企業や個人に対して支給する返済不要の資金です。雇用の促進や労働環境の改善を目的としており、厚生労働省の管轄のもと支給されます。
注意点として、助成金を受け取るためには要件を満たし必要な書類の用意が必要です。障害者雇用に必要なコストを軽減できる点は、企業にとってメリットの1つといえます。
企業のイメージアップにつながる
企業が障害者雇用を進めれば社会貢献につながり、イメージアップを図ることができます。
近年では企業経営の観点においてダイバーシティや働き方改革などの概念が注目されており、企業側が社会課題解決に取り組む必要があると考えられています。
障害者雇用は社会貢献につながっているため、企業価値を向上させる取り組みです。クライアント企業や取引先からの評価も向上するので、企業にとって障害者雇用を実施するメリットは大きいでしょう。
業務環境の見直しができる
障害者雇用を進めるには、現在の業務環境を見直す必要があります。障害者を適切な業務に配置する取り組みが必要になるため、作業内容や進め方を見直さなくてはいけません。
業務環境を見直せば障害者だけでなく部署や会社全体の改善にもつながるので、業務効率化を図れるようになります。
そのため業務環境の見直しができる点は、企業のメリットの1つです。
人材不足を解消できる
現在では、幅広い業界で人材不足が大きな課題となっています。
超高齢化社会かつ少子化が進む現代において、人材の確保はすぐにでも解決すべき課題です。業種によっては人材確保が難しかったとしても、障害者雇用を行うことで人材不足を解消できるようになります。
ITツールを活用したリモートワーク業務も広がりを見せているため、障害者でも柔軟な働き方が可能です。障害者の特性に合わせた職務配置を行えば、人材不足を解消しながら生産性を向上できます。
人材不足の課題を解決できる点は、企業が障害者雇用を行うメリットといえるでしょう。
障害者雇用で注意すべき企業側のデメリット
障害者雇用で注意すべきデメリットとして、以下のような点が挙げられます。
- 納付金を納める義務がある
- 行政指導の対応コストがかかる
- 企業名を公表する必要がある
良い点だけでなく、課題となるポイントについても理解しておきましょう。
納付金を納める義務がある
企業側が法定雇用率を未達成になった場合、障害者雇用納付金を納めなくてはいけません。2024年4月の改正では法定雇用率が2.5%となっており、2026年7月から2.7%に引き上げられます。
現在では2024年4月の改正が反映されるので、従業員数40人以上の企業は障害者の雇用義務があります。
例えば2024年4月の改正をもとに説明すると、300人の従業員を雇用している企業では7名の障害者雇用が義務付けられる仕組みです。
納付金の徴収は企業にとって大きな負担となるため、法定雇用率を達成しているか事前にチェックしておきましょう。
行政指導の対応コストがかかる
法定雇用率の規定内に障害者を雇用していない場合、ハローワークを通じて行政指導があります。行政指導の対応には通常外の業務対応が必要になるため、コストが増えてしまいます。
対応コストを軽減するためにも、企業は法定雇用率を達成する取り組みを実施しなくてはいけません。
企業名を公表する必要がある
ハローワークの行政指導から障害者の雇用状況が改善されない場合、企業名が公表されるリスクがあります。
企業名が公表されると社会貢献度が低いイメージがついてしまい、クライアント企業や取引先との関係性が悪化する可能性も高いです。
そのため適切な障害者雇用をしなければ、自社のブランドイメージが悪くなる恐れがあることを理解しておきましょう。
障害者雇用のデメリットを解決する方法
障害者雇用のデメリットを解決するには、以下のような方法があります。
- 障害者のサポート体制を作る
- 会社の方針を明確化する
- 障害者の特性を把握して現場環境と共有する
スムーズに障害者雇用を進めるためにも、ぜひ参考にご覧ください。
障害者のサポート体制を作る
障害者雇用を進めるには、現場の不安を解消することが大切です。
会社全体で障害者のサポート体制を作ることで、現場の不安を解消できるようになります。
例えば業務目標の設定・評価、現場責任者との情報共有、配属先の決定方法などのサポートを行うことで、障害者が働きやすい環境を構築できます。
ほかにも人事部内に相談窓口を設ければ、障害者が健康面のトラブルを起こしたときも支援機関と連携しながら柔軟な対応が可能です。
会社の方針を明確化する
障害者雇用を社内で浸透させるには、会社の方針を明確化することが重要です。社会的な義務であることを説明するだけでなく、雇用する必要性や計画について丁寧に伝える必要があります。
現在の企業理念や雇用全体の方針が内容と反する場合、障害者雇用を実施するタイミングで見直しが必要です。社内の従業員に障害者雇用を納得してもらうためにも、会社の方針を明確化しておきましょう。
障害者の特性を把握して現場環境と共有する
障害者雇用を進める場合、現場では従業員の不安も存在します。
障害者をどのように稼働させればいいのか心配な点も多いため、障害者の特性を把握しながら現場環境と共有することが大切です。
まずは採用時に本人と話し合い、特性や能力、配慮してほしい部分などを整理しておきます。そして現場の管理者や従業員に共有し、障害者を受け入れる準備を整えていきます。
事前に障害者受け入れに関する研修会を社内で実施すれば、社内理解を深めながら対応方法やサポート体制を考えられるようになるでしょう。
障害者雇用を促進させる方法
障害者雇用を促進させるには、以下のような方法があります。
- 障害雇用支援サービスを利用する
- ハローワークに相談する
- 地域障害職業センターに相談する
それでは詳しく解説します。
障害雇用支援サービスを利用する
障害雇用支援サービスでは、障害者雇用の幅広いサポートを実施しています。企業が障害者雇用を進めるための悩みや不安を解決でき、採用や働き方、採用基準などの提案を行ってもらえます。
業務創出や採用のサポートも得られるので、障害者雇用を効率良く進めることが可能です。
当社が展開している「サテラボ」は、障害者雇用に関する幅広いサポートを提供しているサービスです。
障害者専門の職業訓練施設の直接運営によって、豊富な人材を確保できます。厚労省の障害者雇用代行ガイドラインを遵守したコンプライアンス対応なので、安心してサービスを利用できます。
初期費用は無料で今だけお試し導入キャンペーンを実施しているので、障害者雇用をはじめたいならぜひ気軽にご相談ください。
ハローワークに相談する
ハローワークでは、障害者雇用の相談や支援方法、助成金制度などのアドバイスを受けられます。
障害者に向けた求人票の掲載もサポートしており、総合的な支援が可能です。法定雇用率の指導も行っているため、リスクを回避するためのアドバイスを受けられる点も魅力です。
全国各地にある労働局でもセミナーや見学会などが実施されているので、社内全体で障害者の理解を深められます。障害者雇用を促進させるためにも、ほかの方法と併用しながら活用しましょう。
地域障害職業センターに相談する
地域障害職業センターは、独立行政法人高齢・障害・休職者雇用支援機構の施設です。事業主に対する障害者の雇用管理相談や援助を行っているため、障害者雇用を進めるときに役立ちます。
例えば、障害者が仕事に適応できるようにする取り組みや事業主が行う配慮の助言を受けられます。また、障害者の雇用継続に必要な助成金を受けられるので、利用を検討してください。
障害者雇用を企業が進めるときの注意点
障害者雇用を企業が進めるときは、社内の受け入れ態勢を整える必要があります。
業種や社内環境によって実施すべき内容は異なりますが、適切な職務配置やコミュニケーション方法、勤務形態などを考えることが大切です。
障害者が孤立すると離職の原因になるため、事業主は特性を理解した上で話し合いの場や相談先を用意しなくてはいけません。
また、危険な機器を取り扱う場合、安全面の配慮なども必要になります。コミュニケーションを取るときは、穏やかな対応を心がけながら障害者のストレス状況などを考慮することも重要です。
特に精神障害を持つ人は環境による影響を受けやすいため、企業が雇用するときはそれぞれの特性について十分理解しておくようにしましょう。
障害者雇用で活用できる助成金
こちらでは、障害者雇用で活用できる助成金について紹介します。
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
障害者雇用にかかるコストの負担を軽減するためにも、ぜひチェックしてください。
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、障害者を試行的に雇い入れた事業主や週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に対して支給される助成金です。
トライアル雇用助成金には「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2種類があり、それぞれ受給要件が異なります。
詳細については、厚生労働省の対象ページをチェックするようにしましょう。
参考URL:厚生労働省|障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者介助等助成金
障害者介助等助成金は、雇用する障がい者の職場定着のための措置を行う事業主や、職場適応援助者による障がい者の職場適応の援助を行う事業主に対して、経費や賃金の一部が支給される助成金です。
法改正によって様々な対応が必要ですが、「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」の取り組みが推進されたことから働きやすく活躍できる職場環境の実現が可能です。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、以下のような2種類があります。
- 特定就職困難者コース:ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障がい者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給される
受給要件の詳細については、厚生労働省の対象ページをチェックするようにしましょう。
参考URL:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
参考URL:厚生労働省|特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
まとめ
今回は、障害者雇用を企業が実施するメリットや注意すべきデメリット、雇用を促進させる方法まで詳しく解説しました。
障害者雇用は企業に障害者が働ける環境を用意する取り組みであり、厚生労働省の障害者雇用促進法によって義務付けられています。
企業が障害者雇用を進めることで、多様性のある環境の構築や助成金の支給、自社のイメージアップ、業務環境の見直し、人材不足の解消などのメリットがあります。
ただし、法定雇用率が未達成になった場合、納付金を納める義務や行政指導の対応コスト、企業名の公表といったデメリットがあることも理解しておかなくてはいけません。
ぜひ当記事で紹介したノウハウを参考にしながら、自社の障害者雇用を進めてみましょう。
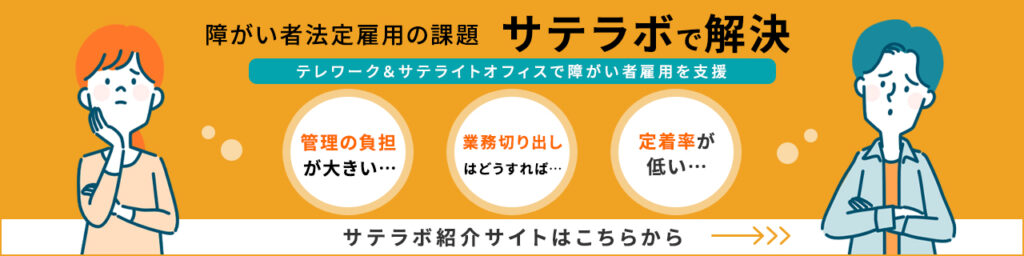
この記事を書いた人
サンクスラボ編集部
サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。