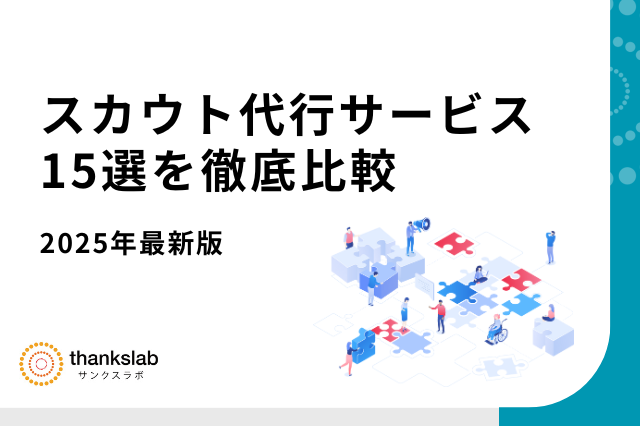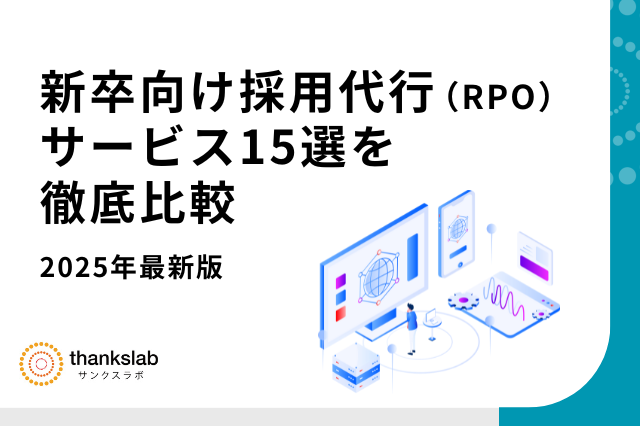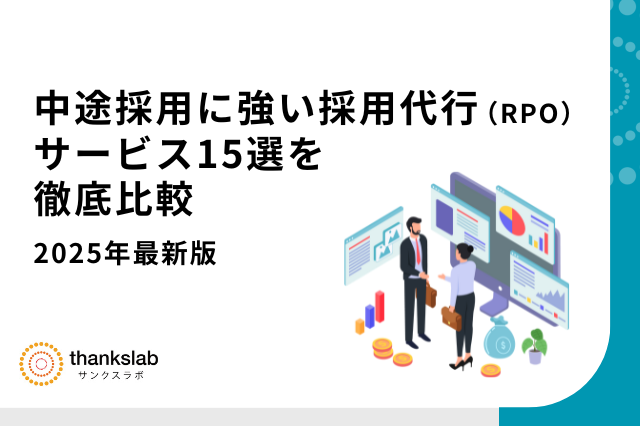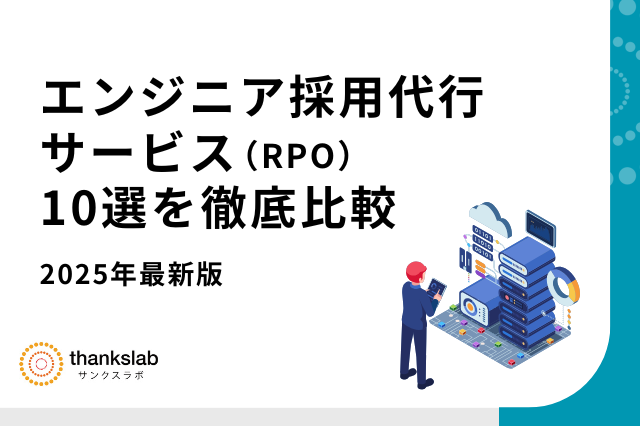ティアフォーCHROに聞く、成長を続ける組織づくりと人事のこれから
- 公開日:
- 2025.10.02
- 最終更新日:
- 2025.10.02

「自動運転の民主化を実現する」。 自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」の開発を主導し、自動運転の社会実装を目指すティアフォー様。現在は500名超の従業員を抱える急成長企業となり、その動向には大きな注目が集まっています。
同社では急拡大する組織・人員を支える「労務」の戦力として障がい者人材が活躍しています。
今回は、執行役員・CHROの村岡様に障がい者雇用の取り組みやサテラボの活用事例、進化・拡大を続ける組織づくりの展望など詳しく伺いました。
企業プロフィール
会社名:株式会社ティアフォー
URL:https://tier4.jp/
障がい者雇用で抱えていた課題:業務に対応できる人材の確保、法定雇用率の達成自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」を開発。自動運転の社会実装を推進するディープテック企業。
従業員数:500名インタビューにご協力いただいた方
村岡 広紀様(執行役員・CHRO)京都大学文学部卒業。社会保険労務士。
日立製作所に入社後、米国勤務含め人事全般を経験。その後、PwC Japanを経て、楽天グループに参画。楽天では広告系カンパニーのチーフピープルオフィサー、QAオフィサーとして、人事総務、広報、マーケティング、品質、法務、リスクコンプライアンスを担当。その後、楽天モバイル等の事業のチーフピープルオフィサー、人事責任者を務め、人事改革を主導。2025年にティアフォーにCHROとして入社。
急成長に伴う雇用課題、解決の糸口はサンクスラボ

―本日はよろしくお願いいたします。 「自動運転 」という、AIの世界でも最も熱い領域で奮闘されているティアフォー様ということもあり、伺ってみたいことがたくさんありますが…どのような経緯で「サテラボ」の存在を知ったのでしょうか?
村岡様:当社はスタートアップで、ここ数年社員数が急増しています。そうした中で社員数の増加に応じて、障がい者の法定雇用率を満たすことが難しくなり、複数の手段を検討していました。
直接雇用だけで満たすのは採用面の時間的な制約等から難しい面があり、一定以上の資質の人材を効率的に採用する手法を検討する中で、御社を知りました。
―さまざまな障がい者雇用の支援サービスがある中で、サテラボのどんな点に興味を持っていただいたのでしょうか?
村岡様:先ほどのお話の通り、障がい者雇用については複数の手段を検討しました。例えば、直接的に当社の業務に関わらないような手段も候補としてありました。
しかし、事業の急拡大フェーズにおいて人手不足であった状況も踏まえると、一定資質以上の人材プールがあり、戦力となる人材を短期間で複数名採用することができる御社のスキームが最もしっくりきました。
HR領域で活躍する障がい者人材と今後の展望
―ありがとうございます。即戦力人材の採用という観点から障がい者雇用を検討いただき大変嬉しく思います。現在、サテラボを通じて雇用された社員の方はどんな業務で活躍されているのでしょうか?
村岡様:主には、HR(人事)ユニットにて労務管理の業務に従事いただいています。
当社の事業成長に伴い、社会的責任を果たすために勤怠管理等の健康管理体制を強化しています。当社のすぐに対応したかった業務の需要ともマッチしてご活躍いただいております。
―雇用された社員の方の様子はいかがでしょうか。また、今後の期待を伺えますか?
村岡様:みなさん日々の担当業務に責任感をもって取り組んでいただき満足しております。
今後については、AI等を活用して、担当業務を効率化するようなことを自律的に期待したいと考えています。
―今度は当社「サンクスラボ」としての期待を伺えたらと思います。 今後サテラボにとどまらず当社のさまざまなサービスやリソースを活用できるとしたら、どんなことが考えられるでしょうか?
村岡様:現状は障がい者雇用のみに留まっていますが、御社はWeb系のエンジニアリングや海外のオフショア開発等もされていると認識しています。
当社にはソフト、ハード、Web、AI等のエンジニアリング領域があり、事業を拡大していっているため、人材不足となる場合があります。
こうした面でもお互いフィットする部分があれば一緒に仕事をできればと考えています。
―ありがとうございます。ぜひご協力できればと思います。
「組織は戦略に従う」──CHROの視点から見た組織改革

―これまでたいへん大きな企業のアドミ領域、人事の中枢で活躍されていましたが、スタートアップ企業であるティアフォー様にCHROとして参画して見えてきたものは何でしょうか。御社が目指す理想の組織や制度、働き方などこれからの展望を伺うことは可能でしょうか?
村岡様:「組織は戦略に従う」という経営学者のアルフレッド・チャンドラーさんのお言葉があります。
おかげさまで当社は「自動運転の民主化」というビジョンの下に事業が拡大し、派遣社員等を含めて500名を超える規模にまで成長しました。年間約100名の採用計画で拡大しています。
かつての小規模だった頃であれば、フラットな組織でダイレクトに指示する方が効率的だったのですが、現在のフェーズにおいては、一定の組織階層が必要だと考えています。各領域の責任者であるCxOを中心に権限を委譲して、経営効率・品質の向上を考える必要があります。
このため、2025年10月に本部・部等の階層や決裁権限を整備しました。
ただ、階層化が進むとデメリットとして、階層間の意思疎通が難しくなる等も生じがちです。
そのため、トータルリワード(グレード、評価、報酬)等についても2025年10月に刷新し、そうした人事制度を通じて、社員に期待する発揮能力をグレードごとに定義し、組織拡大と権限移譲と一体感を両立できるようにしています。
今後も事業状況に応じて組織や制度を見直していくと思いますが、その検討にあたっては、当社のコアバリューである「The Professional」を念頭において検討していきます。
「The Professional」においては、「目指す水準」として「人々の可能性が、広がるものを」としています。具体的には、「自動運転には、人々の感情や生活、そして文化を一変させる力があります。テクノロジーで新しい価値を生み出し、人々を支え、社会課題を解決する。そして、より良い日常を送るために欠かせない社会と文化のインフラとなる。ティアフォーが約束するのは、人や世の中を動かすリファレンスをつくることです。」と謳っており、その時々の事業状況に応じて、あるべき姿を柔軟に模索し続けたいと考えています。
働き方についても同様です。当社は自動運転用のオープンソースソフトウェアである「Autoware」に付随するシステム等を提供しております。
この特性を踏まえて、2025年10月よりオープンソースのエコシステム拡大への貢献に対する副業を積極的に認める方針としております。
また、出社方針についても出社と在宅の最適な頻度を部署ごとに検討し、当社のミッション・ビジョン・バリューを実現するためにどうあるべきかということを柔軟に検討しております。
―まさに今後を見据えた組織デザインの過程にあったのですね。
雇用率達成から次のステージへ、多様性を力に変える挑戦
―改めて障がい者雇用の取り組みについて触れさせてください。今後の計画や展開などお話し可能な範囲で伺わせてください。
村岡様:障がい者雇用をするにあたって法定雇用率がひとつの課題になりましたが、おかげさまで御社のご協力もあり達成しています。
今後は社員の増加を踏まえると、さらに雇用を拡大していく必要があり、いかに当社の人材価値の最大発揮につなげるかという視点で検討していきたいと考えています。
例えば、障がい者雇用の方を受け入れる際には、受け入れ部署に対してDEIB(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン&ビロンギング)の研修を実施し、障がい者に限らず、多様な人材でいかによりよい就業環境を構築していくか議論しながら進めています。
※DEIB:Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)、Belonging(帰属意識)の頭文字を取った概念で、従業員一人ひとりが多様な個性を尊重され、公平な機会を得て、安心して能力を発揮し、自分らしくいられる組織の状態を目指す考え方。
そのように、障がい者雇用をきっかけに当社の社員全体の人材価値の向上につながるようにしていきたいと考えています。
また、AIによる業務効率改善等の強みのある人材がいれば積極的に活用して、強みを活かした業務で当社の企業価値の向上にもつなげていただきたいです。
―ありがとうございます。DEIBとどのように向き合い企業行動に落とし込んでいくかは多くの企業にとっての使命であり課題となっていきますね。
AI×人事の未来像
―ティアフォー様はディープテック・スタートアップで最先端を走られています。純粋な関心としてここから先、AIが働き方をどう変えていくのかを尋ねさせてください。 例えば、アドミ領域の業務ではより効率化や改善可能な余地が多いと思いますが、どんな変化が理想でしょうか?
村岡様:ご指摘の通りで、AIを活用しての効率改善は必須の状況です。
今後、いくつかの段階が考えられていて、AIによる不正の可能性の検知などを通じて、ガバナンスの向上を期待しています。
さらには、それらインサイトからコンサルテーションにまで昇華していくでしょう。このような世界観を見据えて、段階的に進めていくことが大切です。
「人材価値の最大発揮」を軸に、人事ROIを問い直す
―いまこの記事を読まれているみなさんに、ティアフォー様のご経験をもとにお話しできることがあれば伺わせてください。 例えば、障がい者雇用を含む人事のアップデートを考えたとき、どのようなところに目を向け、着手していくのがよいのでしょうか?
村岡様:アドバイスするような立場ではないですが、大事なこととしては人事の機能が在り方を追究していくことではないかと思います。
人事の価値提供先は、経営者、管理職、社員全体や、社外の株主や求職者等が考えられます。多くの活動は「やった方がいい」ものではありますが、ROIをどのように捉えるのかが難しいと思います。活動に対する対価をどのように捉えるのかという問いに向き合っていくことが、結果として、適切なアップデートにつながっていくのではないかと考えます。
例えば、当社においては「人材価値の最大発揮」につながっているのか必ず問い直すようにしています。
―ありがとうございます。おっしゃるとおり哲学的な課題と向き合うことになりますね。「人材価値の最大発揮」につながっているのかへの問いは大変わかりやすい示唆でした。
「自動運転の民主化」へ、実証から社会実装への歩み
―最後になりますが、ティアフォー様の事業や今後の展望について可能な範囲でご紹介ください
村岡様:ティアフォーは、「自動運転の民主化」をビジョンとし、自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」の開発を主導するディープテック企業として、自動運転の社会実装を推進しています。
「Autoware」を活用したソフトウェアプラットフォームを自社製品として提供し、これらの製品を基盤に市場の需要に対応したサービスを展開しています。「Autoware」が生み出すエコシステムを通じて、世界各地のパートナーと協力して自動運転の可能性を拡大し、より良い社会の実現を目指しています。
現在、地方自治体との実証実験も推進しており、運行している自治体の数も増えています 。2025年には長野県塩尻市で自動運転レベル4の運行許可を、石川県小松市で認可を取得し、引き続き実証実験や運行をおこなっています。
今後は自動運転レベル4での運行実績を積み上げるとともに、将来的な自動運転サービスの実装を通じ、運転手不足など地域の交通課題の解決を目指してまいります。
―貴重なお話をいただきありがとうございます。自動運転技術の進化とその周辺で巻き起こる社会の変化が楽しみですね。
村岡様:当社の今後の活動にますますご注目ください!